
豊島氏の滅亡と伝説(4)
石神井城━━練馬区(前編)
江古田原の戦いは四月十四日の朝の四つ時(午前十時頃)には、勝敗がついていたという。豊島泰経勢と練馬城の残党は石神井へ退却した。太田道灌の軍勢もそれを追う。
太田勢は石神井川の南側の通称愛宕山というところに陣を張った。愛宕山にはトーカン山という別名もある。トーカンは道灌のことだろう。そこは現在早稲田大学高等学院の敷地になっている。

民家の背後の木々の所が早稲田大学高等学院

地面が高くなっている
伝承によると、豊島方は城下の麦の刈入れを早めに済ませたというが、事前にここが戦場になると予想していたのだろうか。太田軍と対峙してからでは、麦の刈入れは無理だろう。
四月十八日、泰経は城の要害を破却することを一旦は承知。しかし、泰経は約束を守らなかったので、道灌は外城を攻撃。泰経は夜のうちに城を脱出。落城は二十一日、二十八日などの説がある。

石神井城は石神井川の水源の一つになっている三宝寺池のほとりにある。築城された時期の記録は残っていないが、鎌倉時代末期ではないかといわれている。石神井公園の中に遺構があって、現在でも土塁や空堀の跡をしのぶことができる。
今回約三十年ぶりに訪れてみた。すると、城の主郭(本丸)と思われる場所は金網で囲まれて、立ち入り禁止になっていた。中の地形を保護するためだという。

フェンスや説明板の古び具合様子から、だいぶ前からこの様な囲いがされたのが分かる。


奥の高い所が土塁。主郭内部は土塁の向こうにある

フェンスの向こうは草が生え放題で、低木もかなり生えているので、見通しが悪い。対して立ち入ることのできる部分は、下草もきれいに手入れされている。実はこちら側も城跡の一部なのだが。
昭和六十三年[1988]五月。この頃城跡は誰でも自由に立ち入りができた。下草刈もされ、土塁が主郭の周りを囲んでいるのを確認することもできた。
写真も撮ったのだが、残念ながらお見せできない。光量不足で現像できなかったのだ。(現在のデジカメの性能なら、上の写真のようにきれいに写せただろうが、当時の私のカメラは固定焦点のポケットカメラで、性能はよくなかった)
その代わり当時メモ用紙にスケッチした絵を、清書してみた。

奥の道の部分も濠の一部と思われる

かなり急な斜面で、こちらから攻めることは難しい

これ以上前には出られない
城のある丘の下には石神井城の碑がある。


城はこの背後の斜面の上にあった

左が本丸跡、右の塀は三宝寺の裏手
この小道も城の遺構の一部だろう
なお、三宝寺も城の一部だった

発掘調査で分かった城の縄張りを重ねた
下の部分が切れてしまったが、石神井川までが城の範囲になるだろう
(土偶子作画)
主郭部分はそれほど広くないのがお分かりいただけたと思う。普段は外側に館があってそこで過ごし、戦などの非常時には主郭に立て籠れるようになっていたのではないだろうか。道灌が攻め落とした外城というのが、平常時の館なのかもしれない。

空堀の底から土塁の上まで10m位あったらしい
主郭の内側に入れなかったのは残念だったが、自由に入れた頃、このままにしていたら、そのうち土塁が削れ、主郭や堀部分も埋まってしまうのではと思っていたので、保護するのはよいことだ。
そういえばかつて、城を復元するとかいう話があった。
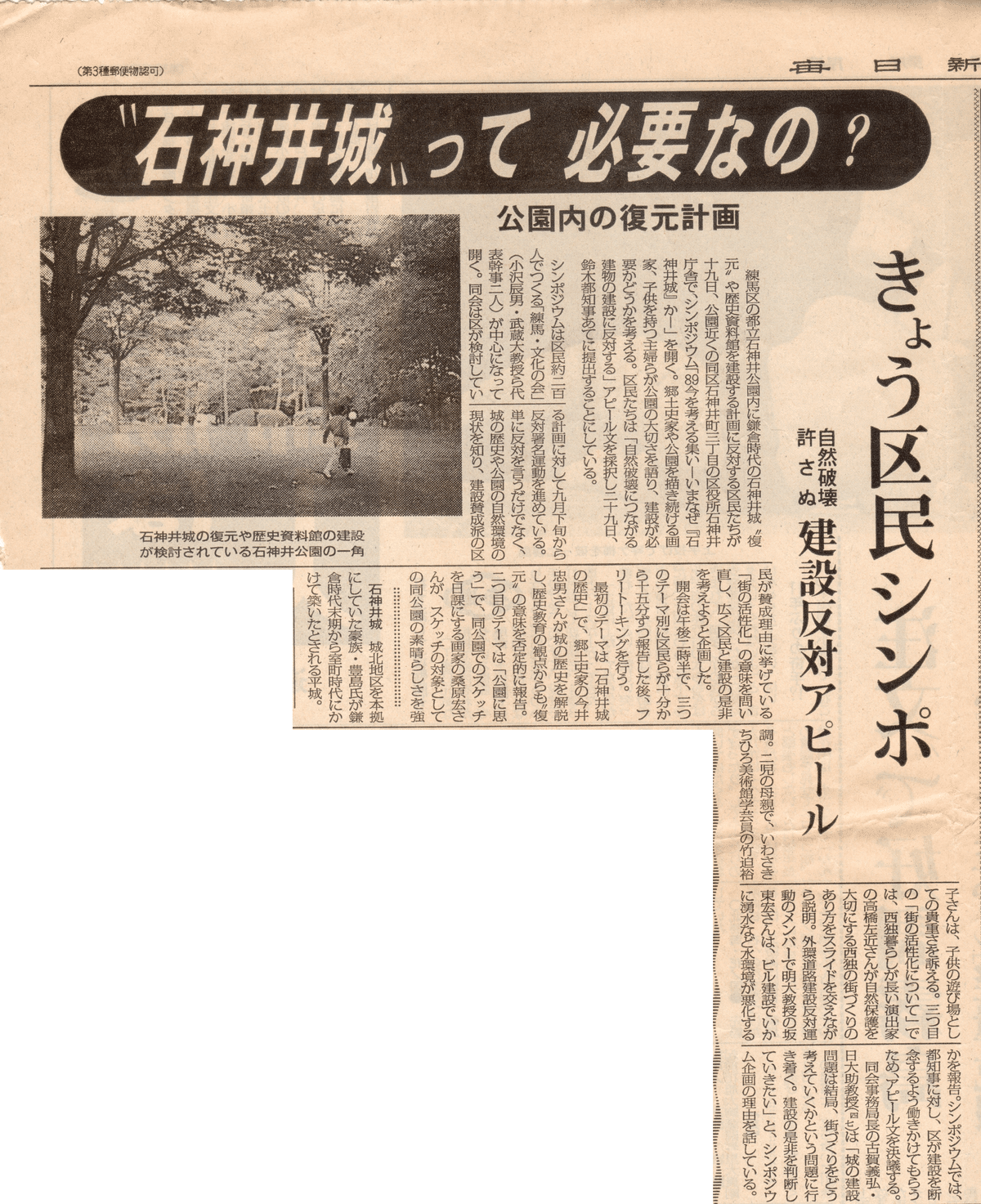
この頃日本はまだ景気が良くて、あちこちで城跡に天守閣を建てて町おこしするのが流行のようになっていた。しかし、戦国時代前夜の城なんぞ、どこまで再現できるのだろう。まさか、天守閣はないだろうし。ジオラマくらいでちょうどよいのではないだろうか。(現代なら、VR再現なんておもしろいかもしれない)
泰経がどこに落ちて行ったのか分からない。多分平塚城だったのだろう。柵や堀などの防備を強化して、再び上杉、太田勢に対抗姿勢を見せた。
平塚城の傍を通る本郷通は昔は岩付道と呼ばれていた。岩槻(付)城は山内上杉氏、太田氏の拠点となる城である。江戸と川越、岩槻の三か所を分断する場所に平塚城はある。
しかし翌年一月、道灌の攻撃に遭い、またしても泰経は城を捨てて足立方面に逃げた。その後、泰経の消息は分からない。記録に残っていないのだ。
これにて豊島本宗家は滅んだのだが、泰経の子孫は続いていて、後北条氏、武田氏などに仕え、徳川幕府の旗本になっている。
つづく
