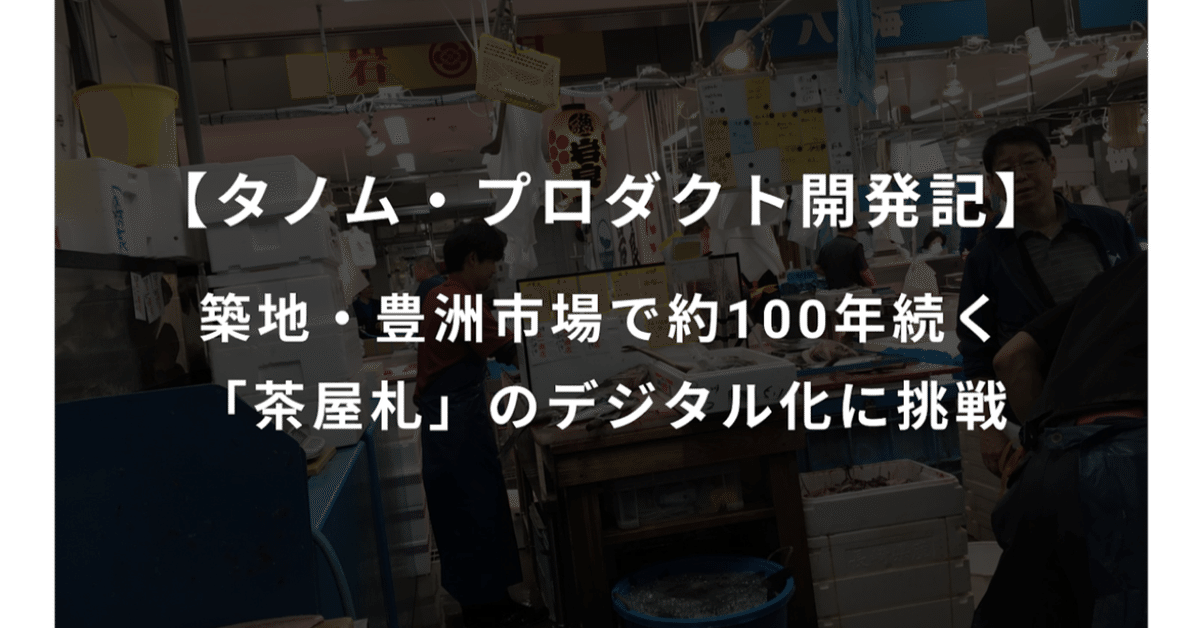
【タノム・プロダクト開発記】築地・豊洲市場で約100年続く「茶屋札」のデジタル化に挑戦
こんにちは!タノム・PRチームです!
弊社では、「卸業者の仕事をシンプルに」をコンセプトに開発したB2B SaaS「TANOMU(タノム)」を提供しています。
タノムは、食材卸業者の課題に寄り添いながら、プロダクトの改善を行っています。(タノムの設計思想についてはこちらの記事をご参照ください)
私たちは「(買い手の飲食店ではなく)売り手の卸売に寄り添ったプロダクト開発」・「スタートアップとしてのスピード感を持った開発・検証」を重んじています。この記事を読んで「タノムで力を試してみたい!」という方は、ぜひこちらのwantedlyから応募いただけると嬉しいです。(エンジニアも、ビジネスも募集しています!)
今回は実際に卸業者の声から生まれた「茶屋札(ちゃやふだ)」という機能の開発事例をご紹介します。構想からMVPの完成・フィードバックまでを1ヶ月半というハイスピードで完結させました。
茶屋札とはそもそもなんなのか。どんな課題が潜んでいるのか。機能開発のきっかけとなった株式会社魚家(うおや)の村松さんに取材協力をいただき、綴ります。
取材協力:株式会社魚家(うおや) 村松 絃太さん
2015年、慶應義塾大学卒業。国内大手人材会社に新卒でエンジニア職として入社し、採用管理システムの開発を担当。その後2017年、家業である株式会社魚家を引き継ぐ。
株式会社魚家は、創業15年目、取引先は個人店中心で100店舗以上、仲卸から買付を行い飲食店に直接配送を行う納め屋という業態で魚卸を営む。
「茶屋札」という水産卸特有のカルチャー
「茶屋札」とは、市場で仲卸業者から鮮魚を買付する際に使う、専用の注文用紙のことを言います。下の写真が実際に使われている茶屋札です。

正方形のメモ用紙の下半分にもともと買い付け先の業者名が記載されており、上半分に商品と注文数の情報を記載し、使用します。
プロダクトを通じて達成したいこと
この茶屋札を手書きで集計・作成するのに、魚屋(うおや)の場合は、この作業だけで月間約200時間ほどの工数をかけています。
・茶屋札作成の工数を削減すること
・集計/起票のミスを削減すること
・(上記達成の上で)タノムを活用し飲食店からの受注を増やすこと
上記の3点を目標に、まずはMVPという位置付けで、茶屋札の機能化を検討することになりました。
業務フロー概要

1/ 注文処理
まず飲食店から注文を受けます。
「飲食店単位」で、イワシが3kg、アサリが1kgという具合でFAXやLINEが届いてきます。

↑実際に届いているFAX。毎朝、これが数十件単位で届き手作業で集計をしている。
2/ 集計・茶屋札作成
集まった注文を、「商品単位」で集計します。
「イワシは全部で10kgだな...」と、1つ1つ手動で計算を行っています。
この集計と平行して作成されるのが「茶屋札」です。先に記載したとおり「発送先の飲食店 x 商品」をユニークデータとして、茶屋札は作成されます。

↑今回の機能開発にあたり、当社代表の川野が作成したメモ。「AAA」、「BBB」というのが飲食店名です。(アサリなどの単価が低いものや、品質のバラツキが少ないものは茶屋札が使われないケースもあるそう)
3/ 注文・買い付け
作成された茶屋札は、そのまま仲卸(豊洲場内にいる一次卸業者)への発注書として使用されます。数百枚の茶屋札と集計表を手渡しし、「今日は、アジ全部で10kgね!」と伝えるわけです。
4/ 荷積・発送
仲卸が場内から競り落とした商品は茶屋札の単位で小分けされ、場外の配送拠点に運ばれます。発注書として仲卸に渡った茶屋札が、今度は出荷指示書兼領収書として、再び魚屋(うおや)の手元に戻ってきます。
UI設計

今回はMVPとして、タノム上に登録された発注を、ボタン一つで起票できる機能を開発しました。
タノム管理画面の「茶屋札作成」ボタンをクリックすると上画像のように、飲食店 x 商品名単位での茶屋札の印刷画面が立ち上がります。
魚屋(うおや)の場合、まだエンド顧客の飲食店へのタノム導入が進んでいないため、現状では以下のようなフローで活用をいただいています。
①FAXで注文受付 → ②魚屋スタッフがタノムに入力 → ③茶屋札出力
②の手間はまだ残っているものの、手動集計と比べると集計の計算ミスが減ったり、文字が読み取れないようなトラブルが無くなったりという効果がすでに出ています。
ファーストユーザー・魚屋(うおや)さんの声
――今回、第一弾としてリリースされた「茶屋札機能」を使ってみてどうでしたか?
村松:今回リリースされた機能で、今まで紙で計算していた店舗からの注文を自動で集計し、正方形の形式で茶屋札をパソコンから出力できるようになりました。
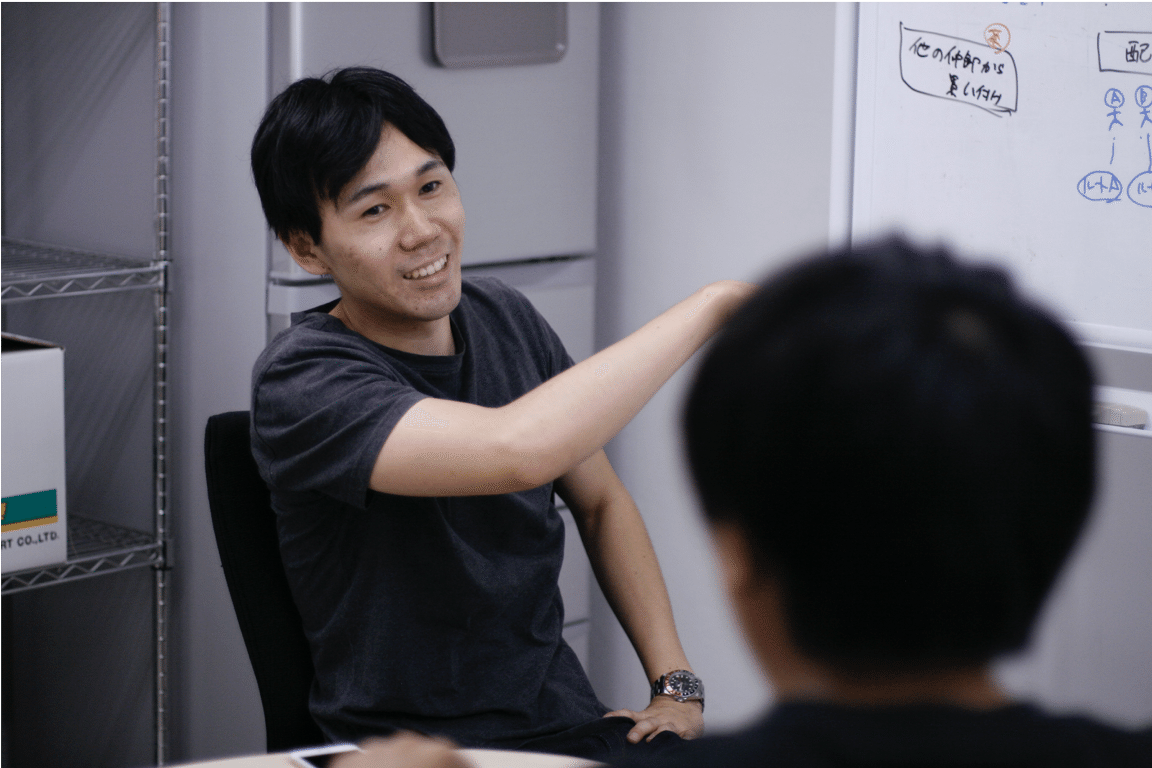
今までは1日200枚ほどの茶屋札を手書きで作成しており、自分含め3人で毎日2時間ほどの時間がかかっていました。また手書きのため発注のミスを起こしてしまうこともありましたが、この機能を使うことで、集計や茶屋札作成の手書きの作業がなくなり、時間とミスを削減できるなというイメージを持つことができました。
同時作業しても更新が同期されるよう機能開発いただいたので、、すぐに現場でも実利用できそうです!
――今後の期待感について教えてください。
村松:最近、卸業者も自分のように2代目、3代目の若い世代に経営が引き継がれ、デジタル化していこうという意思を持った人が徐々に増えてきています。しかし、卸業者に寄り添ったシステム開発会社が少ないこともあり、デジタル化の推進をあまりうまく進められていないのが現状です。
例えば、某大手の受発注システムは、飲食店側の都合で導入するにも関わらず、費用は卸が負担するというモデルになっており、利用することで逆に負担が増えてしまっています。
一方、タノムは移動中でもスマホで使えたり、店舗への導入もカンタンだったり、かゆいところに手が届き、卸業者に寄り添ったサービスだなと思い、大きな期待感を持っています。
まずは自分たちがタノムを活用し業務改善の事例を作ることで、豊洲市場や地方市場など水産卸業界全体のデジタル化の推進が少しでも前に進めばいいなと思っています!
――お話しいただき、ありがとうございました!
いかがでしたか?これからも売り手に寄り添ったプロダクトの改善事例などを定期的に発信していきたいと思いますので、ご期待ください
チーム・タノムでは、事業を共に成長させる仲間を募集しています。
下記よりお気軽にご応募ください!
TwitterのDMを開放しておりますので、こちらからもお気軽にご連絡ください。
→twitter @heeeeeday
