
新書のいい帯のコピーを考える
ふだん、NHK出版新書というレーベルで新書の編集をしている。
皆さんは新書が1年間にどのくらい出ているかご存じだろうか。どこまでが新書かという問題はあるけれど、毎年の新書大賞で1票を投じることの可能な新書の数は、去年は約1300冊だった。
つまり、毎月100冊以上の新書が出ては書店の新刊台を賑わし、翌月にはまた違う100点が新刊台を賑わわせているのだ。あらためて考えると恐ろしい。文化の厚みともいえるけれど。
そんな中で、書き手、切り口(企画性)、内容という本の本文に加えて、テーマを端的に示しつつ、一瞬で人を惹きつけられる「書名(タイトル)」がひときわ大事になる、というのは当然の道理だ。『生物と無生物のあいだ』『さおだけ屋はなぜ潰れないのか』『ふしぎなキリスト教』『独立国家のつくりかた』『バッタを倒しにアフリカへ』など、一世を風靡した新書にはやはりタイトルにインパクトがある。いい本が必ずしも売れるわけではない。だけど、いい打ち出し方をしたいい本は売れていると感じる。
一方で、書名の次に重要な要素が、今回テーマにしたい「帯のコピー」だと思っている。もう少し広く「帯に載せる情報」と言い替えてもいい。
以前、レーベルのウェブ連載の企画で、装丁家の名久井直子さんと奥定泰之さんに、池袋のジュンク堂書店の新書コーナーを回ってもらった。とくにそのお仕事の多くがフィクション分野である名久井さんは、そのとき「新書の棚って、情報量がものすごいですね」とおっしゃっていた。
そうなのだ。新書は毎月100点の競合がいる。たくさんの新書の中から「その1冊」に目を止めてもらうために、何が売りなのか、どういう内容の本なのかを、統一されたデザインの中の限られたスペースで、最適化してアプローチしなければならない(結果、総体として新書棚は「情報量がものすごい」ことになる)。
私のような編集者の仕事にはさまざまなものがあるけれど、著者が書いたその本をどのように演出するか、最適だと思う舞台をどう整えるかも、とても大事なひとつの任務だ。帯の情報というのは、ここでいう演出の一形態といえる。
前置きが長くなったが、この記事では、新書業界の片隅にいる人間の立場から、新書における帯の機能とは何かを考察してみたい。他人の仕事を品評するつもりはないので、あくまで自分の仕事から考えてみたい。
◾️テーマを普遍化する
帯の役割というか機能は、本とそのタイトルの打ち出し方によって少しずつ違う、というのが持論だ。この記事では小見出しに分けて3類型にしてみたい。
最初の例は、最新刊で今まさに新書の新刊台に並んでいる、三牧聖子さんの『Z世代のアメリカ』を挙げようと思う。

情報の組み方はオーソドックスだ。この本にはサブタイトルがついていない。だから、具体的に何を俎上に上げる本なのかがちゃんとわかるように、扱う7つ全てのトピックを置いた。そしてメインでは、この本が何を問うているのかを大きく、端的に表した。日本でも個人と政治が切れてしまっているような状況があるが、アメリカの歴史、そして現在進行形の動きから、望ましい未来に向けて「社会を変える」にはどうすればいいのかを考え続ける、真摯でまっすぐな著者の思いを普遍化させたいという思いが背景にある。
じつは「政治」というワードは新書の帯では必ずしもウケがよくない。でも著者がアメリカ外交史、国際関係論の研究者であることから、そして本の内容からも、逃げずに使うのが正道だと考えた。最後の「各メディアで話題の~」は、近影を入れる意味を補完する重要な情報だ。
こんなふうに、タイトルを補完して「この本は何を伝えたいのか、どういう”普遍”を目指すのか」を明示するのが、帯のひとつの役割だと思う。
新書ではないけれど、柳原正治先生の『帝国日本と不戦条約』というNHKブックス(選書)も、似たような帯のつくりだ。

この本は安達峰一郎という戦間期に生きた稀代の外交官を扱った、今のところ日本で唯一の一般書だ。こちらとしては、そのこととタイトルだけでピンとくる人以外にもたくさん届けたい。そこで、現下の衝撃的なウクライナ戦争の情勢の中で「世界の法(=不戦条約)は、なぜ戦争(=満州事変から続く15年戦争)を防げなかったのか」という本書の痛切な問いが、今の時代ときっと重なり合うものだと思ってひねり出したのが、この言葉だった。
また、やや角度は異なるが、赤坂真理さんの『愛と性と存在のはなし』もこのタイプだと思う。

『愛と性と存在のはなし』というのは、著者である作家の赤坂さんからある時するっと出てきた書名だ。不思議な魅力と味わいのあるタイトルだと思う。その「感じ」を壊さないよう、この本が問おうとしていることを突きつめて、この本の最大公約数はどんな言葉になるだろうか、と考えたときに、「生まれた性に くつろげる人は 本当にいるのだろうか?」という言葉を考えた。社内の意見の中には「ストイックすぎる。著者の写真をドーンと使って、もっと分かりやすくしたらどうか」というものもあったのだけど、この本でそれをやったら台無しになる。「週刊読書人」の特集で、医療人類学者の磯野真穂さんにこの帯について言及してもらって嬉しかった。
◾️本の輪郭を帯で完成させる
「テーマの普遍化」とは別のアプローチも当然ある。諸橋憲一郎先生の『オスとは何で、メスとは何か?』はこんな帯になった。
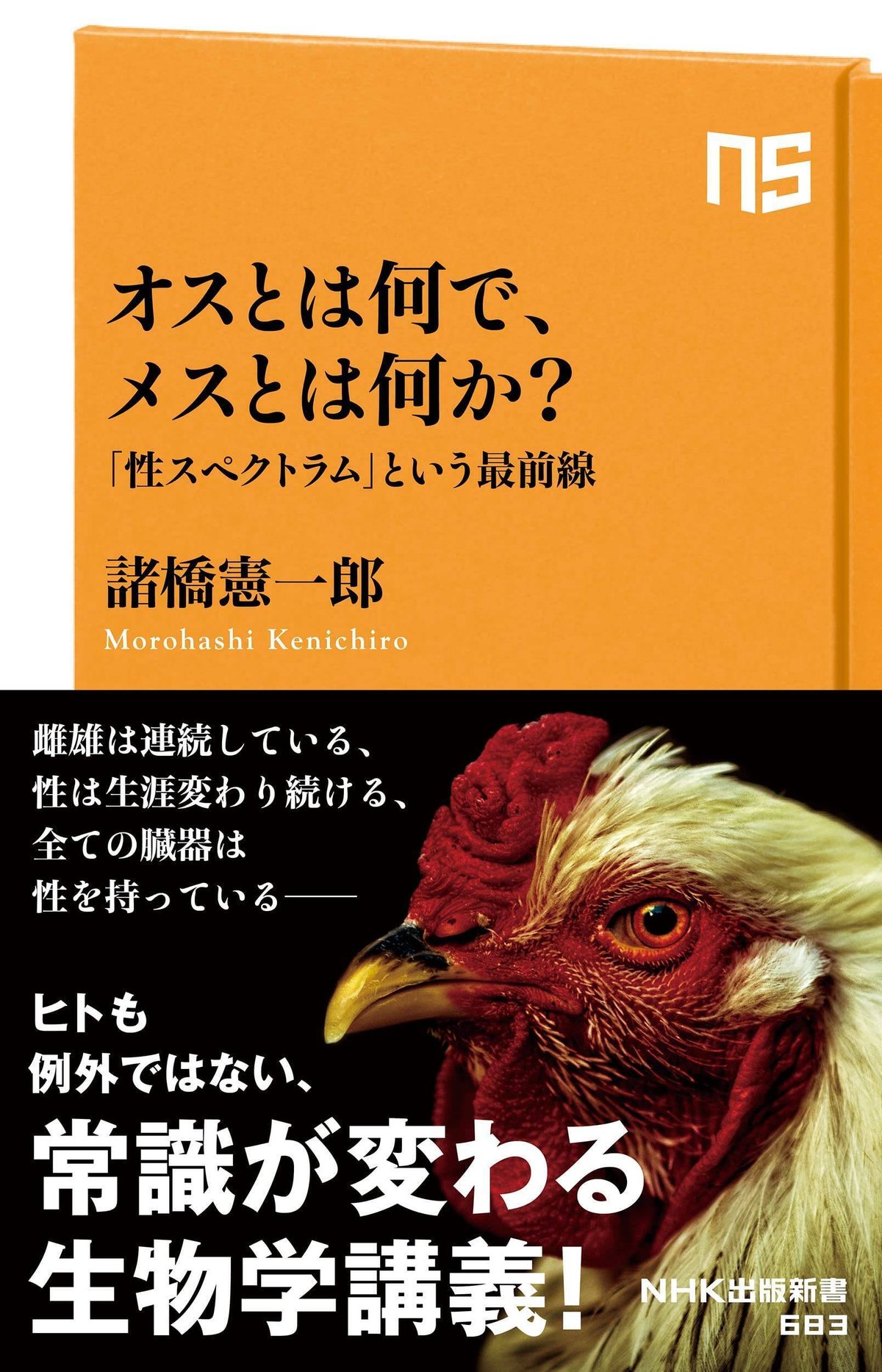
長年にわたって生命の性分化構造の基礎研究を行ってきた先生の初の著作である。内容がまずとても面白かった。タイトルも(先生の反対を押し切る形で申し訳なかったですが)メインに「性スペクトラム」という言葉を使わず、大きく出た。あとこの本のアプローチに必要なのは「興味を引く具体例」と、本のレベル感だ。幸い、前者は考えるまでもない。それが上段のサブコピーである。
問題は後者だ。サイエンス系の本は、新書といえども文系には読むのに骨が折れるものも多い。でも先生の文章はとても読みやすかった。というより、たくさんの人に読んでほしいという熱意に溢れていた。これはふだん、あまり科学の本を読まない人にも読んでもらうチャンスだ。
敷居の高い本ではないことをどう伝えるか悩んだときに、サブコピー以上に具体的なことを書いても読者は限られると考えて、「クリシェ(決まり文句)に頼る」という方法を選んだ。クリシェの安心感が読者の裾野を広げる、と思った。それがよかったかどうかはわからない。でも、SNSで話題になり、たくさんのメディアに紹介されて、話題の一冊になった。「面白くて易しい本ですよ」という本の輪郭を、帯で多少は作れたのではないかと思う。
作家性の強い著者の本も、アプローチが似ている気がする。こちらが色気を出してトリッキーなことをせずに、雰囲気に合わせて帯で本の輪郭を確定させるほうが自然という意味だ。栗原康さんの『サボる哲学』はそういう発想からスタートした。

この本は『栗原康』『サボる哲学』という2つの要素でほぼ完成している。だがそこは新書。大杉栄伝や伊藤野枝伝、一遍上人伝が次々に話題になり、すでに文筆家としての地歩を固めていた方だとはいえ、アナキスト文人である栗原さんのことを知らない人にも手を伸ばしてほしい。栗原さんの主張と「感じ」をうまく、自然に伝えたい。それでこそ本の輪郭が完成する気がした。コピーの「万国の労働者よ、駄々をこねろ」というのは、サブタイトル案で最後のほうまで残った、栗原さん必殺のパワーワードだ。「駄々をこねろ」というのが栗原さんらしいし、新書らしくなくて、とてもアナーキーだ。デザインで遊んで無理にアナーキーな印象にすると、一気につまらなくなる。普通の顔をしてズレるのが面白いのだ。あとはパズルのピースを埋めるように、それを置いて完成した。
世界を壊さず、強度を高めるという意味では、担当した本の中で暫定で一番売れている、堤未果さんの『デジタル・ファシズム』も似た方法だ。

タイトルとサブタイトルで、おおよそのニュアンスはできていた。あとはどのような具体例を添えるかで読者が「どんな本なのか」はっきりと認識できる。そう考えて「デジタル・ファシズム」なるものの、ここが一番耳目を引くポイントだと抽出したものが、黄緑色のコピーになった。刊行当時はデジタル庁が発足したばかりで、国の拙速なデジタル化計画にたくさんの人が懸念を抱いていた頃だった(今も変わっていないけれど)。だからこそ「何がどうヤバいのか」の根源を突くのがこの本のキモだった。社内チームの尽力も実り、電子版も含めると約18万部のベストセラーへと成長した。「この国を売って〜」の部分は個人的には好きではないが、いろいろな調整の末この形が選択された。
◾️タイトルと内容の強度を高める
最後は、2つ目の「本の輪郭を帯で完成させる」よりももっと単純な話だ。ようは、タイトルだけで説明できてしまっている場合である。
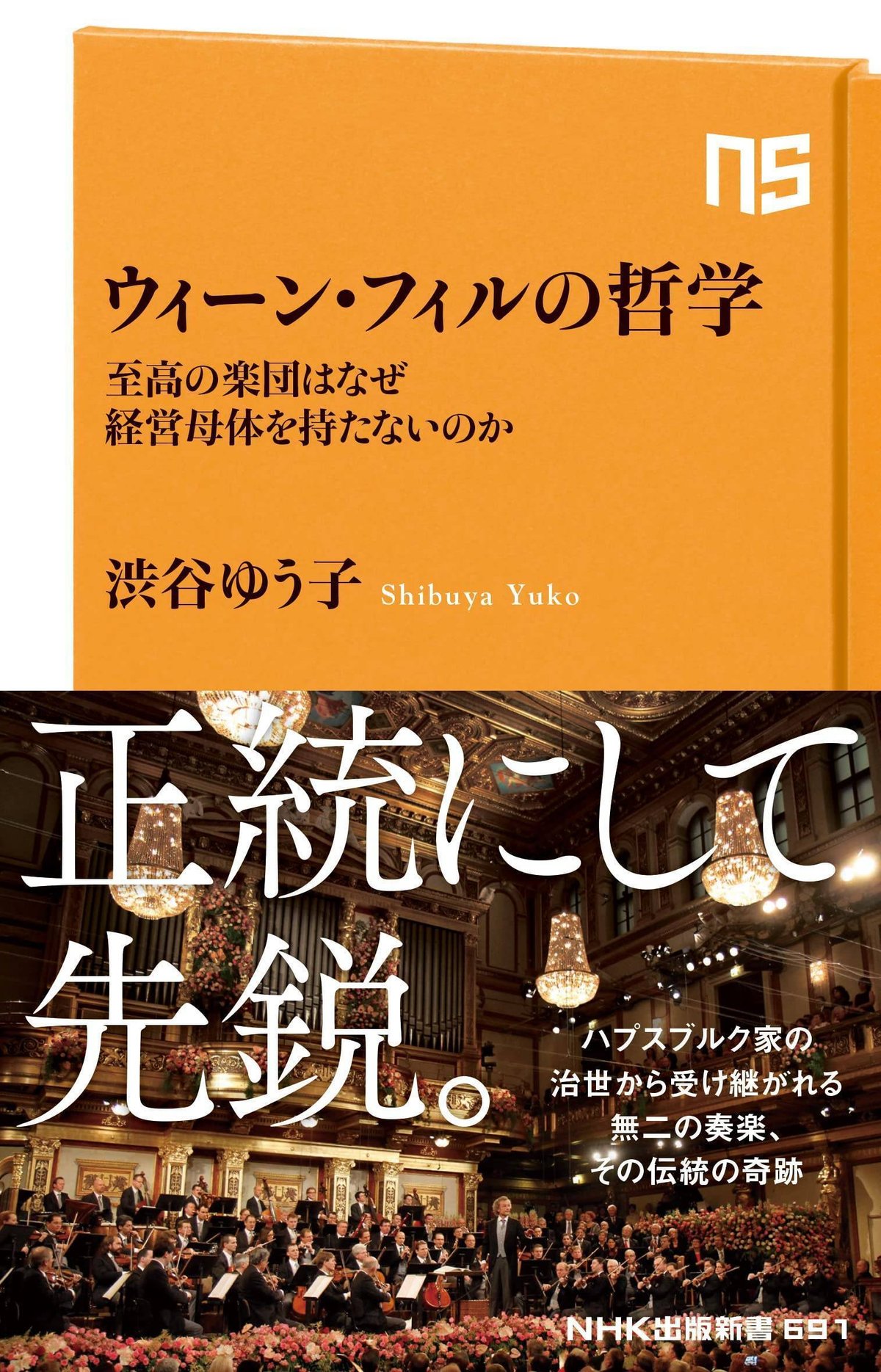
この本は「ウィーン・フィルの考え方について書いてあるんだろうな」ということと「彼らは経営母体を持ってないんだ」という2つの情報をすでに主副の題で表している。オビで具体例を出すと変に専門的に見られかねない。だから、「主副で言っていることをまとめると、つまり何?」ということを、大きなコピーで表し、写真は壮麗な黄金の間でのニューイヤーコンサートを採用した。クラシック音楽をテーマとした新書は、ある程度著者が限られている(市場が確立している)。そこに新しい書き手である渋谷さんが新規参入していくとき、むしろオーセンティックさを補強することが、この本の性格的にもプラスに働くのではないかと考えた。
また、この「正統にして先鋭」というコピーは、お気づきの方もいると思うが、前に挙げた「テーマを普遍化する」ことも念頭にある。この本はクラシック業界の話でありつつ、一般的な組織論として読めることを目指している。業界を牽引する王道な組織でありながら、先鋭(改革的)であるとはどういうことなんだろう? という興味が読者に沸けば、こちらとしてはガッツポーズだ。

『怖い絵』で一大ベストセラーシリーズを築き、言わずとしれた作家・中野京子先生の『異形のものたち』というこの本も、考え方は似ている気がする。主題を補完する副題がついて、絵画は堕胎の罰を描いたセガンティーニの「悪しき母たち」を選んだ。凍てつく大地で女性が木に絡め取られて、枝から生えた幼子の頭部が乳を吸っている地獄絵だ。気味が悪すぎる・・・。もう世界はできていた。こうなれば左手は添えるだけ。世界観を邪魔せず、できるだけ言葉を削りつつ、そっと背中を押すような言葉を考えた。
かなり余談だが、このセガンティーニの作品、フォトエージェントの画像(上)と画集(下)で、風合いとというか色味がぜんぜん違う。

おそらく画集が正しいのだけど、実物を見ないとなんとも言えない。実物はウィーンにある。先生に聞いたところ、色の記憶がおぼろげなことに加え、「しかも最近は美術館が洗浄するので、そうなると全然変わってしまうんですよ」とのこと。かくも美術作品の取り扱いは難しい。

最後に『現代哲学の最前線』という本にも触れておきたい。
この本にも副題がついていないけれど、主題だけで本の趣旨は十分わかる。ここは5つのテーマを前面に出すより(裏にはある)、当時マルクス・ガブリエルが目立ち始めていたこともあって、読者にとって多少馴染みのありそうな哲学者の名前を出したほうがいいと思ってこの形にした。誰を入れて誰を入れないか、かなり悩んだけれど、この作業は結構楽しかった。もし2023年の今なら、やや違う角度の打ち出し方をしているかもしれない。
・・・と、挙げた担当書は一例なのでもっと書きたいところだけど、ずいぶん長くなってしまったので、この辺で打ち止めとさせていただきます。あと、帯を演出するためのレーベルごとのブックデザインの構造についても考えると面白いんですが、マニアックすぎるので控えます。
これからも新書作りを続けていく中で、自分のこの考え方は少しずつ形を変えていくと思う。いつだって今は何かが足りない。でも、これが現時点での自分なりの考え方だ。
帯に時間をかけるのは、新書が「安い」本だからということもある。2000円、3000円では本当に興味がないとなかなか手が出ない。でも、900円代なら淡い興味でも買ってみようかなと思ってもらえるかもしれない。裾野が広がる。読者が増える。そこを自分なりに突き詰めていくのが面白い。そのテーマを「すごく気になってる人」から「言われてみれば、確かに気になるかも……」という人まで、広くウィングを張って、どうすれば裾野を広げられるか、考える余地が大きいからだ。
書店の棚の「総体」としては、新書は圧倒的な情報量ですが、その中でどう打ち出していくのが最適解なのか、この記事で編集者の煩悶を読み取ってくださったら、さらけ出して書いた甲斐があります。
お読みいただき、ありがとうございました。
