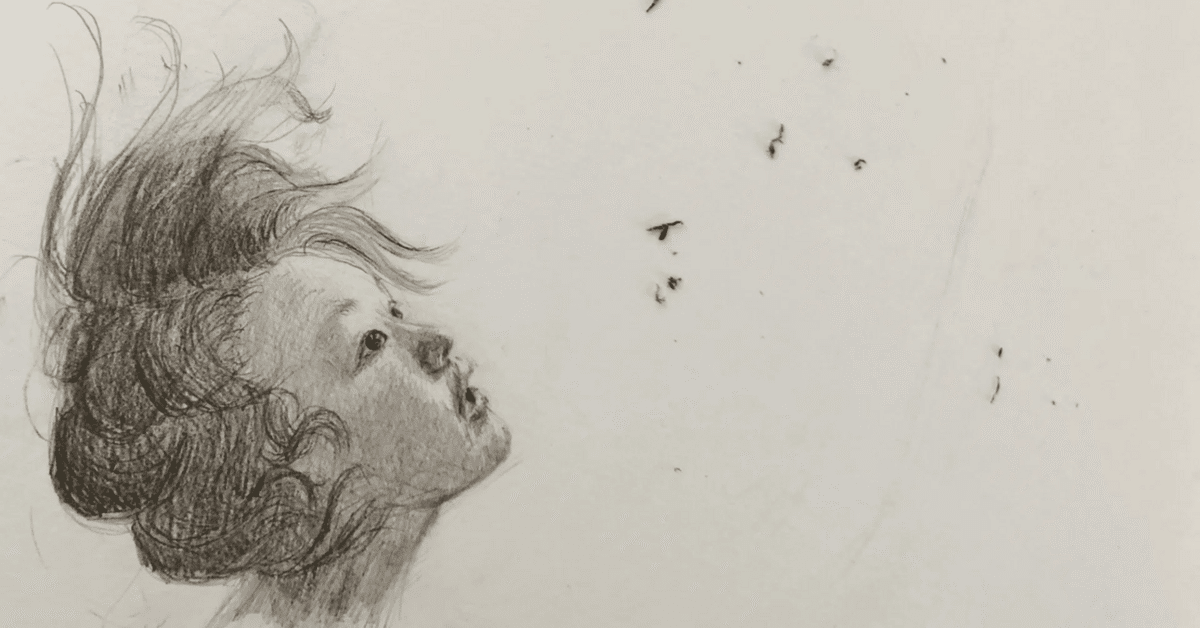
メソード演技の話

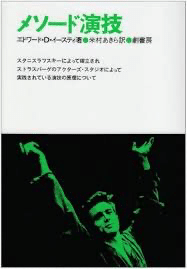



スタニスラフスキー・システムやメソード演技を習って育った俳優、女優の最大の欠点は、舞台上で自己に埋没してしまって作品全体の世界観から外れてしまうこと。つまり感情過多な状況に陥ってしまうことなんだが、ご多聞に漏れず私もこの悪しき癖をバッチリ持ち合わせた俳優風情です(笑)
しかしかつて読み漁ったこれらの本の中には、そうした感情想起に身を委ねるシステムの「有害性」をきちんと指摘した記述があり、ふと最近それを読み直しました。
例えばリー・ストラスバーグの「メソード演技」という著書には、冒頭の導入部ですでに、観客をより魅せる感情表現を実践するには体内リズムのテンポを調律することが大切であることが書かれている。
つまり、スタニスラフスキー・システムやメソード演技で身に付ける「架空の中で体得する実感」や感情表現などは所詮がその役者の素地(土台)に過ぎず、大切なのはそれから先の『表現』であるということなんだな。
「メソード演技」の生みの親である著者は、この本の中で役になり切ることで自身の体内に蓄積する感情をそのまま放散するだけでは、その演技が「商品」にならないことを冒頭ですでに語っているわけです。
この間、芝居の打ち上げの席で「新劇が必ずしもスタニスラフスキー・システムを実践しているとは限らない」というような話を数人がしていたのを耳にした。
まあその場はもう話に加わるのが面倒臭いので無視していたが、その話の主旨はこんな感じだった。
新劇の演出家や、新劇出身の先輩俳優、女優に演技指導を受けると「ココからアソコまで何歩で進め」だとか「このセリフのこの部分までを一息で。そこでアクセントを付けたらこの下りまでをまた一気に喋れ!」などの形骸要素をやたらと注文してくる。それはその役者の内面構築に委ねるスタニスラフスキー・システムの真髄ではない。
いやいや、無視して悪かった。遠くに阿保がいる顔をして聞き流して悪かったがそれは違うんだよ。
そうした新劇の演出家や先輩俳優の助言はすべて、システムの発案者であるスタニスラフスキー自身もその著書の中で語っているもので、このシステムをより深く習得した者だからこそその段階まで意識が及んでいると言ってよいんだ、これが。
「ココからソコまで何歩で歩く」ことを強することは、その芝居全体のリズム・テンポと、その役者の感情のリズム・テンポを融合させる為の「演出術」だし、セリフの言い回しまで指定されることは、その役者がその場で抱く感情と、その役者が演じる登場人物が作品中で抱いている感情をリンクして同化させるための「演出術」なのです。
私はこの辺りのことで、スタニスラフスキー・システムがあくまで万能でないことを思い知りました。
かつてはセリフの行間の「間」を何十秒と長く取って泣きの表現をしてみたり、セリフの語尾の笑いを長引かせて、返しの役者のセリフの入りを遅らせたりしていましたが、これらの暴挙、身勝手な振る舞いはすべてスタニスラフスキー・システムに傾倒したが為の弊害です。
己がその場で抱く感情のみに埋没して役を演じていても、それは真の意味で「役」になっていないことを、今更ながら気付いたのです。
そしてここに紹介する先人たちは、そのことを最初の段階で私たちに明示していたのですよ。
ちょっと齧った程度の知識でスタニスラフスキー・システムやメソード演技を教えようとする講師は今も昔も数知れず。そうした講師ほど「自身の感じたままに自由に…」というような「ゆとり指導法」で金稼ぎ、人望集めに躍起になりますが、少なくともこの国でスタニスラフスキー・システムを最初に導入して鍛錬、継承を続けてきた新劇の後継者はそうした部分にも着目して指導を行なっていると考えて良いかと思います。
皆さん、感情表現が好きですね。僕もそうです。
だったら指導者はよりよく選別しましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
