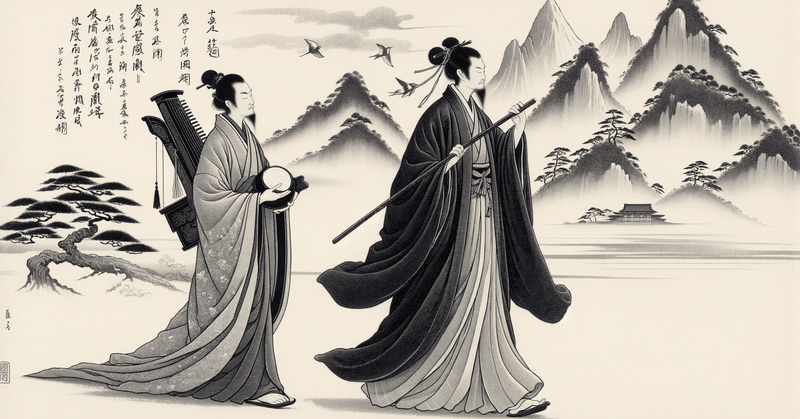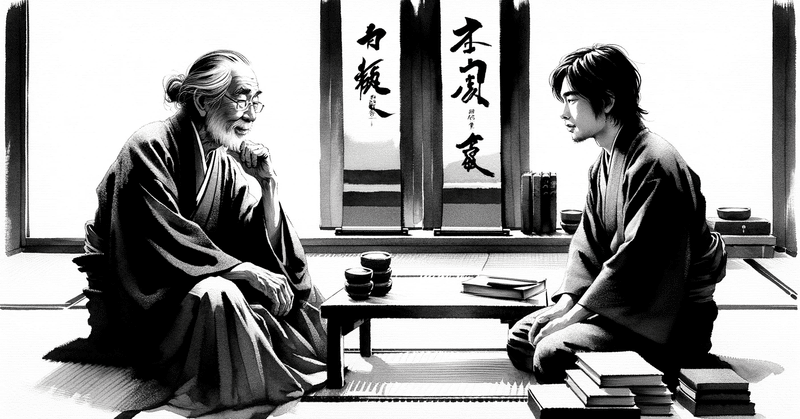「どう生きるのか?」よりも、知りたいのは「生きるとはどういうことか?」だ。
「自分(わたし)らしさ?」よりも、知りたいのは「自分(わたし)とは何か?」「なぜ自分(わたし)は存在し…
¥390 / 月
- 運営しているクリエイター
2024年1月の記事一覧

映画『さまよえ記憶』(脚本・監督・プロデューサー:野口 雄大) 幸せな記憶というものがあっても、記憶の幸せというものはない。
映画『さまよえ記憶』(脚本・監督・プロデューサー:野口 雄大) 予告編を見た時に、主人公の結末はきっとそうなるだろうな、というのが伺えた。でも、この映画は結末を知ることが目的ではない。もちろん、エンターテイメントとしての要素としては、結末は大切かもしれないが、本当に大切なのは監督が、映画というものを通して伝えたかったことなのかもしれない。 なぜ人には記憶というものがあるのだろうか。僕なんかはいつも悪い記憶に苛まれる。別に自分が呼び起こしたいわけではないのに、悪い記憶ばかり