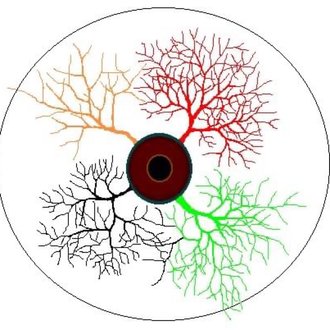★我楽多だらけの製哲書(13)★~時計が見せる意地のようなものとフォークナー~
去年のちょうど今頃起こった出来事を思い出した。
「19時まではまだ50分もあるから、もう一仕事できそうだ。」
私はそう思って、来週には持ち越したくない仕事を進めようとしていた。エンドレスで作業できる職場環境に長く身を置いていた私としては、去年の職場環境にまだ慣れていなかった。
これまで勤めてきた職場を振り返ってみると、20時になると形の上では退勤を促す声かけがなされ、それ以降残るためには「勤務時間延長願」を書いて出すことにはなっているものの、その延長願が拒絶されることなく、またかなり多く出ているからといって労務管理の観点から、勤務状況の改善についてのアドバイスがでることもない実質エンドレス容認の職場があった。その結果、私はいつも自分の最寄り駅の一つ先が終着駅となる0時50分発の終電に何とか乗り込んで帰宅する毎日であった。時折、その終電を逃してしまい、泣く泣くタクシーで6000円くらい出して帰宅することもあった。
他には、日曜日になると電子ロックが自動的にかかり一般職員のカードでは解錠できない職場もあった。ロックが自動的にかかるのは日曜日だけなので、他の曜日については何時まで残ろうがお咎めなしで、日をまたいで午前3時くらい帰るとき自ら電子ロックを設定したとしても、逆に午前2時くらいに出勤してきても電子ロックを解錠しても何も言われず、ここは本当の意味でエンドレスだったと言える。また日曜日になったとしても、部屋の中にいれば外に出ることは可能なので、そのまま何時間も粘ってから部屋を出ることはできたし、途中でトイレのため部屋を出なければならないときは、ドアに棒などを挟んで閉まらないように工夫すると、閉め出されることはないため、日曜の早朝まで残ったりすることも何度もあったと記憶している。逆に、月曜日になれば自分のカードで解錠できるので、月曜日になった瞬間の0時のタイミングで出勤したりもした。
それから、交代で24時間体制のセキュリティーに声をかけさえすれば、退勤するときはいつでも職場のカギを預かってもくれるし、出勤するときもいつでもカギを渡してくれるため、こちらもエンドレスだったという職場もあった。
これに対して去年の職場は、19時には勤務終了を知らせる音楽が鳴り響き、遅くとも19時30分には完全に撤退しなければならないのである。そのため、私にとって19時というのが仕事を切り上げる一つの物差しになっていた。しかし、これまで実質エンドレスというブラック職場の体質に慣れきってしまっていた私にとって、去年の職場の方が違和感を抱いていたのも事実であった。
それでも「郷に入っては郷に従え」の精神で、19時には仕事を切り上げようと努力を続けていた。その日もそのつもりで腕時計を確認して、「50分」という残された時間に集中力を注いでいたわけである。その後どれくらい時間が経ったのか正確には覚えていないが、ふと腕時計を見ると、「19時までまだ50分残っている」という状態だった。それはわずかな時間で2度時計を見たということではなく、しばらく経ってから時計を見たのに、私の腕時計は全く同じ時間を示していたのである。
「私の見間違いだろうか。」
さきほど見たとき「残り50分」だったのに、今も「残り50分」というのは変である。ただこのとき私の頭の中を余計に混乱させたのは、私の時計の設定方法が関係していた。特別な根拠はないのだが、普段私は通常の時間よりも8分ほど時計を早く進めている。そのため、本来ならば「19時まで残り50分」というと、「18時10分」を示すものだが、8分勝手に進めている私の腕時計は「18時18分」を示しているとき、ちょうど「19時まで残り50分」という計算になるのである。そうしていつも、自分の視界に飛び込んでくる腕時計の針が示す時間から8分遅らせるという脳内処理をして、私は実際の時間を判断しているため、その脳内処理をうっかり忘れて何となく時計を見たとき、自分が思っている以上に時間が進んでいると思って焦ることもなくはない。そんな面倒くさい脳内処理をしているものだから、さきほど見たとき「残り50分」で、今見たときも「残り50分」で同じだと思った自分の認識自体、いつもの「8分に関わる脳内処理」の判断ミスが関係しているのではなどと一瞬考えてしまった。しかし問題は「8分に関わる脳内処理」の問題ではなく、さきほど見た腕時計の「長針と短針の位置関係」と、今見た「それらの位置関係」が全く同じであるということに、走馬灯のような長そうで実は一瞬の混乱の末、気づかされたのである。
「腕時計が止まっている」
私はようやくその事実に気づいたのであった。見間違いではない。私は職場にかかっている壁時計を確認した。するとその壁時計はすでに「18時50分」を少し過ぎたくらいの時間を示していた。まだまだ時間があると思っていた私は、「もう10分も残っていない」という現実を突きつけられ、そのまま後ずさりして絶望の淵から突き落とされたような気分になってしまった。

ただこのような事態を全く予測していなかったわけではない。このような事態がいつか来ることを覚悟はしていたつもりだったが、あまり深刻に考えていなかったため、事態の訪れに当惑してしまったのである。
私の腕時計は数年前にシンガポールで購入したものであった。私がシンガポールで好んで訪れていた「リトル・インディア」というインド系の人々が多く住んでいる地域の雑貨屋で購入したのだが、その販売方法からして何とも怪しいものではあった。多く陳列されている様々なタイプの腕時計の中から3つを選んで、それで10シンガポールドルだったのである。当時の為替レートは正確に覚えていないが、1シンガポールドルは80円くらいだったと思うので、3つセットで10シンガポールドルは800円くらい、1つ当たりにすると、わずか265円程度だったのである。
しかも3つ購入して最初に使っていた腕時計(便宜上、これを「初代」とし、その後使った腕時計を「二代目」、最後の一つを「三代目」と呼ぶことにする)は、3日間くらいで動かなくなってしまった。そこですぐに二代目の出番がやってきて、それが数年間頑張ってきたのである。
そして去年の今頃、とうとう二代目が終わりを迎え、いよいよ三代目の登場となった。そうして三代目へ意識を向けようしていた矢先、改めて二代目の様子を見てみると、「長針と短針の位置関係」は変わっていないものの、彼の命の炎は完全に消え去っていたわけではなかった。細く伸びたもう一つの針、すなわち秒針は、彼の弱ってはいるが、しかし止まることなく打ち続ける心臓の鼓動の如く、わずかに右へ左へと動き、そこにまだ生命が宿っていることを訴えかけてくれていたのであった。

「待ってくれ。私はまだ終わっていない。終わっていないんだ。」
そんなうめき声のようなものが、かすかな鼓動の中から聞こえてくるように思えた。長針も短針も動かなくなり、現在の時刻を正しく示せなくなった二代目は、時計という機械としての役割を果たせなくなってしまったわけだが、今ここで、喘ぎ、もがき、必死で動き出そうしている姿は、単なる機械という存在から、一つの生命体としての意地のようなものを感じてしまったのはなぜだろうか。
「時計が止まるとき時間は生き返る」
これはアメリカの小説家で、代表作『響きと怒り』・『サンクチュアリ』・『アブサロム、アブサロム!』などで知られ、ノーベル文学賞も授業しているウィリアム・カスバート・フォークナーの言葉である。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?