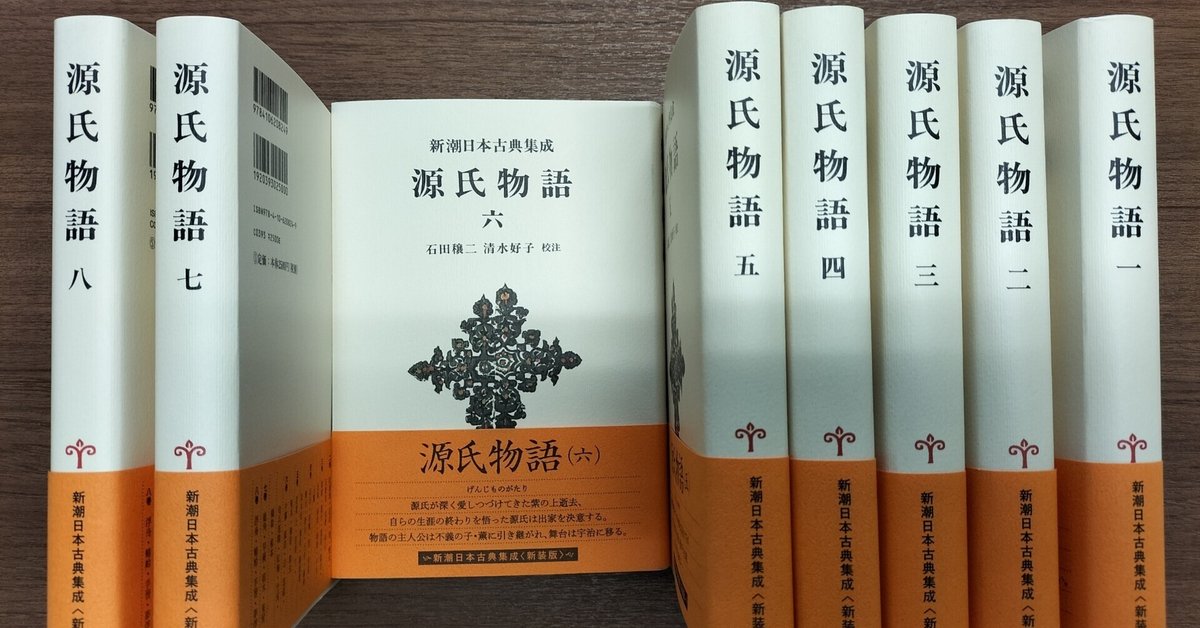
毎週一帖源氏物語 第四十一週 幻
ついにこの時が来た。
幻巻のあらすじ
傷心の源氏には、新春のめでたさも感じられない。対面する相手は兵部卿宮だけで、中納言の君や中将の君といった女房たちと昔語りをして過ごしている。高貴な身に生まれはしたものの、世のはかなさを知るように仏に導かれているという思いを深くする。
春になると、庭先の桜が次々に花開く。若宮は自分の桜が咲いたと喜び、木の周囲に帳台を立てて風を防げば花も散らないだろう、と得意になっている。源氏はそんな若宮の様子を見ながら、残りの日々の少なさを思う。入道の宮のもとを訪れると、受け答えが浅いことに落胆させられる。一方、明石の御方は思慮深く、さすがと思わせられる。衣更えの季節には、夏の御方とも歌の贈答がある。
賀茂の祭の日も、中将の君にたわむれかける以外は所在なく過ごす。五月雨の夜は、さらに無聊をかこつ。大将が訪れて、花橘を眺めながら昔を偲ぶ。六月に螢を眺めても、思い浮かぶのは長恨歌の一節である。七夕にも、逢う人のいない寂しさが募る。
八月は忌み月である。命日には曼荼羅を供養する。
神無月、雁の群れを眺めて黄泉の国を思い、夢でよいから亡き人の魂を捜してくれと幻術士に頼む歌を詠む。
歳末になり、「今はと世を去りたまふべきほど近くおぼしまうくるに」(150頁)、感慨は尽きない。大事にとっておいた文も焼かせる。仏名会では、源氏はようやく人々の前に姿を現す。大晦日、源氏はわが生涯も今日で尽きると悟る。
歳時記
この幻巻では、もはや大きな出来事は何も起こらない。紫の上に先立たれて現世への執着を失った源氏が、淡々と一年をやり過ごす。直接的には何も起きはしないのだが、短い記述を通して、これまでの四十巻でのあれやこれやが何となく思い起こされる。たとえば、賀茂の祭への言及があれば、葵巻での葵の上と六条御息所の車争いのことなどを思い出す。源氏をめぐる物語で、何も起きない季節など一つもなかった。あらゆる季節のあらゆる風物や行事を通して、源氏の生涯を思い出すことができる。歳時記のような巻であった。
紫の上を悩ませた女君
御法巻で六条院の女君たちが次々と姿を現すなか、女三の宮だけが不在だった。気にはなっていたのだが、あれはやはり意図的に排除されていたのだろうという気がしてきた。女三の宮は紫の上の苦悩のもとであり、最期を送る場に登場させないのが、作者の気遣いというものだろう。
この幻巻で、源氏は女三の宮を訪れる。東の対の庭先にある山吹が主の不在を知らぬように咲き誇っていると源氏が述べると、女三の宮は「谷には春も」(137頁)と答える。古今集に収められた歌の一句で、最後は「もの思ひもなし」で締めくくられる。出家の身にふさわしいとは言えるが、その超然とした態度が源氏には思いやりのなさにしか聞こえない。源氏はとうとう女三の宮とは心が通い合わないままだった。なぜ降嫁を受け入れたのかと、後悔の念にさいなまれたことだろう。自分のせいで紫の上の寿命を縮めたと思っても不思議ではない。
桐壺巻から幻巻まで
源氏が紫の上を偲んで憔悴するさまは、桐壺帝が桐壺更衣を悼む姿に重なる。亡き人の魂のありかを幻術士に捜し求める歌は、両者に共通する。
尋ねゆく幻もがなつてにても
魂(たま)のありかをそこと知るべく
大空をかよふ幻(まぼろし)夢にだに
見えこぬ魂(たま)の行方(ゆくゑ)たづねよ
これらの歌は、いずれも白居易の長恨歌をふまえている。唐の玄宗皇帝は最愛の楊貴妃を失い、その魂を道士に捜させる。その道士がすなわち「幻(幻術士)」である。
第一帖の桐壺巻と同じような構造が幻巻でも見出されることは、物語の終わり方(『源氏物語』の表現を用いるなら「とぢめ」)にふさわしい。実際、桐壺巻で生まれた光君(桐壺、第一分冊、41頁)は、幻巻を最後に出家する。その後には死が待ち受けており、光源氏の一生はこれで完結するのだ。
源氏の辞世――源氏は幸せな生涯を送ったのか?
歌がふんだんに盛り込まれているのも、この巻の特徴である。源氏が詠んだ歌だけでも二十近くある。ほとんどすべてが辞世の歌の様相を帯びているが、一つに絞るとすれば、やはり巻末に置かれたこの歌だろう。
もの思ふと過ぐる月日も知らぬまに
年もわが世もけふや尽きぬる
実に素直な詠みぶりで、現代語訳がなくても大意はつかめる。この一年も、わが生涯も、今日のこの日で終わってしまうのか、という慨嘆である。こうして源氏は物語世界から退場する。
一体、源氏は幸せな生涯を送ったのだろうか。本人の意識としては、それほどでもなかったようだ。高貴な身分に生まれ、須磨蟄居で不遇をかこった以外は何不自由ない暮らしだったはずだが、世のはかなさを思い知らされている。そうした述懐が繰り返されている。たとえば、次の箇所のように。
この世につけては、飽(あ)かず思ふべきことをさをさあるまじう、高き身には生まれながら、また人よりことに、くちをしき契りにもありけるかな、と思ふこと絶えず。世のはかなく憂きを知らすべく、仏などのおきてたまへる身なるべし。
鏡に見ゆる影をはじめて、人には異(こと)なりける身ながら、いはけなきほどより、悲しく常なき世を思ひ知るべく、仏などのすすめたまひける身を、心強く過ぐして、つひに来(き)し方行く先も例(ためし)あらじとおぼゆる悲しさを見つるかな〔……〕
源氏は、ものごころがつく前に母である桐壺更衣を亡くした。その後も、育ててくれた祖母を亡くし、慈愛に満ちた父・桐壺院を亡くし、母の面影を求めて愛した藤壺を亡くした。そして今、苦楽を共にした紫の上に先立たれ、一人残されている。長生きした分だけ、ひとより多くつらい目に遭ってきたのである。その悲しみは、高い身分に生まれついても、多くの女君と逢瀬を重ねても、癒されることはない。
源氏の生涯が不幸だったとは言えないまでも、満たされることはなかったとは言えるのではなかろうか。
雲隠
幻巻のあとに、名のみ伝わって本文のない「雲隠(くもがくれ)」という巻が置かれている。字義通りには「雲に隠れて見えなくなること」を意味するが、比喩的には「高貴な人の死」を表す。『源氏物語』においては、光源氏の死を象徴する。
ここで私は、百人一首に収められた紫式部の歌を思い出す。
めぐりあひて見しやそれともわかぬまに
雲がくれにし夜半(よは)の月かな
この歌は人の死を詠んだものではない。月が雲に隠れて見えなくなった情景を描いている。だから直接の関係はないのだが、偶然の符合としてはおもしろい。
千年の形見
この物語が書かれてから、千年が経った。
源氏は紫の上からの文を手に取って、二十数年前に書かれたものなのに墨つきが新しいように見えることに感慨を覚える。そして、「げに千年(ちとせ)の形見にしつべかりける」と洩らす。そういえば、御法巻でも繰り返し紫の上と「千年(ちとせ)」をともに過ごしたかったのに、と述べていた。物語の伝承という形ではあるが、源氏の望みは叶えられたのだ。
