
Books, Life, Diversity #28
全然本題ではないのですが、先日、生まれて初めて著作権使用料なるものをいただきました。自分の書いたものに対して、内輪以外からお金をもらうのは生まれて初めてなので、子どもみたいな感想ですがとても嬉しかったです。研究者として、書くということ(研究するということ)とその対価を安易に結びつけることについてはセンシティブであるべきです。ただ、私自身はこれまでどうにかこうにか民間で働いて食べてきたこともあり、作るものとその対価という意識は、良くも悪くも私の周りの研究者仲間より強い方だと思います。端的に言えば、きみの書いた論文って幾らの金銭価値があるの? ということです。これ、研究の本質なのでしょうか。うーん。
でもその善し悪しはとりあえず置いておいて、人文学研究にとって非常に重要な「本」というアウトプットを考えると、普段私がぼやっと読んでいるそれぞれの書の「商品としての価値」(ほんとうに微妙な表現ですが)を生み出すための出版社や編集者の努力は、凄まじいものなのだよなあということを強く感じています。そしてやっぱり、私にとってのリアルな研究というのも、その辺りにポイントがありそうです。まあいずれにせよ、まずは書かなければどうしようもないのですが……。
+ + +
先日、再び西荻窪にある本屋ロカンタンに行き、面白い本を何冊か入手しました。アマゾンで本を買うことを止めたいま、ロカンタンさんは本を購入する最重要ポイントになっています。西荻窪は活力のある街なので、心はいつもゾンビな私には眩しすぎて厳しいのですが、やっぱり本は本屋さんで直接手に取ってみるのがいちばん楽しいですよね。今回は『植物園の世紀―イギリス帝国の植物政策』(川島昭夫、共和国、2020年)など素晴らしくも美しい本を買えたので、それはまた紹介していこうと思います。今回は以前やはりロカンタンさんで購入した三冊について。
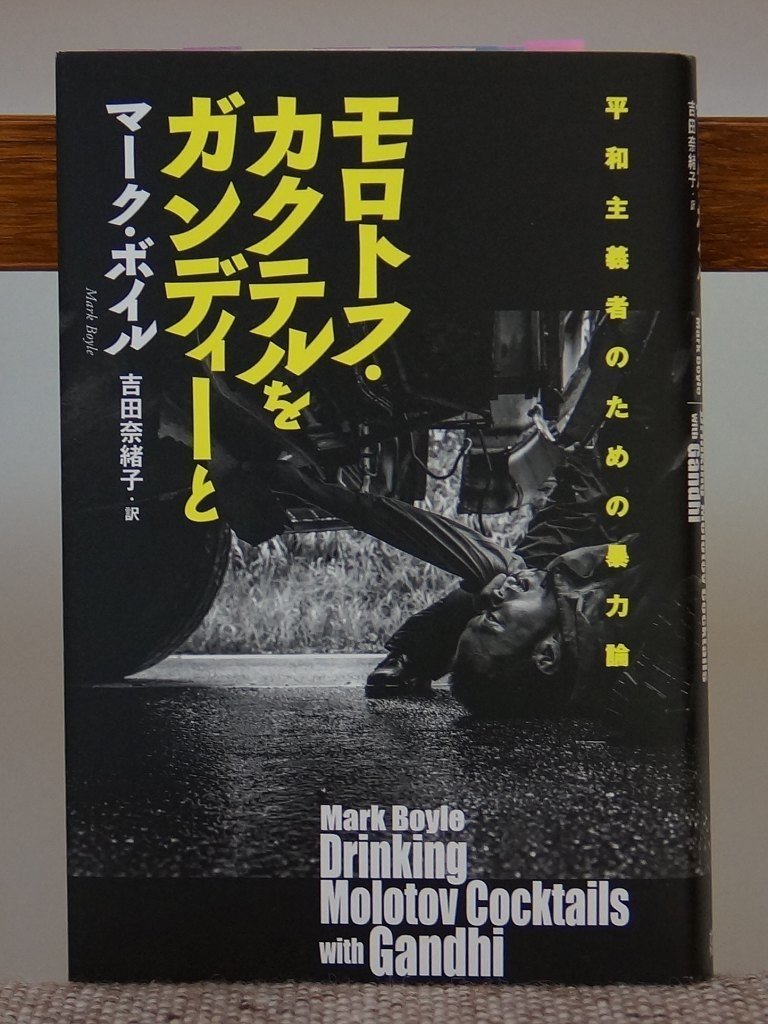
マーク・ボイル『モロトフ・カクテルをガンディーと―平和主義者のための暴力論』吉田奈緒子訳、ころから(noteはこちら)、2020年
本書は『ぼくはお金を使わずに生きることにした』(吉田奈緒子訳、紀伊國屋書店、2011年)などで知られるイギリスの活動家マーク・ボイルによる、暴力とは何か、真の平和を獲得するためにまず壊すことが必要な私たちの固定観念とは何かについて真向から探究している、まさにアクティビストの言葉らしい生きた思想の書です。モロトフ・カクテルとは簡易的に製造される火炎瓶のこと。このタイトルからして攻めている感じがしますし、著者の言いたいことが垣間見えます。
本書でボイルが主張していることは非常にシンプルです。私たちは普段、自然破壊や格差、紛争などの様ざまな悪や不幸を目にして心を痛めたり、あるいはネットで主張したり、フェアトレードの商品を買ったり、平和的な抗議活動に参加したりしています。だけれども、機械文明(ザ・マシン)という社会のなかで生活をしている私たちが、ある意味倫理的に、お上品にそれらの抗議活動や対抗運動をすることに、果たしてどれだけ意味がるのかとボイルは問います。それは無力なだけではなく、むしろその悪を(非暴力主義に囚われているが故に)結果的に見過ごしているのであれば、それ自体が悪なのではないでしょうか。無論、ここでボイルは単純に暴力を肯定している訳ではありません。まったくそうではない。けれど、倫理的に反対のポーズを取り続けることに潜む、それこそ倫理的な問題から目をそらしていることの問題性もまた、否定はできません。
中でも印象的なのは「クリックティビズム」に対するボイルの指摘です(p.201)。クリックティビズムとはクリックとアクティビズムの合成語です。ボイルはここで、私たちが不正義や悪を知ったときに、ネット上でクリックするだけで何か反対運動をしたような気分になってしまうことを批判をします。このように聞くと、多くの、真剣にそういったこと(クリック)をしている方は不快に感じるかもしれません。けれど私の場合、まさに研究の関心はここに、つまりネット上でのリアリティは何によって担保されるのかというところに関心があり、かつ現状をかなり批判的に見ている面があるため、ボイルのこの主張には深く頷けます。先にバトラーの本を紹介したときにも触れたように、私たちはそのクリックに意味を持たせられるほど、自ら何かを支払っているのでしょうか? これは誤解を受けないように強調しなければなりませんが、ネット上での署名などに対して真剣に向かい合っている人に対して、それが無駄であるとか偽善であるとか、単にそういう表面的な攻撃をして悦に入る、ということではないのです。それでも、活動家として自らの人生を賭けて試みてきたことに対してさえ客観的な視点から反省をしているボイルの問いかけは、やはりそれだけ重いものだと私は思います。
クリックティビズムがはやるのも不思議はなかろう。署名したすべての問題について何かをした気になれる一方で、すべての問題の元凶たる体制から生みだされるテクノロジーを享受しつづけられるのだから。(p.202)
これは、仕事以外ではほとんど家から出ることもなく、ひたすらネットに潜って何かを見た気になりメディア論や環境問題を語ってしまっている私自身にこそ、非常に鋭く刺さります。まして(研究では食べていけない)私のメインの仕事はプログラミングです。ザ・マシンの真只中でぬくぬくと暮らしつつ、お上品にアカデミックな形で社会を批判する。そういった限界をちょうど身に染みて感じているときだったので、本書はいっそう切実に読みました。
繰り返しますが、ボイルがここで語っているのは単純な暴力肯定論などではありません。まったくそうではなく、はじめに書いた通り、暴力とは何かという極めて哲学的な問いに対する、生き生きとした経験に裏打ちされた、そしてユーモアと愛に溢れた、魅力的で説得的な思想の書です。
なお、訳者の吉田奈緒子氏は他に『スエロは洞窟で暮らすことにした』(マーク・サンディーン、紀伊國屋書店、2014年)も訳していらっしゃいます。

これもまた素晴らしい本なのでお勧めです。
+ + +
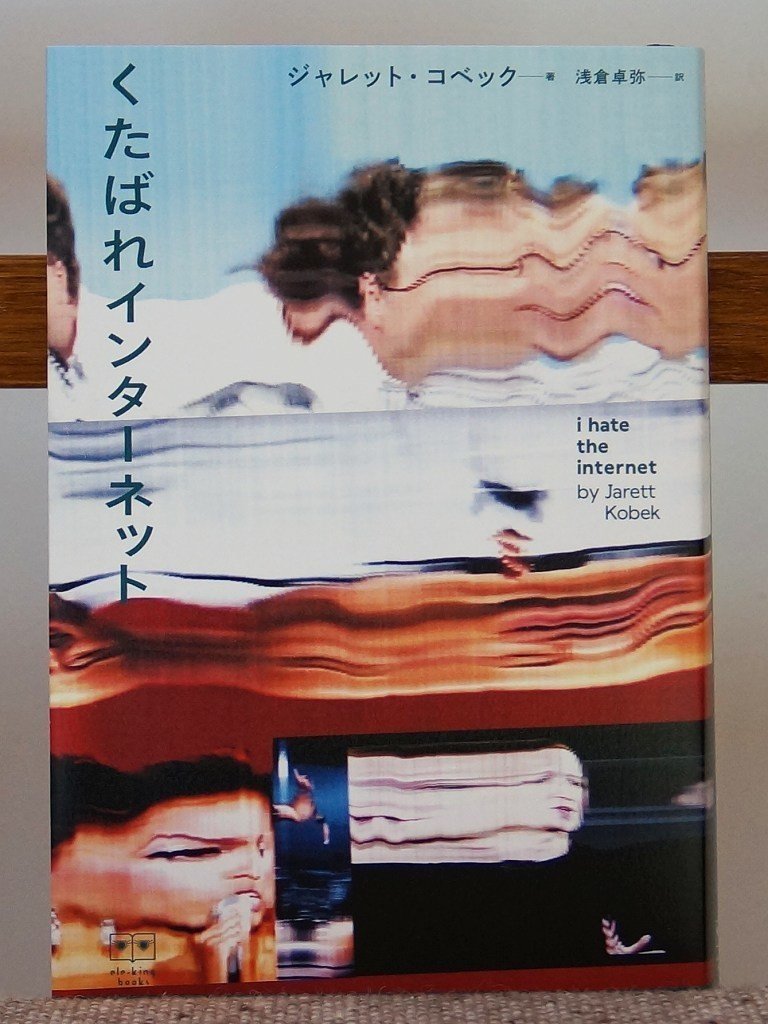
ジャレット・コベック『くたばれインターネット』浅倉卓弥訳、ele-king books、2019年
インターネット、そしてSNSをテーマとした小説です。語り口はかなりの、そして極めて意識的な破調に満ちたものですが、小説を読みなれている方であれば特に違和感なく読めると思います。例えば唐突に作者自身が現れて作品そのものに言及することも(これが凄く冷静な突っ込みで笑えるのですが)、いまでは実験的文体と思う人はいないでしょう。けれどもこれは本書への批判ではありません。むしろ本書のこの技巧的な側面は、取ってつけたような実験的文体としてではなく、インターネットあるいはSNSという制御できない何ものかを丸ごと表現しようとしている著者の型破りな取っ組み合いを、非常に魅力的に、その全体でもって表すための不可避の方法論として成功しています。
大まかなストーリーは、漫画の原作者としてペンネームでのみ知られていた主人公アデレーンが、あることをきっかけとしてSNS上での炎上に巻き込まれ……、というシンプルなものです。ただ、ストーリーは決してまっすぐ進むことなく、まるでインターネットで何かを検索している私たちがいつもしているように、あれを調べている途中でこれに興味が移り、こんどはあちらに関心が向き……、という感じで進んでいきます。しかしそれぞれの挿話は非常に面白く、物語の牽引力が損なわれることはありません。そして、炎上とは言いつつ、この主人公アデレーンの独特の――芯が強いというか、あくが強いというか――性格によって、何とも言い難い不思議な雰囲気のまま事態は進行していきます。でもラストはほろ苦く、混沌としています。
インターネットについて考えるのであれば、これはとてもお勧めの小説です。SFではなく、テクノロジーに寄りすぎることもなく、それでもここまで現代社会のある側面に肉薄して描き出している小説はなかなかありません。また、浅倉氏による翻訳は、恐らくネットスラング塗れであろう本書をよくもまあここまで訳したなあ、とひたすら感心するばかりです。労作ですが、労作であることを感じさせない良い翻訳だと思います。
ただ、これはあくまで私個人の無いものねだりなのですが、きょうたまたまギブスンの『ニューロマンサー』を読み直していたこともあり、黒丸尚氏が翻訳した本書も読んでみたかったなあ、と思ったのでした。ギブスンでもあり、ラッカーでもあり、どこかそんな雰囲気を思い出させる物語です。お勧め。
+ + +

『思想としての〈新型コロナウイルス禍〉』大澤真幸他、河出書房新社、2020年
本書については紹介しようかどうか非常に迷ったのですが、やはり触れることにします。
本書は、タイトルにある通り、コロナウィルス禍に対する人文系研究者や小説家の応答をまとめたものです。……ほんとうに「まとめた」だけのもので、誰が編者なのか、どのような意図でこの人選にし、どのような意図で編集したのか、一切説明はありません。まえがきもあとがきもなし。
全18篇からなる本書には非常に面白い章が幾つもあるのですが、けれどもその良さも打ち消されてしまうくらいに、そもそも何のために本書が編まれたのかが不明です。要するに、これは一冊の「本」とは言えないのではないか? というのが率直な感想です。
今回のコロナウィルス禍は、無論病気それ自体としても問題ですし、経済的にも文化的にも大きな困難を突きつけてきます。世界的な混乱と苦しみのなかで、私たちは普段意識していなかったような様ざまな根本的な問いにも目を向けるようになっています。国家とは何か、民主主義とは何か、自由とは、格差とは、人権とは何か……。そういったとき、人文学の果たすべき役割は決して小さくはないはずですし、それは人文学の責務でもあるはずです。何よりも本書はタイトルに「コロナウィルス禍」を掲げているのですから。
だけれども、手に取って読んでみると、そこには一貫した思想が何もない……。それぞれの思想をただ並置することによって現状をリアルに描き出す、という意図さえ感じられず、はっきり言えば、そんなものを練り上げる時間も惜しみ、ただ集められるだけ論考を集めて一冊の本という形に綴じただけに思えてなりません。
ただ、繰り返しますが、個々の論考には読むべき優れたものが多々あるので、本書そのものはお勧めできます。様ざまな論点や観点がありますし、とっかかりとしても優れた本だと思います。個人的には大澤真幸氏、與那覇潤氏、木澤佐登志氏(木澤氏は次回紹介したいと思っているニック・ランド『暗黒の啓蒙書』の序文を書いているので、また触れることになります)、小泉義之氏による章が、いまの自分自身の興味関心にも合っており興味深く読めましたし、その他にも興味深く読んだ章が幾つもあります。
ただ、その良さは読む人によって、あるいは個々の章の著者によって生みだされるもので、この本を編集し世に問う側の無責任がそれによって免ぜられるようなものではないと、私は思います。本に命を与えるはずの全体性がそこで破れてしまっている。だから、本書のコンセプトがまったく見えない、見せる気もないということについては批判的にならざるを得ませんし、こんなことをやっていては人文学は自死するしかないと危機感さえ覚えます。
この一連の投稿("books, life, diversity")は、本来、コロナウィルス禍、そしてそれに伴う政治的・社会的な問題の顕在化によって引き起こされた出版文化の危機に対して、少しでも本という文化の素晴らしさを伝えられればというところから始めたものですので、批判するような本であればそもそも取り上げたくはないのです。けれども、何度も繰り返しますが、個々の論考には本当に面白いものがありますので、購入自体はお勧めできます。ただ曲がりなりにも――野良研究者とはいえ――人文学の片隅にいる人間として、この本自体の在り方には納得がいきません。
そしてそこから見えてくることは、当然のことではあるのですが、良い本というものは決して著者だけによって生みだされるものではなく、優れた編集者の明確な意図によってこそ作られるものだ、ということなのだと思います。本当に、言うまでもないことなのですが。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
