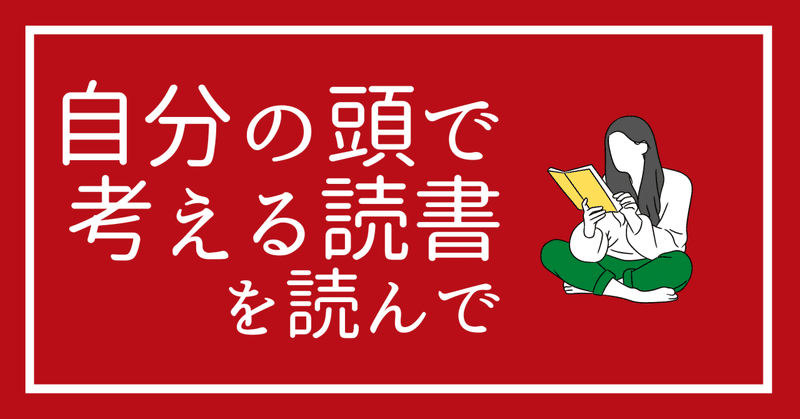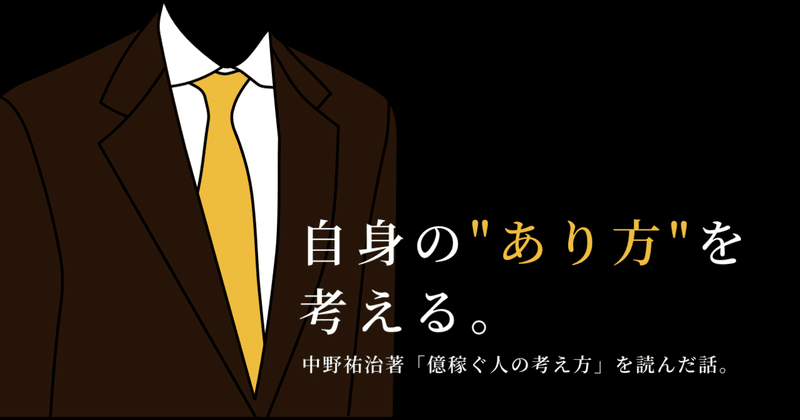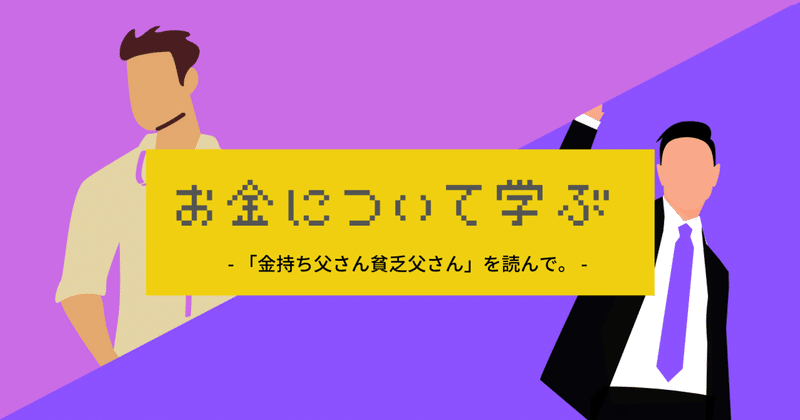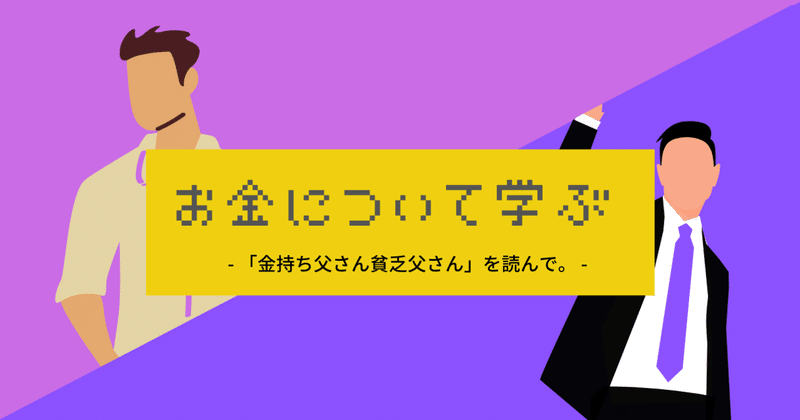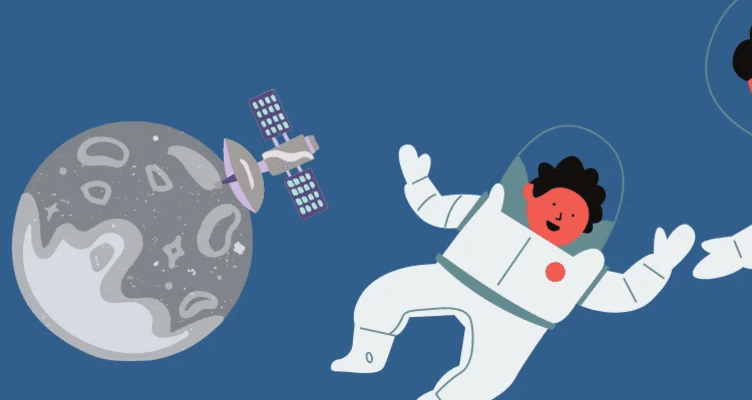
面白くてためになるビジネス書の紹介を通じて、ビジネススキルの向上やキャリアに役立つアイデアをまとめています。書籍を通して考え方にどのように影響を与えたかを共有し、読者の仕事や人生…
- 運営しているクリエイター
#読書
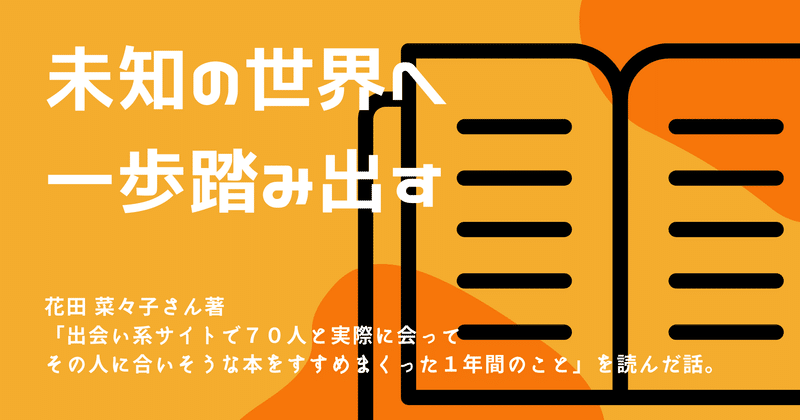
未知の世界へ一歩踏み出す。花田 菜々子さん著「出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと」を読んだ話。
久々に夢中になって本を読みました。 今回読んだのは、花田 菜々子さん著「出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと」です。タイトルの「出会い系サイト」で「本をすすめる」という違和感のある言葉の組み合わせが気になって手に取りました。 本記事では読んでいて面白いと感じたポイントを3つにまとめました!それではどうぞ! あらすじ本の内容は、タイトルにある通り、主人公の「花田さん」が出会い系サイトで出会った方に本をすすめる、というものです