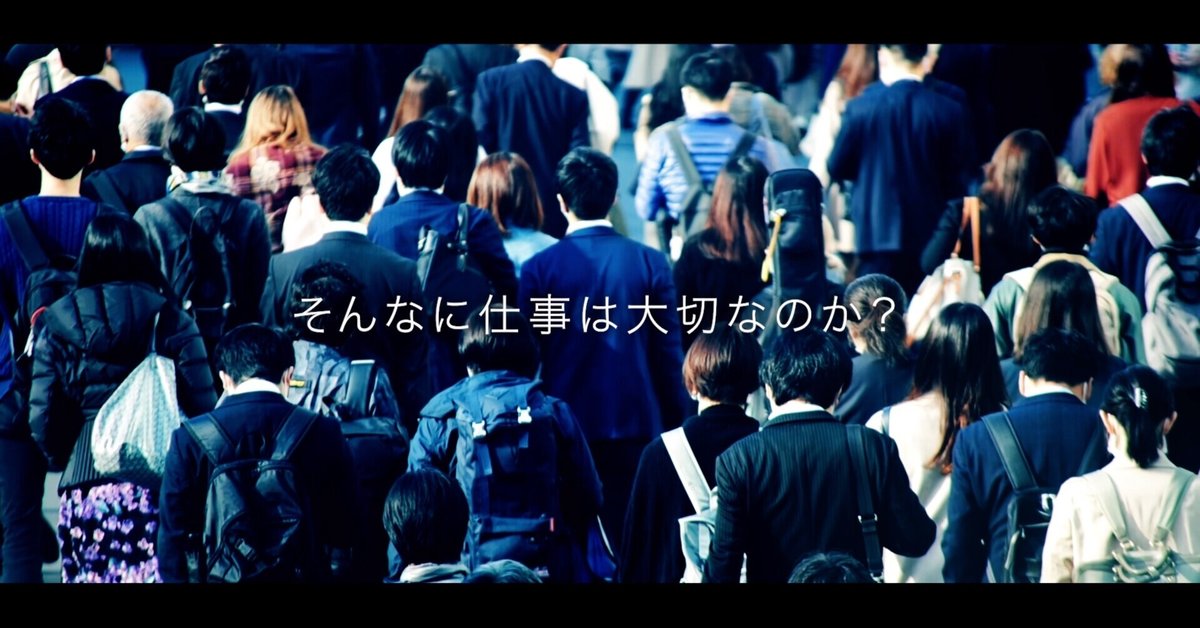
人材流動化主義 経済論
こんにちは、体験入社事務局です。
本日は、弊社CEO 松本の記事をお届けします!

【株式会社体験入社 代表取締役CEO 松本聖司】
株式会社リブセンスで、転職ナビ事業セールスコンサルティンググループを統括。SQLデータ分析・サービス企画、求職者サポートチーム立上げを務める。その後「仕事のリアルな情報が見られる転職サイト『体験入社』」を自身でサービス開発、2019年11月に株式会社体験入社を設立。株式会社リブセンス以前は、株式会社キャリアデザインセンターにて営業職・営業課長を経験、年間の最優秀営業賞を受賞。
体験入社の松本です!
株式会社体験入社を設立して約1年半がたちました。
起業をして1年半たち痛感してるのが、会社が長期的に成長するためには、
社会課題を解決して、社会に必要不可欠な存在になることが必要だということです。
そこで「採用」「転職」が解決する社会課題について考えをまとめました。
人材流動化主義 経済論
労働力人口の減少、GDP成長率の低下、デフレの長期化など、日本経済には問題が山積みです。平均であと60年は生き続ける20・30代の私たちにとって、必ず解決しなくてはならない問題です。
日本経済の問題を解決するために様々な政策が実施されています。その一例として金融政策があります。
2013年から日本銀行はデフレ脱却を目指し2%の物価安定の目標を掲げ、異次元の金融緩和を実施しています(これがいわゆるアベノミクス「大胆な金融政策」です)。しかし、8年経過した今でも2%の物価安定目標が達成されていません。
※デフレが良くない理由を簡単に
デフレだと企業は、商品・サービスの価格を上げられないため、売上を伸ばすことが難しいです。そして、設備投資や私たちの給与である人件費を抑制します。給与が上がらないと人々は消費を抑えます。消費が抑えられると企業は商品・サービスの価格をさらに下げて消費を促します。この負のスパイラルがデフレスパイラルです。
8年間も実施した金融緩和の成果は何なの?と感じると思います。
金融緩和の主な成果は「株高」と「企業の内部留保(利益余剰金)の増加」で、私たちが感じる実体経済への成果は低いと考えてます。
事実として給与(実質賃金)はほとんど伸びていないため、消費も向上せずデフレが継続しています。結果、金融緩和の成果を実感しているのは、富裕層の人々です。金融緩和後に1000万円以上の高級外車の販売数は倍増しています。
※実質賃金指数の推移の国際比較(出典:全国労働組合総連合資料データ)赤色が日本です

つまり、金融政策では一般の人々は経済効果の恩恵を受けづらいと考えてます。一般の人々が経済効果を実感するためには、金融政策より人材の流動化です。人材の流動化こそ、経済成長のエンジンになります。
なぜ、人材の流動化が経済成長に効果があるのかを説明します。
あなたは、何市(何区)に住んでいますか?
ちなみに、株式会社体験入社の本社は鎌倉市です。
もし、私が100万円を持っているとします。

その100万円が鎌倉市でしか使えなかったらどうでしょう?
普通に困りますね。
全国(世界)で使えるから、今の100万円の価値が生じてます。
・鎌倉市でしか使えない100万円
・全国(世界)で使える100万円
であれば、後者の方が価値のあることは一目瞭然です。理由は、後者の方が流動性が高いからです。
これを人材のスキルに置き換え、考えてみます。
・あなたが今働いている会社だけで活かせるスキル
・どこの会社でも活かせるスキル
では、どちらの方が価値があるでしょうか?
どこの会社でも活かせるスキルですよね。

つまり、自分の市場価値を向上させたい場合は、
今いる会社だけで活かせるスキルよりも他の会社でも活かせるスキルを身につける必要があります。
一番良いのは、今いる会社で活かせるスキルが他の会社でも活かせることです。ITエンジニアなどの専門職がそのパターンになることが多いです。
このように、人材(スキル)の市場価値は、流動性の高さにより決まります。
それでは、社会の人材の流動性を高めるにはどうしたら良いのでしょうか?
それは「より多くの人が、より多くの会社(自社も含み)から必要とされるスキルを向上させる」ことです。
より多くの人のスキルが向上して、人材の流動性が高まれば日本経済は成長します。金融政策より、スキル向上による人材流動化の方が、実体経済にはよっぽど効果的だと考えます。
【経済成長のスパイラル】
多くの人のスキル向上
⇩
多くの会社で成果が高まり売上向上
⇩
多くの人の給与上昇
⇩
多くの消費が促進
⇩
多くの会社の売上向上
⇩
多くの人の給与上昇
金融緩和政策により、市場に大量のお金を供給しても、企業が人材に投資(自社社員の給与上昇、外部人材の採用など)をしない限り実体経済への効果は出づらいです。
なぜ、企業は人材に積極投資をしないのでしょうか?
それは「投資をしない」ではなく、「投資をしたくてもできない」からです。
自社社員でも外部の人材でも、投資対効果が高い人材がいれば必ず積極投資をします。しかし、そういった人材の数が少ないのです。企業の需要に対して、圧倒的な供給不足であるのが現実です。これは「社会全体のスキル不足」とも言えます。今話題の、DX人材が分かりやすい例だと思います。
より多くの人が、より多くの会社(自社も含み)から必要とされるスキルを向上させ、人材の流動性を高めることが、これからの日本経済には必要不可欠です。
スキルを向上させるためには、“仕事の喜び”を感じることが重要であると考えてます。
私たちは、1日のほとんどを仕事に使っています。
これは、家族や友達と過ごす時間よりも長いかもしれません。

そんなに仕事は大切なのでしょうか。
正直、私も仕事をするのが嫌な日もあります。
仕事を辞めたいと思う時もあります。
でも、私の今までの人生に仕事が無かったら
大切な仲間に出会えてなかったかもしれません
自己成長できなかったかもしれません
人生について真剣に考えてなかったかもしれません
ビールがここまで美味しいと感じなかったかもしれませんw
大切なことは目に見えません
それが「仕事の喜び」だと思います。
あなたはどんな時に「仕事の喜び」を感じますか?
実は、仕事は人間の本質的欲求を満たす素晴らしいものです。私も今までの仕事の経験を通じて、それは実感しています。
人間の本質的欲求については、アブラハム・マズロー氏が「欲求5段階説」にて提唱してます。(欲求5段階説は、キャリアコンサルティング理論でも活用されてます。また、経営学・教育学など様々な領域にも大きな影響を与えてます。)
【欲求5段階説】
1 → 2 → 3 → 4 → 5 の順番で1つの欲求が満たされると、次の欲求を満たそうと欲求のレベルが高まっていきます。高いレベルの欲求が満たされることにより幸福感が高まります。
【1】 生理的欲求
→食欲、睡眠欲、性欲など
【2】安全欲求
→暮らしの安定、経済の安定、健康の安定
【3】所属と愛の欲求
→社会・会社・友人との繋がり、家族・恋人との愛
【4】承認欲求
→自己成長・達成欲、他者からの承認欲
【5】自己実現の欲求
→自分の持つ能力を発揮して自分らしさを表現したいという欲求
仕事でお金を稼げば、食欲を満たしたり、安定的な暮らしを実現できます。
そして、仕事を通じて社会・会社と繋がり、仲間もできます。
仲間と協力して目標を達成することで、自己成長・他者承認を得ることもできます。
極めつけは、仕事を通じて自分らしさ・アイデンティティを表現することができます。

人は単にお金を稼ぐために仕事をするよりも、自己成長や人から認められたり、自分らしさ・アイデンティティを表現できる仕事をすることの方が幸福感を味わえます。
大切なポイントがあります。「【4】 承認欲求」以降は、スキルが向上しないと満たすことが難しいです。なぜなら、スキルの向上なしには自己成長や目標の達成ができませんし、周りから認められる成果を出すことも難しくなります。
今、自分のスキルを最大限に活かせていますか?
今の会社でスキルを最大限に活かせていないと感じていたら、
・今の会社でどうやったらもっとスキルを活かせるか?
もしくは、もっと伸ばした方が良いスキルは何か?
を考えた上で
・他の会社だったら自分のスキルはどのくらい活かせるのか?
もしくは、もっとスキルを伸ばせる環境があるのか?
と考えるのも、自己分析のために良いと思います。私たちも求職者さんの転職サポートをする際、まず転職を前提で考えるのではなく、自社での可能性をもう一度分析して、それが難しかったら転職を考えていただくようにしてます。
しかし、他の会社の方がスキルを活かせそうか?もっとスキルを伸ばせる環境があるのか?を確かめるのが難しいという問題があります。
原因は、確かめるために必要なリアルな情報の開示が少ないからです。具体的には「実際の仕事内容」「一緒に働くメンバーの人柄、社風」「働き方のスタイル(労働環境)」といった3つの情報です。
スキルを活かすためには、第一に仕事内容がフィットする必要があります(スキルフィット)。
しかし、スキルフィットしていても一緒に働くメンバーとの相性が合わなければスキルを活かすことが難しいです(カルチャーフィット)。
働き方のスタイルも同じです。労働環境や裁量などが合わなければスキルを活かすにあたり障壁になります。
つまり、3つがフィットすることで、スキルを最大限に活かせる可能性が高まります。
しかし、求人情報の文章だけでは、「実際の仕事内容」「一緒に働くメンバーの人柄、社風」「働き方のスタイル(労働環境)」のリアルを確かめることが難しいです。転職活動で3つのリアルを確かめられないことで起きる主な事象は2つです。
・1つ目は、「不安」になり転職できない
・2つ目は、転職したがミスマッチ
実際、私も10年間の人材業界の経験を通じて2つの事象を目にしてきました。また、3つの情報取得の不足によりミスマッチが発生してることは「独立行政法人 労働政策研究・研修機構」の調査データから見ても自明なことです。
※出展:独立行政法人 労働政策研究・研修機構「早期離職の理由」

「不安」になり転職できない
転職しても今の会社より良くなるか?という「不安」があると、なかなか動けません。この「不安の解消」こそが人材流動化の鍵を握ります。そして、これからの日本経済の成長の鍵になります。
私たち“株式会社体験入社”は、求人情報市場を革新して転職活動時の「不安の解消」することで人材の流動性を高め、適職に巡り合う人を増やします。
人は適職に巡り合うことで、給与、一緒に働く仲間、やりがい(自己実現)などの満足度が高まり、仕事や人生に対する「不安」も抑制されます。
そうすると、仕事とお金に対して積極的になり、仕事ではさらにスキルを向上させてのチャレンジ、お金も貯蓄より消費・投資に回す傾向が強くなり、人とお金の流動性が高まりさらに経済は成長します。
実はこの現象、2010年に日本を抜きGDP世界2位となった中国では起きてると思ってます。今後、中国はさらに経済成長をしてGDP世界1位の米国を脅かすでしょう。今はGDP世界5位のインドも経済成長が著しいです。2028年には日本を抜き世界3位になることを多くのシンクタンクが予測しています。
中国、インドの人口は約14億人。
日本の人口は約1.2億人。今後はさらに人口減少していきます。
数では勝負できません、日本が先進国であり続けるためには、
一人一人の質で勝負です。
以上、私たちが考える「人材流動化主義 経済論」です。
仕事のリアルな情報が見られる転職サイト『体験入社』、
『体験入社』で提供している「体験入社動画」にはこんな想いが詰まっています。
■体験入社ミッションムービー「仕事の無い人生は、つまらない。」
■体験入社動画は、東証一部上場企業やメーカー・IT企業に導入いただいています
求人の文字だけでは求職者が欲している情報である「実際の仕事内容」「一緒に働くメンバーの人柄、社風」「働き方のスタイル(労働環境)」を伝えることが難しいです。『体験入社動画』は、体験入社モデルが企業に1日体験入社をして求職者が欲しているリアルな情報をお伝えします。
