
伊賀紀行4 「芭蕉足跡 記念館と俳聖殿編」
今回は、「芭蕉翁記念館」と「俳聖殿」をたずねます。
いずれも上野公園のなかにあります。

記念館入館料は300円ですが、「蓑虫庵」と「芭蕉生家跡」の三個所共通券だと、たしか700円でした。私はセット券にしました。

記念館ではちょうど「令和6年度企画展 芭蕉と源氏物語」を開催中でした。

記念館の建物は、明るくこぢんまりとしています。
奇をてらった様式でないのも雰囲気いいです。

[芭蕉と源氏物語]について
「NHK大河ドラマの影響で源氏物語が脚光を集めています。芭蕉さんとは無関係と思われるかもしれませんが、実はそうではありません。芭蕉さんたち江戸時代の俳人にとって、源氏物語をはじめとする古典文学は必須の教養であり、創作の源泉にもなっていました。」(企画展チラシより)
「芭蕉は、伊賀で藤堂新七郎家に仕え、俳諧に出会ったころ、貞門俳諧に親しんでいました。貞門俳諧は、源氏物語を含むさまざまな古典をふまえて句を詠むため、知識が必要で、このころ多くの作品に出会ったと考えられます。芭蕉は、江戸時代を通じて愛用された源氏物語の注釈書『源氏物語湖月抄』を執筆した北村季吟に教えを受けたともいわれ、若いころに見つけた古典文学の知識を大切にしながら、生涯作品を生み出し続けました。」(企画展チラシより)
なお、展示物(文書資料含)の写真は撮ってません。

古典文学の学びの壁が高いので、私が真似できそうなのは、とりあえず「旅」ですな。
芭蕉さんは「旅の詩人」「漂白(さすらい)の旅人」といわれ、すんごい旅好きでしたからね。外形的には真似できそうです。
旅人と我名よばれん初しぐれ 芭蕉
[芭蕉さんの主な旅]
「野ざらしの旅」 門人千里(ちり)と近畿地方へ
「鹿島詣」 曽良と宗波を伴い鹿島詣へ(鹿児島ちゃうよ)
「笈の小文の旅」 上野帰郷、吉野・大和巡遊、須磨・明石遊覧
「更科の旅」 越人が同行し木曽路を経て美濃、信州更科へ
「おくのほそ道の旅」 曽良を伴い行程六百里、百六十日間の長旅へ

芭蕉さんの旅姿は、「僧形」「一笠一蓑(いちりゅういっさい)」であったと。
その旅姿を建築に表現したのが、「俳聖殿」です。俳聖殿は、記念館から歩いてすぐ。移動途中にある忍者博物館には、今回立ち寄りませんでした。





芭蕉座像のお姿見えませんので、さらに具体の芭蕉さんの旅姿のイメージをふくらませるため、昔(令和三年度)記念館に来たときの企画展チラシをひっぱりだします。



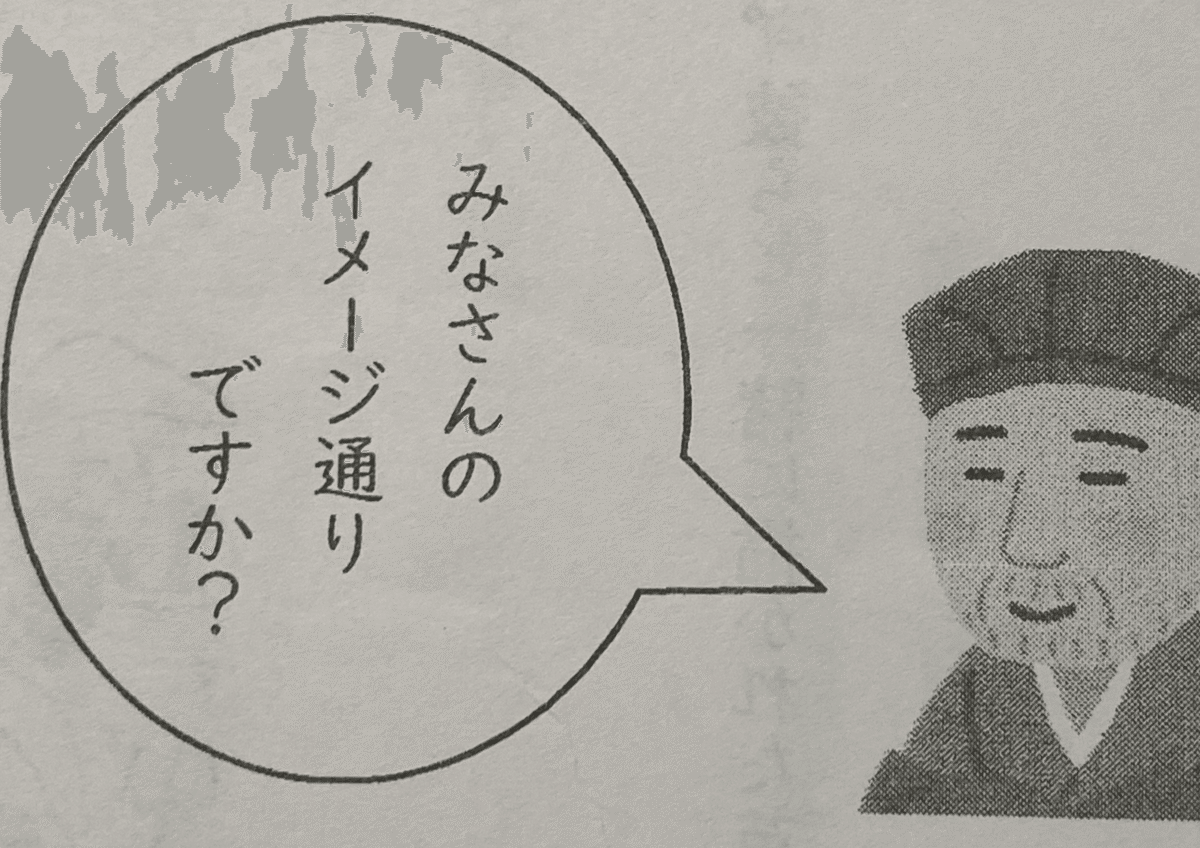
次回「伊賀紀行5」は、芭蕉さんが処女出版「貝おほひ」を奉納したという「上野八幡宮」をたずねます。(まだ続くんかい! 一応「7」まで予定)
2024.5.26
(2024.5.31記)
