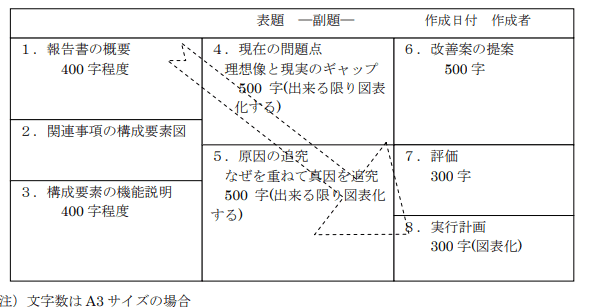思い込みが変わったこと その二
私の二つ目の大転換は
技術屋->事務屋
であった。私の20代は、マイクロプロセッサによる、監視制御装置のソフトウエア開発で、いくつかの分野で標準化などで、成果を出していた。例えば、同業他社が同じ規模の増設改造に、10人が1ヶ月かかる現地作業を、3人で1週間で終える等の技術力による合理化を実現した。
こうした、技術者としての作業は、本質的には
物理学のように正解がある
問題の解決であった。数学の証明を行うように、決まった事項から、ち密にプログラムでの実現を考える。こうした発想で、技術者として成果を上げていた。
さて、私は30代半ばで、社員研修を行う総務部門に異動した。総務部門は、事務屋の世界であり
社会科学など文系の文明
へ考え方を切り替える必要があった。ここで
「論理的でない!」
と何度も批判された。そこでは、私も
技術者としての論理
はしっかり展開していたので、戸惑うことが多かった。この違いを理解するために
社会科学の議論法
について、色々と学ぶことになった。そこで
基本原理から展開する法律の発想
影響する事項を切り出す経済の発想
の思考法について、当時の上司から教わったことが転機になった。それまでにも、ヘイグの「理論構築の方法」小松・野中訳・白桃書房や、ヴィーコの「学問の方法」上村・佐々木訳・岩波文庫を読んでいたが、正直
「何を言っているのか解らない」
状態であった。
それでも、色々な文書を作っていくと、何となく
全体像を描きながら因果関係を示す
等のコツがつかめるようになった。特に、A3用紙一枚にまとめる訓練は、厳しいモノがあったが有効な方法であった。
こうして
議論の前提は人により異なる
従って
背景の説明も大切
という風に
技術屋の狭い発想から解放
されるようになった。
この変化は、10年ぐらいの長い時間をかけたが、自分の考え方は大きく変わったと実感している。