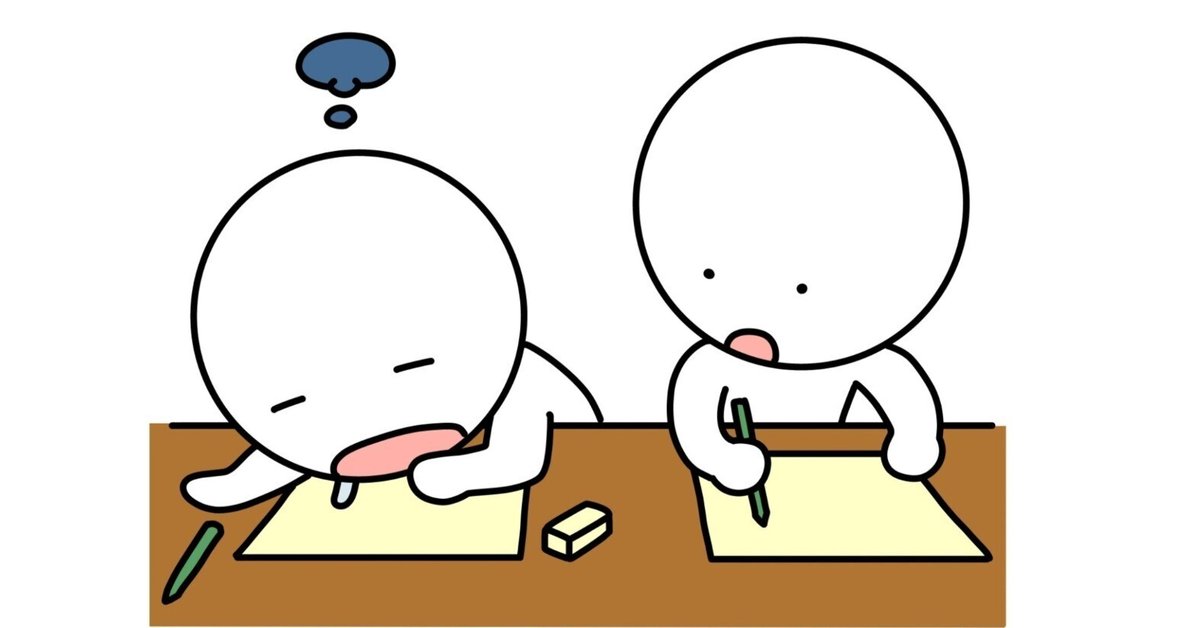
#131 読書日記19 学びの手法に特効薬はあるのか 逆向き設計

グラント ウィギンズ& ジェイ マクタイ (著)
西岡 加名恵 (翻訳)
結論は「子どもの可能性を信じる」ことか。
学校を卒業してしまえば、子どもは教師の手から離れてしまう。
恩師と思ってもらえれば、何かしらの接点はあるかもしれない。
教職を志す学生たちに志望動機を聞くと、大概は
「尊敬できる先生と出会い、自分も教師になりたいと思った」
といった物語を持っている。
私は自分の数々の失敗や至らなさを悔いて、贖罪として教師になったようなものだ。
先生方にさんざん面倒と迷惑をかけた罪滅ぼしだ。
一方で、親と子の関係性とはどうあるべきなのか考えることがある。
子は、この世に誕生した瞬間、母親とつながっていたヘソの緒が切れる。
それでも親は、見えない精神的な “ ヘソの緒 ” でつながろうと、愛情を注いだり叱咤激励しながら、そしてあれこれ思い悩む。

私は父親として出産経験がないので、精神的なヘソの緒で何とかつながろうとしてきた。
いつかは断ち切らなければならいヒモではあるが。
受験シーズン真っ盛りである。
志望校に合格するため必死で頑張り、悲壮感さえ漂っている受験生も少なくない。
親子共々、薄氷を踏む思いにかられる。
「息子さんはどうやって東大に入ったんですか?」と聞かれるが、それについて私が断言できる「これです、これ!」というものはない。
ひとつではないと言ったほうがいいかもしれない。
教職課程の学生とよく議論する。
抽象的な「モチベーション」「やる気」「頑張る」「努力」は数値化できない。
こころの内に宿る思いは個人差がある。
純度や熱量というとまた曖昧になる。
「頑張れ!」という抽象的な言葉が子どもを追い込むことにもなりかねない。
どう頑張ればいいのかわからないから負のスパイラルにハマっている子も多い。
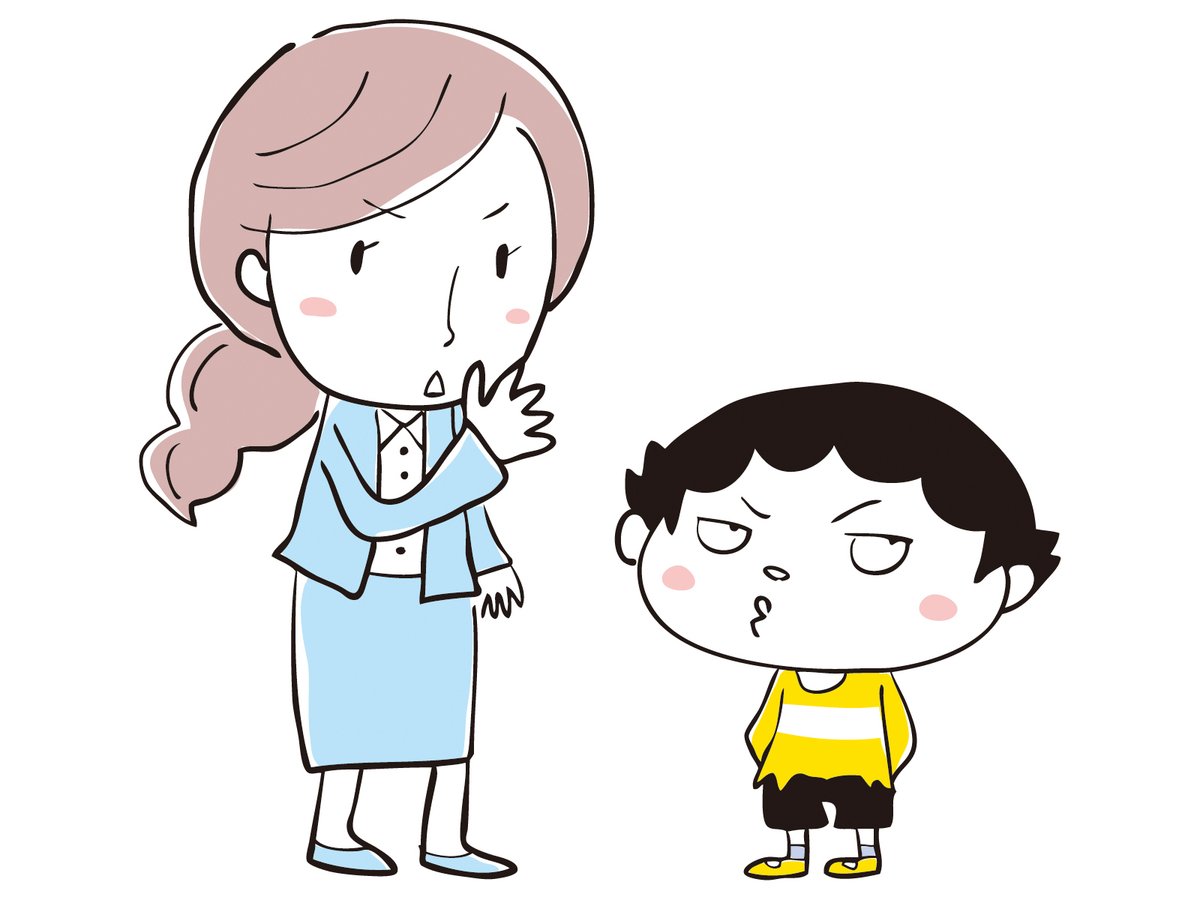
どうすればいいんだ?
教育の手法や学びのあり方の正解ってどこにあるの?
教えて、教えてセンセー!・・・・と、学生にせがまれる。
正解なんてあるのか?と思うことがある。
客観的な評価とは、はっきり数値化できる認知能力としての「成績・得点」「偏差値」「合格可能性」だけである。
ただし、テストの質の善し悪しで若干のズレは生じる。
数値データは到達度を示しているが、受験においては確率・可能性として用いられる。
運まかせでなく「確かな力」をつけるために必要なことはあるはずだ。
私たちは数値化できないものに不安を感じたり疑念を抱いたりする。
「これでいいのだろうか?」
「大丈夫なのか?」
周囲は
「大丈夫!ダイジョーブだぁ~」
「自分を信じるんだ!」
「全力を尽くせ!」
と言う。

抽象的で曖昧な言葉によって勇気づけられる子もいれば、迷走する子もいる。
ダメだったらメンタルをフォローする。
勉強法、学習法に絶対的な王道はあるのか?
そもそも「学び」とか「理解」とはどういうものなのか。
世の中には、脳のメカニズムや発達心理学、教育学等の分野も動員した解説があふれている。
子育ての成功体験を書いている親もいる。
何度か書いたが、「これが正解」などと単一の要素では語れないはずだ。
私自身は、各発達段階で、「ヒトとの出会い」「コト体験」が重要なファクター(要因)になると考えている。
しかし、リアル体験が不足していても、バーチャル体験で補う方法も考案されている時代だ。
何かしらの出会いと体験が必要であることは間違いない。
子育ての「正解」「不正解」は分からない。
子どものWell-being(幸せ)は、人生のもっとずっと先の先にあるもので、自らの力でつかみ取らなければならないものだ。

親だけで子育てをしているわけではない。
私は、「親の責任論」を振りかざして過度に責めることはしたくない。
一方では、「毒親」の存在を何とかしようと、これまでにいろいろな支援活動をしてきた。
人がどのように成長していくかを眺めれば、親の管理下の外で体験することのほうが多い。
それが育ちに与える影響は大きい。
親は、子どもがチャレンジする時に応援を惜しまなければいい。
失敗したら抱きしめればいい。

よい環境にいれば、よいメンターに出会い、ここぞという時にいろいろなことを言ってくれる。
世の中には、偏差値30~40台から難関高校や難関大学への合格を果たしたという起死回生の例は結構あるが、小中高校の12年間でやるべきことを一気に圧縮してやるので、かなりの努力と苦労を要しているはずだ。
そういう例は除いて、順調に結果を出し続ける子は中学生段階で頭角を現す。
その前に通過すべき関門は、抽象概念が怒濤のように押し寄せる「小4(10歳)の壁」を超えることだ。
そして学習の習慣化。
それができないから苦労する。
教育現場の先生方は必死である。

得点に基づいた正規分布曲線を描くと、左側に寄っている学習者が常に存在することがわかる。
右側にいる学習者を増やしたいが、手が回らず、伸び悩み現象も発生する。
先生方は、一斉授業で取りこぼした子たちを何とか拾い上げようと「個別最適な学び」を模索する。
学業不振や人間関係で不登校になっても、学校以外の学びの機会と場が提供され始めている時代、「意味ある学び」のあり方と、人としての生き方を重視した教育が動き出している。
とはいえ、歴然とした学校間格差・地域間格差があり、決して十分な環境が整っているとは言いがたい。
G.ウィギンズとJ.マイタイの『理解をもたらすカリキュラム設計』には、副題として「逆向き設計の理論と方法」が掲げられている。
教職志望の学生たちに読ませようと思って購入したが、読んでみて、なるほどと思う箇所がいくつもある。
正直、まだ理解できていないところがある。
何しろ、自分自身が教師としてやってきたことの捉え返しができていない。
「これでいいんだ!」などとは思っていない。
むしろ「何かが足りない・・・何が足りないんだ?」
という自分の中の “ 無いもの探し ” に苦悶する日々だ
(私はこれを苦悶式学習と名付けている)

カバンの中も 机の中も探したけれど
見つからないのに まだまだ探す気ですか?
それより僕と踊りませんか?
「逆向き」の理論が見えてきた。
ひたすら前を向いて突き進み、ダメだダメだとぼやくのではなく、過去に遡って(逆向きの視点で)原点を見つめ直すこと。
「ふっ、過去は振り向かないゼ!」と言っている場合ではない。
文科省が言う例のアレだ(どれだ?)
「なぜ学ぶ? どのように学ぶ? 何ができるようになる?」
原点に立ち返ること。
そして、もうひとつは、教師自身が教師としての目標にこだわるよりも、子どもが自分を主語にして、自らが問いを立てることだ。
過去・現在を見つめ自分に必要なことをはっきりさせること。
学習者自身も逆向きで振り返ることが必要なのだろう。
20年以上前だが、マーケティングを教える教員として企業研修に参加し、本物の「ポートフォリオ」の設計と「ルーブリック」による評価を学んだことがある。
社員の活動を客観的に評価する手法だが、今は内容がより洗練され緻密になり、学校教育でも用いられている。
結局、「型」は理解したけど、検証が足りなかったのだと反省している。
【ポートフォリオ】
学習成果物を保存・蓄積し、整理・分析するための入れ物(紙媒体などが綴じ込まれたバインダー、電子データが入っているフォルダー、クラウド)
【ルーブリック】
学習達成度を表(観点・尺度)を用いて測定する評価方法。
評価者による評価の偏りを少なくし、明示された評価基準によってより細かな評価をすることができる。
ヒントは得られた。
問題は、教師個々の理解度、教師間の共通理解、教員研修、そして実践によるエビデンス(裏付け、根拠)の構築だ。
教育は理想なくして語ることはできない。
いかにして可能性・確率を高めるか。
学生たちを信じて共に学びたい。

