
「えんたくん」課題設定ワークショップ
丸い模造紙「えんたくん」を使うことでより効果的になるワークショップを3つ紹介します。
先日、静岡県川根本町にて講演した際に、久しぶりに「えんたくん」を使いました。もっと多くの自治体で導入してもらうと良いと思います。
経験上、円になることで例えばこんな効果があるからです。
➊ コミュニケーションの促進
✔ 全員の顔が見える
✔ 一体感の醸成
➋ 心理的な効果
✔ 安心感の向上
✔ 親近感の醸成
✔ 場の共有意識の向上
➌ 発想や創造性の促進
✔ 自由な発想が広がる
✔ 教育的な相互作用
口の字にレイアウトされた会議よりも、丸くお互いが見えるようにした会議の方が、話しやすいことは簡単に想像できますよね。
私はワークショップを行う時にできるだけ「〇(丸)」を意識しています。
ワークショップでは「多文化共生のまちづくり」をテーマに行いました。どんなテーマでも応用できます。丸い模造紙の使い方の参考にしていただければ幸いです。
WORK1




1ラウンド目
「今の状況で一緒に取り組んでいる人・団体」もしくは「呼び掛けたらすぐにでも一緒になって取り組んでくれることが確実な人・団体」を付箋で出し合います。なお、「○○な人」といった条件を書くのもOKです。

2ラウンド目
今度は、外側の三重目の円を使います。今回の場合、「多文化共生のまちづくりをしていくために誰に理解や共感をしてもらいたいのか?」「担い手になってもらいたいのか?」といった視点で、どんどん付箋を出し合います。

3ラウンド目
最後に2重目の円を使います。1重目の円に書いてある人たちが3重目の円に書いている人たちへどう伝えたら良いのでしょうか?きっとその間にいる協力者がいるはずです。例えば、「子どもたちに担い手となってもらいたい」と思うなら、2重目の円には「学校」「教員」「PTA」などが入るはずです。

こういう順序で考えることによって、考え及ばなかったステークホルダーの存在に気付くことができます。例えば、ざっくりと「NPO」と書いていたけど、「具体的な団体」や「具体的な人」を考えることにもつながります。
余裕があれば、ペンで線を引いて関係を示すとさらに良いです。

WORK2
続いて、新しい模造紙を使います。
ステークホルダーが明らかになってきたところで、そのみんなでどんな「多文化共生のまち」を作っていきたいのかを考えます。ありたい未来の姿を出し合ったとことで、今の現状について考え合い、そして、多文化共生のまちを進めるためにどんな障壁=問題があるのかを探っていくワークとなります。
準備として、同じように2つ円を描きます。
1ラウンド目
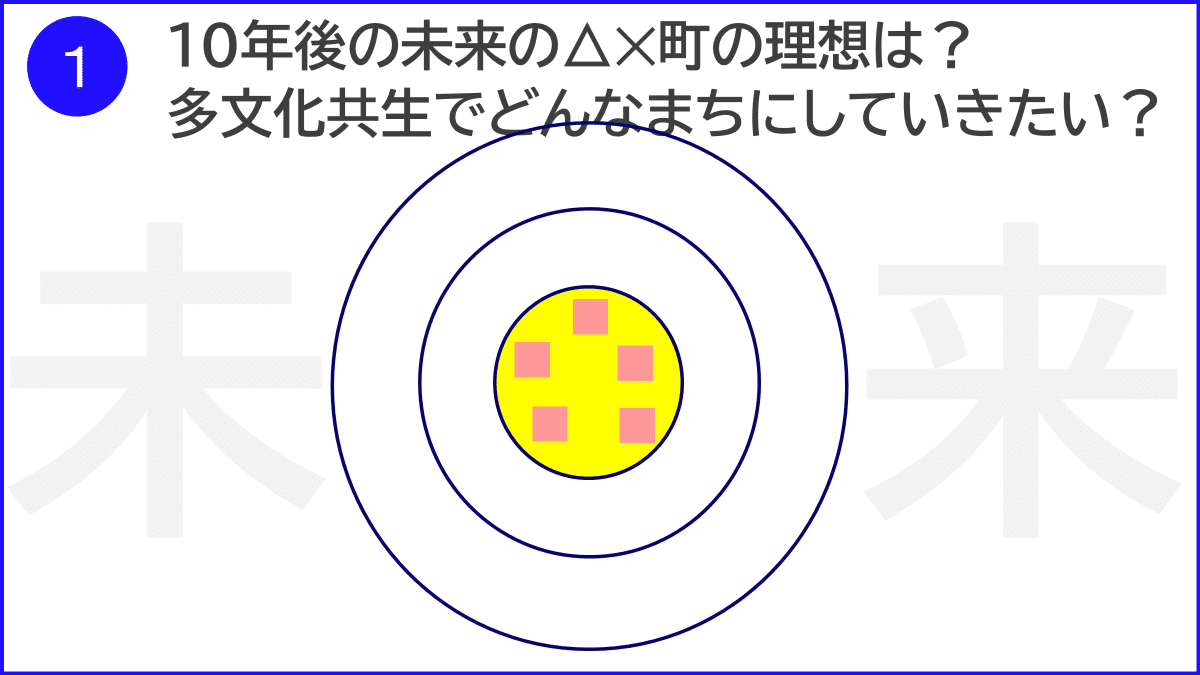
2ラウンド目

3ラウンド目

WORK3
ワーク2は「問題」を発見するためのものでした。
ワーク3は「課題」を設定するためのものです。
ポイントは「原因」を深掘りすることです。「問題を引き起こしている原因は?」「原因の原因は?」「原因の原因の原因は?」・・・と深掘りすることで行き詰った原因こそ真の原因です。
そして、最も大切なことは「課題」に「意志」を乗せること。
この手順で考えることによって「問題」と「課題」の違いがよく分かるようになり、自分たちで課題をうまく設定して活動できるようになります。
1ラウンド目

2ラウンド目

3ラウンド目


課題設定力なきまちづくりの問題点
問題と課題の区別は何のためでしょうか?
それは、まちづくり活動やイベントにおいて正しい対策や効果的な対策を打てないためです。そして、その対策を考えるために必要な学びや活動を企画・計画できないためです。
まちづくり活動の多くは、課題をうまく設定できるようになることでもっと効果的に進められるようになります。このあたり、noteで今後記しておきたいと思います。
いわゆる「課題解決」という言葉を正しく紐解くと、このようなプロセスになっています。

このプロセスを共有できている組織は強いです。反対に共有できていない組織では、話し合いの中で感覚や考えのズレがどうしても生じてしまいます。
本来もっと効果的な取組を考えられる可能性があるはずなのに勿体ないと思います。
地域のみんなで導いた課題を「地域課題」といいます。
地域のみんなで取り組むことによって初めて達成できるものです。
だから、地域課題はこう考えることができます。

私はそう信じてまちづくり活動を支援しております。
解決すべきは課題ではなく「問題」の方です。
読んでいただいた皆さま、ありがとうございました。
