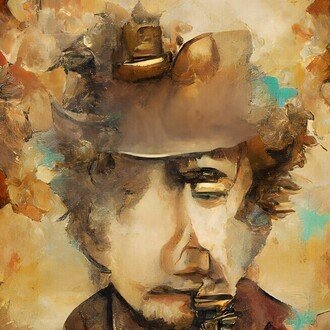大いなるいたちごっこ、SNSで行われる二元論の対立
SNSが生む「いたちごっこ」
SNSは、人々が簡単に意見を発信し、共有する場として進化してきた。しかし、そこで行われる議論や対話はしばしば建設的な結論に至らず、単純化された二元論(善vs悪、正vs誤、賛成vs反対)に陥る傾向がある。この二元論は、一見すると分かりやすい構造を提供するが、実際には対立を助長し、問題解決を妨げる要因にもなっている。
SNSのタイムラインを眺めていると、まるで終わりのない「いたちごっこ」を目の当たりにするような感覚に陥ることがある。特定の議論が再燃し、同じ対立構図が何度も繰り返される。それは環境問題であれ、政治的なテーマであれ、単純な二項対立に収束する構造が影響しているのだ。
なぜSNSでは、議論が複雑性を欠き、二元論に陥りやすいのか?その背景には、SNS自体の設計やアルゴリズム、人々の心理的な傾向が深く関わっている。本質的な問題解決を妨げるこの「いたちごっこ」を超えるために、まずは二元論が生まれる理由を紐解いていきたい。
二元論とは何か
二元論の定義
二元論とは、物事を二つの対立する側面(善vs悪、正vs誤、勝者vs敗者)に単純化して捉える思考のことだ。議論をシンプルにし、多くの人に理解しやすい形で提示する手法でもある。しかし、この単純化は多様な意見や背景を省略してしまう。
例えば、気候変動を巡る議論では「環境保護派」と「経済優先派」という対立構図が目立つ。両者の主張にはそれぞれ複雑な背景があるにもかかわらず、SNSでは単純な二元論として扱われることが多い。その結果、議論は深まらず、感情的な対立だけが目立つ状況に陥る。
二元論が生まれる理由
議論のシンプル化
本質的な議論には背景知識や多角的な視点が必要だが、SNSではそれが省略されがちだ。二元論はシンプルで分かりやすいため、議論に参加しやすい形になる。
感情的な引き金
二元論的な議論は、感情的な反応を誘発しやすい。「正義」と「悪」のような構図が描かれると、人々は直感的にどちらか一方に立つ傾向が強まる。
即時性への対応
SNSでは即座の反応が求められるため、複雑な議論よりもシンプルな二元論が優先されやすい。これがさらに問題を単純化し、対立を深める要因となる。
SNSで二元論が注目される理由
- SNSのアルゴリズムは、極端な意見や感情的な投稿を優先して拡散する傾向がある。
- 明確な敵と味方の構図が提示されると、フォロワーが感情移入しやすく、議論が盛り上がりやすい。
- SNS上の「見られている」という意識が、発言を過激化させる。
SNSが議論をいたちごっこにする構造
SNSの設計そのものが、二元論的な議論を助長する構造を持っている。
繰り返される対立
SNSでは、一度終わったはずの議論が再燃することが多い。例えば、ジェンダー問題や環境問題、政治的な議論では、何度も同じような対立が形を変えて繰り返される。このような「いたちごっこ」の背後には、新しい視点や解決策が提示されないまま、対立の構図が強化される仕組みがある。
アルゴリズムの影響
SNSのアルゴリズムは、感情的で極端な投稿を優先的に拡散するため、対立を煽るような二元論的な議論が目立つ。これにより、より多くの「いいね」やリツイートを集めるために、議論が過激化していく。
ユーザー心理
SNS上では、多くの人が自分の意見を正当化し、他者を論破することに注力する傾向がある。その結果、議論の目的が「問題解決」ではなく「勝ち負け」にシフトし、本質的な対話が成立しにくくなる。
ここから先は
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?