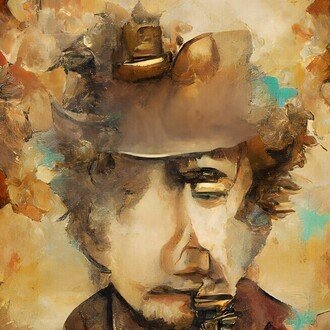自転車操業から降りられない人たち
自転車操業に囚われる若者たち
仕事に追われ、毎日を自転車操業のように過ごしている若者は少なくない。生活費を稼ぐために長時間労働を続けながら、夢やキャリアを追いかける日々。そこには「今の仕事を辞めると次がない」「ここで踏ん張らないと夢を叶えられない」という強い思い込みがある。しかし、そのような先入観が、実は若者を搾取する構造の中に閉じ込めていることに気づく人は少ない。
年配者が若者を「小間使い」のように扱い、自分たちの利益を守るために酷使する。この現実は、職場や業界の文化に深く根付いている。そして若者たちは、現状を変えようとするどころか、「これがチャンスだ」と自ら納得し、搾取構造に加担してしまうことさえある。
だが、本当に「次がない」のだろうか?なぜ若者たちはそのように思い込むのか?そして、その思い込みから解放されるには、どうすればいいのだろうか?
自転車操業と搾取構造の現実
若者が自転車操業に囚われる背景には、労働環境と心理的な要因が複雑に絡み合っている。
まず、労働環境の問題だ。多くの若者は長時間労働や低賃金に耐えながら、成長機会も限られた環境で働いている。与えられる仕事は「雑用」や「使い走り」のようなものが多く、スキルや経験を積む余裕がない。それでも彼らは、「ここで認められればチャンスが広がる」と信じ、辞める勇気を持てない。
年配者側の構造的な問題も大きい。経験や権限を持つ年配者は、自分たちの利益や地位を守るために、若者を都合よく使う傾向がある。「若いからこそ努力が必要だ」「下積みが大切だ」という言葉で、実際には過剰な労働を強い、正当な評価や報酬を与えない。
さらに、若者が「次がない」と思い込む心理が搾取を助長している。この思い込みは、社会的なプレッシャーや教育の影響によるものだ。学校や職場では、「一つの道を極めることが成功への近道」という価値観が根強く植え付けられている。その結果、職場を離れることを「キャリアの終わり」と捉える若者が多い。
このような環境と心理が組み合わさり、若者は自転車操業の輪から降りられなくなる。しかし、これは必然ではなく、変えられる現実である。
「次がない」という先入観の打破
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?