
メリット?デメリット?エジソン箸脱出計画。
こんにちは!すけ@児発のスーパーバイズしてる人(@sukeryoiku)です。
今回は【とんでもないエジソン箸脱出計画】をご覧いただきありがとうございます。
本note長いです。途中画像を多めに入れてますが、それでもトータル7000文字近くありますのですべてをしっかり読んだら10分前後かかるかもしれません。
そして一回読んですべてを理解するのも正直難しいと思います。
ブックマーク保存推奨です!
本noteは
・普通の箸が上手に持てない理由を知りたい人
・エジソン箸脱出に向けて手立てを知りたい人
・エジソン箸を使い始めようか迷っている保護者
・児童発達支援事業所で子どもたちと関わっている支援者
に読んでもらえると嬉しいです。
逆にこのような方は読む必要がありません。
・一生エジソン箸でいいやと思っている人
・作業療法士の方
・エジソン箸を卒業するための見通しが立ってる人
・エジソンが大好きな人
本編に入る前の私のことを知らない方もいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介をさせてください。

「持続可能な療育の世界観を創りたい」ということを軸に子どもたちと真剣に向き合うパパママ、療育施設に従事する指導員のサポートをしているすけ@児発のスーパーバイズしてる人(@sukeryoiku)です。

・児童発達支援での出来事
・保護者に向けて日々の困難さ解消に向けたヒント
・支援者に向けて喝を入れるような内容
・重度知的障害&ASDの息子の日常
現在、私は児童発達支援事業所と放課後等デイサービスで働いております。
通所していただいているお子さまへ、これまで500人以上直接支援をしてきました。
また、社内の新入社員の指導員に向けて研修をしたり、新入社員の方々と定期的に振り返りの機会を担保して支援の質を高めるような役割を担っております。
保育所等訪問支援事業の枠組みで幼稚園保育園・小学校へ訪問しています。
担任の先生に「理想のクラスとは?」を語ってもらい、その理想に近づけるための手立てを一緒に検討して実施のサポートなどをスーパーバイズしています。

過去のnoteを読んでいただいた方々のありがたいお言葉をいくつか紹介します。




本noteの構成は以下の通りです。
序章:イントロダクション
1章:感覚機能
2章:運動機能
3章:認知機能
4章:心理機能
5章:コミュニケーション
6章:安定した姿勢を保持できているか
7章:食事に集中できているか
8章:こぼすタイミングはどこか
このnoteを見ると
・子どもを観察するときのポイントがわかる
・子どもの現在地を把握できるようになる
・上手に箸を持てない背景がわかる
・もしかしたらエジソン箸を使い続けてもいいかもしれないとわかる
・心にゆとりが生まれて毎日の食事でイライラしなくなる
改めまして本noteをご覧いただきありがとうございます。
現在エジソン箸を使っている方がエジソン箸を卒業するためにいろいろ検索してこのnoteにたどり着いていると思います。
「明日からすぐにエジソン箸卒業!」とはいきません。
普通の箸が上手に持てない背景が何となく知れると思います。
焦らずじっくりとお子さんと向き合っていきましょう💪

イントロダクション



今回はエジソン箸脱出計画のためのnoteですが、そもそもの話からしていきます。
「とりあえず」で使い始めたエジソン箸ですが、思うように普通の箸へ移行するのが難しいお子さんはたくさんいます。
子どもの現在地を把握して、なぜ普通の箸が持てるようにならないのかを知っていく必要があります。
・感覚特性
・運動機能
・認知機能
・心理機能
・コミュニケーション
の5つのポイントで情報収集と深堀をしていくと上手くいかない理由がわかってきます。
感覚機能

最初は感覚機能の視点で情報収集と深堀をしてみましょう。
この章では7つの感覚特性について、感覚特性は普段どんな働きをしているのか、偏りがあるとどうなるのかみていきます。
7つの感覚特性

感覚特性って聞いたことありますか?
いわゆる五感と前庭感覚・固有受容感覚という感覚が加わります。
前庭感覚とはスピードや傾きを感じる感覚。
固有受容感覚とは身体の位置や力の入れ具合を感じる感覚。

前庭感覚、固有受容感覚、触覚を総合的にみたときに
過敏さがあるか鈍感さがあるかどうかをみていきます。
さらに日常生活の様子を観察して活動全般が積極的or消極的と見たときにどこに属するのかでお子さんのタイプをラベリングします。
特性に優劣はなく、いいとかわるいとかじゃないです。
あくまでタイプ。
お子さんにどんな傾向があるのかを把握するだけ。
支援の受け入れやすさとか苦手さなどを判断するときに使ったりします。

人間はこの7つの感覚を使って自分の身体や周囲の環境を把握しています。
感覚の感じ方はひとりひとり異なります。
同じ工事現場の音だったとしても、
人によっては全然平気で歩ける人もいれば、
うるさすぎて耳をふさぎたくなる人もいます。
この感覚の感じ方に偏りがあると・・・


感覚特性は練習して治るものではありません。
環境側を工夫して配慮したり、周囲の刺激を増やしたり減らしたりして調整して自分らしく楽しく生きていくための方法を探していきます。
運動機能

次は運動機能がどれくらい発達しているか情報収集と深堀をします。
運動機能は主に粗大運動と微細運動に分けられます。
微細運動が上手にできるようになるためには体幹の土台の安定が必要不可欠です。粗大運動が上手になると微細運動も上手になっていきます。
運動機能がまだまだ発展途上のお子さんはこんな様子が見られます。



粗大運動

粗大運動とは【座る】【立つ】【走る】【ジャングルジム】【ブランコ】など、粗大運動の発達には重力に負けないように適度に筋緊張させて姿勢をコントロールする必要があります。
微細運動

微細運動とは【折り紙】【ハサミ】【箸】【鉛筆】など。
手先を器用に上手に使いこなすためには体幹の土台の安定性が必要です。
粗大運動がうまくなることで微細運動も上手にできるようになります!
こちらのnoteは運動機能の発達を促すような運動遊びを紹介しております。
なわとびのnoteは有料になってしまいますが、お子さんの運動機能の発達段階を明らかにしてレベル別の運動遊びを紹介しています。
認知機能

認知機能とは理解、判断、論理などの知的機能のこと。 認知とは理解・判断・論理などの知的機能を指し、精神医学的には知能に類似した意味であり、心理学では知覚を中心とした概念です。 心理学的には知覚・判断・想像・推論・決定・記憶・言語理解といったさまざまな要素が含まれますが、これらを包括して認知と呼ばれるようになりました。

口頭での説明だけでは理解できず、
次の活動に移れないお子さんいますよね。
そういったお子さんは言語理解能力がまだ発展途上かもしれないわけです。
言語理解にも単語の理解と指示の理解があります。(他にももっとある)
私たちは「リンゴを見たり聞いたり触ったりすることでリンゴを認識することができるようになります。(感覚統合の視点)
また、説明を聞いてからどんなことをすればいいのかイメージが難しい場合には指示理解が苦手になることも。。。
心理機能

・子どもの好き楽しいが機能しているのか
・感情のコントロールがどれくらいできるのか
・人生でどんなヒストリー(※1)を歩んでいるの
心理的面に配慮しないと失敗体験が積み重なり、子どもの活動に自信がなくなっていく可能性があります。


これまで紹介した感覚・運動・認知の問題から、
子どもたちが安心して取り組めるような空間づくりや子どものレベルに合わせた活動を提供してチャレンジ力をサポートしていく必要があります。
コミュニケーション


コミュニケーションとは人と人が意図や感情を共有すること
児童発達支援の現場で保護者たちの話を聞いていると【言語による会話】にこだわる人が多い印象です。
ただ絵カード・手話・ジェスチャー・筆談これらすべてがコミュニケーションになるということを認識しておく必要があります。
「しゃべれるか」ということだけではなく、「どんな方法なら他者とのコミュニケーションを取れる」かという観点で深堀ができると支援の幅が広がっていきます。
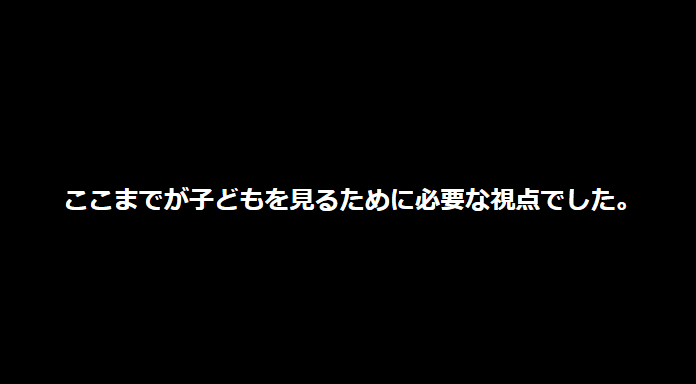


ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
