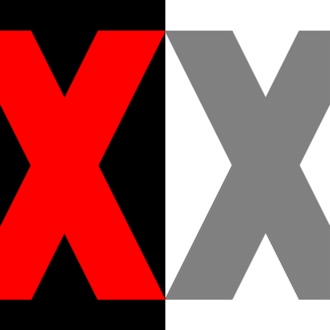「現実を仮想する」VR美術館を味わう
今年は春頃から「外出自粛」と言われ続ける世の中、あらゆる業種が閉鎖やイベントの中止が相次いで、ステイホームと言われ続ける時期が長く続いた。
私は休日に、美術館やアートに関するイベントに行くことが多い。そのような趣味を持つ者にとっても、大きな影響を受けている。
例えば、関西在住の私にとって、2月末に京都で開催予定だった、大規模なアートフェア「ARTISTS’ FAIR KYOTO 2020」が中止。
京都市内で3月にリニューアルオープン予定だった「京都市京セラ美術館」もイベントの中止や延期が相次ぐ。
大阪では「国立国際美術館」は2月末からから臨時休館が続いていた。
6月に入って緊急事態宣言が解除されるなど、少しずつオープンの兆しを見せているが、京セラ美術館は観覧を予約制にして制限を設けるなど、まだまだ先は厳しい。
そんな中、自宅でも美術館を味わう方法の一つとして利用され始めているのが、「ネット配信」、中でも「VR(バーチャル・リアリティ)」を使ったコンテンツが増えている。
情報としては、美術手帖の記事でまとめられている。
そこで、私も早速、VR美術館というものを試してみた。
手軽にVRを味わう方法
VR美術館のコンテンツには、PCのマウスやスマートフォンのタップ操作によるものと、VRヘッドセットを使うものがある。

最も簡単な方法として、スマートフォンを装着するVRゴーグル(私が購入したのは2000円程度)と、無料のVRアプリをインストールするだけで楽しむことができる。
この中で日本の美術館、神奈川県川崎市にある「岡本太郎美術館」
リンク先のサイトでは、PCでもマウス操作で鑑賞できる

スマートフォンの画面をそのまま撮影すると、このように左右に分かれた映像が映し出されるが、これをスコープを通して見ることで、目の前に「岡本太郎美術館」が映し出される。
その中で、首を動かすと背景が連動して動く、まるで実際にその場にいるような感覚であたりを見回すことができる。そして移動やメニュー画面などの操作は、画面中央にある小さな点に視点を合わせて1秒くらい見つめると反応する。つまり「焦点」がカーソルとなる。
VRと言っても、スコープで目の前に映像を映し出すのみで、これといった演出はない。でもこれだけでも、館内の壁や美術品などは自分とどれくらい離れているか、進むとどれくらい近づいたか、その大きさは、その存在感は…などが掴める。
視界と自分の動きの全てを映像に奪われるおかげで、その「空間」を味わうことができる。これがなかなか面白い。
これを企画・製作しているのは、一般社団法人「VR革新機構」
で、サイト内には、いくつかのVRコンテンツが置かれている。
VRで、現実に興味を持つ

この映像は、岡本太郎美術館の3Dマップで、この中を自由に移動することができる。
でも、移動できる場所や美術品の鑑賞は、全て決められた地点のみで、観賞場所も美術品に近づける距離も限られる。もっと近づいて美術品を観たいという衝動に駆られるができない。
それを感じると、実際に岡本太郎美術館には一度行って、本物を鑑賞してみたい気持ちにもなる。
VRとしての「もどかしさ」も味わうおかげで、本物に興味を持つ。ああ、こういうVRの効果ってあるんだと思った。
VRは「仮想現実」と呼ばれるが、私なりに、ゲームなど「仮想的に作られた空間を現実のように味わう」ものが主と思っていた。でもこの美術館は全く逆で「現実を仮想的に再現して味わう」ものだ。
今見ているものはVRだが、この世界は本物がある。だから、現実のものに興味を持つきっかけになる。そんな効果を実感した。
いいなと思ったら応援しよう!