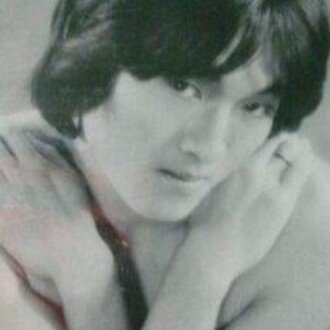目からビーム!92 武士はいついなくなったか~特攻隊犬死論の傲慢さ
毎年この季節になると、テレビには特攻隊を題材にしたドラマが登場するようだ。僕も何年か前までは可能なかぎりそれらを観ていたが、そのほとんどが、違和感のみが残る残念な出来栄えのものだった。あるドラマを観て、その違和感は決定的になり、以後、特攻隊ドラマや映画の類は一切観ていない。観る気もしない。
どんな内容かはというと(細かい記憶違いはご容赦)、出撃を前に故郷の中学校を訪れた特攻隊員が、その学校の音楽教師をしている幼馴染の女子にこう呟いて慟哭するのである。
「こんな時代に生まれたことが悲しい。僕は教師になりたかった」。
はたして、本物の特攻隊員がそんなふうに人前で泣くだろうか。もちろん、死を前にして懊悩はあるのは当然だろう。しかし、彼らはそれらをすべて受け入れ、ある種の悟りにも近い気持ちで旅立っていったのだ。それは見送る方も同様だったろう。
僕は元特攻隊員の方を何人か取材させてもらっている。それは貴重な体験だったと今でも思う。
お話を聞いていて衝撃的だったのは、彼らの死生観というものを聞いていると、昔の武士のそれに近いということだ。同時に、武士という存在は明治維新で姿を消したのではなく、あの敗戦によって消滅させられたのだと思った。四民平等とは、それまで武士の美徳だったものをすべての身分に開放したことを意味するのではないか。少なくとも戦前の日本人には、規範と倫理としての武士道が備わっていたのだ。それらを理解していない者が作ると、前出のような違和感だらけの特攻隊ドラマになってしまうのである。
たとえばだ、白虎隊のドラマを作ったとしよう。
「こんな時代に生まれたのが悲しい。俺は武士になんか生まれたくなかった」
と泣き叫ぶ隊士が出てきたら噴飯ものだろう。郷土の誇りを侮辱するのかと、会津の人は激怒するに違いない。これと変わらぬ愚の産物をテレビは毎年夏、垂れ流しているのだ。
「こんな時代に生まれて」の「こんな時代」とは何だろう。令和の今は「こんな時代」ではないという確証はあるのか。
戦後に生きるわれわれが、戦後の価値観で「こんな時代」を描くことの傲慢を知れ。
いいなと思ったら応援しよう!