
カスミルのとしょかん(伊藤整「生物祭」)
皆様こんにちは。カスミルのとしょかんへようこそ。
ここでは、隔週で私のおすすめの本や作品をご紹介したり、時にはこっそり雑筆を残したりしていきます。忙しない日常の事は少しだけ忘れて、どうぞごゆっくりお楽しみくださいね。
では早速。記念すべき第一回目にご紹介する作品はこちら。
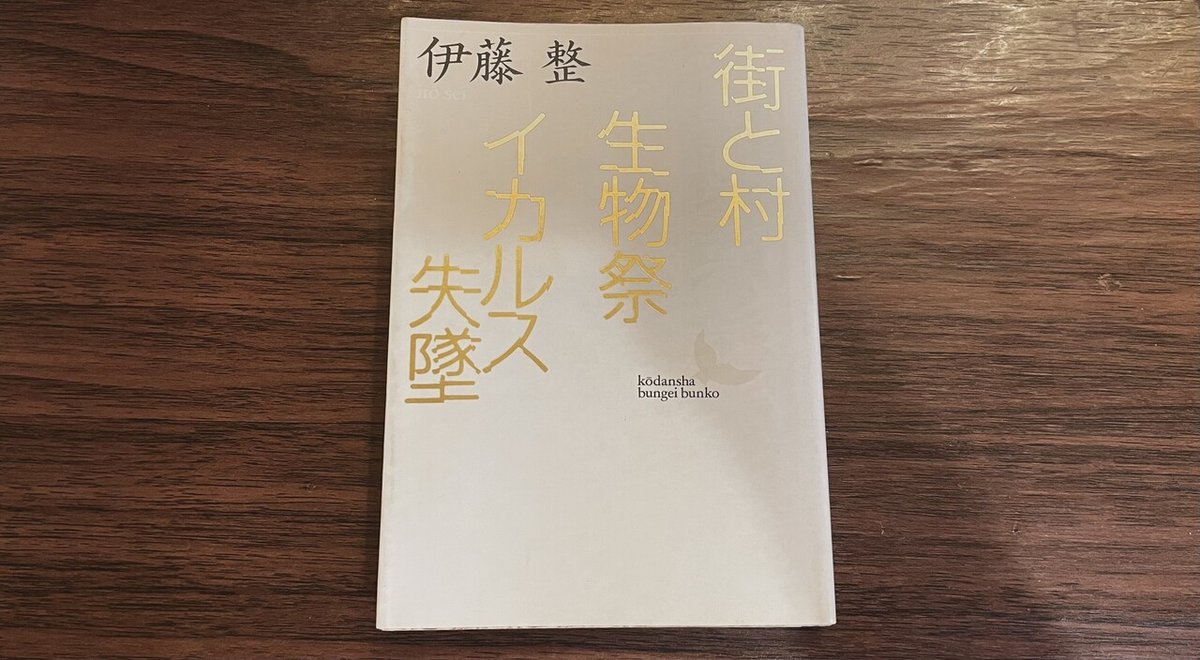
本日は、伊藤整『街と村・生物祭・イカルス失墜』より「生物祭」をご紹介致します。近所の桜はとうに散ってしまいましたが、まだギリギリ春だと信じて。春にぴったりの作品です。
◯作品の舞台、主な登場人物、梗概
作品の舞台は6月、春真盛りの北国です。主な登場人物は三人、病気でもう先の長くない父と、母と、語り手(「私」)です。
父の危篤を知らせる電報を受けた語り手が実家に帰ってくる所から話が始まり、父の容態や、春の様子について描かれていきます。

◯個人的に思う見所
以下引用は講談社から出ている伊藤整『街と村・生物祭・イカルス失墜』を参照し、引用ページ数のみ丸括弧で記載します。詳しい書誌情報等は最後にまとめて載せています。
私を呼びもどしたのは父の病気であった。それなのに、私の這入って来たところは、人を狂気にするような春の生物等の華麗な混乱であった。(242頁)
父は今まさに死にかけていると言うのに容赦なく生を振りかざす、この春の何とも残酷な事!
何よりも生と死の対比が鮮やかな作品だと思います。
引用にもありますが、父の危篤を知って実家に帰った語り手は、そこで様々な「生の象徴」とも言えるものに出会います。そのひとつが咲き乱れる春の花。この作品では、花が生の象徴、更には生殖の象徴として描かれる場面が多くあります。例えばこちら。
外へ出ると、病院の垣根には遅い八重桜が咲き乱れていた。これらの花の息詰まる生殖の猥雑さを、人は怪んでいないのだろうか。白い看護婦たちの忍び笑う声を内包した病院の建物の外で、桜は咽せかえるように花粉を撒きながら無言のうちに生殖し生殖しそして生殖している。(244頁)
皆様今年桜はご覧になりました?あんなに綺麗に咲いている桜も、伊藤整が書くとこんなにも猥雑になるのです。素敵。
次の引用は、語り手が、李の匂いを嗅ぐために夜の散歩に出る場面から。
私は花の匂のなかに女の匂を捜し、そこに閃きすぎる女の皮膚の、髪の、性の匂にすがりついて眼をつぶる。(247頁)
そして語りは次のように続きます。
この李の匂のなかにいる、ここに私をとり巻いているのは何だ。女どもだ。数限ない、裸形の、匂をまき散らす妖精どもだ。(248頁)
続きがまた素敵なんです。もう少しお読みになって!
夜のなかに群がってそれ等が私の方に腕を差しのべている。私は歩いて行く。壁のような花の並樹の底を。ずっと向うまで李は枝をのばして私の近よるのを待っている、私がその匂に窒息して、昏倒するまで、この花の列は尽きそうにもない。朝、路上に私は俯向けに長くなっているだろう。昼見れば、藪の中に不恰好な枝を交わし、紙屑のような花を飾っている李の下に。(248頁)
素敵すぎやしませんか。読んでいる私まで、生の匂いに窒息して死にそうです。ふふ。素敵。

作中には、他にも看護婦が生の象徴あるいは性の象徴として描かれています。先程の引用中にもちらっと看護婦という語が登場していますね。
私は立上って出て行ったが、廊下の正面の薬局の前まで来るとそのなかで看護婦が二人なにか忍び笑いしていた。すると私は、自分の笑えなくなっている状態を思出した。私と彼等との間にある差異は、生の方へ繋がるものと死の方へ繋がるものとの、絶間なく増してゆくそれであった。(244頁)
ここでは語り手は、看護婦らを「生の方へ繋がるもの」と捉えています。もう少し引用いきますよ。
そして看護婦等の肉体は粘液のようなものを唇や腰部から分泌する、病院の光った廊下をスカアトを曳いて走り、扉の握りを開くときに。洗面所のタイルの中で水が流れている。彼女等は看護服の中に棲息している女性なのだ。処女であり、またない。処女である女と処女でない女とが白い看護服に身体を包んで笑っている。その窓の外にある桜の花の生殖。それに彼女等は気づかないのだろうか。総ての花や女等はなにかを分泌し、分泌して春の重い空気を一層重苦しくしている。(244頁)
このように、語り手は見るもの出会うものに多分の生を、あるいは性を見出し、捉えています。しかし語り手が捉えるものはそればかりではなく、その裏には常に死が付き纏っているように思います。
先程語り手が李の匂いを嗅ぎに散歩に出る場面からの引用を提示しましたが、同じ場面には次のような語りもあります。
此処は闇の中だ、と私は自分に言う。この強烈な匂に溺れるがいい。此処には匂のほかに何もないのだ。私の頭を勝手に酔わせるがいい。父はどうしているか。眠って、死の前の不安な呼吸を喘いでいる。お前は誰だ。その父の子だ。今死のうとしている者の子が此処の花のなかで眼をつぶっている。(248頁)
作中で語り手は、何度も自身を「今死のうとしている者の子」であると表しています。死が常に脳裏にあるからこそ、生に縋りたくなるのでしょうか。
あともうひとつ、死が象徴的に描かれている場面があります。語り手が花と新芽の藪の中を歩く場面からの引用です。
足下に音を立てるものがあるので、見ると、蛇が石の下から褐色の長い肉体をのぞかせていた。こいつだ、と私は思った。蛇は滑り出した。私は少年時代の激しい感情の戦くのを感じながら、大きな石を持って、追いかけてゆき、叢に隠れてじっとしている蛇の頭の上からそれを落した。蛇は尾の方をひどく痙攣させていたがやがて動かなくなった。その石をステッキでのけて見ようとして、私は躊躇し、やめた。(242頁)
この場面ね、何の根拠もない事を言いますが、語り手が春の生命力にあてられて蛇を殺してるような気がしてならないのです。反動にも似た衝動。
私の勝手な想像はさておき。何となく雰囲気はお伝えできたでしょうか。危篤の父と春の猥雑さ。その両方を受け止めざるを得ない語り手。この辺りが作品の魅力であると、私は思います。
長々とお話してしまいましたね。大好きなんです、「生物祭」。少しでも魅力をお伝えしたくて沢山たくさん書いてしまいましたが、却って雑多になってしまったような……。
兎にも角にも、これで終わります。
次回、何を書くか未だ決めていませんが、また気が向いたらでいいので読んで頂けると嬉しいです。嘘。ほんまはめちゃくちゃ読んでほしい。わはは。
では。また二週間後に。
「生きてるって素敵でしょ?」
そうね、性も死もうまく受け入れられればね。
◯書誌情報
伊藤整「生物祭」(『新文芸時代』、1932年1月)初出、未見。
伊藤整「生物祭」(『街と村・生物祭・イカルス失墜』、講談社、1993年2月10日)参照。
