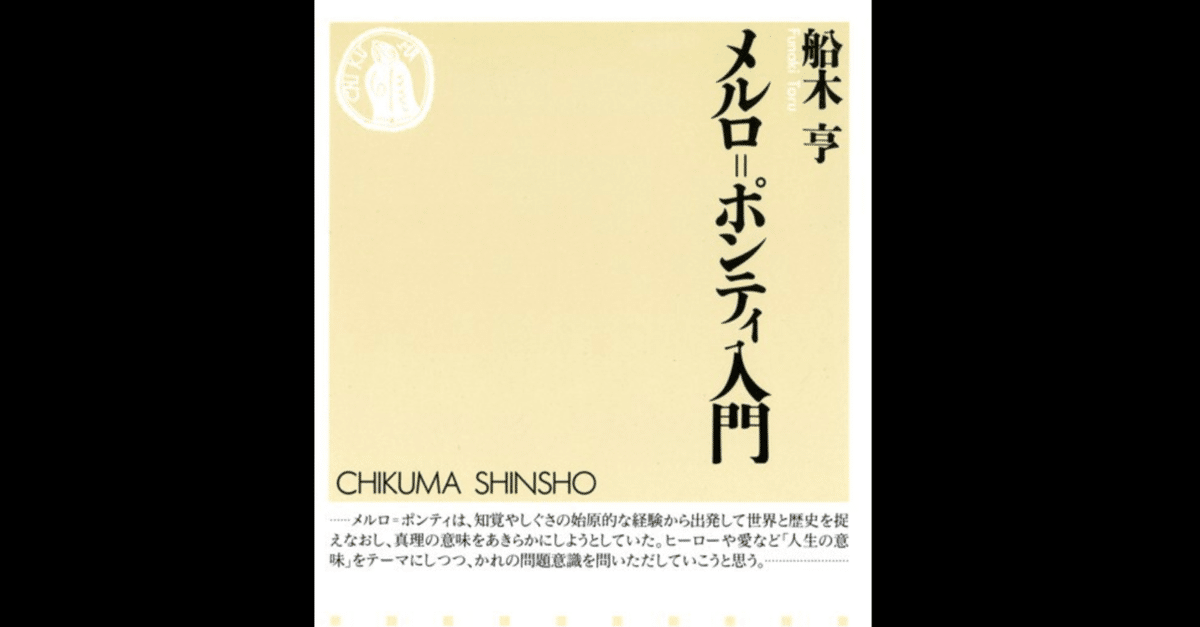
時間感覚とは私が私にとっての他者になること——メルロ=ポンティの時間性の現象学
思考や行為が自分そのものであるのに対し、対象化するのはその思考や行為が関わってくる相手の立場によってでなければならない。自分であることと、自分を対象化して捉えることのあいだには、他者が存在していなければならない。とすれば、わたしがわたしにとっての他者になるのに、時間が必要だということであろう。
というよりも、もっといえば、こういうことではないか。すなわち、わたしがわたしにとっての他者になることをもって、時間がたつというのである。 熱中しているとき、あるいは怯えているときには、時間はたたない。疲れて仕事をやめたとき、解放されたときに時間がたったということが分かる。時間感覚とは、わたしがそれ以前のわたしではなくなって、それ以前のわたしを眺めるという他者生成の感覚であり、他者生成とは、わたし自身の現在(到着時)と過去(出発時)の分裂なのである。わたしは、アイデンティティ(統一)なるものを生きているのではなくて、(完全には切離されてしまわないような)分裂を生きているというべきなのだ。 歴史のなかにあるということは、時間という複雑な過程のなかにあるということである。その複雑さは、時間自体のもつ抽象的な形式によるのではなく、つきつめていけば他者的なもの一般によって構成された時間というものの実質的内容によるのである。
モーリス・メルロー=ポンティ(Maurice Merleau-Ponty、1908 - 1961)は、フランスの哲学者。主に現象学の発展に尽くした。ロシュフォール生まれ。18歳のとき高等師範学校に入学し、サルトル、ボーヴォワール、レヴィ=ストロースらと知り合う。21歳のときフッサールの講演を聴講し、現象学に傾注する。以後現象学の立場から身体論を構想する。37歳のとき主著『知覚の現象学』を出版するとともに、サルトルと「レ・タン・モデルヌ(現代)」誌を発刊する。戦後は1949年にパリ大学文学部教授となり、児童心理学・教育学を研究する一方、冷戦激戦化の状況の中、マルクス主義に幻滅し、サルトルとは決別した。
メルロ=ポンティは、知覚の主体である身体を主体と客体の両面をもつものとしてとらえ、世界を人間の身体から柔軟に考察することを唱えた。身体から離れて対象を思考するのではなく、身体から生み出された知覚を手がかりに身体そのものと世界を考察した。1959年、『見えるものと見えないもの』を刊行。パリの自宅で執筆中、心臓麻痺のため急逝(1961年)。
本書『メルロ=ポンティ入門』は、フランス現代哲学が専門の船木亨氏による解説書である。
現象学において「時間性」は重要なテーマである。ハイデガーは『存在と時間』において、現存在が時間性とともにその存在を現出させるさまを見事に示した。ハイデガーの哲学を批判的に継承し、独自の他者論を展開したエマニュエル・レヴィナスにおいても、時間性は大きなテーマである。レヴィナスは他者とともに到来する時間を「隔時性(diachronie)」と呼び、自己にとっての他者がもたらす隔絶された時間が、その他性ゆえに時間を成立させると説いた。
メルロ=ポンティの現象学にとって「時間性」はどのような意味をもつのか。メルロ=ポンティの時間性においても、他者が重要な役割をもつとされる。メルロ=ポンティは「歴史」という言葉を用いる。歴史という出来事の積み重なりにおいて、そこに私たちの時間経験の固有な特性が現れるからである。出来事において、潜在的なものと現実的なものの、この二重性こそが、各時刻における過去や未来を特徴づけている。私たちは、各時点の過去と未来とを、統一的に通覧することはできないのである。もっといえば、私たちはただ現在を経験しているのではなくて、潜在的なものと現実的なものの交替を通して、ふたつ以上の時点を分裂しながら生きている。こうした分裂は、次の出来事の出発点において、よりふさわしい過去と未来の配置を得るためにたえず再生産されていく。
メルロ=ポンティは、ふさわしい配置に向かおうとするこうした歴史の運動がめざすものを「真実」と呼んだ。メルロ=ポンティによれば、歴史の中での決断、状況の引受けとは、過去と未来を行ったり来たりしながら現在が移行し、そのただなかで、どのようにしてその配置に収まるかということにかかっている。
そこでは「他者」が重要な役割をはたしている。私の行動は時間がたつことと切り離されず、その瞬間瞬間に私の捉え方も変わっていく。そこで生じる出来事の意味は、他者がどう反応するか、他者がどう理解するか、私が他者をどのように遇するかということと密接に関わっている。そして、そうした関わりのなかでしか、何が歴史的なことなのか、何が重大なことであって私の生活を規定するのかを理解することができないのだし、人間というものは、その理解を通じてしか、自分の行為を決められない。
自己と歴史、時間と他者は、お互いがお互いの定義の一部をなしていて、ほとんど別物ではないともいえる。
船木氏は、手紙を書いていても一晩置いておくと、「熱」がさめる、という経験を例に挙げている。ここでは何が起きているのか。一晩たつと、書いていた最中の熱が薄れ、あたかも他人のように読むことができるということである。これは、自分の思考や行為と、それを対象化して捉えるという他者の立場が接続するために時間が必要だということである。すなわち、「私が私にとっての他者になる」ことをもって時間がたつということなのである、と船木氏はいう。時間感覚とは、私がそれ以前の私ではなくなって、それ以前の私を眺めるという他者生成の感覚であり、他者生成とは、私自身の現在(到着時)と過去(出発時)の分裂なのである。私は、アイデンティティ(統一)なるものを生きているのではなくて、完全に切離されてしまわないような分裂を生きているのである。
