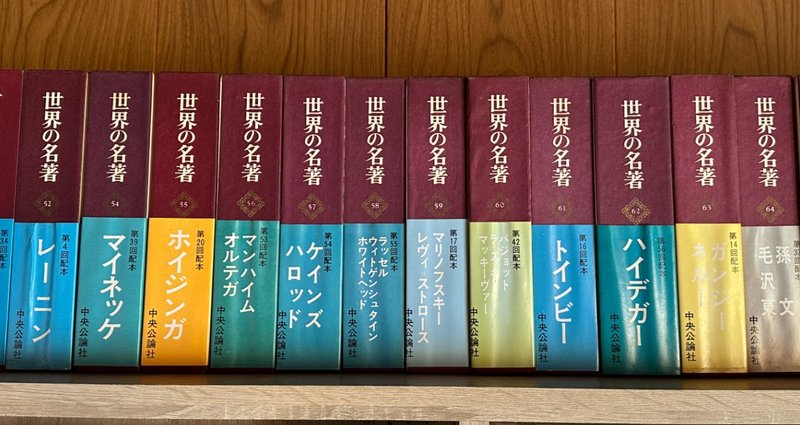
一日一冊、そんそん文庫から書籍をとりあげ、その中の印象的な言葉を紹介します。哲学、社会学、文学、物理学、美学・詩学、さまざまなジャンルの本をとりあげます。
- 運営しているクリエイター
記事一覧

他者の物語を埋葬すること、自分の声を見つけること——榎本空氏『それで君の声はどこにあるんだ?——黒人神学から学んだこと』を読む
榎本空(えのもと そら, 1988 - )氏は日本の神学者。滋賀県に生まれ、沖縄県伊江島で育つ。同志社大学神学部修士課程修了。台湾・長栄大学留学中、C・S・ソンに師事。米・ユニオン神学校S. T. M 修了。現在、ノースカロライナ大学チャペルヒル校人類学専攻博士課程に在籍し、伊江島の土地闘争とその記憶について研究している。 本書『それで君の声はどこにあるんだ?——黒人神学から学んだこと』は、榎本氏がユニオン神学校で師事した黒人神学教師のジェイムズ・コーンから学んだことを自伝














