
さらば、全てのエヴァンゲリオン
「さようなら、すべてのエヴァンゲリオン」
これ以外のことを書くのは蛇足だと思うけれど、見終えた新鮮な気持ちを冷凍保存しておきたい。
最初にTVシリーズのエヴァンゲリオンを見たのは高1の時だったと思う。
なぜ見始めたのかはもはや覚えていないけれど、この作品には暗い気分の人を呼び込む不思議な魔力があった。
誰だって10代の頃は1つや2つコンプレックスがあるし、自分もそうした面倒くさい子供の一人に過ぎなかったことなんて、今ではもうわかりきっている。
でも、そのときに抱えていた苦しみは誰のものでもない自分のものであったのも事実で、そういった苦しみを抱えている人が世の中に溢れていたからこそ、エヴァンゲリオンという作品はここまで語り継がれてきたのだと思う。
しかし、本来はここまで引き伸ばされるべき作品ではなかったはずだ。
素人ながら自分でも物語をつくるようになって気がついたことは、やはりTVシリーズの終わり方は物語として破綻しているということ。
結局エヴァは、主人公のシンジと父ゲンドウの物語が中心にあるのだから、その二人が抱える課題を解消して終わるべきだった。
でも、その二人のやり取りはずっと描かれないままだった。
そして、シン・エヴァがようやく公開されることが決まった。
キャッチコピーは「さらば、全てのエヴァンゲリオン」。
見終えた今、テーマもこれであったことがわかる。
これを初めて聞いたとき、僕は「まどマギだな」と思った。
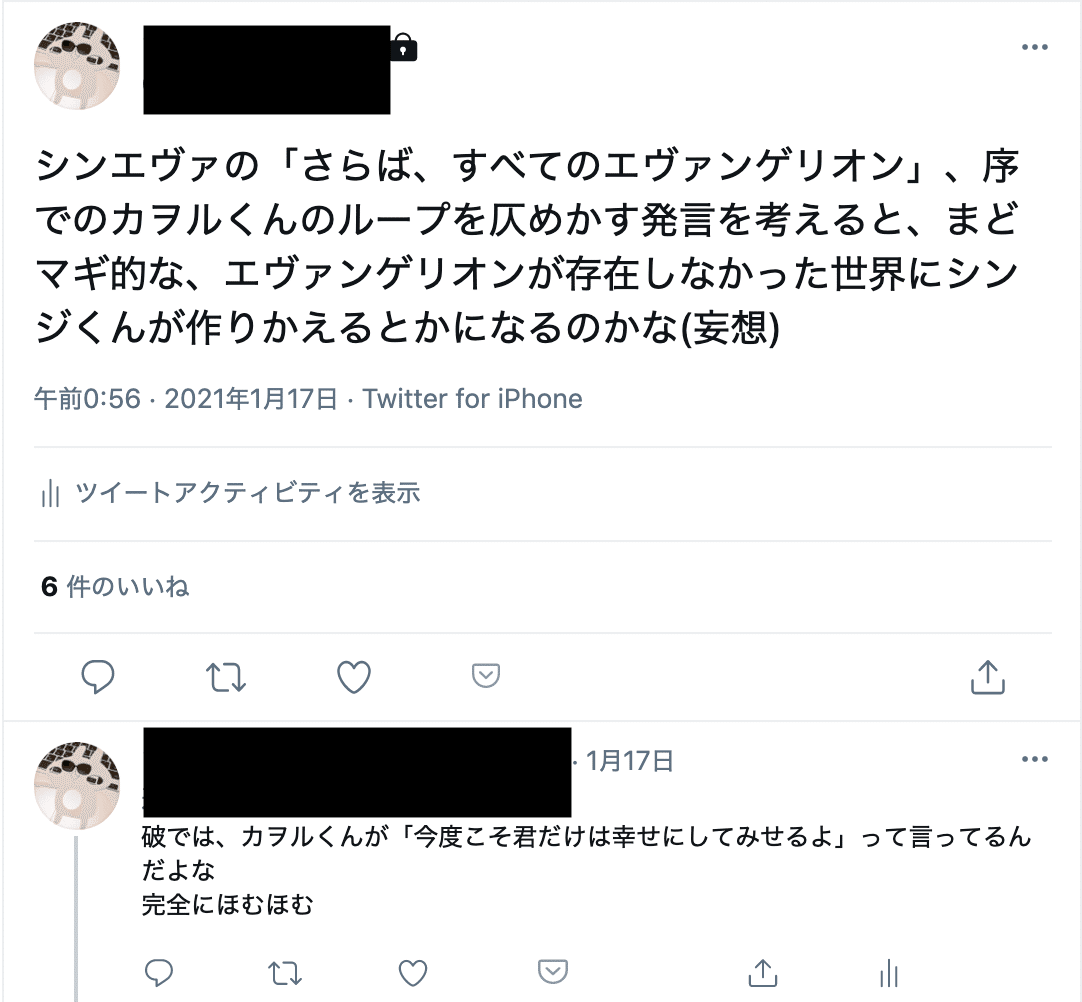
「すべてのエヴァンゲリオンをなかったことにする」と言って、終わり。
ここの予想はだいたい当たっていた。
問題は、どうやってそこに持っていくのか。
自分は、シンジがゲンドウを乗り越えるために父殺しの物語として終わらせるのだと予想していた。古来からよくある物語の類型。
もっと言えば、コードギアスとか、ダークナイトとか、天気の子とか、もうすぐ終わる某人気漫画のように、「自分がやりたいことをやるために自分が悪になってでもやるんだ」というダークヒーローものになるんじゃないかと予想していた。アニメーションとしても映えそうだし、自分がそういう作品が好きなのもある。
実際、ミサトさんは作中で、「子供が父親にしてやれることは、肩を叩くか、殺してあげることだけよ」と言っていた。
この場面で、僕たちは二択を突きつけられていたのだ。
ゲンドウの肩を叩いてあげるか、殺して引導を渡すか。
そして庵野監督は、父殺しは選ばなかった。
シンジくんは、ゲンドウと対峙するまでに、既にゲンドウすら乗り越えて成長していた。
庵野監督にとってシンジとゲンドウの間に必要だったのは、暴力や恐怖ではなく、対話・コミュニケーションだった。
グレンラガンとかプロメアのようなTRIGGER作品だとよくあるような超展開にせず、ある意味最も現実的な解決方法であるコミュニケーションこそが、一番必要なものだった。
ここまで観て、やっぱりエヴァという作品は、最初から最後まで庵野監督の私小説だったんだなと思った。作中でキャラクターに語らせていたセリフも、良くも悪くも、庵野監督の言葉にしか聞こえなかった。
でも、そうして監督が抱えてきた課題やコンプレックスがこうしてエヴァンゲリオンという物語に昇華され、ようやく終わったことに意味がある。
Qであれだけキャラクターたちが抱えていた問題にも、決着がついていた。
エヴァンゲリオンは、ちゃんと終わった。
庵野監督も新劇場版が始まる頃に語っていたように、創作の本来の役目は、人々が抱える課題や苦しみをキャラクターに乗せることで、現実世界で生きる人々の糧となることだと思う。
そういった物語をこれからも見ていきたいし生み出す助けになりたい。

それこそが、現実と虚構を等価に捉えることができる人間(リリン)に与えられた、「物語」の醍醐味なのだから!
いいなと思ったら応援しよう!


