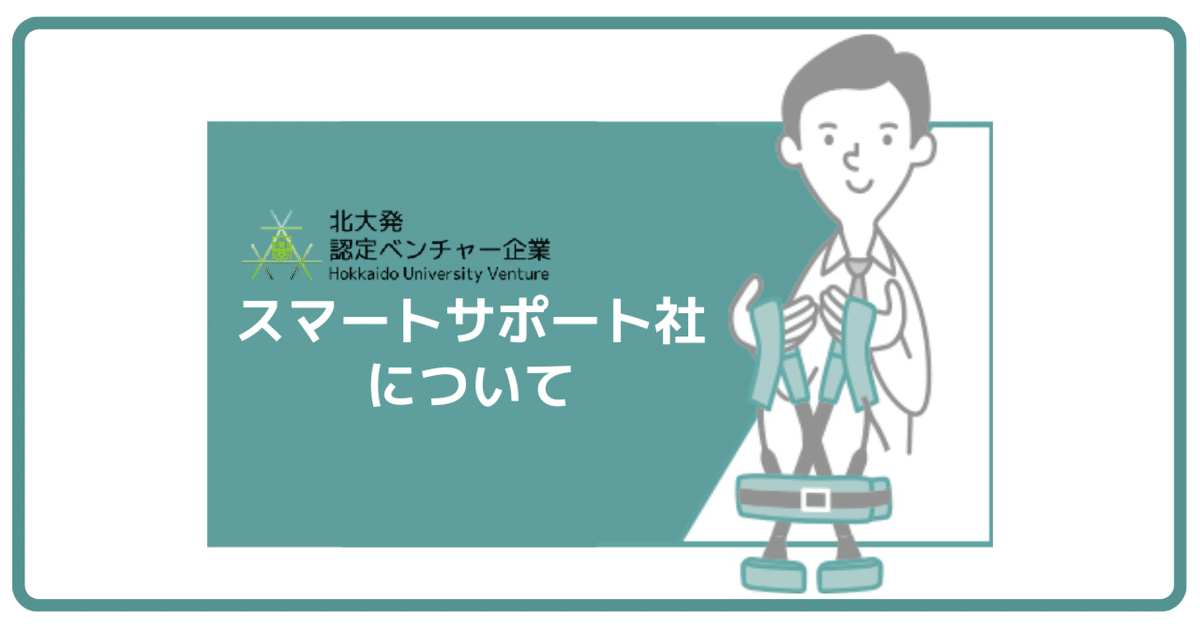
【自己紹介】スマートサポート社について
株式会社スマートサポート
Smart Support Technologies Inc.
北海道大学発認定ベンチャー企業
主な事業:
スマートスーツ の開発、製造、販売
軽労化技術の研究開発
労働災害予防のための身体にかかる負荷計測、分析、評価
労働者のための体力測定、体力づくり支援
連絡先:
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西5丁目7 愛生舘ビル4階
電話: 011-206-1462 (平日9:00-17:00) FAX: 011-206-1463
お問い合わせフォーム
会社概要詳細
(もっと詳しく知りたい方はこちらからどうぞ)
沿革や想いのようなもの
スマートサポート社は2008年に札幌で創業した研究開発型のベンチャー企業です。何を研究開発しているのかといえば、軽労化技術で作業によって身体にかかる負担と疲労を軽減して、腰痛などの疾病症を予防するためのアシストスーツの研究開発をしています。
アシストスーツの存在は2013年ごろ話題になるようになりましたが、我々はそれよりも5年以上も前から着目し、開発を始めていましたので、業界では老舗になります。ベンチャー企業なのに老舗って、この分野がいかに新しい研究開発分野であるかということです。いえ、すでに社歴を重ねて、ベンチャーとも言えないのですが。
もともとは創業者のひとりである私(鈴木)が、2003年に北海道で農業コンサルティング業を立ち上げたことから始まります。駆け出しの農業コンサルであった私が農家のお役にたてることはないかと多くの農業者を訪問しているうちに、重量物の持ち上げや中腰姿勢の維持が多い農作業が原因で腰痛を発症される方が非常に多いことに気づきました。
多くの方が湿布を貼ったり、コルセットをしたりして腰痛予防をされていましたが、抜本的な解決にはなっていませんでした。
農作業は毎日、同じことの繰り返しというのではなく、季節によって、また、作付けしている作物によって作業体系が異なります。だから何かの作業専用に機械化、ロボット化しても年間の稼働日数は数週間と少なく、費用対効果が合わないといった課題があります。
作物あるいは家畜と向き合い、日々、成長の過程で経験則に基づく判断や天候の変化などによる変則的な作業にも対応しなければなりません。結局は、「人」が必要であり、「人」の能力を高めること(拡張すること)、ケガや病気、疲労などから守り、常に高いパフォーマンスを維持し、生産性を高めることが求められます。
機械やロボットに置き換えることのできない「人」でなければできない作業というのは、農業に限らず、製造業や建設業、介護などまだまだ多くあります。長い経験から得た知識や的確な判断、容易に真似することのできない技能を大切にしたいと考えています。
このような技能を持つ方々に話を聞くと、多くの人は”定年”とか”引退”とかを考えておらず、身体が動く限り続けていきたいと言います。とはいえ、人の体力などは加齢とともに衰えていって、作業による身体への負担に耐えられなくなる時がきます。
私たちは、そのような方々のために、作業による身体への負担をできるだけ軽減し、なおかつ作業を通じて適度な運動刺激、すなわちトレーニング効果によって体力を維持・増進できないかと考えました。これが、私たちが開発の基本概念とする「軽労化」です。
「軽労化」という概念は、共同創業者の北海道大学大学院情報科学研究科の田中孝之教授が発案、命名したものです。(商標取得済)
田中教授が、北海道大学に助教授(当時)として着任して、そうそうに私と出会いました。農業コンサルタントである私は、田中教授の持つ、ロボットや機械の知識や技術を用いて農家の腰痛問題を解決することができないかと提案しました。北海道に来たばかりの田中教授は北海道の基幹産業である農業に自分の研究成果を活かすことができるのではと考え、開発に着手したのです。
当初、開発していたスマートスーツには、モータやコントローラ、センサなどのロボット要素を付帯していましたが、屋外での使用が想定され、水濡れや土ぼこりなど機械にとって過酷な環境で壊れないようにするため、また、より安価で使いやすい機器とするために、このような機械的装置をとり外して、今のスマートスーツを開発しました。
技術は、何かの目的を達成するための手段です。私たちは目的を見失わず、技術に陶酔することなく、常に現場で働く人のために、高齢化社会における高年齢労働者の働く場を作るために行動していきたいのです。
