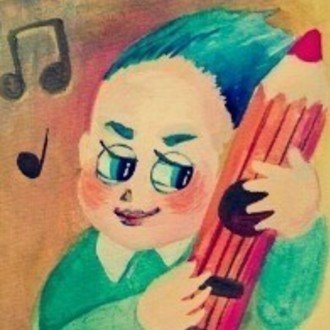【心の詩歌】新しい論語
論語の話です。論語という本がありますが、古い本なので誤解が多い。
論語についてまず説明しますと、思想家・孔子と弟子との会話を記録した書物です。
たとえば「温故知新」も論語の言葉です。
ただし、孔子は紀元前に生きた思想家です。そのため誤読する場合が多い。孔子が難しいことを言っているのではなく、こちらが現代の常識に当てはめて解釈してしまい、結果的に誤読になっているケースがあります。
たとえば呉智英『現代人の論語』では、有名な言葉について誤解が多いことが指摘されています。
学びて時にこれを習う、また悦ばしからずや。朋あり、遠方より来たる、また楽しからずや。人知らずして慍みず、また君子ならずや。
この「学びて時にこれを習う」の部分ですが、呉は語釈上の誤りを指摘します。「時に」という部分を、現代人はしばしば「時々」と考えますが、正しい解釈は「適切な時期に」です。
さらに、「学びて」「習う」について、勉強のようなイメージを持ちがちです。しかし孔子は受験勉強を教える先生ではありません。
ここで学ぶ対象は「礼」、文化のことです。
古くからの祭事の手順を学び、時期を見て実践練習してみるような感じですね。
机に向かって単語を覚え直すようなものとは異なるようです。
先日、書店で小倉紀蔵『新しい論語』という本を見つけました。
これが面白い本でした。論語をアニミズムの観点から再解釈するという内容です。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?