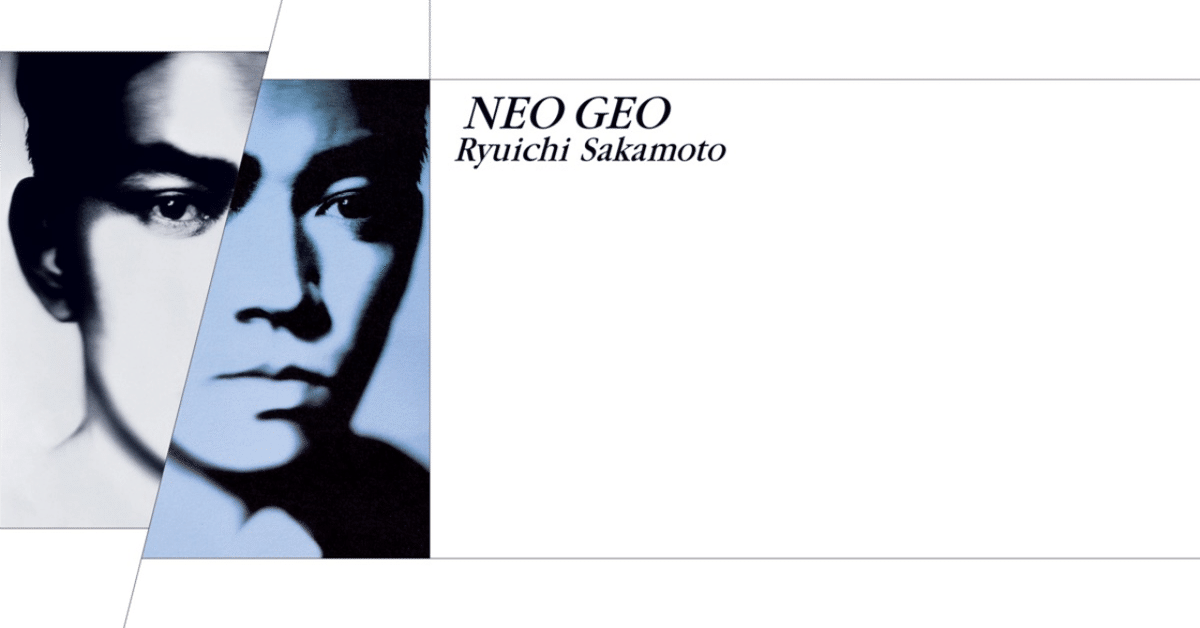
坂本龍一『NEO GEO』のリイシューに寄せて⑦
ノーウェイブとニューウェイヴ
前節ではフリクションのレックを取り上げることで、1970年代後半までの東京とニューヨークの温度感の違いを浮き彫りにすることで、当時の音楽的状況の変化や、坂本龍一とPASSレコードの微妙なスタンスの違いを明らかにした。
それでは、レックがニューヨークアンダーグラウンドシーンの空気を東京に持ち帰えるべく帰国した2年後の1980年、坂本龍一の音楽的な興味はどこにあったのだろうか。
当畤、吉祥寺には芽瑠璃堂という輸入レコード店があって、仕事の合間によく行っていました。その店で働いていたのが、後にPASS RECORDSを設立する後藤美孝くんだった。彼がまだ髪が長くて、ウェスト・コースト・サウンドが好きだった頃。その後、ぼくの仕事の方向も変わって吉祥寺に行く機会もなくなったのですが、79年かな。世の中がニューウェイヴの時代になった頃に彼からコンタクトがあったんです。今度、PASS RECORDSというものを始めたんだと。会ってみたら彼もニューウェイヴの人になっていて髪も以前より短くなっていた。そしてPASSで手がける予定のアーティストのデモ・テープを聴くと、そちらも、ぼくがその頃好きだったスロッピング・グリッスルなどのイギリスのニューウェイヴに近い感触があったんです。
上記引用のコメントにあるとおり、坂本龍一は後藤美孝と共鳴しながら、イギリスのニューウェーブに興味を持っていたのである。
この頃のYMOは2回目のワールドツアーの最中、東京でも話題となり、1980年に入ってからは、ライブアルバム『パブリック・プレッシャー』がオリコン1位を獲得し、過去のアルバムもすべてチャートインするなど、すでにYMOブームは到来していたのである。
1979年9月25日にリリースされ、1980年7月14日にはオリコン1位となる、YMOの2ndアルバム『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』について、細野晴臣は次のようにコメントしている。
1枚目のディスコ臭さから、もう1歩出たいという気持ちがあったと思います。恐らくニュー・ウェーブができつつあるころの、そういうスピリットに影響されているところはありますね。非常にアメリカ寄りだったのが、イギリス的になってきて。
このように坂本龍一がPASSレコードをコラボレーションする1980年は、ニューヨークのパンクシーンで生まれたノーウェイブではなく、イギリスを中心としたニューウェイヴが最先端の音楽として流行りつつあったのだ。
実際、フリクションがその中心的存在であった「東京ロッカーズ」というムーブメントも坂本は興味がなかったようである。
――その流れか、日本でも70年代末に東京ロッカ-ズという運動を生みます。坂本さんは、その象徴的な存在だったフリクションらを擁したPASSレ-ベルに関わり、ちょうど『B-2UNIT』に至る半年前ぐらいから、プロデュ-ス作を残していますよね
坂本:ええ。
――そうしたPASSでの実験か、初めて自身のソロに持ち込まれたのが『B-2UNIT』になったのかと
坂本:ではないですね。僕、東京ロッカ-ズとか全然知らなかったし、(関わるまで)聴いてもいなかった。
――PASSでプロデュ-スしたア-ティスト、フリクション、Phew、グンジョ-ガクレヨンなどが興味の対象としていたのではなく?
坂本:単に後藤(美孝/PASSプロデュ-サー)くんが面白がって。
――坂本さんに引き合わせたんですね
坂本:ええ。でも、あまり興味なかったですね。東京ロッカ-ズというムーヴメントには。
――わからないものとして関わったものか、たまたまレコ-ドとして残ったと。
坂本:東京ロッカ-ズというム-ヴメントはわからなかったけど、個々のア-ティストとしてPhewとかを見れば、フリ-・ミュ-ジック的視点から、なかなか面白い人たちだと思ったんですね。
そして興味深いのは、PASSでのプロデュースワークと自身ソロアルバム『B2-UNIT』への影響を明確に否定している点である。
これはPASSでのコラボレーションを、『B2-UNIT』制作の起点とする後藤美孝の見解とは異なる。
PASSでは坂本くんに、Phewやフリクションのプロデュースを頼みました。この作業の合間に、この音はこうしようと、お互いにアイデアを持ち寄り、結果的に、それが『B-2 UNIT』制作の起点になったような気がします。
それでは『B-2 UNIT』の制作にあたり、坂本龍一と後藤美孝に共通点はなかったのだろうか。この点について次節で検証していきたい。
アンディ・パートリッジという共通項
坂本と後藤をつなぐ共通項は、アンディー・バートリッジである。
実はXTCのアンディー・パートリッジの『テイク・アウェイ』が『B-2 UNIT』のモデルとなっていたのだ。
ちょうどフリクションのレコーディングをしている頃、XTCのアンディー・パートリッジの『テイク・アウェイ』がリリースされ、ぼくのところにアルバムの解説の依頼があったんです。時間もなかったので、坂本くんと吉祥寺時代からよくふたりで話していた音楽談義をそのまま文字に起こし、それを解説とすることにしました。このときのやりとりの中から『B-2 UNIT』の方向性のひとつが具体的なかたちになっていったのかなと思います。
後藤がこう語る一方で、坂本龍一もアンディ・パートリッジの影響についてストレートに言及している。
――この時期にソ囗・アルバムを出すことになった経緯は、何だったのでしょうか。
坂本:たぶん、YMOが売れたので、僕にもソ囗を作らないかって言われたんだと思うんです。あるいは自分から言ったのか。メンバーのソ囗を出そうという環境に自然になってたんですね。僕のほうは当時、ダブとかかなり実験的なものに入れ込んでいたので、こういう内容になるとは、アルファのほうは夢にも思わなかったんでしょうけど。アンディ・パートリッジのソロ・アルバム『テイク・アウェイ』にものすごく刺激を受けていたんで、ああいうものを作りたかったんです。
実際にXTCのアンディ・パートリッジや、スリッツやザ・ポップ・グループをプロデュースしていたデニス・ボーヴェルなどをゲストに迎えることになる。
――刺激を受けたというXTCのアンディ・パートリッジを含め、豪華メンバーが参加していますが、そうした参加メンバーや口ケーションはどのような経緯で決まっていったんですか?
坂本:それは、当時、刺激を受けていたもの全部ということで。ほとんどブリティッシュ・レゲエ傾向で、そういうものを好んで聴いていたんです。それで「こいつ面白いからやってもらいたい」ってお願いしまして。まあ、YMOが売れたんで、アルファでもそういうことができる環境にあったということでしょうね。普通、ちょっとあり得ないですから(笑)。
破格ともいえる条件でのソロアルバム作成が実現した背景には、アルファレコード副社長でYMOのエグゼクティブ・プロデューサーだった川添象郎の特別な図らいがあったことは否定できないだろう。
それは坂本龍一が2回目のワールドツアーに参加しないと表明したためである。
出発を目前に、坂本龍一は二度目の世界ツアー行きを渋っていた。前回のツアーでの疲労困憊を大きな負担だと感じていたようだ。まさかツアーを中止にするわけにもいかず、僕は半ば叱りつけるようにして坂本龍一を説得した。
「ツアーが終わったあと、ソロアルバ厶を制作しよう」と提案し、ようやく坂本はツアーへの参加を承知した。
たしかに坂本はYMOの脱退を決意したと後に告白している。
79年~80年にかけて、第1回のワールド・ツアーとそれに続く国内ツアーの後、細野さんにYMOをやめたいと正式にいった記憶がある
こうしてYMOの大ヒット、それに続く坂本のYMO脱退騒動により、ブリティッシュ・レゲエやニューウェイヴのアーティストを中心に、坂本龍一の海外ミュージシャンとの交流が本格化したのだった。
