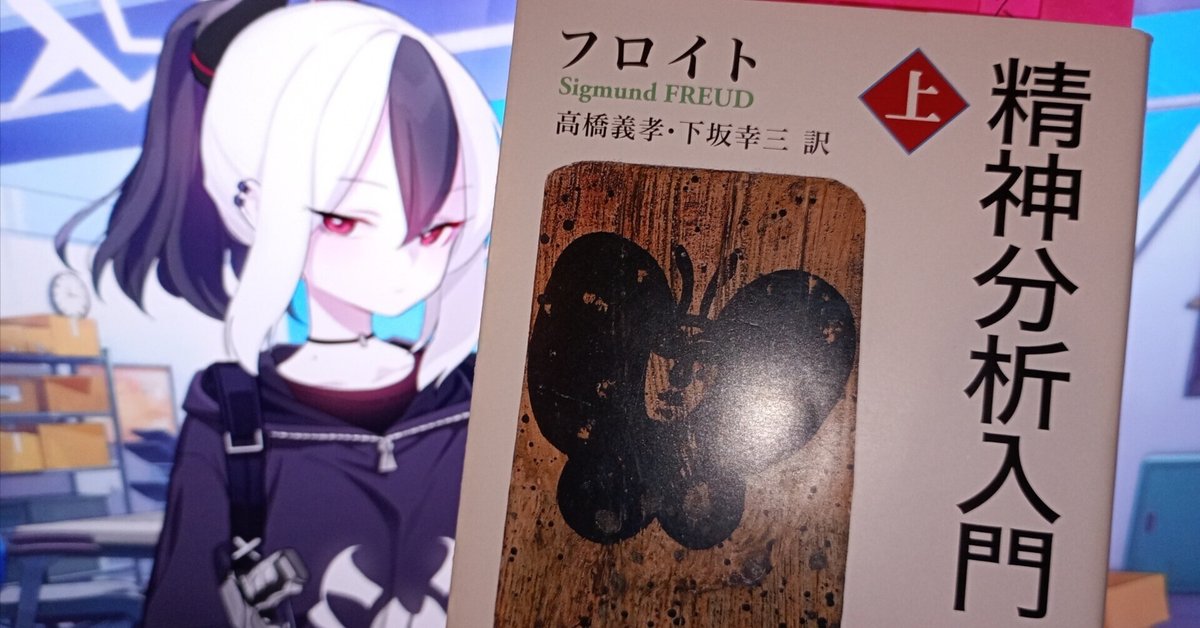
フロイトを読むと、"邪推"がはかどる【読書録】
実はあたしにはお付き合いしている方がいまして。鬼方カヨコっていうんですけど。
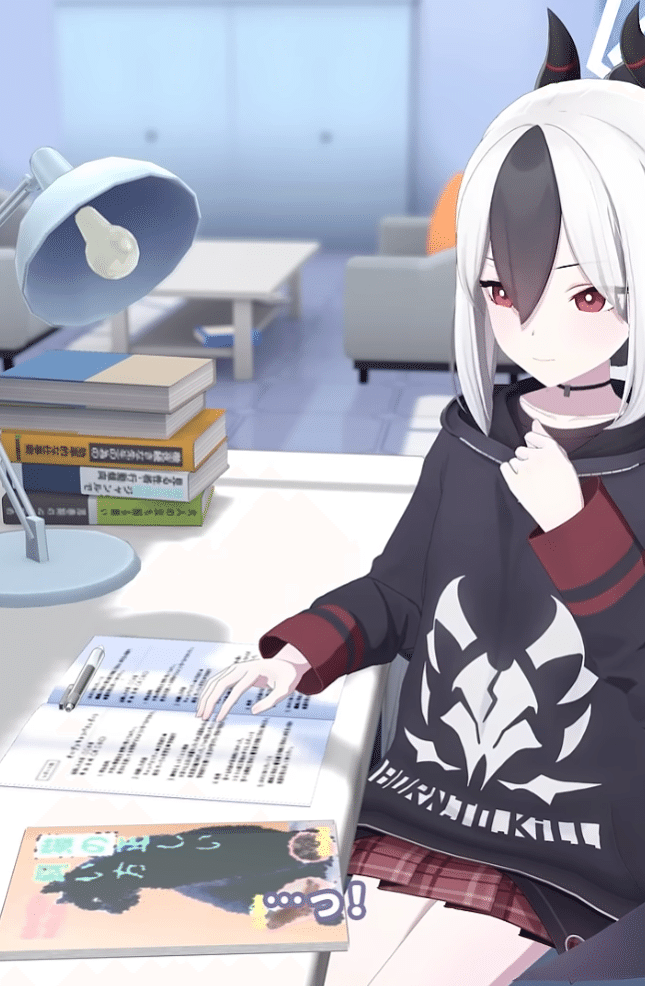
この子、「猫の本を出しっぱなしにしてしまう」といううっかりをしたことがあります。
普段はクールでしっかり者なのに、あたふたしちゃってかわいいね……😊 と、ギャップ萌えが光る一コマではあるのですが、こうした何気ない行動を"邪推"してしまうのがオタクの性というもの。
そもそもカヨコはなぜ猫が好きなのか。これまでの言動から察するに、かつて縛られていた過去があり、その時から続く孤独感や鬱屈した思いを野良猫に仮託している可能性があります。普段は警戒心が強く、気丈に振る舞っているけれど――信頼できる相手には、誰にも打ち明けられない自分の弱い一面や、寂しがり屋なところを知ってほしい。そんな思いを心の奥底で抱えていたからこそ、あのうっかりをしてしまったのかもしれません。要するに、本が偶然出しっぱなしになっていた、ではなく、無意識的な欲望や悩みが漏れ出てしまった。そう解釈することができるのではないでしょうか。
そう考えると、もう愛おしくてたまらなくなってしまって。やっぱりあたしが隣で支えてあげなきゃねですね。カヨコ、俺たち結婚しよう。
まあそんなオタクの妄想惚気話はさておき。何気ない台詞や言葉の端から"邪推"する、という経験は誰しもあるのではないでしょうか。それこそ登場人物の深層心理を読み解くだけではなく、メタ的視点に立てば、作家の思想や精神性を見出したり、note記事ではその文体や言い回しから、その人の生活風景を思い浮かべたり。やっぱこういう感覚ってあるあるだよなあと、先月からフロイトの著作を読みながら深く頷いています。
たとえば『夢判断』。曰く、「いかなる無意味な夢刺激物もない。したがってまたいかなる無邪気な夢もない」。覚醒するとただちに忘れてしまうようなどうでもいい夢、荒唐無稽な夢、あるいは見る者に苦痛を与えるような夢であっても、夢とは願望充足である。無意識的な欲望が、自意識の領域に辿り着かないよう、前意識によって検閲・歪曲された痕跡が残されている。その理論と実践例を、患者やフロイト自身の夢を元に展開する。
いわゆる夢占いとは一線を画す内容であり、人間に啓示を与えるといったオカルト的・象徴的解釈を排し、フロイトは臨床的に実践する。(いやいやさすがにそれはこじつけすぎでは……?🤔 と思ってしまう解釈もやはり少なくはないけれど)一見すると不可解な夢を緻密に検証することで、実は友人に嫉妬している、近親者の死を願っているといった、当の本人にとってもショッキングな潜在内容を明らかにする過程は、何気ない手がかりから真実を暴く名探偵の推理さながらだ。まず読み物としての面白さがある。そして、先に述べた"邪推"にも通ずるものがあって共感できる。なるほど、これは文学理論に応用されたのもわかる。古典として読み継がれているのも納得できる名著でした。
備忘録がてらもう少し語ると――1900年(実際は前年の11月)という節目に刊行された『夢判断』は、精神医学の分野だけではなく、文学理論や芸術分野に至るまで多岐に渡って影響を与えたのだそう。NHKブックスの解説書では、以下のように力強い言葉で示されている。
そして、フロイトが「無意識」を発見したことで、人間はついに自分自身の中心ですらなくなりました。フロイトの発見は、人間の前近代的なナルシズムに終止符を打ち、コペルニクスに始まる「人間の脱中心化」を完成させる一撃だったと言ってもよいでしょう。
意識で捉えられる自分は自分自身の中心ではないという認識。それこそが、ヒステリーや強迫神経症、恐怖症といった神経症に向けた第一歩であることは、フロイトにとって、もはや疑いようのないことでした。
(太字引用者)
これが誇張表現ではないことは『夢判断』を読み終えた今なら痛感できる。知的発見による爽快感だけではなく、昼間覚醒している自意識が、まるで得体の知れない他者にすり替わっていくかのような、不気味な感覚にすら陥るのだ。晩年の講義録『精神分析入門』では、無意識(エス)は混沌であり、あわれな自我は外界・超自我・エスという三人の暴君に仕えている、といった比喩表現がなされている。「人間の行動や思考は無意識に左右されている」とは、現代では一般常識として広く浸透している言説だが、それがどれほど恐ろしいものであるかを思い知らされた。世界の見え方、自分という存在の捉え方が、読む前と読む後で劇的に変わった。
どちらかと言えば私は「フロイトってあれでしょ? 幼児期のエディプス・コンプレックスや性衝動にこじつけたりするんでしょ?」という偏見を抱いている方だった。実際、男体のアナロジーとして読み解くような女性観は、現代人の感覚からすれば、はなはだ前時代的で受け入れがたい。しかしフロイト自身は少なくとも、夢や無意識的な欲望の分析について、決して安易に解答に飛びついてはならないと再三にわたり注意を促しており、読者への啓蒙を怠らない。
〔……〕換言すれば、人は自己の内部のものについては何も知らないのであって、それを自覚するにはある種の努力を要するのです。自我と意識、抑圧されたものと無意識とは一致しないのです。われわれは意識-無意識の問題に対するわれわれの態度に徹底的に検討を加える必要を感じます。
高橋義孝・下坂幸三訳
人間の無意識という"混沌"の領域に、一人の医者として立ち向かい、解明を試みる――『精神分析入門』におけるフロイトは、医者・科学者として、直面している問題や寄せられた反論に真摯に向き合い、そして初学者のために平易かつ丁寧に講義を進める姿が印象的だ。その誠実な姿勢には、かつて私が抱いていた偏見が覆されて、尊敬の念を抱き、一介のオタクとしても学べるものが多かった。文学理論や現代思想の本でよく名前を見かけるので何となく気になって手に取ってみましたが、思わぬ大収穫となりました。今年読む本の指針になりそうです。
そして、フロイトがまなざしを向けたのは、人間の無意識だけではない。晩年の彼は、ナチスによるユダヤ人迫害・ファシズムの脅威から逃れるためにロンドンに亡命し、その地で遺著となる『モーセと一神教』を刊行したのだという。

医者としてのフロイトは、社会に潜む病理を、時代という怪物を、どう読み解き、処方を試みたのか――とても興味が湧いたし、より視野が広がりそうなので、今月も引き続き読んでみます。何か発見があればまた備忘録としてまとめます。フロイトを読んだからにはユングやジャック・ラカンにも手を出してみたいですね。それではまたどこかで。
(鬼方カヨコさんに狂わされてた時の記録です)
