
きょうだい支援 #1 「きょうだい」って?
こんにちは、池ちゃんです。
僕の「noteでやっていきたいこと」で、自己紹介しましたが、僕は“きょうだい”なんです。
ひらがな表記の“きょうだい“についてご存知の人もいるかと思いますが、ひらがな表記の“きょうだい”とは、障がいのある者の兄弟姉妹を指します。そして、僕は発達障がいのある弟がいます。ここでは、きょうだいと兄弟姉妹を分けるために、障がいのある者を「同胞」とします。
きょうだい支援のPartでは、きょうだいとしての僕について、大学院で研究したことと共に、書いていきます。今回は、初回となるため“きょうだい”について紹介します。

1.はじめに
僕は、発達障がいのある弟と、生まれてからの20年間と社会人になって離れて暮らす10年以上を“きょうだい”として過ごしてきました。社会人(看護師)となって、きょうだいとしてボランティアへの参加や現在ではきょうだい支援の講演会を行い、そして大学院での研究を通して、きょうだい支援について考えてきました。
最近では、地域の支援団体様からお声をかけていただき、“きょうだいの話“をさせていただきました。そこでも、きょうだい支援のニーズが高いことを改めて認識しました。今後もきょうだい(当事者)として、声をあげていきたい、と強く思った経緯もあり、きょうだい支援のPartも作っちゃいました。

2.弟(発達障がいのある人)について
僕の弟は、発達障がいのうち、「自閉スペクトラム症」であり、先天性の脳機能障害と考えられています。また、対人関係が苦手であったり、強いこだわり、言葉の遅れ、会話が成り立たないといった特徴を持ちます。しかし、僕は疾患的なところは重要視していません。なぜなら、病的なのではなく、弟の性格(また、こだわり)だからです。
もちろん、看護師としての自分、としては発達障がいという疾患的な知識や観点は必要ですが、それ以前に、僕は“きょうだい”であるため、病気に着目するのではなく、生活や人生価値に重きをおくからです。
弟ちゃんは、とても平和主義で、真面目で頑なで、思いやりのある子です。そして、幼い時から兄弟喧嘩という喧嘩をしたことがありません。なぜなら、まず、会話が成り立たなかったからです。
今は、幼い頃からの言語訓練や特別支援学級から繋がる学校生活からの学び、たくさんの友人との交流で、社会人としてお仕事をしてます。なので、僕たちと同じように愚痴を言ったり、いろんな想いを絵で表現してくれたりしてくれてます。
あ!弟は、“絵”が得意(好き)なんです!!

これは、中学生(弟)だった頃に描いた絵です。これを見ると、弟の世界観がわかって嬉しかったです。個展もしてたので、いつも眺めては、「弟は何を思ってこれを描いたんだろう」と考えてました。
なので、他の家族の兄弟姉妹を見て、喧嘩をしているところを見たり、聞いたりすると羨ましかったんです。殴り合いたかったわけではありませんよ(笑)。考えを共有したり、自己開示したり、話し合いがしたかった、言い合いをしたかったんです。人は、“心”があります。弟のことを理解したい、という兄としての気持ちの表れだったかもしれません。
3.何も知らずに過ごしてきた幼少期
お出かけや遊びの一環として、施設や病院巡りをしていました。そして、何をするにも弟といつも一緒でした。
そこでは、弟と同じ発達障がいの子や知的障がいの子、身体障がいの子など、幼い頃から関わる機会が多かったです。母から聞いた話だと、脳性麻痺の子と関わっている時に、ヨダレが垂れていまってたので、母が拭こうとハンカチを手にとろうとしたときに、幼い時の僕は、自分の服で「大丈夫だよ」と拭いていたことを思い出すようです。
このように、僕の周りには障がいのある人がいて、その周りにはその人の家族がいつもいたんです。なので、社会人になっても、障がいのある人や関わっている家族を見ても、日常とギャップを感じなかったんです。というのは、障がいのある人は、社会からの差別や偏見(スティグマ)がある背景をもつためです。

4.特別支援学級へ
弟ちゃんも、学校へ行くことになりました。それは、弟ちゃんが初めて家族以外の人と過ごす社会に行く、ということにもなります。
弟が生まれた年は、今以上に“発達障がい”に対して差別や偏見(スティグマ)が多く、たくさんの勘違いや理解があったのかな、と思います。現代は、当時と比べたら緩和はされてきているのかな、と思います。しかし、まだまだスティグマからのいじめや冷たい視線は拭えないです。
スティグマについては、この先もずっと残るものだと思ってます。しかし、それがあっても、弟ちゃん含め、同胞の人たちも“自分らしく生きていける”、そして、きょうだいも“自分らしく生きる“社会を、これから作っていきたいです。きょうだいが、“かわいそう“ではなく、「きょうだいが作ってきた関係性が、同胞を守っている」のだ。ここについては、長くなりそうなので、また別のPartでエピソードを含め、書きますね。

そうなんです。弟は、クラスで浮いてる存在だったんです。だって、独り言を言いながら笑顔で同じ場所を行ったり来たりして、多動で、こだわりも強く、人と上手に会話もできないのですから。
僕にとっては、それが日常で可愛い可愛い弟ちゃんなんです。けど、その友達や学校の子達、その親にしたら“異常”なんですね。なので、いじめもありましたよ。けどね、ここで守り続けてくれたのが、“僕の友達たち“だったんです。
そうなんです、それが先ほど言った「きょうだいが作ってきた関係性が、同胞を守っている」ことなんです。そこが、これから作るきょうだい会のビジョンであり、目指すものでもあり、きょうだい支援なんです!

学校に連れて行くにも一苦労していたようですよ(↑右上にいる人が班長なんですが、置いてけぼりですね。笑)
多動だけど、こだわりの場所であったら突然動かなくなるなどなど、僕自身が体調崩したりもしてたようです(覚えてませんが✌️)。けど、それでも可愛い可愛い弟ちゃんです。

たなばたのお願い事に、「〇〇(弟)くんのあたまのびょうきをなおしてください」とお願いしてたみたいですね!
5.みんないっしょだよ
僕が、小学校2年生の時に書いた作文があります。「話し方大会」という大会があって、そこで作文発表をしました。
その作文に、当時の想いや僕の育ちが書いてあると言ってもいいぐらいです。ここでは、長くなりすぎるので、別枠(きょうだい支援#2「みんないっしょだよ」)で紹介しますね。読んでいただけると嬉しいです。
6.そして、弟の想いを考えるようになる
弟ちゃんは、“何を想っているのだろう“と考えることが多くなってきました。よく、独り言を言っているけど、よく同じ場所を行ったり来たりしているけど、洗濯物かごに入って好きな漫画を見ているけど、、一体弟ちゃんは何を想っているのだろうか。


弟ちゃんのこだわりとして、よく独り言を言っていたり、同じ場所を行ったり来たりして、洗濯かごを見つけたら、その中に入って好きな漫画を見たり。たくさんありますが、それをやってる時の弟ちゃんの顔が、とても笑顔なんですよね。ノンストレス、というのか。あとは、弟のモノマネをよくしてました。よく独り言を言っていたり、同じ場所を行ったり来たりしていたので、モノマネをしていたら…楽しくなっちゃったんですよね(笑)。弟ちゃんには、「バカにしないでよ!」と、怒られてました(笑)
けど、弟ちゃんのことを知れている自分が嬉しかったんです。だって、自己表現することが苦手で、会話も上手にできない弟ちゃんだからです。

7.表現方法は、人それぞれで良い
僕たちもそうですが、自分自身の表現方法なんて、人それぞれですよね。なんら変わりないんですよ。こだわりも価値観も人それぞれじゃないですか。じゃあ、同胞の子達は何が違うんですか?いのちがあることは一緒なんじゃないですか?…
少し熱くなってしまいましたね。スティグマを持つ人たちは、自分の価値観を押し付けている、いわゆる“わがまま”であり、“自分軸”がない人たちであると思うんです。
そしたら、同胞の子達が何を持っていて(好きなことや得意なこと、こだわりなど)、それがその子達の表現方法であったら?
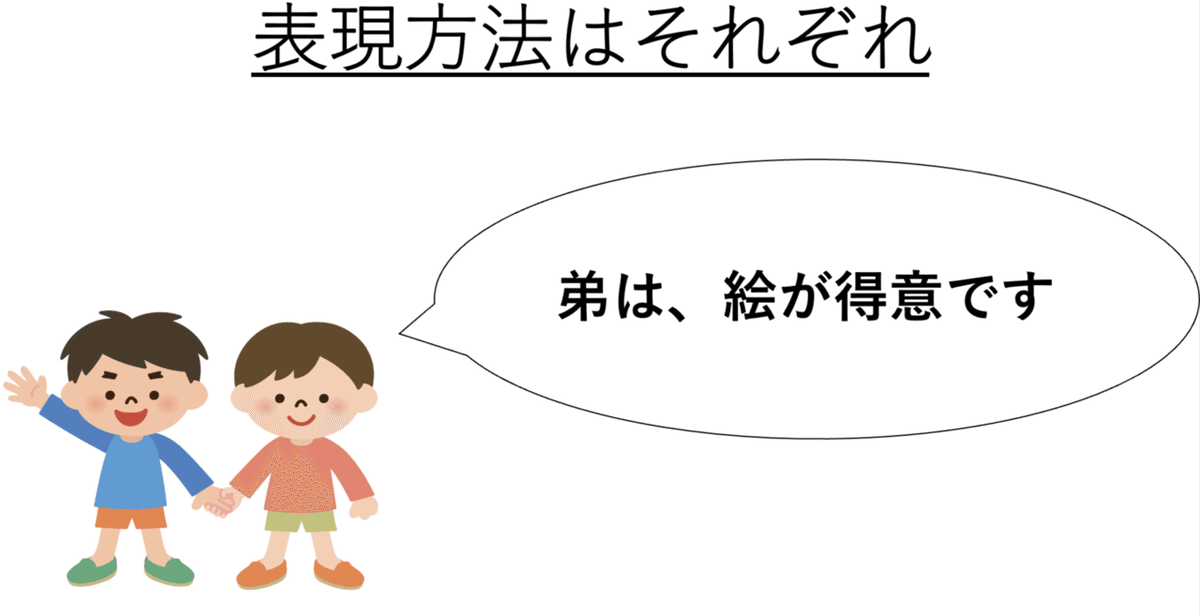
弟ちゃんは、絵が得意で、特に毎日欠かさず漫画や絵を描いてます。すごいですよね、“欠かさず“です。真面目なんです。
先に紹介しちゃいましたが、トマトの絵を見ると

「がぶっとかじったら しるが ぴゅう〜っ」
中学生ぐらいの弟ちゃんですが、すごいですよね。いつトマトをかぶりついたのか、実際に体験した弟ちゃんのことを想像すると笑顔になります。
このように、絵を伝って想いを表現しているのかなって。弟ちゃんの感性はすごいんです。
あとは、個展をしていたときもあり、絵を買いたい!という方もいたようですね。
8.県を出て、俯瞰的に見れるようになる
看護師となり、実家を出て(県外)病院に就職しました。実家から離れることで、きょうだいとしての僕、というよりは、看護師としての僕や本来の自分自身としての僕でいるようになりました。
そうしてると、俯瞰的にきょうだいとしての僕を見れるようになり、自分自身と向き合うことが多くなりました。そして、親亡きあとのことを考えるようになりました。
そして、看護師として働きながら、きょうだいについての研究を、当事者として、自身のライフワークとして福祉の大学院で行いました。
「自分らしく生きること」に着目して、2年間。がんばりました。このプロセスが今のきょうだい支援活動の糧となり、エネルギーとなってます。
9.今の自分(価値)があるのは、「弟がいる家庭環境から」
隣には、弟ちゃんがいて、その弟と関わる両親の姿を見て、僕の価値(また、障がい者観)があります。そして、僕の周りには、いつも障がいのある人やその家族がいました。
弟がいなければ、看護師にもなっていません。そして、今ある環境や友人、仲間とも会えていません。本当に素敵な出会いを、弟ちゃんが繋げてくれています。

“お互いに承認し合うこと“
僕たちに足りないこと、だと感じてます。
10.最後に
僕が尊敬している、“相田みつを“さんの作品から1つ皆さんに紹介します。
「トマトとメロン」

一人ひとり、違って良いじゃないですか。
その人の価値は、少しも、1mmたりとも変わらないんですよ。
そのままで良いじゃないですか。
そんな自分は、世界に1人だけですもの。
だから、良いんですよ。そのままで。
今回も、読んでいただきありがとうございました。
今後も、きょうだいとして生き生きと活動していきます。たくさんの繋がりができたら嬉しいです。
他にも、医療現場での看護師の視点や趣味で描いている筆ペン活動もしていきます。
コロナ禍だからこそ、一緒に“繋がりの輪”を拡げていきましょう!
