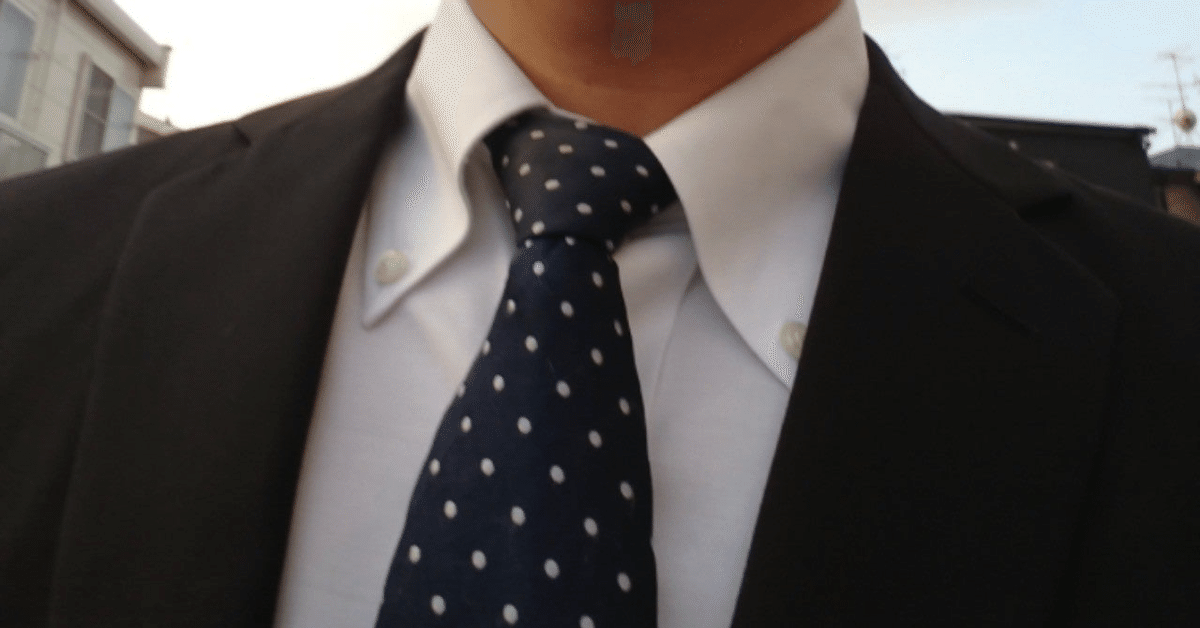
ビジョナリー・カンパニー② 飛躍の法則
読書記録です。
肝心な所は忘れてしまいましたが、何かの本を読んでいた中でこの著書について触れていたので気になって読んでみたのがきっかけ。
著書の紹介
タイトル:ビジョナリー・カンパニー② 飛躍の法則
著者:ジェームズ・C・コリンズ(山岡洋一 訳)
出版社:日経BP社(2001年12月21日第一版第一刷)
(今回読んだのは2008年5月23日 第一版第十八刷)
概要
1994年に出版され、経営書としてベストセラーになった『ビジョナリー・カンパニー』(Built to Last)の著者が、6年の歳月をかけて築き上げた本。
(背景には調査チームも多数おり、延べ1万五千時間にも及ぶ調査に渡ったことを言及している。)
タイトル通り飛躍への法則にフォーカスを当てた本で、長きに渡る調査の中で厳選された、偉大な企業へと飛躍を遂げた企業にみられる共通の法則を記載している。
調査対象の十一企業と、比較対象の企業を対比して飛躍と転落のストーリーが語られている。
章ごとに要約がまとまっており、基本的には要約部分の引用と少しの所感といった構成の読書感想になる点ご承知おきください。
第一章は以降の章で詳細に語られる内容の総括的な内容になるので、割愛。
第九章 ビジョナリー・カンパニーへの道についても割愛。
第二章 野心は会社のために
偉大な企業への転換を成し遂げた際のCEOが備え持つ『第五水準のリーダーシップ』をベースに直接対象企業との決定的な違いを交えつつ内容は展開される。
要点
・偉大な実績に飛躍した企業はすべて、決定的な転換の時期に第五水準の指導者に率いられていた。
・「第五水準」とは、企業幹部の能力に見られる5つの水準の最上位を意味している。第五水準の指導者は個人としての謙虚さと職業人としての意志の強さという矛盾した性格をあわせ持っている。野心的であるのは確かだが、野心は何よりも会社に向けられていて、自分個人には向けられていない。
・第五水準の指導者は次の世代でさらに偉大な成功を収められるように後継者を選ぶが、第四水準の経営者は後継者が失敗する状況を作り出す事が少なくない。
・第五水準の指導者は徹底して謙虚であり、控えめで飾らない。
・第五水準の指導者は、熱狂的と言えるほど意欲が強く、すぐれた成果を持続させなければ決して満足しない。偉大な企業への飛躍に必要であれば、どれほど大きな決定でも、どれほど困難な決定でも下していく。
・第五水準の指導者は職人の様に勤勉に仕事をする。見栄えの良い馬より農耕用の馬に近い。
・第五水準の指導者は成功を収めた時は窓の外を見て、自分以外に成功をもたらした要因を見つけ出す。結果が悪かったときは鏡を見て、自分に責任があると考える。
・第五水準の指導者になりうる人材は、どの点に注目して探せばいいのかが分かれば、周囲にたくさんおり、第五水準になりうる素質を持った人が多いとみられる。
P62~63 章の要約
予想外の調査結果
・非凡で有名な変革の指導者の招聘は、偉大な企業への飛躍とその持続との逆相関の関係にある。飛躍を導いた十一人のCEOのうち十人は社内からの昇進であり、比較対象企業は外部の人材を招聘した頻度が六倍も高かった。
・第五水準の指導者は成功をもたらした要因として、個人の偉大さではなく、幸運を挙げている。
・われわれは当初、第五水準のリーダーシップやそれに近いものを探していたわけではないが、データの圧倒的な説得力によって、この概念に行き着いた。第五水準のリーダーシップは事実から導き出された概念であり、何らかの思想に基づく概念ではない。
P64 章の要約
第五水準までの段階として第一~第四の水準は以下のように本書では記載されている。
・第一水準・・・有能な個人
→才能、知識、スキル、勤勉さによって生産的な仕事をする。
・第二水準・・・組織に寄与する個人
→組織目標の達成のために自分の能力を発揮し、組織の中でほかの人たちとうまく協力する
・第三水準・・・有能な管理者
→人と資源を組織化し、決められた目標を効率的に効果的に追及する
・第四水準・・・有能な経営者
→明確で説得力のあるビジョンへの支持と、ビジョンの実現に向けた努力を生み出し、これまでより高い水準の業績を達成するように組織に刺激を与える。
<所感>
真摯に情熱的でいてかつ熱狂的でありまっすぐに強い意志を持った謙虚で誠実な人で……と悪い表現をすればいいとこ取りの人間であるのがまさに第五水準の人間。
理想的ではありつつも、私が師として仰いだ10年上の先輩は間違いなくその素養を持った私利私欲にとらわれず真っすぐな目標に向かって我々を正しく指導してくれる人間だったが、大義名分のもと別の部署へと。。。
次の章で語られるが、適切な人材としてバスに乗せられていったのかどうかは現時点ではわからないが少なくとも私は違和感を感じたままでいる。
第三章 だれをバスに乗せるか
読めば読むほど章題の意味がわかる。私の会社の中で始まっていた悪循環に対する皮肉も鑑みて、特に好きな章だった。
章の要約 ~最初に人を選び、その後に目標を選ぶ~
・偉大な企業への飛躍を導いた指導者は、まずはじめに、適切な人をバスに乗せ、不適切な人をバスから降ろし、次にどこに向かうべきかを決めている。
・適切な人材を集めることだけではない。「だれを選ぶか」をまず決めて、その後に「何をすべきか」を決める。ビジョンも、戦略も、戦術も、組織構造も、技術も、「だれを選ぶか」を決めた後に考える。そのあとに「何をすべきか」を決める。この原則を厳格に一貫して適用する。
・比較対象企業は、「一人の天才を一千人で支える」方式をとっている場合が多い。天才的な指導者がビジョンを確立し、ビジョンを実現するために有能な兵士を集める方式である。この方式は天才が退けば崩れる。
・飛躍を導いた指導者は、人事の決定に厳格であって冷酷ではない。行政機構上の主な戦略としてレイオフやリストラを使うことはない。比較対象企業はレイオフをはるかに頻繁に使っている。
・人事の決定で厳格になるための実際的な方法
1.疑問があれば採用せず、人材を探し続ける(関連する点として、成長の最大のボトルネックは何よりも、適切な人々を採用し維持する能力である)。
2.人を入れ替える必要があることが分かれば、行動する(関連する点として、まず、坐っている席が悪いだけなのかを確認する。)
3.最高の人材は最高の機会の追及にあて、最大の問題の解決にはあてない(関連する点として、問題の分を売却する決定をくだしたとき、優秀な人たちを一緒に売り渡してはいけない)。
・偉大な記号への飛躍を導いた経営陣は、最善の答えを探し出すために活発に議論し、方針が決まれば、自分が担当する部門の利害を超えて、決定を全面的に支持する人たちで構成されている。
P101~102 章の要約
意外な調査結果
・経営陣の報酬と飛躍とを結びつけるような一貫したパターンは発見できなかった。報酬制度の目的は、不適切な人々から正しい行動を引き出すことにはなく、適切な人をバスに乗せ、その後もバスに乗り続けてもらうことにある。
・「人材こそがもっとも重要な資産だ」という格言は間違っている。人材は最重要の資産ではない。適切な人材こそがもっとも重要な資産なのだ。
・どういう人が「適切な人材」なのかは、専門知識、学歴、業務経験より、性格と基礎的能力によって決まる。
P102 章の要約
<所感>
多くの企業ではこのバスに乗る人々の選別が不適切な例が多いのではないかと感じた。
思うところが色々とある章だったのでぜひ色々な方に目を通してもらいたい部分であった。
大事なことは要約にキレイにまとめられているのでそちらを読みかえしていただくほうが良い……
第四章 最後にはかならず勝つ
章の要約 ~厳しい現実を直視する~
・偉大な実績に飛躍した企業はすべて、偉大さへの道を発見する過程の第一歩として自分がおかれている現実の中でももっとも厳しい現実を直視している。
・自社がおかれている状況の真実を把握しようと、真摯に懸命に取り組めば、正しい決定が自明になることが少なくない。厳しい現実を直視する姿勢を貫いていなければ、正しい決定をくだすのは不可能である。
・偉大な企業に飛躍するためにまず行うべき点は、上司が意見を聞く機会、そして究極的には真実に耳を傾ける機会が十分にある企業文化を作り上げることである。
・上司が真実に耳を傾ける社風を作る基本的な方法が四つある。
⑴答えではなく、質問によって指導する。
⑵対話と論争を行い、強制はしない
⑶解剖を行い、非難はしない
⑷入手した情報を直視できない状況に変える「赤旗」の仕組みを作る。
・飛躍した企業は、比較対象企業と変わらぬほど逆境にぶつかったが、逆境への対応の仕方が違っている。厳しい現実に真っ向から取り組んでいる。この結果、逆境を通り抜けた後にさらに強くなっている。
・偉大さへな飛躍を導く姿勢のカギは、ストックデールでの逆説である。どれほどの困難にぶつかっても、最後にはかならず勝つという確信を失ってはならない。そして、同時にそれがどんなものであれ、自分がおかれている現実のなかでとっとも厳しい事実を直視しなければならない。
P.140~141 章の要約
意外な調査結果
・カリスマ性は強みになると同時に、弱みにもなりうる。経営者が強い個性を持っているとき、部下が厳しい現実を報告しなくなりかねない。
・リーダーシップはビジョンだけを出発点とするものではない。人々が厳しい現実を直視し、その意味を考えて行動するよう促すことを出発点とする。
・従業員や幹部の動機づけに努力するのは、時間の無駄である。ほんとうの問題は、どうすれば従業員の意欲を引き出せるか」ではない。適正な人たちがバスに乗っていれば、全員が意欲を持っている。問題は、人々の伊予kを挫かないようにするにはどうすればいいのかである。そして、厳しい現実を無視するのは、やる気をなくさせる行動の中でもとくに打撃が大きいものだ。
P.141 章の要約
<所感>
大きな困難に直面したとしても、現実を受け止めたうえで、適切な人々との適切な対話を通じて理解を深めるということに重きを置く必要性について考えさせられる章だった。
第二章の鏡の話とも通ずる部分があるが、もっぱら典型的な偉大ではない大きい企業体であればあるほどこの点はまるでダメだと感じさせられる。
赤旗の仕組み・・・ただ目の前に情報があるという状態でそれを見なければ意味は無いので、しっかりと無視できない現実として受け止めるための情報に変化させなければならない。
ストックデールの逆説・・・ベトナム戦争の最盛期、「ハノイ・ヒルトン」と呼ばれた捕虜収容所で、最高位のアメリカ人だったジム・ストックデール将軍に因んだ言葉。困難にぶつかった際、現実を受け止め、そしてあきらめず楽観視せずに立ち向かうことの大切さを語っている。
第五章 単純明快な戦略
針鼠と狐をモチーフに偉大への飛躍を成し遂げた企業とそうでない企業の対比を物語る。
要点
・偉大な企業になるためには、三つの円(情熱をもって取り組めるもの、経済的原動力になるもの、自社が世界一になれる部分)の重なる部分を深く理解し、単純明快な概念(針鼠の概念) を確立する必要がある。
・その際のカギは、自社が世界一になれる部分はどこか、そして同様に重要な点として、世界一になれない部分はどこかを理解することである(世界一に「なりたい」分野ではない)。
・針鼠の概念は目標でも戦略でも計画でも意思でもない。理解である。
・中核事業で世界一になれないのであれば、中核事業は針鼠の概念の基礎にはなりえない。
・世界一になれるとの理解は、中核的能力(コア・コンピタンス)よりもはるかに厳しい基準である。能力があっても本当に世界一になれるほどの能力だとは限らない。逆に世界一になれる事業があるが、現在はその事業について能力がない場合もある。
・経済的原動力になるのが何かを見つけ出すには、最大の影響を与えるひとつの分母を探し出すべき(「一人あたり利益」や、「地域あた利益」といった「XX利益」など。)
・偉大な実績に飛躍した企業理解に基づいて目標と戦略を設定している。(虚勢に基づいて目標と戦略を設定していては偉大にはなれない)
・針鼠の概念の確立は、反復の過程である。(評議会が有益な手段になりうる)
P187~188 章の要約
意外な調査結果
・偉大な実績に飛躍した企業は針鼠に似ている。針鼠は単純で冴えない動物だが、たったひとつ、肝心要の点を知っており、その点から離れない。(対比して、偉大になれない企業は狐に似ている。狐は賢く、様々な点を知っているが、一貫性がない。)
・飛躍した企業は、針鼠の概念を獲得するまでに平均四年かかっている。
・戦略を確立しているという点では偉大な企業とそうでない企業に違いはないが、飛躍した企業のほうが戦略の開発に時間とエネルギーをかけたといえる事実は全くなかった。
P188~189 章の要約
<所感>
本章を通じて必要だと感じた点をさらに短くまとめると大きく以下の2点と感じた。
1.複雑な世界をシンプルにとらえること
2.本質を見抜き、本質以外の点を無視する力に長けていること
私が属している企業グループでも、「世界一」の称号を頂いているものはあるのに、多角的にという建前で攻めようとしていて”狐"だなぁと感じる部分も多々あり……時代に流されやすく典型的な一貫性の無い事業体になっている気がする。
次章でも語られる"規律の文化"のポイントが欠けている所以だと感じる。
第六章 人ではなく、システムを管理する。
規律について語った章。この本の内容としてもかなりの部分は規律の文化をいかに作り上げるかに関するものである。
章の要約 ~規律の文化~
・偉大な業績を維持するカギは、自ら規律を守り、規律ある行動をとり、三つの円が重なる部分を熱狂的ともいえるほど重視する人たちがあつまる企業文化を作り上げることにある。
・官僚制度は規律の欠如と無能力という問題を補うためのものであり、この問題は不適切な人をバスに乗せていることに起因している。適切な人をバスに乗せ、不適切な人をバスから降ろせば、組織を窒息させる官僚制度は不要になる。
・規律の文化には二面性がある。一方では一貫性のあるシステムを守る人たちが必要だ。しかし他方では、このシステムの枠組みのなかで、自由と責任を与える。
・規律の文化は行動の面にかぎられるものではない。規律ある考えができ、つぎに規律ある行動をとる規律ある人材が必要である。
・飛躍した企業は、外部からみれば退屈だとか月並みだとか思えるかもしれない。しかし内部をくわしく見ていくと、極端なほど勤勉で、おどろくほど徹底して仕事に取組むひとったちが大勢いる。
・規律の文化と規律をもたらす暴君とを混同してはならない。このふたつは全く違ったものであり、規律の文化は極めて有益だが規律をもたらす暴君は極めて有害である。救世主のCEOが強烈な個性によって規律を持ち込んだ場合、偉大な業績を維持できないのが通常だ。
・偉大な業績を維持させるために最も重要な点は、針鼠の概念を熱狂的ともいえるほど信奉し、三つの円の重なる部分に入らないものであれば、どんな機会でも見送る意思を持つことである。
P228~229 章の要約
意外な調査結果
・宗教的ともいえるほどの一貫性をもって、三つの円の重なる部分に泊まる規律を持つほど、成長と貢献の魅力的な機会が増える。
・「一生に一度の機会」であっても、三つの円が重なる部分に入っていないのであれば、飛びつく理由はまったくない。偉大な企業になれば、そのような機会にたくさんぶつかるようになる。
・超優良に飛躍した企業では、予算編成は、それぞれの活動にどれだけの資金を割り当てるかを決めるべきものではない。どの活動は針鼠の概念に最適で、したがって集中的に強化すべきか、どの活動は完全に廃止すべきかを決めるものである。
・「止めるべきこと」のリストは、「やるべきこと」のリストよりも重要である。
P229 章の要約
<所感>
しっかりと、見据えた枠の中に適切におさまり行動すべきことの重要性を説いた章だった。
文中の以下の内容がすべてを表現している。
第五水準の指導者がいて、適切な人をバスに乗せ、厳しい現実を直視する規律をもち、真実に耳を傾ける社風を作り出し、評議会を作って三つの円が重なる部分で活動し、全ての決定を単純明快な針鼠の概念にしたがって、虚勢ではなく現実の理解に基づいて行動すれば、正しく選択した分野への非分散型投資戦略を行う事ができる。
第七章 新技術にふりまわされない
インターネットバブル期の世界の転換期をもとに偉大な企業の歩んだ道を解析。
章の要約 ~促進剤としての技術~
・偉大な業績への飛躍を遂げた企業は、技術と技術の変化について、凡庸な企業とは違った考え方をしている。
・飛躍した企業は技術の流行に乗るのを避けているが、慎重に選んだ分野の技術の利用で先駆者になっている。
・どの技術分野に関しても決定的な問いは、その技術が自社の針鼠の概念に直接に適合しているのかである。この問いへの答えがイエスであれば、その技術の利用で先駆者になる必要がある。ノーであれば、ごく普通に採用するか無視すればいい。
・技術は適切に利用すれば業績の勢いの促進剤になるが、勢いを作り出すわけではない。偉大な企業に飛躍した企業が、先駆的な技術の利用によって転換を始めたケースはない。しかし、三つの円を理解するようになり、業績が飛躍するようになった後に、どの企業も技術の利用で先駆者になっている。
・飛躍した企業が開発した最先端技術を直接比較対象企業に無料で提供しても、比較対象企業は偉大な企業に近い業績を上げることはできないだろう。
・技術の変化にどのように反応するかは、偉大な企業と凡庸な企業の同期の違いを見事に示すものになる。偉大な企業は思慮深く、創造性豊かに対応し、自社の可能性を実現したいとの動機によって行動する。凡庸な企業は受け身になって右往左往し、取り残されることへの恐怖によって行動する。
P.260 章の要約
予想外の調査結果
・かつて超優良であった企業の没落(そしてほとんどの企業が凡庸さから抜け出せていないこと)が技術の変化を主因とするものだとの見方を支える事実はでてこなかった。たしかに技術面で遅れていては、偉大な企業にはなれない。しかし、技術そのものが偉大な企業への飛躍や偉大な企業の没落の主因になることはない。
・偉大な業績への飛躍を見びいた経営幹部を対象に行ったインタビューでは、全体の八十パーセントは、飛躍をもたらした上位五つの要因の一つとして技術をあげてはいない。
・技術が急激に大幅に変化する時期にすらも、「這い、歩き、走る」方法が極めて効果てきになりうる。
P.261 章の要約
<所感>
技術は業績の勢いの源でなく、促進剤。
技術そのものでは、汎用な企業を超優良な企業に飛躍させることはできないし、企業の没落を防ぐこともできない。
という点については特に同感であった。
昨今ではDX,AI活用といったワードでありふれている業界ですが、なんでもかんでもとりあえず流行に乗っておこうという、まさに今日によっての行動という感じが否めない。
第八章 劇的な転換はゆっくり進む
弾み車の比喩を用いて飛躍に向かう動きを捉えた章。
章の要約 ~弾み車と悪循環~
・偉大な企業への飛躍は、外部からみれば劇的で革命的だとみえるが、内部から見れば生物の成長のような積み重ねの過程だと感じられる。最終的な結果(劇的な結果)と過程(生物の成長のような積み重ねの過程)を混同すると、見方がゆがんで、実際には長期的にわたる動きであることが見えにくくなる。
・最終結果がどれほど劇的であっても、偉大な企業への飛躍が一気に達成されることはない。決定的な行動、壮大な計画、画期的な技術革新、たったひとつの幸運、魔法の瞬間といったものはない。
・偉大さを持続できる転換は、準備段階から突破段階に移行するパターンをつねにたどっている。巨大で重い弾み車を回転させるのに似て、当初はわずかに前進するだけでも並大抵ではない努力が必要だが、長期にわたって、一貫性をもたせてひとつの方向に押し続けていれば、弾み車に勢いがつき、やがて突破段階に入る。
・比較対象企業はこれとは全く違う「悪循環」のパターンに陥っている。はずみ車を押し続けて一回転ずつ勢いを積み重ねていくのではなく、準備段階を飛び越して一気に突破段階に入ろうとする。そして業績が期待外れになると、右往左往して一貫した方向を維持できなくなる。
・比較対象企業は、賢明とはいえない大型合併によって突破口を開こうと試みることが多い。これに対して、偉大な実績に飛躍した企業は通常、突破段階に達した後に、すでに高速で回転している弾み車の勢いをさらに加速する手段として、大型買収を使っている。
P.295~296 章の要約
意外な調査結果
・飛躍した企業の内部にいた関係者は、転換の時点ではその規模の大きさに気づかず、後に振り返ってみてはじめて、大規模な転換であったことに気づいている場合が少なくない。転換の動きには名前や、標語や、開始の式典や、特別な計画など、何か特別なことをやっていると思わせるものは何もなかった。
・偉大な企業への飛躍を導いた指導者は「力の結集」「従業員の動機づけ」「変化の管理」にはほとんど力を入れていない。条件がうまく整えば、意欲や力の結集や動機づけや改革への支持の問題は、自然に解決する。力の結集は主に実績と勢いの結果であり、逆ではない。
・短期的な業績向上を求めるウォール街の圧力は、弾み車の方法と矛盾しない。弾み車効果はこうした圧力の下で発揮できないわけではない。それどころか、こうした圧力に対応する際のカギになる。
P.296 章の要約
<所感>
偉大への道は、一貫性を持った行動の小さな努力の積み重ねによって開かれていく。
当たり前の様なことでもこれが出来ると出来ないで大きな違いが出るということを改めて示された内容だった。
<本書全体を通しての所感>
第九章 ビジョナリー・カンパニーへの道については今回の読書記録で触れていないが、筆者は前著「ビジョナリー・カンパニー」の前編に今回の著書はあたると記載している。
残念ながら筆者は前著を読んでいないため今回は割愛したが、いつか前著を読んだ際に併せて記述したいと考えている。
付録の調査方式部分もなかなかのボリュームで延べ調査時間の大きさを物語っている。今回の著書の内容に至った経緯が読み解ける資料になっているので、興味がある方はぜひこちらも見ていただきたい。
予想外の調査結果は本当に予想外の部分も多くあった。
筆者も第九章で記述していたが、これら偉大への法則を適用して大がかりな改革をせよと勧めているわけではない点に留意したうえで、ビジネスマンの一参考として頭に入れておけば良いという内容だったと感じる。
