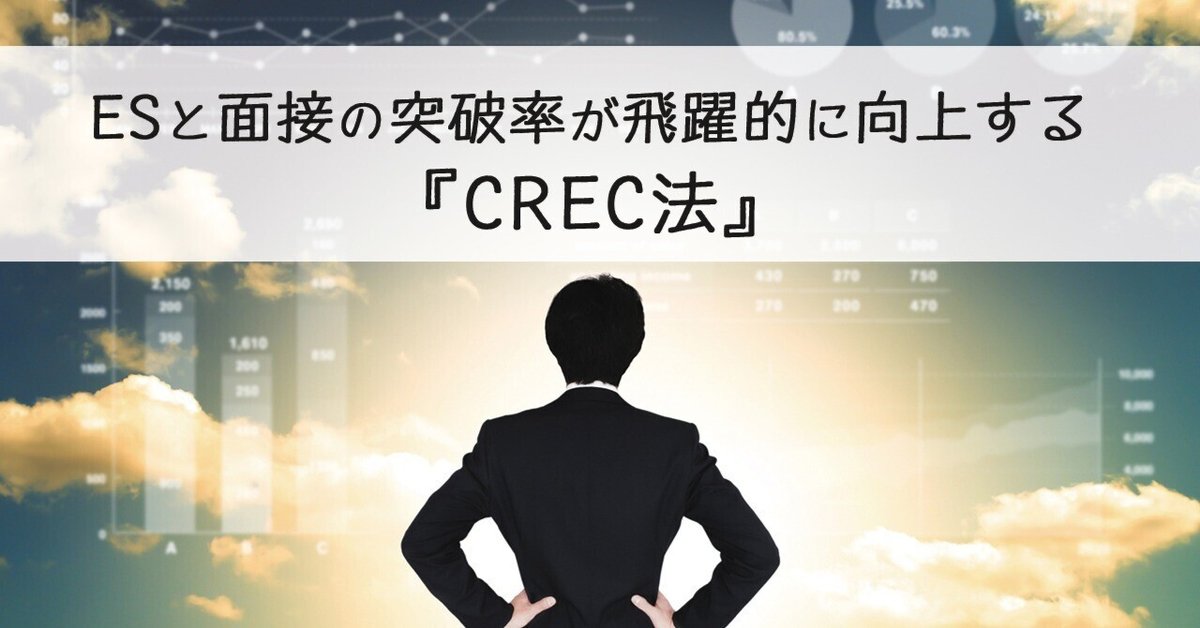
ESと面接の突破率が飛躍的に向上する『CREC法』
※当記事は約4分で読めます【約1,600文字】
1. CREC法とは
伝え方の型と言われている『CREC法』というものがあります。
C:Conclusion<結論>
R:Reason<理由>
E:Example<具体例>
C:Conclusion<結論>
① まず結論を伝えて、
② 次に結論に対する理由を述べる。
③ そして、理由の根拠となる具体例を添えて説得力のあるものにする。
④ 最後に、②と③で述べたことからも結論である
という順に説明していく流れが『CREC法』です。
これは、就活生だけでなく、社会人もよく利用している型です。
『CREC法』を意識することで、自分の意図が飛躍的に相手に伝わりやすくなります。
2. 『CREC法』がなぜ有効なのか
一つの結論に対して相手に共感してもらいたい時に、話す内容に含まれているべき要素が『CREC』です。
これを意識するだけで、数々の説得要素を「これでもか」というくらい相手にぶつけるよりも、伝えたいことがはるかに的確に相手に伝わるようになります。
そして、『CREC』は相手にとっても、必要な情報が頭の中で整理しやすく、ストレスなく聞きやすい順番になっています。
つまり、『CREC』は人が情報を受け取る時、頭の中で整理しやすい順番となっているため、自分の考えが整理しやすくなるだけでなく、聞き手にとっても内容が頭に入ってきやすく、印象にも残りやすくなります。
この有効性について、わかりやすいように『CREC』を使った場合とそうでない場合の比較をしながらまとめてみます。
『CREC』を意識した場合
・伝えたい内容をまとめる際、フレームワークに沿って簡潔に整理しやすい
・「CREC」の順番を意識することで、相手にわかりやすく伝えることができる
・説得に必要な要素が網羅されているため、共感を得やすく印象に残りやすい
『CREC』が意識できていない場合
・話の内容が整理できていない=支離滅裂になる
・話す順番を気にしていないため、ダラダラと長くなりがち
・以上のことから、論点がわかりにくく、共感も得られず、印象に残らない
このようになります。
また、『CREC』が意識できていない時に陥りやすいのが、「理由」から述べて最後に「結論」が来るというクライマックス法。
ドラマや映画、お笑いなどクライマックス(オチ)を最後に持ってきた方がいい場合には有効ですが、それ以外の時は、聞き手にストレスを感じさせてしまうケースが多いため、職場や日常生活においては、「CREC」を意識した話し方が理想的です。
3. 就活における『CREC法』の効果
『CREC』法は、就職活動において、かなり有効な手法です。
一つの結論に対して相手に共感してもらいたい時に、話す内容に含まれているべき必要な要素が『CREC』。
と先ほども述べたように、自己PRや志望動機など基本的には、質問に対して回答する形式のため、
【C】一つの結論を述べる
⇒【R】結論に対する理由を述べる
⇒【E】理由の根拠を示す
⇒【C】最後に結論で締めくくる
という型は理想的な形となります。
したがって、『CREC』に従って、ESや面接の内容をまとめ、実際に面接でも『CREC』の順序で話を進めることで、人事に対して、ロジカルで論点を的確に押さえているという好印象を与えることができます。
その結果、他エントリーしている学生よりも人事の印象として残るという差別化ができ、内定へと繋がるわけです。
4. まとめ
当記事では『CREC』についてご紹介しました。人は本来、話を聞くとき、「何の話かな?」と目的を気にしながら聞いています。
その目的を先に示すことで、考えながら聞くというストレスから相手を開放し、認識のずれも生じにくくなるため、記憶や印象にも残りやすくなります。
就活生の皆さんには、是非この『CREC』を習得して、自由に使いこなせるようになり、内定を勝ち取ってもらえたらと思います。
