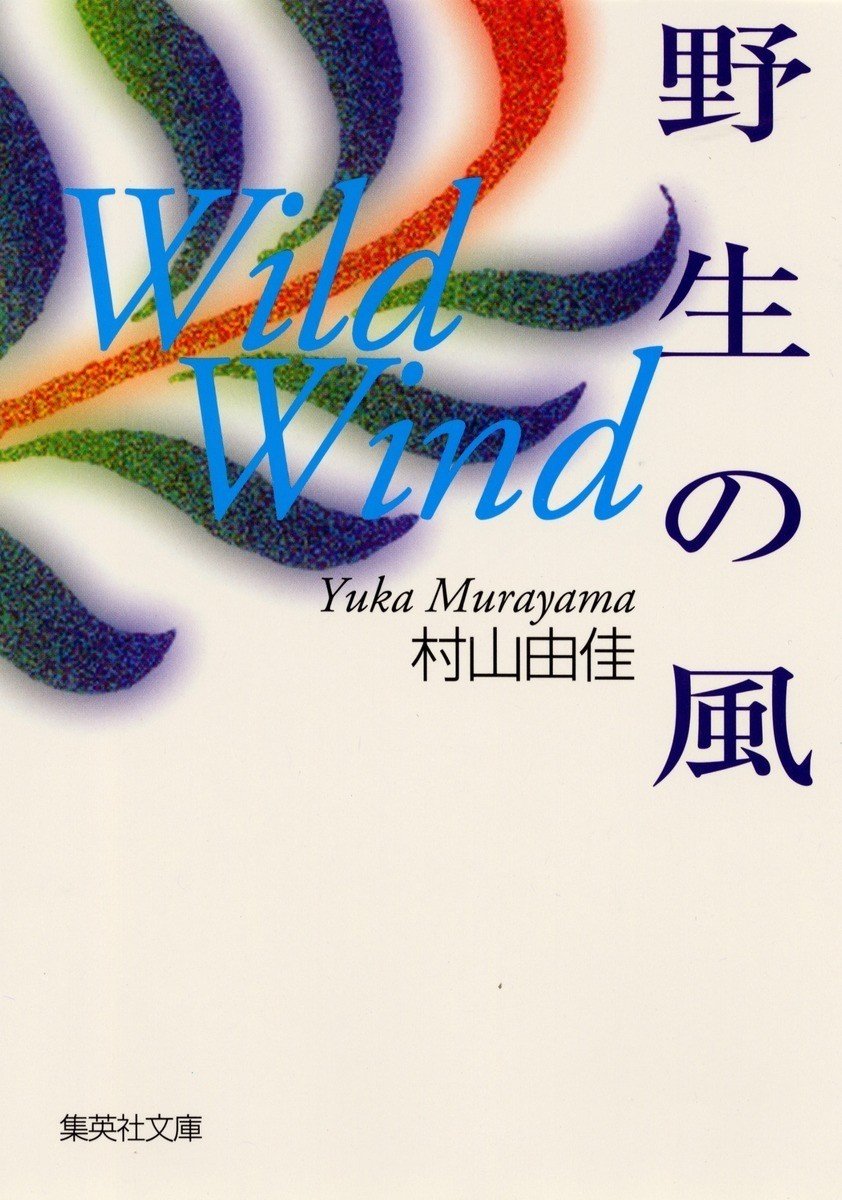小説すばる新人賞歴代受賞者インタビュー「こうして私は作家になった」 第4回・村山由佳さん
『小説すばる』本誌上でスタートした、歴代の新人賞受賞者によるリレーインタビュー企画。
小説すばる新人賞出身の作家の方々に、創作活動の裏側から新人賞を目指す人へのアドバイスまで、幅広く語ってもらうコーナーです。
佐藤賢一さん、篠田節子さん、荻原浩さんに引き続き、第4回では村山由佳さんにご登場いただきました!
胸締め付けられる恋愛小説はもちろん、海外取材をした作品や半自伝的な私小説まで、幅広いフィールドで活躍中の村山さん。
読み手の感情を揺さぶる物語の数々は、どのようにして生み出されるのでしょうか。
デビュー当時を振り返って
―デビュー当時のお話からお伺いしてもよろしいでしょうか?
本格的なデビューは小説すばる新人賞なのですが、実はその前に、『もう一度デジャ・ヴ』という時代物ファンタジーでジャンプノベル大賞の佳作をいただいたことがあるんです。でもそのあと二作続けてボツになってしまって。当時の編集の方に「村山さん、ジャンプノベルの読者を意識しなくてもいいから、本当に書きたいものを書いてみてくださいよ」と言われたんです。それででき上がったのが、新人賞受賞作の『天使の卵 エンジェルス・エッグ』の原型にあたる作品でした。ところがいざ書き上げて渡したら「これはジャンプノベルの読者には荷が重い」と言われてしまって。「読者意識しなくていいって言ったじゃん!」と思ったんですけど(笑)。その時「もったいないので、どこか文芸の新人賞に応募してみたらどうか」と言われ、結果として小説すばる新人賞をいただいたという流れですね。その後ジャンプノベルの方では、改めて『おいしいコーヒーのいれ方』を書くことになりました。
第6回小説すばる新人賞受賞作
『天使の卵 エンジェルス・エッグ』
集英社文庫 本体390円+税
『おいしいコーヒーのいれ方 Ⅰ キスまでの距離』
集英社文庫 本体400円+税
―そもそも小説すばる新人賞の存在はご存知だったのでしょうか?
『小説すばる』創刊号が、当時勤めていた大学内の書店に並んでいたんです。人気のイラストレーター・ペーター佐藤さんが描いた女性の顔の表紙がすごく目立っていたんですよね。「あ、面白そうな雑誌が始まったな」と思いました。それと同時に小説すばる新人賞という賞があることを知って、最初に読んだ受賞作は花村萬月さんの『ゴッド・ブレイス物語』。その後、草薙さんや篠田さんの受賞作も読みました。すぐに応募するというわけではなかったのですが、いつか物書きになりたいという気持ちはあったので、かなり強烈にインプットされましたね。
―『もう一度デジャ・ヴ』の前にも小説は書いていらっしゃったのですか?
当時は若くてお金がなかったものですから、賞金に目がくらんで、横溝正史賞やサントリーのミステリー大賞に応募していました。実はミステリはほとんど読んだことがなかったんですけど、誰か人が死ねばいいんだろう、と(笑)。最終選考か、その前段階くらいまで進んで、そこで落ちるというのを二、三度繰り返していました。
具体的な執筆方法について
―デビュー後はどのような日々を送ったのでしょうか?
時代もあったんだと思いますけど、いきなり長編の連載が始まって、終わればまたすぐ次。毎回本当に必死でこなしていました(笑)。だけど、締め切りに追われる中、常に火事場の馬鹿力で書かせていただいたことで、すごく勉強にもなりましたね。基礎体力がついた気がします。
細かいところで言うと、当時はラストまでの流れを決めてから物語を書き始めていましたね。ノートに書いてしまうと前後を変えにくくなるから、大きな付箋に思いつく場面やセリフを書き出して、それをぺたぺた貼り替えていた。全体の見取り図ができてから、照準を定めて一行目を書き出すという感じでした。
あと、その頃はラストシーン命でもあって。まだ誰も見たことのない映画のエンドロール部分が自分の頭の中だけにあるんです。たとえば『翼 cry for the moon』だと、最後に鷲の目線が来て空の高みから下界を見下ろして、そこにクレジットが流れて、っていうラストを思い描いていました。それを書きたいがために、そこに至る道筋を組み立てていく。

『翼 cry for the moon』
集英社文庫 本体770円+税
―プロットを立てて書き始める、という書き方は今も継続されているんですか?
今は両方します。伏線に次ぐ伏線、みたいなストーリーの場合は先にプロットを立てておかないと、畳んでいく時の折り目がきっちりできないので、立てるようにしていますね。反対に、感情に任せて自分の中から芋づる式にいろんなものが出てくるのを待つような時には、あえてプロットを立てないこともあります。
―村山さんご自身は、どちらが得意だと感じておいでですか?
両方に違った醍醐味があります。ハリウッド映画的な楽しみと、昔の日本映画的な楽しみというか(笑)。全然違うのでどちらも面白いですね。でも、ラストを決めずに書き始めるというのは、最初は怖くて全然できませんでした。初めてその書き方ができたかなと思ったのは『海を抱く BAD KIDS』の時なんですけど。当時、自分でも本当に書きたいものはなんなのだろうというところが漠然としていて。瀬戸際まで文章を積み上げていってみないと出てこないんじゃないか、と。この書き方を初めてできたというのは、一つ大きな自信になりました。「書きながら揺れる」って面白いな、と。
―「揺れている」中で、なかなか着地できないことは?
ありますね(笑)。いやな夢を見て飛び起きたり、自分はものすごい駄作を書いているんじゃないかと不安に思ったり。でも始めてしまった以上は自分で畳むしかないわけだし。「連載って怖いな」と、何年も経ってから思うようになりましたね。最初の頃は無我夢中で、「力技でねじふせたれ!」とやっていたんですけど(笑)。
ただ、仮に結末がぼんやりしていたとしても、そこまで読んでゆく過程で気持ちを昂らせてくれたり、じわじわ沁み込んできたり、「それだけで十分です、ありがとうございました」となる作品ってあるじゃないですか。それってたぶん、綺麗に風呂敷が畳まれているかは問題ではなくて、どこまでも誠実に読み手に向き合い尽くした一文、また一文の積み重ねじゃないかな、と今では思うんです。
―「読み手と誠実に向き合う」ために、どんなことに気を付けていらっしゃいますか?
最近はできるだけ言い訳をしないようにしようと思うようになりました。途中から私小説的な作品も書くようになったんですけど、そうすると主人公をできるだけ自分から切り離して、「彼女」の心情描写をしよう、その行動に至った理由を読者に納得してもらえるようにしようと、色々事細かに書くわけですよね。ところが読者の目から見ると、その登場人物というのはどこかで作者である私と二重写しになっているので、私の言い訳を聞かされているように思えてしまうわけです。前までは、そうはいってもこれはフィクションなんだから必要だと思って、描写や説明を加える方を選んできたんですけど、仮にこれから『ダブル・ファンタジー』をもう一回書くとしたら、そういう説明は全部削ぐかもしれないですね。「なんだこの主人公、わけわからん!」と思われてもいいから、色々と削ぎ落として書くかもしれない。
『タブル・ファンタジー』
文春文庫 (上)本体520円+税
才能は尖っているとは限らない
―挙げていただいた『ダブル・ファンタジー』にはじまり、『放蕩記』や『ミルク・アンド・ハニー』などの私小説や半自伝的な作品を書かれる中で、一番意識していらっしゃるポイントはどこですか?
特殊が特殊のままで終わらないように、というところでしょうか。デビュー作の授賞式の晩に、選考委員の渡辺淳一先生が三次会に来てくださって、二つ大事なことを言ってくださったんです。当日の式で寂聴先生が「作家は、一に才能二に才能、三四がなくて五に才能」という、凄く厳しいことをおっしゃっていたんですけど、それをお聞きになった渡辺先生が、「寂聴先生がおっしゃっていたのも本当だけど、でも三四からあとは運と体力じゃないかと思う」と。なぜならば、「自分よりも才能があったのに、病に倒れて、気力が潰えて消えていった人たちを僕はたくさん知っているから」と。最後の一行を研ぎ澄ますことができるのは、体力があってこそではないかと、そうおっしゃっていましたね。
もう一つ、「特殊を描いて普遍に至るのが文学だよ」とも教えてくださいました。最初は何を言われているのやら、と思ったんですけど (笑)。でも、この仕事を続けていけばいくほど、渡辺先生は作家としての芯の部分を最初に教えてくださったんだな、と気が付いて。どんなにぶっとんだ主人公であれシチュエーションであれ、その特殊を描いて特殊のまま終わってしまうのだったら、それは仮にうまくいったとしても単なるエンターテインメントに過ぎない。何かしら文学なり文芸なりに行きつくためには、それが普遍に通じていないといけないんだな、と。そういう意味で、自分の作品で果たしてそれができているのかどうか、いつも気を付けて書いていますね。これを書くことに意味があるのかな、書き手の私だけじゃなく読んだ人にとっても何か変化のきっかけになれるかな、と。
―たとえば直木賞を受賞した『星々の舟』だと、老若男女問わず様々な登場人物の視点から物語が語られます。ご自身と性別や年齢が異なる人間のうちに、どうやって読者が共感できる「普遍」を見つけ出しておいでなのでしょうか?
デビュー時に、やはり選考委員だった五木先生に、「最初から中庸ってすごいことだよ」と言われたことがあるんです。尖った才能っていうのは目にはつくけれど所詮そこまでのものだ、むしろ鈍さこそがあなたの才能じゃないか、と。その時は「何ももってまわってそういうふうに言わなくても!」と思ったんですけど(笑)。でもその後、ちょうど私の三年目と五木さんの三十周年が重なって対談をさせていただいた時に、「本質的に中庸」というのはとても大きな強みだと改めておっしゃってくださって。みんな上下左右に振ってしまう中で、どうやって普遍やポピュリズムとバランスをとろうかと苦労するのに、あなたは本質的に中庸なんだとしたら、それはあなたが書くものがそのまま多くの読者の胸に響くということなんだよ、と。それまで才能とは尖ったもの、人と違うものだとしか思っていなくて、自分にはないからと苦しかった時もあったので、それを伺ってすごく気が楽になりました。中庸であるということは、みんなと繋がれる触手をたくさん持っているという才能じゃないか、と思えるようになりましたね。
『星々の舟』
文春文庫 本体750円+税
感情を言葉に置き換えてみる
―日々の生活の中で、なにか執筆に役立てるための工夫はなさっていますか?
自分の感情の揺れをなかったことにしない、ということに気を付けていますね。私は性格上、そういう感情の揺れや乱れを表に出すのが不得手なんです。でも、少なくともその揺れや乱れから目をそらさないようにはしてきました。そしてこれは工夫というよりただの癖なんですけど、その感情の揺れをすぐさま言葉に落とし込んでいます。たとえば、言葉が出てこないくらいに激高した時、ようやく息が普通になったところで、「今のはなんだったんだろう」と思い返して、それに長い名前を付けてみる。それを繰り返しているうちに、その感情にできるだけ近い言葉が自然と引っ張り出せるようになるんです。特にメモすることもなく、頭の中だけでやっていますね。言葉にしてみる作業ができた後は、すぐに忘れちゃいます。言葉に置き換える過程が大事というか。
―普段から題材やアイデアなどについてのメモはとりますか?
本当に特殊な状況にいる時だけですね。長年一緒に暮らしてきた愛猫のもみじを亡くした時はメモをとりました。担当編集者に「鬼のようなことを言いますけど、今しかでてこない言葉があるはずなので、全部メモしておいてください」と言われて。でも本当にそうしてメモをとってみたら、一か月たって見返してみると、書いた覚えのない言葉がたくさんあるんですよ。極限状況みたいな時だと、普段は外に表れてこない言葉というか、言葉の組み合わせが生まれるんだな、と。結果的にそのメモは、もみじとの思い出を綴った『猫がいなけりゃ息もできない』というエッセイにまとまりました。
言葉にならない経験をする
あとは、面白いものを書きたいと思うんだったら、まず自分自身が面白い人生を歩んだほうがいいと思う。ネットの中でどれだけいろんな情報を得ていたとしても、どんなに物知りだとしても、「あなた、それを肌で思い知ったことがありますか?」と。たとえば「目の前が真っ白になった」という言葉があるけれど、私が本当に言葉を失ってどうしようもなくなった時は、目の前が真っ黄色になったんです。もちろん人によって違うと思うんですけど、実際にその経験をしないかぎり、悲しみや怒りが何色をしているかというのはわからないですよね。だからこれから小説を書く人には、喜怒哀楽すべてがレッドゾーンまで振り切れるくらいの経験をしてほしいです。そういう体験は、体を使って外へ出ていかないと得られない。皮膚感覚とか聴覚とか、あらゆる感覚をフルに使って生きるのがいいんじゃないかなと思います。
―五感をフルに使うことで初めて得られるものがある、と。
たとえば、『野生の風 WILD WIND』の執筆の際にケニアに取材に行ったんですけど、当時もテレビでいくらでも現地の映像は見られたわけです。それだけでも書こうと思えば書けたのかもしれない。けれど、ナレーションの付かない体験をしたくて。ああいうテレビの映像って、必ず「お母さんライオンはおなかが空いたようです」なんていうナレーションがつくじゃないですか。そうではなくて、間に他人の感覚という触媒を挟まずに、自分で見て聞いて何を感じるか、というのを知りたかった。
初めての土地に行くと、必ず靴を脱いで裸足で地面に立ってみるのが習慣なんです。その時も生まれて初めて三百六十度の地平線に囲まれて立っていたんですけど、地平線の向こうから何かが近づいてきたんです。一時間くらいかけてそれがようやく人だとわかった。マサイの人であることがわかって、牛追いだったりして。その光景をずっと見ていた時に、なぜか涙がぼろぼろ出ちゃったんです。たぶん、見ているものの巨きさに感覚がおいつかなくなっちゃったんでしょうね。
感情を言葉にする訓練も大切ですけど、言葉にならないものを取り込む経験もそれ以上に必要だと思うんですよね。それを浴びたり吸収している最中って、「いったいどうやってこんなものを言葉にすればいいんだろう」と打ちのめされるんですけど、匂いに慣れるみたいにして、人ってその感動に慣れていくわけですよ。そして慣れてからようやく、それが言葉に変わっていくんだと思うんです。言葉にすることでやっと自分の中に収めることができるというか。だからぜひ一度、異文化の中に行ってみてほしい。そういう時に、今まで思ってもみなかった生命力があふれ出してきたりする。自分が壊される経験って、慣れた環境にいるとなかなかできないと思うので。
『野生の風 WILD WIND』
集英社文庫 本体476円+税
小説家として書き続けていくということ
―村山さんといえば恋愛小説、と言われることが多いかもしれません。どうやって、ご自身の核となる題材にたどり着いたのでしょうか?
誰しも、それまで読んだり見たりした中で、宝物だと思う作品を振り返ってみると、そこにヒントが表れてくると思います。私は動物ものが大好きで、あとはなんとなく最後が悲しい話も好きで、つまり私の原点は「ごんぎつね」なんですね(笑)。動物ものに限らず、ひととひとはこのようにわかりあえないもので、このように取り返しがつかないものなのだ、という部分が好きなんです。取り返しのつかない後悔の中にあるほろ苦い甘さというか、そのエッセンスがいいんですよ。今まで自分が好んできたものもやっぱりそういうエッセンスを含んだものが多くて、それが自然に自分の書くものにも繋がっていったのかな、と。いずれにしろ人間の感情の針が極限まで振り切れるところを書きたいんですけど、そうなる要因ってたいてい、悲しみか怒りか恋愛だと思うんです。そのなかでも、多くの人間が一度は足を踏み外しておかしくなるのが恋愛なので、それをほろ苦くも甘いエッセンス込みで書こうかなと。当たり前のように恋愛小説を書き始めた気がしますね。
―小説家として長く書き続けるための気構えやコツはありますか?
先ほど言った体力のほかにもう一つ、自分を好きでいられるということが、凄く大切じゃないでしょうか。私は自分のことがある部分で物凄く嫌いで、でも嫌いだと意識するってことはつまり、同時に物凄く好きなんです。必ず好きの方が上回っているから、自分の書く作品に愛着を持てている。自意識が強い人はたくさんいると思うんですよ。今生き残っている作家で自意識と自己顕示欲の強くない人なんているわけがないし(笑)。でも、それに見合うくらい健康的に健全に自分を愛せるかどうかって、すごく大きい。「今の私にできる全てを込めました」といって差し出すのが作品なわけで、肝心の自分に自信が持てなかったら、作品を差し出される方も迷惑でしょう(笑)。屈折して自分を愛せない人間が断末魔の叫びのようにして差し出したものも、それはそれで力はあるかもしれないけれど、続かないと思うんです。その作品によって救われる人がいるかもしれないし、意味がないとは全く思わない。けれど、長く書き続けるためには健全に自分を愛することですね。
―これからどういう方向に向かっていきたいとお考えですか?
やっと弾が揃ってきた感じかな。自分が狙いを定める的に対して、ようやくぴったりの武器が手元に揃ってきて自由度が増した感じ。最近は依頼してきてくれる方々が投げてくれるものが面白いですね。「村山由佳にこういうものを書かせてみたい」とやってくる題材が、常に自分が思っているものよりも少しハードルが高くて。それを死ぬ気で跳んでみせるのが今はすごく楽しいです。昨年『小説すばる』で連載していた「風よ あらしよ」も、「村山さんの書いた伊藤野枝を読んでみたい」という編集者からの提案を受けてチャレンジしたんです。
あと、いつか時代小説をやってみたいんです! 大ベテランの先達も、〈江戸警察〉みたいな読者も、いっぱいいらっしゃっておっかないんですけど(笑)。現代小説では書けない面白さがあると思うので、いつか挑戦してみたいですね。
新人賞を目指す人たちへ
―最後に、新人賞を目指している方々へアドバイスをお願いします!
皆さんがおっしゃることだと思うんですけど、まずは完成させることですよね。未完成の傑作がどれだけあっても応募はできないので。
あとは、自分にとって一番恥ずかしいことから逃げない方が、いいものが書けるような気がします。みんな自分の得意なことを書こうとするじゃないですか。それはもちろんすごく大切で、大きなアドバンテージになることも多い。でもそこにプラスして、自分が今凄く恥ずかしいと思っていることを、登場人物の誰かに肩代わりさせる形でもよいので書いてみたら、「おっ」というものができるんじゃないかと思うんですよ。その人にとっての恥は、物凄く大きな鉱脈だと思うんです。性的なものなのか、かつて犯した罪に対する後悔なのか、なにか自分にとってネガティブなことを物語に溶かして書いてみると、びっくりするようなものが掘り当てられるんじゃないのかなと思います。
―実際に執筆するうえで気を付けた方がいいことはありますか?
あくまで私は、という前置きのもとでお話しするんですけど、建物として美しい小説に惹かれるんです。柱はちゃんと立っているか、屋根を支えているか、窓はちゃんとあるか、扉があって出口までの動線は考えられているか。隅々まで目配りをしてほしいんですよね。CADシステムってあるじゃないですか、PCの中で3Dの家の模型がぐるぐる回るような建築のシステム。それくらい自分の小説をぐるぐる回して、隙がないようにしてから差し出してもらいたいな、と。それでも新人さんだから隙はあるんですけど、努力の跡は見えるものなので。今回の受賞作でいうと『言の葉は、残りて』はこのタイプかもしれませんね。自作をつきはなして客観的に眺められるかどうかは、とても大事な才能の一つです。
―直しの作業を行う時は、どこに気をつけていらっしゃいますか?
増やすよりは削ることかな。たいてい読み直すと説明を加えたくなるものなんです。ここはわかりにくいんじゃないか、とか。でも説明も描写も簡潔であるに越したことはないんですよ。そのほうがインパクトも強まって濃度も高まるし。たとえば、二つに分けた文章だけど、これは一つにまとめて言えないかな、と試してみるとか。必要じゃないところをどう削ぐか、という部分はよく考えますね。
―選考委員をなさっていて、新人賞の作品全体に言えることはありますか?
わりと優等生な作品が多くなってきたのかな、という感じがします。建物として綺麗であることと、物語がつるつるしていることは別なんです。物語はもっとざらざらしていていいと思っていて。映画みたいにすべてが目に見えてしまうものは、相当周到にCGとかを使わないと、ありっこないことを信じさせられない。でも言葉って、書くだけでそれを信じさせられる素晴らしいエンターテインメントなんですよ。「消えた」って書けば消えるんだから。まず自分でとんでもないことを信じてみて、それを読者にも信じさせてほしいなと。それこそ今回の『しゃもぬまの島』が受賞に至ったのは、読み手までがまんまとしゃもぬまを信じこまされたからですよね。書き手が信じて書いてくれたから、生々しい匂いまでが立ち現れたわけで。自作を客観視すると同時に、そうやって自分の書きたかったものを最後まで信じ切って書き上げてほしいと思います。

【プロフィール】
村山由佳(むらやま・ゆか) ◆ '64年東京都生まれ。'93年「天使の卵 エンジェルス・エッグ」で第6回小説すばる新人賞を受賞しデビュー。'03年「星々の舟」で直木賞を、'09年「ダブル・ファンタジー」で柴田錬三郎賞、島清恋愛文学賞、中央公論文芸賞を受賞。「放蕩記」「天使の柩」「おいしいコーヒーのいれ方」シリーズなど著書多数。最新刊は「晴れときどき猫背 そして、もみじへ」。
(本インタビューは『小説すばる』5月号掲載分です。)
※小説すばる新人賞についての詳細や応募方法については、以下のページをご覧ください。http://syousetsu-subaru.shueisha.co.jp/award/