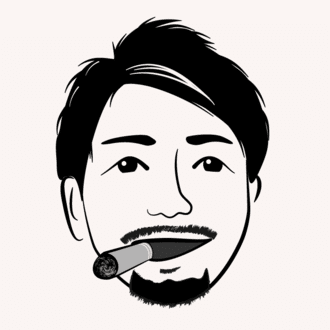2024/12/30週|従来のブランディング理論 vs バイロン・シャープ理論について整理するメモ
『宣伝会議 2025年2月号 NO.1000』の通巻1000号特別企画 Marketing is cosmos. 拡張を続けるマーケティングの現在地 において、スタートアップの一員として感じてきていたことを僭越ならコメントさせてもらう機会がありました。
同時期にセールスフォース様のブログでもタイミーのこれまでについてお話しする機会がありました。
もしお時間ありましたらご覧くださいませ🙇
==
『ブランディングの科学』などで有名なバイロン・シャープ氏のマーケティング理論は従来のブランド理論と相反するところはあるように思います。今日はその辺りを整理してみるメモです。
バイロン・シャープが言う「ライトユーザー戦略」をやりつつ、ロイヤリティ強化もきちんとやるには、どう優先度づけをすればいい?
差別化(Differentiation)と際立ち(Distinctiveness)の違いがいまいちピンと来ない…実務でどう使い分ける?
ブランド拡張やサブブランド展開を考えているが、コアブランドを薄めずに拡張するには?
についても考えてみたいと思います。
従来型ブランド論とは?
AakerやKeller、Fournierなど、多くのブランド研究者が提示する従来のブランド論は、大きく言えば下記のような特徴があります。
ロイヤリティ重視
ブランドに強い愛着や絆を持った顧客を増やすことで長期的な売上を安定化させ、競合優位を築こうとする考え方。差別化によるブランドエクイティ向上
競合との違い(Points of Difference)をはっきり打ち出すことで、「このブランドじゃないとダメ」という意識を高める。ブランド拡張・サブブランド戦略
親ブランドのエクイティを活かして、新たなカテゴリーや市場へ進出することを成長手段として重視。
要するに、顧客との深い関係性を築き、それを支えにブランドの守備範囲を広げていくアプローチがメインです。
バイロン・シャープ理論のエッセンス
一方、バイロン・シャープは『How Brands Grow』のなかで、購買データ分析や統計的視点を軸に、下記のような主張を展開しています。
ライトユーザーの大量獲得がブランド成長に不可欠
“ファン”を深く育てるよりも、むしろ「たまに買う層」をいかに広範囲で取り込むかが、シェア拡大に大きく寄与すると説く。差別化より際立ち(Distinctiveness)
消費者はブランド間の違いをそこまで深くは認識していない。だからこそ、競合と間違えられないよう、ロゴ・パッケージ・色・名前などを一貫させて強く印象づけることが重要だという考え方。可用性(Availability)の最大化
“いつでも、どこでも、誰でも買える状態”を整え(フィジカルの可用性)、認知(心的可用性:Mental Availability)を高め続けることで、ブランドは成長する。メンタルの可用性とは、顧客がブランドを容易に想起できる状態を指し、フィジカルの可用性は、顧客がブランドを購入しやすい状況を作ることを意味します。これらの要素を高めることで、ブランドは顧客の選択肢として常に意識され、購入される可能性が高まります。シャープの理論は、これらの可用性を高めるために、広範囲な露出と多様な顧客へのリーチを重視しています
有名なダブルジョパディの法則は、ブランドの市場シェアが大きいほど、顧客数が多く、ロイヤルティも高いという現象を説明しています。この法則は、ブランドが成長するためには、広範囲なリーチが重要であることを示しています。つまり、ブランドは多くの顧客にリーチすることで、自然とロイヤルティを高めることができるという考え方です。シャープの理論は、この法則を基に、ブランドの成長には広範囲な顧客へのアプローチが不可欠であると主張しています。
つまりは、“深い愛”より“浅く広い裾野”を重視するアプローチです。ここで「ロイヤル顧客をもっと増やしたい」という従来論と、「より広いライトユーザー層を獲りに行こう」というシャープ理論が、一見するとぶつかるように見えるわけです。
「全部やろう」とすると戦略がブレる理由
マーケターの思考としては、「理論はすべていいこと言ってる気がする。じゃあ全部取り入れよう」となりがちかもしれません。しかし、そこには落とし穴があることがあります。
1. リソース分散とメッセージ混乱
ロイヤリティ施策とライトユーザー獲得施策を同時に全力投球しようとすると、
広告費や人員リソースが二分され、どちらも中途半端になる可能性
部署間で「どの指標が最重要か」がブレて、メッセージに一貫性がなくなる
結果的に、「何をやっているブランドなのかよくわからない」と認知されてしまう危険も。
2. 新カテゴリー拡張 vs. コアカテゴリー集中のジレンマ
また、「コア商品にはしっかり投資したいけれど、ブランド拡張で新しい市場も開拓したい」という場合、親ブランドのDistinctivenessが薄れる恐れがあります。
サブブランドだらけで、ユーザーからすると「どれが本流?」となりがち
名称やデザインが散逸し、競合と間違えられるリスクが上がる
こうした状態は、シャープが警鐘を鳴らす「心的可用性の分散」を引き起こし、結果としてブランド自体が弱体化する恐れがあるのです。
3. 差別化と際立ちの混同
「とにかく差別化!」「いや、際立ちが大事!」という主張も、両方やればいいじゃんという短絡的な結論に陥りがちです。
差別化ポイントを多くアピールしすぎてメッセージが散漫になる
際立ち(色・ロゴ・パッケージ)を都度変えては再設計し、逆に消費者を混乱させる
差別化と際立ちは同時に達成できる部分もありますが、やみくもに足し算すると、むしろ逆効果になり得ます。
両者の理論を併存・両立させるポイントとは
では、どうすれば理論と理論がぶつかることなく、うまく併存させられるのでしょうか。
まずは「最優先KPI」を絞る
「ロイヤル顧客数の増加」なのか「ライトユーザー数の拡大」なのか、どちらを最優先するかを先に明確化してください。
「カスタマーサクセス部門はロイヤリティ指標、マーケティング部門はライトユーザー指標」という割り振りをする場合でも、最終的に経営方針として「どちらを優先するか」を決めておかないと、会社全体の認知やリソース配分が混乱します。
フェーズごとに施策を切り分ける
戦略を一括りにするのではなく、「フェーズ1は認知拡大」「フェーズ2はロイヤリティ向上」「フェーズ3で拡張検討」といった形で時系列に区切るやり方もあります。
バイロン・シャープ型施策(ライトユーザー重視)を導入期や成長期でしっかり行い、そのあとロイヤリティ戦略で深堀りする。
コアカテゴリーを十分に伸ばしてから、ブランド拡張やサブブランド展開に手を広げる。
Distinctive Assets(際立ち資産)を“軸”に統一
バイロン・シャープはブランドカラー、ロゴ、ネーミングなど、一貫して使うことで「他社との混同を防ぐ」Distinctive Assetsが重要だと説きます。
従来ブランド論でいう差別化施策を検討するときも、「その差別化はDistinctive Assetsを補強するか、矛盾しないか?」をチェックしましょう。
いくら差別化が魅力的でも、ビジュアルや名称がバラバラになるなら、本来の強みを弱める可能性があります。
小規模テストで“やる施策”と“やらない施策”を区分
「ロイヤリティ強化策がどれだけ効果ある?」と疑問なら、小規模コミュニティや特定顧客層で先行テストしてみる。結果データで“やる価値あり”と判明したら大きく展開すればいい。
同様に、ライトユーザー向けのマスマーケティングも最初は限定的エリアで試すと、ROIなどが見えやすいです。こうして実験から学習することで、無駄を削ぎ落としながら両方の理論を適切に使い分けることができるでしょう。
まとめ
ここまでのポイントを整理すると、以下のようになります。
従来ブランド論は「深い愛」(ロイヤリティやブランドラブ)を重視しがち。バイロン・シャープは「広い裾野」(ライトユーザー)を重視する。
“全部取り入れたい”と欲張ると、戦略がブレてリソース分散やメッセージ混乱を引き起こすことも。
最優先KPIを絞り、フェーズを区切り、Distinctive Assetsを軸にするのが、ブレずに両理論を併存させるコツ。
小規模テストでデータ検証しながら取捨選択していくと、成功確度が高まりムダも減る。
今週はこの辺りで。お読みいただきありがとうございました🙇
📓この記事について
株式会社タイミーで執行役員CMOを務めている中川が、マーケティング関連の仕事をしている中で感じたことを綴り、コツコツと学びを積み重ねる『CMO ESSAY』というマガジンの記事の一つです。お時間あるときにご覧いただければ幸いです。オードリーのオールナイトニッポン 📻 で毎週フリートークしているのをリスペクトしている節があり、自分も週次更新をしています。
タイミーは、すぐに働けてすぐにお金がもらえるスキマバイトアプリです
いいなと思ったら応援しよう!