
【書評】 中井久夫 「私の日本語雑記」
「私の日本語雑記」 著者:中井久夫 出版社:岩波書店 発行:2010年
著者は精神科医の中井久夫である。精神科医として、統合失調症の寛解過程理論、風景構成法の考案、その業績は枚挙にいとまが無い。一流の精神科医でありながら、現代ギリシャ詩の頂点であるカヴァフィスの全訳を行い、フランスの詩人ポール・ヴァレリー の詩集『若きパルク・魅惑』まで訳す翻訳家でもある。さらに、本書のような一般読者に向けたエッセイでは、その教養の深さから様々なテーマの問題を取り上げ読者を知恵の森に引き込む書き手である。
簡単に来歴を紹介する。1934年奈良県に生まれる。幼少期から旺盛な知識欲を持ち、おもちゃよりも本を好んでいた。幼少期の愛読書はシャンドの『地球と地質学』、山本一清の『天体と宇宙』、ヴェルヌの『海底二万里』だった。かなりの理科少年であった。読書は暗い戦時下のもとで宇宙や広大な世界に想いを馳せると気持ちが楽になる、一種の自己慰安の方法でもあったという。この戦争体験は人格形成に大きな影響を与えたであろう。
高校生になると学校の図書館に哲学者九鬼周造の所有本が全書寄付され、九鬼周造文庫なる膨大な書物にアクセスできるようになった。この時代に、中井は後に訳すことになる、ポール・ヴァレリー をフランス語の原書で読み、ドイツ語でリルケを、その他の名著と呼ばれる古典の乱読をしている。
大学は京都大学に進学。しかしながら、精神科医は全く考えておらず、法学部に進むことになる。本人の言うところでは「会社員になりつつ趣味として文学作品を読む静かな生活をしたかった」。
しかし運命の悪戯が起こる。法学部入学後すぐ、結核を患うことになり休学を迫られる。この休学中に、ヴァレリー やリルケの訳詩を試みることになる。曰く「精神的な危機を乗り越える手段としての知的防衛」であったという。結核が無事に治ると、京都大学医学部に転向。京都大学ウイルス研究所に入ることになる。法学からウイルスである。ここで科学的実験の基礎、思考法、生態変化を図式して経過観察をする方法論が確立し、その後の統合失調症寛解過程論の考察につながっていく。この時期、中井はDNAの「二重らせん」でノーベル賞を受賞したワトソンにも会っており思い出深い経験だった。しかし、ここでもキャリアは順調にいかず、半ば追い出される形で研究所から除籍されてしまう。
この経験をしたのち、東京の眼科、精神科、神経内科を回った末に精神科医としての職業的アイデンティティを見つけることになる。そこからの業績は凄まじい。今日でも心理療法で用いられている「風景構成法」の考案。これは心理療法家である河合隼雄の箱庭に関する学術発表会を聞いている最中、「箱庭を紙の上で作ったらどうなるのだろう」と考えた結果、一挙に創造された。翻訳も多く行い、難解で知られる米国精神科医のサリヴァンの著作『現代精神医学の概念』『精神医学の臨床研究』『精神医学は対人関係論である』『分裂病は人間的過程である』などを邦訳。「関与しながらの観察」という名言を日本精神医学に周知させた。その他、ナウムバーグの「スクリブル法」を日本に紹介、バリントの『治療論からみた退行 基底欠損の精神分析』『スリルと退行』、コンラートの『分裂病のはじまり』などの著作群も邦訳する。優れた言語感覚から日本の読者にも読みやすい、むしろ、原文よりも格調の高い文章で翻訳がされている。
晩年には神戸にて、阪神淡路大震災を経験する。ここでの経験がPTSD概念の模索につながる。還暦を過ぎてから専門である統合失調症からトラウマ概念へ足場を変えることになる。米国の医師ハーマンの『心的外傷と回復』の邦訳をする。この著作にはフェミニズム的な主張も多く、政治的な問題を多くはらむPTSD概念ではあるが、中井は「役にたつものは全て役に立たせる」という信念のもとに全訳をする。日本の精神医学界では「あの中井久夫があんなもの(PTSD)に熱中するなんて」と陰口を叩く者もいたという。しかし中井はそうした政治的な対立、イデオロギーからは距離を保ち、治療論としてのトラウマケアを日本に波及させた第一人者とされている。
以上、少し長くなったが著者の経歴を概観したが、膨大な仕事量である。紹介していない著作、邦訳なども数知れない。しかし、本題であるエッセイ『私の日本語雑記』に論を進めようと思う。
内容としては、翻訳家である著者の多彩な言語体験が綴られたエッセイである。ここでは内容は本書を読んでもらうとしてあまり立ち入らない。中井の文章の独特な構成、その思考法の「型」について少し考えてみたい。
訳詩体験について中井は「詩モード」という身体的感覚を説明する。
「詩モード」の基底は「うたう状態」である。その表現は「ことばの響き」「ことばの音楽」「皮一枚下まできている律動の、まだ声にならない存在」に敏感になり、シラブルに色がついてくる状態である。
詩作にはある種の「モード」が必要である。ヴァレリー は、詩とは言語によって完全に閉じたひとつの体系であると言った。これは数学の世界とも言えるだろう。詩は言語で織りなす数学である。たしか、言語学者ウンベルト・エーコも「完全言語」の概念をつくっていただろうか。言葉を厳密に扱おうとする者は完全性に憧れるようだ。ある種の、自閉的な言語活用を目指す。ヴィトゲンシュタインはその言語の限界を設定したとも言える。自閉的な言語があるならば、拡散的な言語も考えられるだろうか。思いつくのは小説である。小説は基本的に拡散を目指す文体になる。物語の厚みは読者の多様な解釈から生まれ、ひとつの正解を求めるものではない。「開かれた言語」という感じだろうか。
さて、中井の言う「詩モード」は、現実の世界を体験するモードとは異なる、言うならば意識下の感覚を感じ取る感覚となる。意識下を意識するという矛盾を通りぬけたところに詩ができる。中井自身、「共感覚」の持ち主だった。「共感覚」とはひとつの知覚から別の知覚が生じることで、文字を読むと色が付いて見えたり、音が聴こえたりする現象のことをいう。「シラブルに色がついてくる」とはまさに共感覚者の表現だろう。ランボーは詩の中に色と音を対比させたが、彼も言語と色を同時に感じる感覚があったのかもしれない。「うたう状態」とはヴァレリー の言う「詩を音楽化させる」ことの証左だろう。中井の言語体系の軸には「言語と音とリズム」の調和がある。
N氏とは最近物故された有名な詩人である。詩人には、偉大さとは別に、人口に膾炙(かいしゃ)する詩句をつくる能力のある者とない者とがあるとは、文学史家としては辛辣なアンソニー・バージェスの言葉であるが、偉大さとともに、第二の詩才にも恵まれた氏はただ「覆された宝石のやうな朝」の一句をもってしてさえ後世に残るであろう。
これは結核に臥した中井少年が詩人と文通をした思い出を語るエッセイの最初の文である。美しい一文だと思う。
文末の「であろう」を「である」と断定しないことで、遠い過去を回想する精神科医の姿が見える。基本的に「である」調の文章を中井は好まない。これは中井の言語感覚をよく表している部分だと私は思う。断定調の言い回しについて中井は次のように語る。
私は自分の文章の中の「のである」をたくさん消しても何も内容が変わらないことに気づいた。「のである」は自信をふるいたたせて前進するための自己激励である。(中略)
「のである」「なのである」は、頻用されると、読む私は頭にこれでもかと釘を連打されている感じになる。「これでもわからんか。早く賛同せよ」というわけである。それに「やはり〜である」となると「私はまだ読んでいないのに筆者はもう賛成側に巻き込もうとしているな」と感じてしまう。
なるほど、断定文の特徴を言われてみればこの通り。文末の処理にこそ書き手の態度が見える。
日本語の文末はむずかしい。日本語は主語と述語が離れており、文末まで聞かないと意味が取れない文構造である。たとえば、文末で「〜ではない」という否定形を加えると、それまでの話が最後にひっくり返ってしまう。聞き手の集中力を求める言語といえる。このような日本語に対して、英語やフランス語では文末の処理は聞き流しても大意を損なうことはないだろう。日本語から見ればせっかちな言語ともいえる。移民によって成り立つ国の言語は、簡潔でわかりやすくなければならない。主張をはっきりさせる。玉虫色の表現自体が辞書的に少ない。日本語の特徴といえる。
中井の文構造に対する理解は、言語学の知見に支えられる。主にフェルナンド・ソシュールに依拠するものが多い。またはロラン・バルトであろうか。文を構築する際の法則として「パラディグマ的選択」と「シンタグマ的選択」を取り上げている。「パラディグマ的選択」とは類似のものからひとつを選ぶ選択であり、「シンタグマ的選択」とは全体的・相対的観点からひとつを選ぶ選択である。
人生には様々な選択がある(中略)。しかし、似たものの中からひとつを選ぶ選択」と全体を睨んでからひとつを選ぶ「シンタグマ的選択」とは重要で核心的な選択であろうかと思う。文房具からパートナー選びまで、2つの選択原理が働いている。この選択は言語にもっとも端的に現れている。
この引用から分かるように、言語は思考の道具であり、その言語の選択のされ方には法則がある。そのため、言語学の原理を人生の原理として敷衍して語っている。ひとつの知見を精神に応用すること。
さらに別の例では、
日本語は各助詞と接続に重点がある。格助詞はたしかに使うのが楽しい。この辺りは美しい日本語を目指す方々の領域である。認知症でまとまった文章を声に出せない人でも、各助詞を誰かが使い損ねるとただちに横槍を入れる人をみたことがある。格助詞は「世界」の深いところまで入り込んで「世界」を構成しているようである。
格助詞の使用例から格助詞のもつ力について言及する。「言語=世界」という図式の補完である。臨床医ならではの具体性のあるエピソードは説得力がある。
「無意識は言語によって構成されている」と言ったのはフランスの精神分析家のラカンだった。しかし、中井に言わせると「彼の論文を見ていると研究室でフラスコを振っている科学者のイメージ」だという。つまり、臨床医というよりは研究者であり、あたたかい情感のある精神科医ではないということだ。たしかに、ラカンは人格者とは程遠い性格であったことは今日明らかになっている。中井はその点、精神医学を志したときから「患者を喰い物にしない」という不文律を自らのうちに立てており、それを実行した稀有な人だろう。あるいは、斉藤環がラカンのことを「羊たちの沈黙の博覧強記だがマッドサイエンティストなレスター博士と相通ずる」と語っていたが、中井久夫はその逆と言えるだろうか。彼の文章には常に患者への温かい視線と献身がにじみ出ている。それが中井久夫には看護師のファンが多いと言われる由縁だろう。「看護できない患者はいない」という中井の名言が示す通りである。
こうした中井の言語感覚は、ヴァレリー の詩によって、ソシュールの言語学によって支えれる。
臨床医としての精神科面接では「患者の話の内容よりも、言葉の響き、リズム、調子を聞き取り波長を合わせること」を重視してたことにもつながっていく。言語のもつ生命力を深く理解する精神科医の耳にとって、患者の声は音楽であり、詩であったのだろう。
本書にはそうした中井久夫の言語観が散りばめられている。読まれた方は彼のことを「叡智の人」として感じるように思う。

叡智の短文である

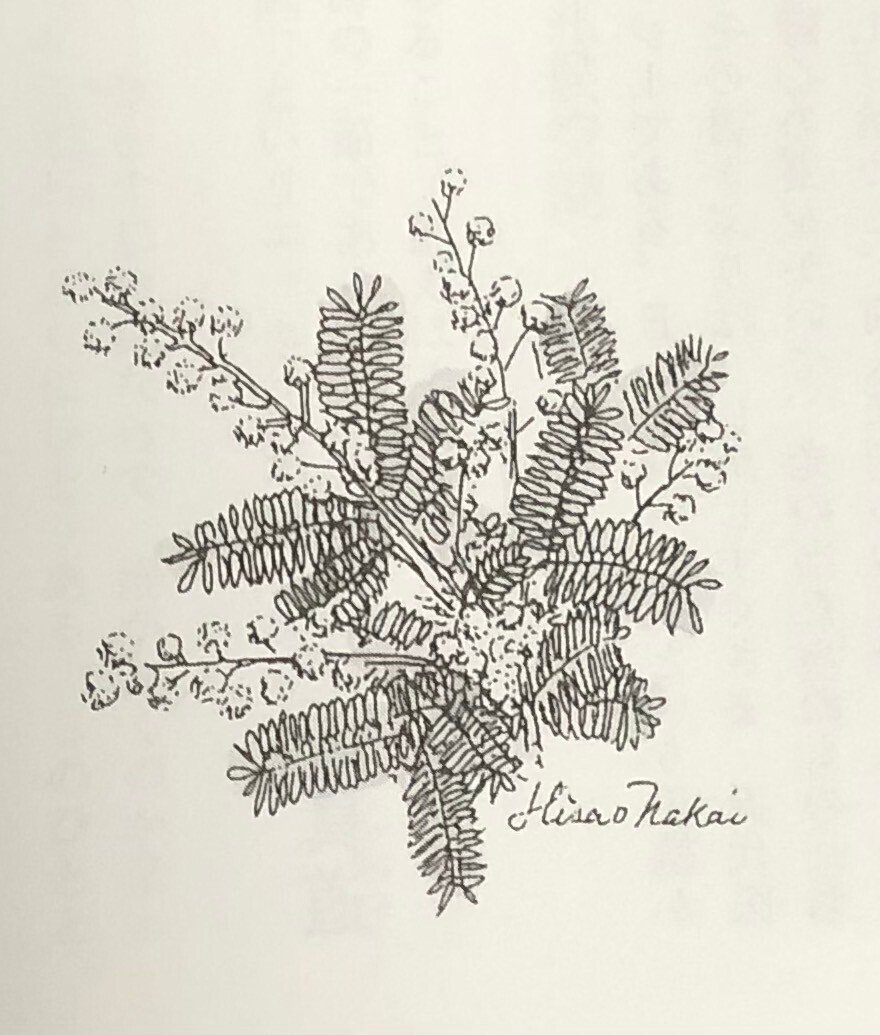

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
