
YA「未来の鐘(かね)」(9月号)


塩野達也は緑ヶ丘中学校の制服姿のまま、たった今、追い返されたばかりの新聞店の窓ガラスに張り付いている。
「お願いします。アルバイトさせてください。オレ、一生懸命に働きます。絶対に遅刻しません。体も丈夫です」
達也は、面接で力説した言葉を繰り返す。背中から夕日をうけて、首筋が焼けるように熱い。短髪の毛の根本から、汗がふきだす。
「た、達也くん、やめてくれ。人が見ているじゃないか。とりあえず、今日のところは帰ってくれないか、な?」
中年の男性店長が飛び出してくる。
「アルバイトさせてください!」
「だから、無理だって。きみ、中学一年生だろう? もし、どうしても、アルバイトしたいのなら、学校の許可と親御さんの許可がいるけど、うちは、あいにく、今はアルバイトを募集していないんだ」
店長も同じ言葉を繰り返す。ウソだ。朝刊と夕刊の新聞配達のアルバイト募集の張り紙が窓ガラスに貼ってある。店長は、いろいろと面倒な中学生を雇うよりも、高校生や社会人を雇いたいのだ。
達也はあきらめられない。携帯電話を買う金が欲しい。達也の家は普通のサラリーマン家庭だ。三歳年上の兄ちゃんは、高校の入学祝いにスマートフォンを買ってもらった。中学生の達也はまだ買ってもらえない。
「うちには、そんな余裕はありません。そんなに携帯電話が欲しいのなら、自分で稼いで買いなさい」
昨日の夜、母さんにしつこく携帯電話をねだったら怒られた。佐々木も、横山も、達也の友だちはみんな携帯を持っている。達也も腹を立てて、言い返していた。
「わかった、自分で稼いだら、携帯を買ってもいいんだね」
「どうぞ!」
母さんは、できっこないという態度だ。
「約束だぞ!」
達也は小学生だった頃、近所の中学生のお兄さんが夕刊を配達しているのを見かけたことがあった。それならと、達也は新聞店にかけこんだ。でも、近所の新聞店では、中学校の制服を見るなり帰ってくれと言われた。
だから、少し離れた新聞店に来たのだ。それでも、働かせてもらえないとわかると、達也は悔しくなった。裕福な家の子は小学生の時から、防犯ブザー付きの携帯をランドセルにぶらさげていた。
「スマホが欲しいだけなのにさ」
「は、スマホ? 最近の子どもは、携帯やゲームやパソコンや、そんなもんばかり欲しがって、金がかかって仕方がない」
店長は達也がアルバイトしたい理由を知ると、ガミガミと説教を始めた。達也は逃げだした。雇ってもらえない上、説教なんて最悪だ。
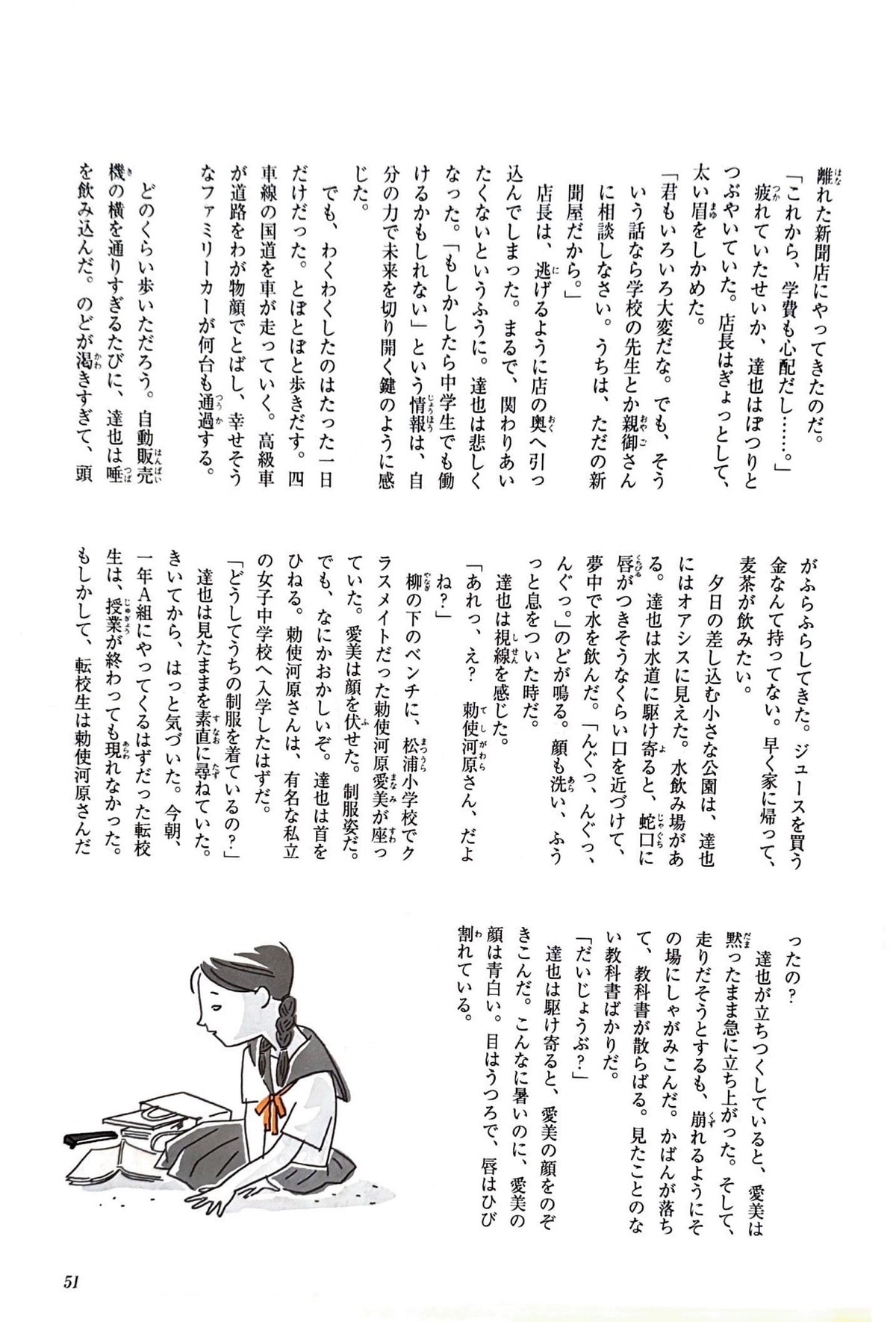
どのくらい歩いただろう。赤い自動販売機の横を通りすぎる度に、達也は唾を飲み込んだ。喉が渇きすぎて、頭がふらふらしてきた。ジュースを買う金なんて持ってない。早く家に帰って麦茶が飲みたい。
夕日の差し込む小さな公園は、達也にはオアシスに見えた。水飲み場がある。達也は夢中で水道にかけよると、蛇口に唇がつきそうなくらい口を近づけて水を飲んだ。んぐっんぐっんぐっ、喉が鳴る。顔も洗い、ふぅと息をついたときだ。
達也は視線を感じた。見ると、
「あれっ、勅使河原さん?」
柳の下のベンチに、松浦小学校でクラスメイトだった勅使河原愛美が座っていた。愛美は顔をふせた。制服姿だ、でも、なんかおかしいぞ。達也は首をひねる。勅使河原さんは有名な私立の女子中学校へ入学したはずだ。
「なんで、緑ヶ丘中学校の制服を着てるんだよ?」
聞いてから、達也は、ハッと気がついた。今朝、一年A組にやってくるはずだった転校生は、授業が終わっても姿を見せなかった。もしかして、転校生は、勅使河原さんだったのだろうか?

達也が立ち尽くしていると、愛美は黙ったまま、急に立ち上がった。そして、走ろうとして、崩れるようにその場にしゃがみこんだ。鞄が落ちて、教科書が散らばる。見たことのない教科書ばかりだ。
「おいっ、大丈夫かよ?」
達也はかけよると、愛美の顔を覗き込んだ。こんなに暑いのに、愛美の顔は青白い。目はうつろで、唇はひび割れている。
「バ、バカにしないでよ」
愛美はバカにしないでよと繰り返すと、達也が拾い上げた教科書をひったくった。固く結んだ三つ編みがゆれる。
「なんだよ」
達也が立ち去ろとしたときだ。
「みんなの笑い声がきこえるの」
愛美は意味不明な言葉をつぶやいた。
達也は怖くなった。貧血か? 熱中症で、頭がへんになっているのか? もしかして、勅使河原さんは朝からずっとこの公園のベンチに一人で座っていたのか?
「何か食べた? 何か飲んだ? ジュースでも買ってこようか?」
言ってから、しまったと思った。
金がないのだ。
「あっ、ごめん、ジュースだなんて。オレ、金を持ってなくてさ」
ちぇっと、達也は舌打ちした。
達也は決まった小遣いをもらっていない。金がいるときに、何を買うのかをきちんと説明して、母さんからもらうのだ。それでも、遠足のおやつ代をもらうときにも、母さんはぶつぶつ文句を言った。
貧乏ってカッコ悪い。
自動販売機のジュースも自由に買えない。早く大人になって金を稼ぎたい。父さんみたいに零細企業で働くもんか。もっと、でっかい会社に入るんだ。
達也は考え事をしながら教科書を拾い集めると、愛実に突き出した。
すると、百円玉を二つ出された。
「オレンジジュース」
愛美の唇が、そう動いた。

達也が買ってきたオレンジジュースを、愛美はいっきに半分ほど飲んだ。それから、ありがとうとつぶやいた。
達也からお釣りを受け取ると、愛美はベンチに座ってうつむいたまま、スペースを空けるように横にずれた。
突っ立っているのもおかしくて、達也は愛美のとなりに腰かけた。なんだか、尻が落ち着かない。したたり落ちる汗をシャツでぬぐう。
達也が何を話したらいいのかわからずに困っていると、愛美は小声で話しはじめた。
「パパがリストラされたの。それで、あたしは、白百合から緑中に転校」
愛美は足元の土を見ながら続けた。
「親って勝手だよね。二学期の今なら、間に合うって。あっという間に、転校の手続きをして。小学校のとき、塾とか行かせて、あれだけ勉強させておいて、私立だとこの先お金がかかるから、公立にしてくれって」
達也は何て答えていいのかわからなかった。
「何が間に合うのか、わけわかんない。あたしは今更、どんな顔して、教室に入ればいいの? 小学校で一緒だった子がたくさんいるのよ。転校した理由をいちいち説明してまわるの? カッコ悪くて言えないわよ」
愛美の声は段々大きくなった。
言葉の一つ一つが、達也の胸に冷たく刺さる。もう尻はもぞもぞしなかった。
「でも、オレには言えたじゃん……」
まるで言い返すように、達也はつぶやいていた。
愛美は言葉につまった。公園の水を飲むところから、ずっと見られていたはずだ。オレにはジュースを買う小銭もない。カッコなんてどうでもいい。どうでもいいからアルバイトしたかった。
達也は小学生のことを思い出した。
達也の家が貧しいことは、修学旅行を休んだことでみんなに知られた。それまでも、穴の空いた靴下を縫ってはいていったら、笑われたことがあった。遠足の弁当も、米ばっかりでおかずが少ないとバカにされた。
「確かに親って勝手だ。親というより、大人って勝手だよな」
達也は立ち上がった。
夕日を正面に見る。
「でも、オレは早く大人になりたい。そうすれば、大人たちにとやかく言われることもなくなる。自分で未来の鍵を見つける」
じゃあと、達也が歩き出そうとしたときだ。
目の前に、飲みかけのペットボトルが突き出された。受け取ろうか迷っていると、
「あんたは、あたしのこと、笑わないでしょう。だから……」
愛美は涙声になった。
達也は、さっき愛美に言い返したことを後悔した。
達也の家が貧乏なのは愛美のせいじゃない。達也はペットボトルを受け取ると、生ぬるいオレンジジュースを口に含んだ。思わず吹き出しそうになる。
「公園の水の方がうまいぞ」
達也が言うと、ふっと、愛美は口元を緩めた。
#YA #小説 #短編小説 #教育雑誌 #言霊さん #言霊屋
〜創作日記〜
これは思い出深い依頼原稿でした。担当さん、困っていました(笑 中学生の貧困を描いて欲しくない、いや、欲しくないというより「一般受けする明るく楽しく」そんな内容が良かったというのが、やり取りで伝わってきて。でも、本当に良い担当さんで私の厄介な原稿に真剣に向き合ってくださいました(感謝
新人さんからベテランさんまで年齢問わず、また、イラストから写真、動画、ジャンルを問わずいろいろと「コラボ」して作品を創ってみたいです。私は主に「言葉」でしか対価を頂いたことしかありませんが、私のスキルとあなたのスキルをかけ合わせて生まれた作品が、誰かの生きる力になりますように。
