
日経doorsオフ会 わたしたちの産みどきっていつ?
こんにちは。会社員をしながらフラワーフォトグラファー/ライターをしているshionです。
先日参加してきたイベント「日経doorsオフ会 わたしたちの産みどきっていつ?」
凄く有意義な時間で、記憶が新しいうちに&忘れないうちに!という想いが募り、今こうしてnoteを開いている。
女性の労働力率は、かつてM字カーブといわれた。結婚出産子育て世代の労働力が一旦低くなり、育児が落ち着くと再び復活。しかし現在の労働力率は、M字の凹み部分が少しずつ盛り上がり、台形型になろうとしている。
つまり、働き続けながら結婚→妊娠→出産→子育てというライフイベントに向き合う女性が多くなってきたのだ。
私自身、昨年結婚し「いつかは子どもがほしい」
だが、今の仕事は安定的な収入が得られるし、既婚者とはいえ身軽だし、趣味もまだまだ楽しみたい。細々と続けてきたパラレルキャリアも芽を出し始め、連載も綴れるようになってきた。
果たして、【いつか】っていつだ??そんなモヤモヤを少しでも解消できれば!という気持ちで今回の参加に至った。
トークセッション(1)働くこと+出産・カラダのこと
助産師の小笠原千恵さん、日経doors編集部の秋山さんによるトーク。
小笠原知恵さんは「世の中の女性は1人で悩みすぎでかわいそう。助けてあげたい。」と強く言う。
というのも、高校生向けの講演会や今回のような20代30代向けのイベントに登壇する機会が多い小笠原さんが、一貫して受ける3大質問があるらしい。
①いつまで産めますか
②無痛分娩どうですか
③妊娠出産にお金はかかりますか
だそう。世代問わず、若い時から30代でも1人で悩み続ける女性が多いと実感。小笠原さん自身、企業で働きだした時に、(職場で子どもの話が全くでないのは何故だ?&プライベートの話がしにくいのは何故だ?)
そんな印象を受けたという。
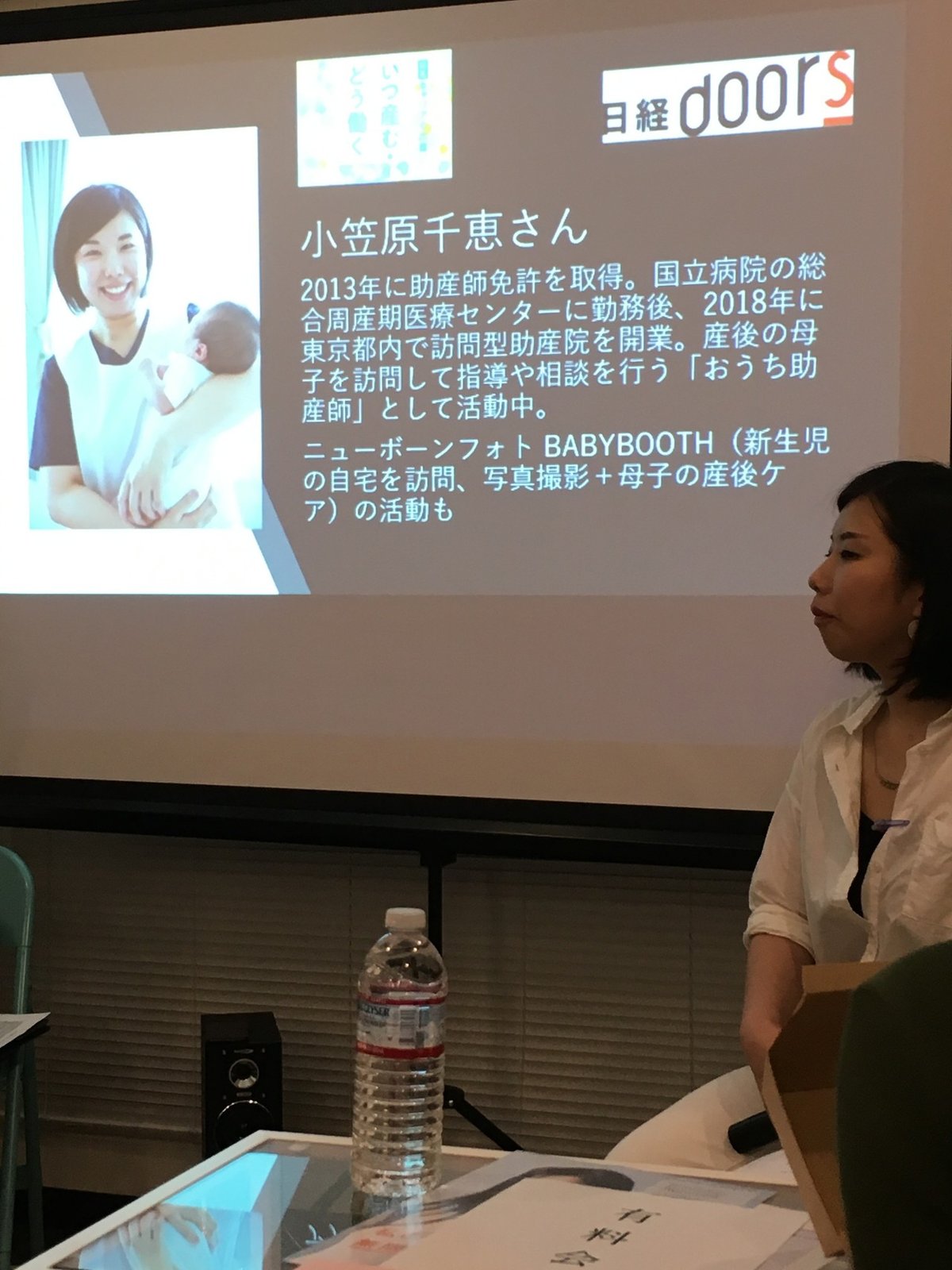
せっかくなら妊娠出産というライフイベントを楽しんでもらいたい。
そして、いつか妊娠を希望するのなら、その目標に向けて今できることを1つずつ取り組んでいけば、選択肢は必ず増える。(例えば、どこで産むかを考えたときに、助産院では健康的な女性でなければ、受け入れることができない、など)
さらに、最近はネットの記事が先行しすぎていて、誤った情報も多く、専門家と話すきっかけも少ない。
これらの現状を打破したい、と企業で働きながら、小笠原知恵さんは訪問型助産院を開業している。

トークセッション(2)キャリアと出産を考える
・「いつか産む」今できること
・いま「産む」を迷う理由
上記2点について、助産師の小笠原知恵さん、日経doorsアンバサダーのお二人、日経doors編集長の鈴木陽子さん、日経doors編集部の秋山知子さんのよるトーク。
「いつか産む」今できること
・自分の身体に少しだけ気を遣うこと
これはかなり衝撃だったのですが!!!!!
助産師の小笠原さんによると…妊娠している段階で、すでに自分の孫世代までの卵巣の組織を作り上げているらしい。自分の不摂生な状態が孫世代まで続くと考えると、少し責任を感じるぞ…?いつか出会いたい孫のためにも、バランスの整った食事を、ゆるく続けたいと思った。
そして、男性の方が、どちらかといえば妊娠出産をのんびり捉えがち。
女性の身体にはやはりリミットがあるし、自分の納得したタイミングで産みたい。育てたい。日経doors編集長の鈴木さんによれば、産みどきをコントロールするのはかなり難しかった、とのこと。自分が元気であっても、仕事のストレスや不摂生で、身体の状態が良くなく、「隠れ赴任」だと認識するのに、かなり費やしてしまったそうだ。39歳と41歳で出産したが、今いえることは「子育てがキツイ・ツライ→妊娠適齢期に産みたかった。小さな後悔をしている」という。
日経doors編集長、鈴木さんのコラムはこちら
・周りの声に流されない強いメンタルをもつこと
妊娠初期のつわりなどで、思うように身体が動かない。そんななか、周りに迷惑をかけたくない…ただでさえ1人1人がタスクを最大限に抱えているのに…今休めない…と考え、と妊娠を隠しながら仕事する人が多い。しかし、妊娠初期は切迫流産などの危険もあり、無理は禁物。妊娠を報告するタイミングで、周りから陰口を言われる場合も多く、それらに流されない強いメンタルをもつことが重要。「他人は他人」「自分は自分」と気持ちの切り替えをしっかり行うことも大切。

いま「産む」を迷う理由
・マミートラック
日経doorsアンバサダーの後藤久里子さんによると、マミートラックの種類は2つあるそう。明らかに仕事量を少なくされるケースと、周りが逆に気を遣い、優しさがある上でのマミートラックになるケース。後者を防ぐために、後藤さんは職場復帰前に上司としっかりコミュニケーションをとったそう。子育てがあるなかで、自分がどこまで&いつまで&何時まで仕事ができるのか?どんな仕事をしていきたいのか?どの立ち位置で仕事をしていきたいのか?これらについて、自己開示し、密なコミュニケーションをとることで、マミートラックが解消されたそう。
・ロールモデルがいない
職場内で、育休を経て復帰する女性が居ない。もしくは、産休前と同職で復帰する女性が居ない。お手本となる人物がいないと、自分のキャリアを築くのが難しく、いま「産む」を迷う理由の1つになる。しかし、マミートラックで述べたように、上司とのコミュニケーションをとったり、ロールモデルがいないことをポジティブに捉え、自分から会社に要望を伝えるなど、働きかけることも可能になる。
後藤さんは、そのうちの1人で、逆にロールモデルが居なくて良かったかも、とも言う。
というのも、ロールモデルがいると、その人の型にはめられてしまいそうで、自分の行動が制限されかねない…と思ったそうだ。あの人がこうだったから、この人もこうだろう。という職場の型にはまった考え方があると、こちら側も仕事をしづらくなりそうで…とも言っていた。
(付け加えると…このような場合は、上司や職場の人とはしっかり信頼関係を築けていないと、密なコミュニケーションをとるのがまず難しいが…)
トークセッションのあとは、グループトークをして終了。
イベントに参加して、思ったこと。
それは…
いつか、のためにできることをしておく。
産み時に正解はなく、産み時をコントロールすることも難しい。
ただ、自分が考えて計画し、納得した選択をとることができれば、それが正解になる。だから、まず初めの一歩として、そういった選択肢を机に並べられるように、正確な知識を選び取り、時には検診を受け、しっかり自己管理をしていきたい。
最後に、イベントで特に印象的だったお言葉を。
助産師の小笠原千恵さん:
「ふにゃふにゃなビーズクッションみたいな感じ?そんな感じでいいと思うんですよね~」
女性だからこうしなきゃいけない。職場のルールだから、こうしなきゃいけない。周りに迷惑がかかるからこうする、ああする。母親になるんだから、バランスの良い食生活を心がけなきゃいけない。子育ても家事も、仕事も頑張らなきゃいけない。
マストな考え方ではなくて、ビーズクッションのような柔軟性をもつこと。肩肘はらず、しなやかに。情報過多にならず、自分を信じて、情報を選択する。
最後に言っていた彼女の言葉が、自分に心地よく響き、帰宅中の足取りがとても軽快になった。
主催の日経doors編集部のみなさま、助産師の小笠原千恵さま、アンバサダーのみなさま、有難うございました!!
