
カラマーゾフの兄弟 その1 ー しんすけの読書日記
今回は第一部と第二部だけを対象にする。
十五歳くらいで河出版の米川正夫訳をを読んだのが最初だった。分かりにくい箇所もあったが、肉親の憎しみを文章にしたものとしたと捉え興味を持ったことを憶えている。
それから六十年近く経っているが、人生の折り目折り目で『カラマーゾフの兄弟』に接してきたように思える。
けっして希望が抱けるような作品ではないのだが、ぼくなりに考えさせられる先品だったのだろう。
冒頭に書いた「肉親の憎しみ」を、当時通っていた教会の牧師に語ったことがある。
すると牧師からは
「読み方が間違ってる! もっと敬虔なものを考えなさい」
って怒られた。でもぼくは、
「ぼくには,、ぼくの読み方がある」
って、その後は教会に通わなくなってしまった。
米川正夫訳は、現在では岩波文庫に所収されている。
以上の出来事が『カラマーゾフ.の兄弟』を、ぼくにとって重すぎる存在にしたのだと思う。
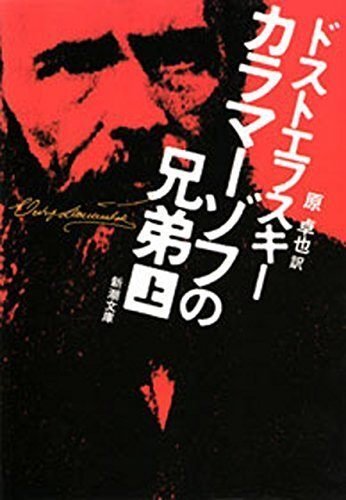
今回の再読で新たに気づいたこともあった。
前書きとなる「筆者より」で主人公が三男のアレクセイで、その一代記を書きはじめると書かれている。
ドストエフスキーの研究者によって『カラマーゾフの兄弟』の続編では、アレクセイを社会主義者として描く予定だった、と書かれていたことを思い出した、
それは『カラマーゾフの兄弟』が、ドストエフスキーの未完成の作品であることを暗示している。
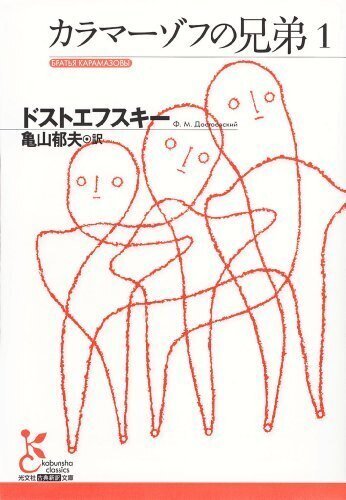
第二部の冒頭での、十七歳(と思われる)のアレクセイと十四歳のリーザの会話が微笑ましい。リーザには少女らしい不安定なところもあるが、アレクセイはそれに優しく答えている。
予定されていた続編では、この二人が夫妻として登場するはずだったと、ぼくは確信している。
今回は次兄のイワンが構想した物語「大審問官」がアレクセイに語られる。
カラマーゾフを語る場合には無視できないのが「大審問官」である。
語ると長くなる内容だが、語らず通過してはカラマーゾフを読んだことにならない。
いや再読時は「大審問官」だけを読んでカラマーゾフの矛盾を考えるだけでも意義あることだと強く思っている。
上記の理を持って以後「大審問官」を中心に書き進める。ただしぼくの個人的な感慨に過ぎないことを最初に断っておく。
最初のほうで、ゾシマ長老が下記を語っている。
無神論者、悪を教える者、唯物論者を憎んではなりません。そうした人たちのなかには善人はむろん、悪人も憎んではなりません。そうした人たちのなかの善人はむろん、悪人も憎んではなりません。なぜかと言えば、とりわけ今のような時代には、そういう人のなかにもたくさんの善人が降りますからね。
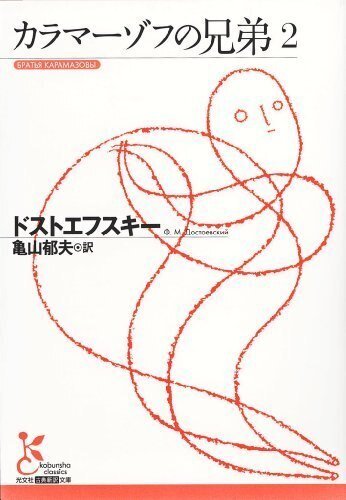
なにか『歎異抄』を読んでいるような気分にさせられる。
イワンは「大審問官」を語る前に、今の世の専制者の非道を多く語る。
それにはアレクセイも、「絞首刑にするべきです」とつい口にする。神に仕えようするアレクセイは、この自分の言葉に恥じるだけだった。
「大審問官」の舞台は十六世紀のスペイン。
大審問官は、ある犯罪者と対面する。その犯罪者は、かって「人はパンのみに生きるのではない」と言ったらしい。
人は食うだけで生きているのではない。だがパンがなくては人は生きていけないのだ。
イワンは語る。
自由と、地上に十分にゆきわたるパンは両立しがたい...
大審問官は語る。
人間の自由を支配するかわりに。おまえはそれをそれを増大させ、人間の魂の王国に、永久という自由という苦しみを背負わせてしまった。
ぼくは思う。自由とは人間の苦悩なのではないかと。安逸に自由を貪るだけの虚しさを人類は知る必要があるのでではないか。
より多く生きていくためには自由を貪るのでなく、自由を分かち与えることではないか。
だが、愚かな人間にそんなことができるはずもない。
実人生では愚か過ぎたドストエフスキーの苦悩の姿さえ、ここに観えてくるのだ。
「大審問官」を語るイワンは、無神論者を自称する男だった。
第二部後半はゾシマ長老の死と、それにいたるゾシマの生涯が語られる。
体裁は語られるというより、アレクセイが聞き知ったことをまとめた形になっている。
だがゾシマの肉声が聴こえる
ここでも「自由を分かち与えること」がリフレインされているような感慨に浸らされる。
ゾシマが九歳の時、十七歳で死んでいく兄は、「召使いに仕える」と吐く。
長じたゾシマが昔の下僕にあったとき、かって己がその下僕を虐げたことに、ひたすら許しを請う。
罪を裁くのは、陪審員でも神でもない。己の良心が己の罪を裁くのだ。
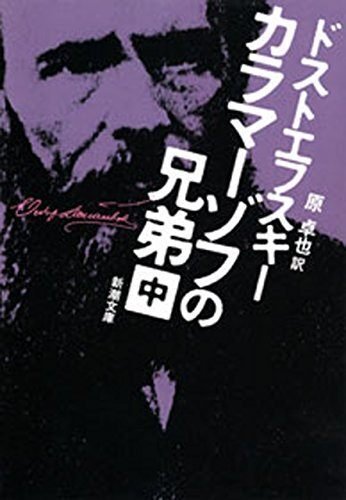
こうして融和を考えさせるもの、次の第三部冒頭でゾシマの死体から腐臭が漂うことが記述される。
なにか、あのリフレインが人間臭いものであるような、そんな期待感すら抱く今のぼくに驚愕さえしている。
実生活が罪多く乱れたものだったドストエフスキーの懺悔の声が聴こえないだろうか?
