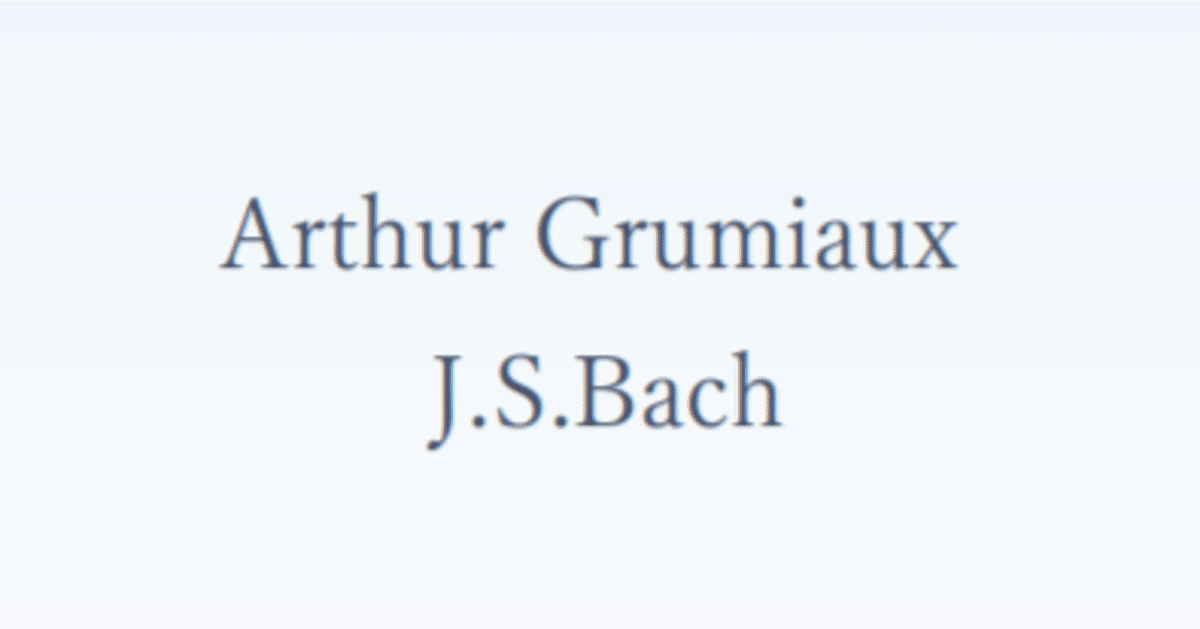
濁りのない、清冽な音──アルテュール・グリュミオー『J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタとパルティータ(全曲)』【名盤への招待状】第9回
濁りのない、清冽な音を浴びたいとき、アルテュール・グリュミオーの『J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタとパルティータ(全曲)』をかける。ソナタ第1番ト短調の冒頭の和音が響いた瞬間から、耳の奥にこびりついたさまざまなものが洗い流されてゆく。淀んだ空気さえも凛とさせてしまう澄みきった音は、宿命的な響きをもつト短調の悲しみをたった独りで引き受けるような高潔さに満ちている。繊細だが内向的ではなく、響きを尽くしてアダージョのゆったりとした旋律線を綿々と歌う。しかしそのヴィブラートからは、悲しみを引き受けることへの、微かな怯えも感じられる。
ソナタ第1番の「悲しみ」に対して「哀しみ」が刺さるパルティータ第1番でも、鋭くはないが弛緩しないリズムと音楽の運びによって、沈み込まずその哀しみに毅然と対峙する。ソナタ第1番のフィナーレもそうだが、クーラントのドゥーブルなどの急速楽章で駆けてゆく音の残す肌触りは、爽快とすら言えるほど鮮やかだ。
その透明感は、各ソナタのフーガなどで、声部ごとのラインが明瞭に聴き取れることにも通底していて、声部構造がすみずみまで見通せる。バッハの作品の演奏なので、拍節感は揺るぎないが、全体に、重厚な構築感よりも、清流のように淀みない流れのほうに耳が寄せられる。パルティータ第2番の終楽章シャコンヌでも、13分を一気に聴かせ、とりわけニ長調の中間部分、静かな祈りに始まった音楽が降り注ぐ光のなかで大きな賛歌へと昂揚するまでの長い過程を、ほとんどひとつの弧で描いてゆくような息の長さは圧倒的である。
それにしても、自分でもそれを望んで再生しておきながら、聴く度にその音の清冽さ、高潔さに驚嘆してしまう。このアルバムのブックレットや帯も例外ではないが、グリュミオーの演奏を語る文中には、ほぼ必ず「比類のない美音」といった言葉が使われている。本来、歴史的演奏家である彼の演奏をいまわざわざ取り上げるからには、あまり指摘されていない魅力などについて語るべきで、評価の定まったことを改めて称賛するなどなんと凡庸なことだろうと思うのだが、やはり聴き終えて一番耳に残っているのは、アプローチやスタイルよりも、彼にしか出せないその音なのである。
音というものは、音楽と演奏を構成する最も基本的で最小の要素であり、それ自体が大きな魅力を備えていることは、演奏においてやはり強みだろう。私は基本的に、人間においても芸術においても、何かたったひとつの部分にそのすべてが凝縮されるというようなものの見方を好まないが、グリュミオーの音を聴いていると、他のあらゆる要素の魅力もその一点がすべて含んでいるように思えてくる。
グリュミオーが音についてどのような思想を持っていたのか私は知らないが、ピアニストのヴァレリー・アファナシエフによると、ヴァイオリニストのギドン・クレーメルは「良い音」など存在しないと「言い張って」いるという。音は何かを表現しているべきもので、たんに美しい音というものはない。それは演奏する作曲家や作品ごとに異なるはずで、音は演奏全体を構成する一要素に過ぎないと。ちなみに、アファナシエフは、「良い音」の存在を信じている。
理想とする自分の音というものが個々の作品を手掛ける前に存在するのか、理想の音は作品ごとに異なるものなのか。私自身を含め、多文化主義の現代に生きる人間にとっては、クレーメルの言うような後者のほうが、論理的には馴染みやすく、説得的に感じられるかもしれない。しかし、私には、そのクレーメルもまた自身に固有の音を持っているように思われる。アファナシエフもクレーメルも、グリュミオーと同じく私の好きな演奏家だが、共通しているのはその点──他の誰からも聴くことのできない音をそれぞれに持っているということなのである。
意識的か否かの違いに過ぎず、大家と呼ばれ得る演奏家はみな固有の音を持っているということだと言ってしまえばそれまでだが、改めてグリュミオーのバッハを聴き、頭の中で反芻させるなかで思ったのは、バッハの書いた音によってグリュミオーの弾く音はますます輝き、グリュミオーの弾く音によってバッハの書いた音もますます輝いているということだった。それは、作品と演奏家との関係として、ひとつの理想だろう。音楽が高みに昇るほどに、その音は研ぎ澄まされてゆく。ソナタ第3番ハ長調のフーガの終盤や、フィナーレのやはり最後の高音の繊細な動きでは、ヴァイオリンの音を超えて、光そのものが可聴化したような音にまで至っている。
このような録音を遺してくれたことを有り難く思うが、やはり、その音を同じ空間で直接浴びられた人たちが羨ましい。
