
PTA嫌いからPTA会長になった話と今後の目指す姿
みなさんこんにちは!@ShinjiTakenaka です。
今日は、私が紆余曲折を経てなぜPTA会長になったのかという話と今後の意気込みについて書きたいと思います。
1. そもそもPTAとは何か
みなさん、そもそもですが、PTAとは何を意味するものかご存知でしょうか?PTAとは
P=Parents(保護者)、T=Teacher(先生)、A=Association(組織)の略。
子どもたちのすこやかな成長のために、親(Parent)と先生(Teacher)だけでなく、家庭、学校、地域社会がお互いに協力し合ってさまざまな活動を行う集まりを指します

知っていましたか?
PTAって保護者が集まって色々しなきゃいけない集まりでしょ?という方が多いかもしれませんが、学校の先生や地域も含め、みんなで子どもたちのために活動する組織ということです。
実は、PTAの歴史は古く、日本で始まったのは1945年だそうです。
アメリカから派遣された教育の専門家が、戦後の日本の教育について示した基本方針のひとつに「PTAの設立と普及」が掲げられ、文部科学省を通じて全国的に広がったそうです。
私がこれを知ったのは、PTA会長になってからです(笑)
2. なぜ、PTA会長になったのか
そんな私がなぜPTA会長になったのか?
実は、当初私は、PTAなんていらないのにと思っていた一人です。
なぜなら、PTAって何してるかよく分からないと思っていたからです。
これ、何か新しいビジネスなどを始めるときも同じなのですが、人は未知に対しては恐怖を覚える生き物です。
“人類の感情で最も古く、最も強いのが恐怖心である。
そして恐怖の中でも最も古くて最も強いのが、未知への恐怖なのだ”
そう、よく分からないから、自分でわざわざする必要はないなと思っていたのです。今思うとひどいものです・・
一方で、昨今のコロナ禍で、保護者同士のコミュニケーションが希薄になっていることにもやもやがありました。
昔はパパ友・ママ友ぐるみで気軽な飲み会や集まりがあったでどんな人かわかっていたけど、今はそれほど会わないので、どんなパパ・ママのどんなお友達と遊んでいるんだろうか?と。
(もちろん、子ども経由から聞いてはいるのですが)
つまり、潜在的には、保護者を含めたいろんな方との接点の必要性を認識していました。
加えて、私自身の興味・関心が最近少しずつ変化してきたことも影響しています。
企業を含む外部人材と、教育現場をつなぐプラットフォームである「複業先生」というサービスをご存知ですか?

私は、このプラットフォームを通じて、これまで高校生向けに「キャリア教育」の授業をさせていただいたり、小中学生向けに「金融」の授業をさせていただきました。
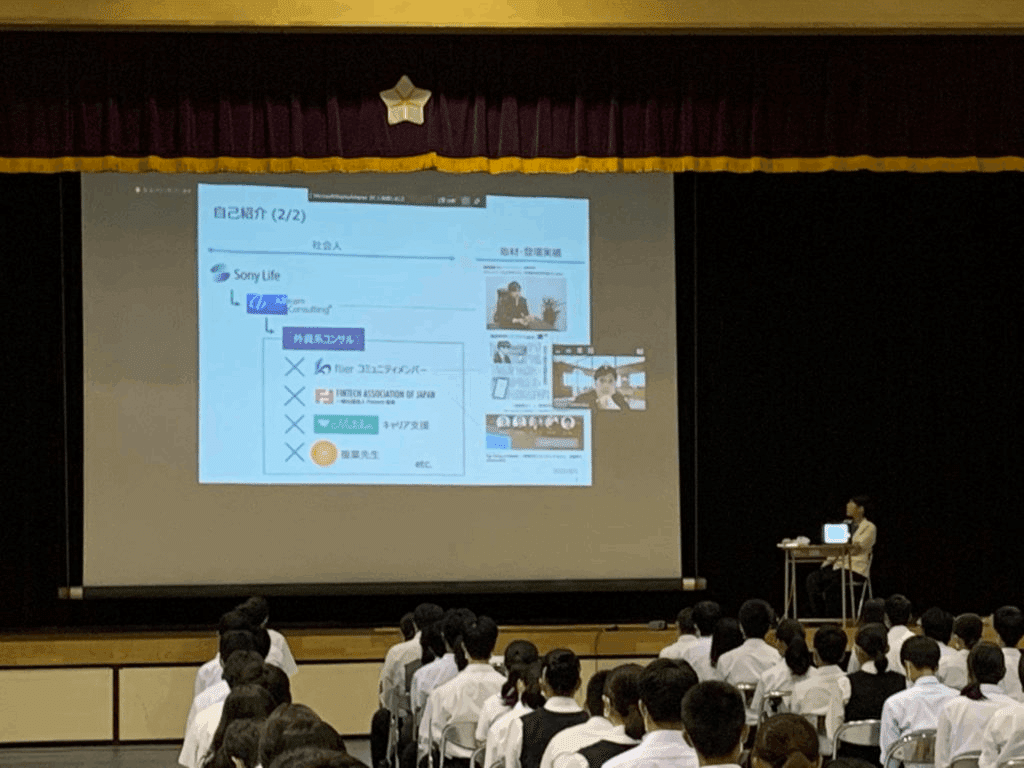

こういった社会(外部人材)と教育現場をつなぐことは、「未知」が「既知」に変わるきっかけだと思うんですよね。
しかも、そういうキッカケは子どもたちのみならず、教職員や登壇してくれている複業先生にとっても次のようなベネフィットがあると思っています。

以上のような背景があり、
・子どもたちの未来にとってもっと貢献できる仕組みがないか
・「未知」がなくなれば、人はもっと好きなことができるのではないか
・保護者や地域の人も巻き込むことで、子どもたちに何かできないか
そんな風に思っていたときに、PTAにたどり着きました。
3. PTA会長としてしていきたいこと
多くのPTAは毎年役員や委員が変わることが多く、中々情報やナレッジが蓄積されていない学校が多いと聞きます。
また、1年が任期だとすると、たとえ無駄だなぁと思っている作業やルールであっても、仕方なく受け入れている場合がほとんどです。
(背景にあるのはまさに「現状維持バイアス」だなと思います)
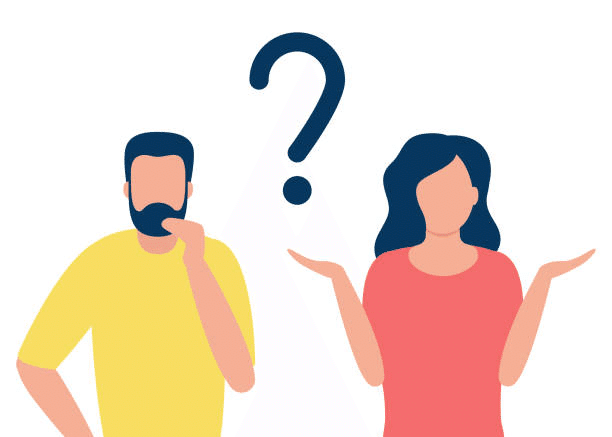
私は、そういうところにメスをいれていきたいと思っています。
「前任者がこう言っていたから、こうしないといけない」とかは思い込みだと思っていて、本当に子どもたちにとって必要なことであればルールは変えていっていいと思います。
例えば、何かにつけてまだ捺印が必要と言われることがありますが、昨今の押印廃止の流れを受けて本当にその捺印を続ける必要があるのでしょうか?
PTA活動は、保護者の方たちの大事な時間をいただいているわけです。
だからこそ私は、「違和感を感じたら声に出し、変えていこう」を体現してく活動をしていきたいと思っています。
4. 目指していきたい姿
私自身、もともと教員免許を取得したこともあり、やはり学校現場全体が良くなっていくといいなと思っています。その一つがPTAという活動を通しての保護者と教育現場、地域のより良い関係の模索だと思っています。
また、以前のnoteで触れたように、私個人としても学校の先生に寄与できればと思っています。
加えて、最近ではコミュニティ・スクールという概念が徐々に浸透し始めています。
コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)とは、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組みです。

私は、ここの活動にも少しずつ足を踏み入れていく予定です。
これにより、学校支援本部としてのNPOや地域団体との関係も深めていくことが、子どもたちにとってのよりよい環境作り・体験につながると思っているからです。
一方で、文科省の資料を見れば分かる通り、このような素晴らしい構想も予算としては削減傾向にあります。(令和3年度予算額は前年比11百万円減額の19百万円)


いくら制度として存在しても、そこをうまく回し続ける(財政面含む)仕組みがないとサステナブルなコミュニティ・スクールになっていかないと思うんです。
だからこそ、私はそこにもっとお金が流れやすい仕組みが重要だと思っています。そこで考えたのが、次のような仕組みです。

そのために、学校支援本部をもっと支援しやすい横断的な推進機関を作り、そこに文科省のみならず、民間からの支援も受けることができれば、
・もっと財政面での制約がなくなり、学校支援本部として動きやすくなる
・もっと他のNPOや教育系企業ともつながるきっかけができる
・企業等のノウハウ/リソース等も上手く活用でき、持続可能な仕組みになる
と思っています。
もちろん、このような仕組みを実現していくには、大変な労力がかかりそうですが、まずはできることから1歩ずつ進めていきたいと思います。
まずは、学校関係者を中心に対話を始めています。
一人ひとりが自律的に自分の人生をデザインできる社会の実現に向けて、一歩ずつ進んでいければと思っています。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
いいなと思ったら応援しよう!

