禅宗に満足しなかった大友宗麟と細川ガラシャ・宗麟とガラシャの禅宗からキリスト教への改宗の同一性

細川ガラシャ肖像画・前田青邨画伯(1885年~1977年)
1974年(昭和49)ローマ法王庁からの依頼によりバチカン美術館に収めた絵
髙田重孝所蔵











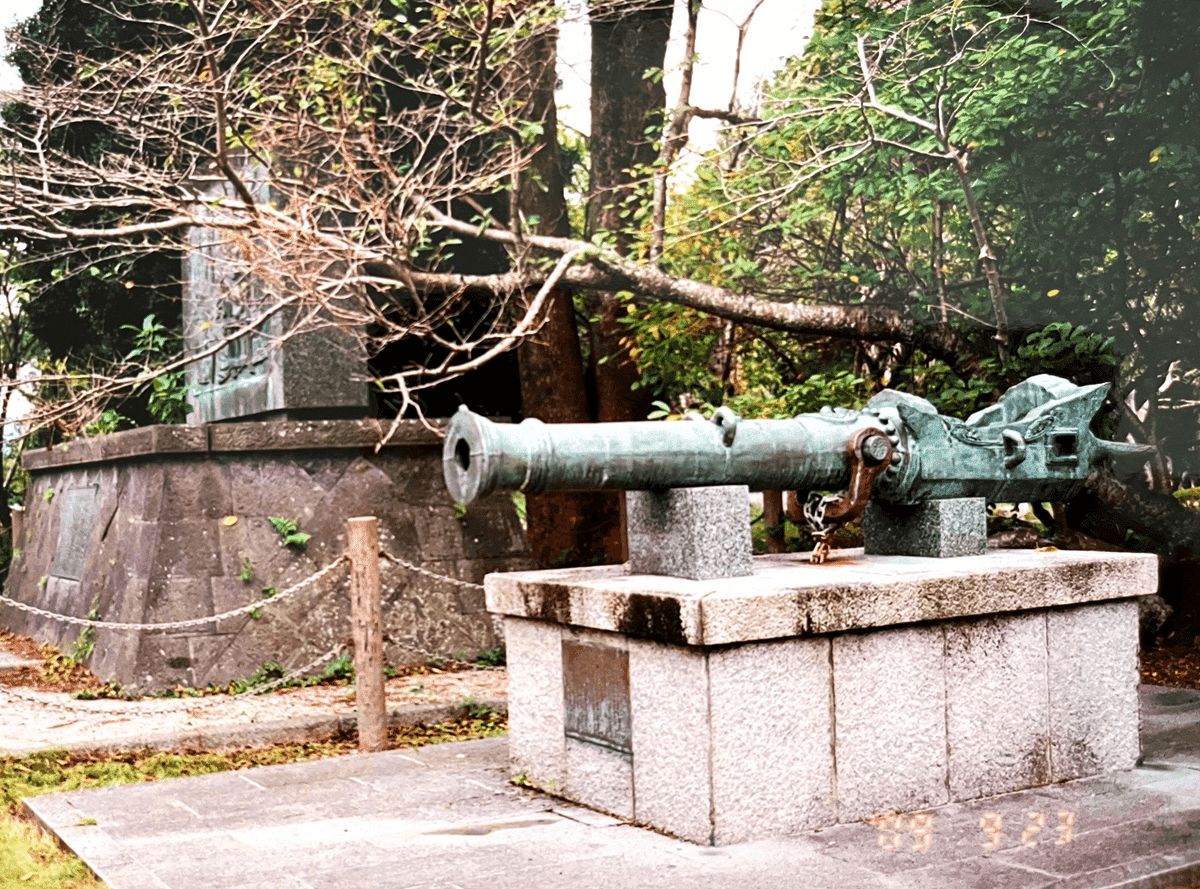







禅宗に満足しなかった大友宗麟と細川ガラシャ
宗麟とガラシャの,禅宗からキリスト教への改宗の同一性
大友宗麟 1530~1587年・享禄3~天正15年
細川ガラシャ 1563~1600年・永禄6~慶長5年
細川ガラシャ(伽羅奢) 略歴
1563年(永禄6) 明智十兵衛光秀の三女、玉(玉子)誕生
1578年(天正6) 細川忠興と結婚(16歳)
1579年(天正7) 長女 長誕生(宮津城)
1580年(天正8) 長男 忠隆誕生(宮津城)
1582年(天正10)6月2日
父・明智十兵衛光秀謀反「本能寺の変」、玉、三戸野へ幽閉
1583年(天正11) 次男 興秋・三戸野に於いて誕生
1584年(天正12) 三戸野より宮津城へ戻る
1586年(天正14) 三男 忠利誕生 大坂玉造の細川邸へ移転
1587年(天正15) 玉、大坂の教会訪問。以後キリスト教を学び始める
禅宗よりキリスト教に改宗・清原マリアより受洗・洗礼名ガラシャ(伽羅奢)
興秋大病により洗礼を受ける。兄忠隆(7歳)も受洗
忠興、ガラシャの侍女たちへ迫害を加える
ガラシャ、忠興との離婚を考える
1588年(天正16) 次女 多羅誕生
1589年(天正17) ガラシャ、忠興に自分がキリシタンであることを告白 忠興、ガラシャのために、細川邸内に祈祷室を造る
1595年(文禄4) 興秋(12歳)叔父興元(キリシタン)の養子となる1600年(慶長5)7月17日 ガラシャ、石田三成の人質を拒否して自害する
思想の構築としての信仰
大名の中には新興宗教であるキリスト教に一時的に感激して入信洗礼を受けた大名もいれば、豊後の国主・大友宗麟の様に長年自分自身の心の葛藤を経験して1562年(永禄5) 5月30日、33歳の時、禅宗へ帰依した後、禅宗の思想の浅さに矛盾を感じてキリスト教を学び直して改宗し16年後、1578年(天正6) 7月25日、49歳の時に受洗した豊後の大名大友宗麟がいる。
ひとりひとりの魂が回心に結びつくまでには、それぞれの事情があり遍歴がある。信仰を構築することは思想を構築すると同じ過程があり、人それぞれに学びの時間と経験の蓄積が必要となって来る。
信仰することとは神を信じて生きることであり、そのためには確立した自己がなればならない。キリスト教を自分の生き方として受け入れ、その信仰に自分のすべてを賭けて生きることこそ、新しく生まれ変わった自分の生き方になる。
人間の尊厳や人間の存在そのものまでも疑わせるキリシタン禁教の時代にあって、キリスト教の信仰を自分のものとして受け止め、絶対に譲れない神を信じる信仰の自由、それに命を賭けて自分の生き方を神の前に問い続ける姿勢を持ち日々を生きることを選び、その中に生きることこそキリシタンとしての信仰者の生き方だった。
大殿宗麟と同じ禅門徒であった細川(明智)玉は1584年(天正12)、三戸野での2年間の幽閉の後、宮津城に帰った後から慎重にキリスト教の教理を学び、思想的に禅宗とキリスト教の教理を比較した末に入信を決断して、1587年(天正15)初めて大坂のキリスト教会を訪問し、その後17人の侍女たちを先にキリシタンにした。キリシタンになった侍女たちの手を借りて、教理の学びを深め、信仰という思想を構築して、その上で侍女頭の清原マリアいとの手により洗礼を受けて1587年(天正15)「ガラシャ」(加羅奢)となった。
玉の信仰構築の学びの基本は、禅宗の禅問答である。禅宗に於いては毎日、ひとつの課題について黙想して自分の考えを纏めて書いて提出することが義務付けられていた。玉はキリスト教を学ぶ際にも、禅問答と同じように徹頭徹尾、自分の考えを指導者、神父や修道士たちに修正してもらいながら自己の信仰を構築している。信仰するということは、自己の思想を構築することと同じであり、そのように構築された信仰とは、命を賭けることができる自己の思想だった。
玉のキリスト教への入信経緯
忠興公御年譜第三に『伽羅奢様(ガラシャ・忠興公夫人)始めは建仁寺の祐長老に三十四、五則参学被成しが忠興公大徳寺の参学よりは心安きものなるべしと被仰候、其後加賀山庄右衛門(隼人佐也)が母吉利支丹にすすめ申候しが、常々殊の外物祝いを被成候て軍しげく、事騒敷時分武具衣装之事に附けても日を余り御選び被成はかの行かぬ気之毒さに吉利支丹は物を打破りにして、はか行くへしと被思召、其時分迄は御法にてはなし共に進めて彼の宗門に被成しが後には無用なりと被仰けれども最早御聞込有て御承引なかりしなり』とある。
*忠興公御年譜第三
『伽羅奢様(ガラシャ・忠興公夫人)始めは建仁寺の祐長老に三十四、五ほど参学して禅宗の学びをしていたが、忠興公がキリシタンは大徳寺の参学よりは心安きものだろうと言われた。ガラシャは常々殊の外物忌み・縁起を担ぐので、合戦の時も武具や衣装、日取り等を気にして物事が進まない様子を見かねた家老の加賀山隼人の母が、キリシタンになったら物忌みや縁起担ぎから解放されるのではないかと言って、キリスト教を勧めた。その当時、キリシタンは違法ではなく容認されていたので、ガラシャはキリシタンになった。その後、キリシタンは違法となり、忠興がガラシャにキリシタンをやめろと言ったが、ガラシャはキリシタンをやめようとはしなかった。』
*忠興公御年譜第三の訳
玉(ガラシャ)は日本の仏教と禅宗の教えについて非常に知りたがり、特に禅宗(日本の宗派の中でも主なもので、貴族が多く信じている)については非常によく学んで奥儀を深く理解していた。ガラシャの禅宗に関する強い関心や学んだ知識は、当時の細川家と吉田家、清原家との血縁関係からも伺えるし、自天清祐長老(英甫永雄)という親戚にいた高僧の存在を背景に持っていて学んだことによる。
『伽羅奢様(ガラシャ・忠興公夫人)始めは建仁寺の祐長老に三十四、五則参学被成しが忠興公大徳寺の参学よりは心安きものなるべしと被仰候、』とあり、ガラシャが建仁寺の祐長老に学び、34~5回ほど通って禅宗の奥儀について学びを深めていたことが書いてある。
建仁寺の自天清祐長老は細川家とは親戚である。自天清祐長老は英甫永雄(えいほ・えいゆう・?~1602年)と言い、若狭宮川の新保山城主・武田信重の子、母は幽斎の姉である宮川尼(細川元常の娘)。1580年(天正8)文渓永忠に師事し如是院に居住した英甫永雄は、同年秋から若狭へ下り、やがて丹後に移り、細川家より田辺に一如院を建立してもらい住持を務めている。その後、1586年(天正14)建仁寺第92世となった。叔父細川幽斎、松永貞徳等と深い交わりがあった。細川家に輿入れして間もない玉に『碧厳禄』を教授した。玉の「参学」は、青龍寺城時代や丹後時代と考えられる。
玉は忠興の両親・細川幽斎と妻麝香と共に寺に通って禅宗について学んでいた。「細川幽斎はすでに老境に入った現在、妻や嫁とともに丹後の国にいて禅宗に励むことをもって信心の務めとしていた。そのため彼(幽斎)は参学を行っていたが,それは、良心の呵責を消していくために、禅宗が示している千七百の要点のひとつずつを毎日黙想し、その最高の域である内心の平和に到達することである。
禅宗の到達点である混沌状態(カオス)
「(彼らが説くところによれば)その平和とは、来世などは存在せず,苦患も栄光もなく、自然界の創造者や宇宙の支配者もおらず、人間の魂は肉体を離れて後は,本分と称せられる混沌状態(カオス)に融け込んでひとつとなる。そこには生命も死も苦も善も悪もない。そこは外的な感覚や内的な能力を欠いた状態があり、無感覚の境地のみがある、ということを納得することにある。」
「上記の舅(幽斎)姑(幽斎の妻・麝香)ならびに嫁(玉・ガラシャ)は、その宗派の学識ある一僧侶(自天清祐長老・英甫永雄)が説く要点の話を聞き、それらについて黙想したところを件の僧侶に語るために、ほとんど毎日のように同所に詣でていた。
彼らのうち、嫁(玉)は(彼女をよく知っている人たちの言葉によれば)繊細な才能と天賦の博識において超人的であったので、他の誰よりも一段と秀でており、すでに彼女は師匠のそのまた師匠で有り得るほどであった。」*完訳フロイス(Luís Fróis)日本史3 織田信長編Ⅲ
第62章(第2部106章)220~222頁
ガラシャが後にキリスト教に対して示した篤い信仰心は、すでに禅宗において示されていた信仰心が、禅宗からキリスト教に変わったということであり、ガラシャ本人の元々持っていた宗教を探求する思想の資質が根底にあった。ガラシャが備えていた宗教を探求するという思想の資質は、父明智光秀から受け継いだものだった。ガラシャの宗教に関しての強い関心と探究心は、性格を異にする2つの資料、細川家の『忠興公譜』と『イエズス会関係資料』により証言されている。
「物忌み」(縁起を担ぐ)が強かったガラシャ
また玉は娘の時代から非常に「物忌み」が強かったと書いてある。「物忌み」とは、本来は神官が神事に奉仕するに先立ち、ある期間行いや禁止されている飲食を慎み、心身を清めてこもることを意味し「精進料理」に表われているように、いっさいの肉、魚、酒を絶ち、身を清めることを意味していた。それに伴い、神事に先立ち、ある物事を不吉として嫌い、避けることが本来の「物忌み」の語源である。
この「物忌み」が拡大解釈され、迷信を信じることも「物忌み」と言われるようになった。いろいろな占いも「物忌み」に含まれ、方角占い、鬼門の考え等も「物忌み」に含まれる。「物忌み」の中には「縁起を担ぐ」ことも含まれていた。
玉は非常に縁起を担ぎ、合戦の時にも武具や衣装,日取りなどを気にして物事が進まない様子を近くで見ていた家臣の加賀山隼人興良の母(キリシタン)が、玉の目に余る「縁起担ぎ」を見て気の毒に思い、玉の考えが変わればとキリスト教を勧めてみた。玉はキリスト教に関しては夫忠興から、忠興の友人・髙山右近よりキリスト教の話を度々聞いていたので強く興味を強く示したようだ。
玉はそういう「物忌み」が大変強かったことが、夫忠興の証言からも判る。そこで忠興は玉に「お前のような物忌みの強い女、迷信を固く信じている者はキリスト教にでもなったら、頑なに信じている迷信や縁起担ぎから解放されるのではないか、大徳寺への参学よりはましだろう」と言って安易に友人・髙山右近より聞いていたキリスト教を勧めてみた。玉に向かって軽い気持ちで「物忌み・迷信・縁起担ぎばかりを信じているようだったら、いっその事(髙山)右近の勧めていたキリシタンにでもなったら、その考えが変わるのではないか」と思い言ったのだろう。
ところが実際、玉がキリシタンになったら、玉はひとつのことに集中(固執)する性格の持主であるから、一度キリシタンになったら、キリスト教に凝って(はまって)しまい、何事もキリスト教式でなくてはならなくなり、後日キリスト教が御禁制になった時、忠興がキリシタンは無用、キリシタンを辞めろと言っても、絶対にキリシタンを辞めようとはしない、と言って忠興は愚痴を言い嘆いている。そういうひとつの事に固執する玉の性格だから、忠興の方が大迷惑をしたと書いてある。玉の頑固一途な性格に振り回されている忠興の困った(困惑した)顔が見えるようだ。
『奥方(玉)は学ぶことには極めて執着心が強く、そうした彼女の決心を思いとどまらせることができる者は誰もいなかった。』
玉は生まれ持って学ぶことに対して非常に熱心で執着心が強かった。思想や宗教に対する感覚が鋭い持ち主だったことが判る。玉本人の元々持っていた宗教を探求する思想の資質が根底にあった。これは父・明智光秀譲りの性格にも依るし、また光秀による教育の賜物だったと考えられる。
明智光秀は感情性が豊かで、感性が鋭く、思考においては深く物事を追求する持ち主だった。光秀は軍事行動に於いても、主君織田信長の様な相手を殲滅する戦い方はせず、戦う相手を懐柔して、なるべく自軍の戦力を消耗するような戦いを避け、自分の家臣たちの損害を出さない戦いをしている。敵であった相手が降伏した後は自軍に組み込み、その部隊を明智軍本隊の中で使う戦い方をすることで、明智軍は次第に組織力と勢力を拡大している。
その光秀の物事を深く追及する思考性を、娘三女の玉は受け継いでいる。探究心の強い玉は、父明智光秀の持っていた感性の鋭さ、深く物事を思考する素晴らしい考察力を受け継ぎ、その才能を自覚して自らの意思で発展させることを欲する才能豊かな女性だった。
玉はキリシタンのどこに魅かれたのであろうか。建仁寺の自天清祐長老に深く禅宗の教えの奥儀を学んだことがあるので、聡明な思考の持ち主である玉の中で、禅宗とキリスト教の教義の違いの明確な区別はついたはずである。
「霊魂の不滅を否定する禅宗」に対して「霊魂は永遠に死なない」と教えるキリスト教(カトリック教会の教義)の正反対の思想に玉は驚いたことだろう。
また仏教と禅宗には少ない隣人への愛、あるいは社会奉仕をする精神性、歴然と存在する階級制度を超えたキリシタンの平等の考え、神の前における人間の平等の精神、君主も平民も農民さえも、教会内では同じ席に付き、助け合う信徒同士の連帯性、宣教師たちの献身的な布教努力と仏僧にない自己犠牲を伴う社会での奉仕と献身。貧しい人々へ向けた慈愛のまなざしと貧困に喘ぐ人々への施しと救済活動。特にこの世の中で治療を必要としている病んだ人々への医療活動。これらは仏教・禅宗の教え(教義)の中にあっても、当時は実際に仏教寺院では行われていなかった。
これらすべてを実践している教会の宣教の姿と、お題目だけを唱えている仏教集団とを比較した時に、玉は自分が求めていたものがすべてキリスト教の教え中にあることを改めて見出した。それゆえに、玉はキリシタンになることを強く望んだと考えられる。
*完訳フロイス(Luís Fróis)日本史3 織田信長編Ⅲ 第62章
(第2部106章)220~222頁
丹後の国の貴婦人にして明智(光秀)の娘であり、異教徒(細川)越中殿(忠興)の奥方 なるガラシャの改宗について
禅宗を信仰していた細川家
「都の近くに丹後と呼ばれる国がある。その領主は(細川)越中殿と称する若く高貴な殿で、明智(光秀)の息女である貴婦人と結婚している。彼女の父の明智(光秀)は、その(丹後の)国に娘を嫁がせたのだが、両人(忠興と玉)は24,5歳を出るか出ないかの年輩である。彼女に夫の父(細川幽祭)、すなわち舅(細川幽斎)は、かつて公方様の邸における主要人物に一人で、公にはともかく、常に我らの(キリシタンの)教えに反対の立場をとってきた。彼はすでに老境に入った現在、妻や嫁とともに丹後の国にいて禅宗に励むことをもって信心の務めとしていた。そのため彼(幽斎)は参学を行っていたが,それは、良心の呵責を消していくために、禅宗が示している千七百の要点の一つずつを毎日黙想し、その最高の域である内心の平和に到達することである。」
禅宗の説く行き着く先の混沌(カオス)とした世界
〔(彼らが説くところによれば)その平和とは、来世などは存在せず,苦患も栄光もなく、自然界の創造者や宇宙の支配者もおらず、人間の魂は肉体を離れて後は,本分と称せられる混沌状態(カオス)に融け込んで一つとなる。そこには生命も死も苦も善も悪もない。そこには外的な感覚や内的な能力を欠いた状態があり、無感覚の境地のみがある、ということを納得することにある。〕
巧妙な禅の教理習得過程の欺瞞
禅宗(の輩)は極めて狡猾で弁舌に長け、謹厳を装っているので、その教えを高く売りつける術を心得ており、ごくわずかの要点を習得させるために十年、十五年、二十年の長期にわたって一人の入門者を引き留め、秘密裏に極めて緩漫のそれらの修業を行わせる。それがため彼らは多くの譬喩とか表象をもってし、遠回しの表現や虚構の説話を用い、修業期間を故意に延長していった。すなわちその修業期間中も,弟子たちの骨の髄まで食い尽くし、己が生活に必要とする金品を彼らから取り立てていた。
こうした修業は、あまりにも長期に及び、かつ困難で、しかも多額の費用を伴う者であったから、貴人たちとか生活に余裕のある者以外、そうした黙想を続けることは不可能だった。
ところでこうした修業をするために、丹後の国の殿の館と城の近くに、一定の収入を付した僧院が設けられ、上記の舅(幽斎)姑(幽斎の妻・麝香)ならびに嫁(玉・ガラシャ)は、その宗派の学識ある一僧侶が説く要点の話を聞き、それらについて黙想したところを件の僧侶に語るために、ほとんど毎日のように同所に詣でていた。
彼らのうち、嫁(玉)は(彼女をよく知っている人たちの言葉によれば)繊細な才能と天賦の博識において超人的であったので、他の誰よりも一段と秀でており、すでに彼女は師匠のそのまた師匠で有り得るほどであった。
禅宗徒にはある独特の考え方があって、彼らはその宗派の奥儀を究めれば究めるほど、そして曖昧模糊とした境地に入れば入るほど、一段と知識を究め、他のあらゆる宗派の者より優れた者になり得たと自負していた。彼らは多宗の者を無知で邪道を歩む者と見なし,他宗の異教徒たちが寺院に詣で、断食や苦行をしながら自分たちの許に救いを哀願して来るときは彼らに対して憐れむかのように振舞った。そして自分たちだけが真理の精髄を究め、内心の平安を獲得しているかのように信じていた。
禅宗に心から帰依できなかった細川玉
このような品位があり,才幹の恵まれた同国の(領主)夫人であったが、後に彼女自らが言っていたように、(当時、彼女が修業によって)会得したことは、彼女をして精神をまったく落ち着かせたり,良心の呵責を消刧せしめるほど強くも厳しくもなかった。それどころか彼女に生じた躊躇や疑問は後を絶たなかったので、彼女の霊魂は深い疑問と暗闇に陥っていた。彼女はそれらの疑問に答えるためには仏僧たちの教えが十分でないことを感じてはいたものの、より豊かな光と、より堅固な教えを示してくれる者とてはおらず、仏僧たちによる救済に頼らざるを得なかった。(中略)
髙山右近が玉に与えた間接的影響
奥方の父(明智光秀)の遺産として、かの(丹後の)国の所領を得たが、彼女は時々、夫(細川忠興)の口から、彼の大の親友である(髙山)右近殿が彼に話して聞かせたデウスの教えに関することとか説教のことを耳にした。そして彼女の夫は、我らの教えを改めて聴聞し、すでにキリシタンになりたいとの気持ちを抱いていた。彼女はそれらの話を夫から聞かされた時に、それをもっと深く知りたいと異常な望みに駆られたが、たとえ彼女が我らの教会へ説教を聞きに行く許可を願ったとしても、また誰か一人の修道士が自分の家に説教に来るようにしてもらいたいと頼んだところで、いずれも到底許してもらえるはずはないと思われたので、彼女は知らぬふりをしていた。
神が備えた福音の好機・初めての教会訪問
そこで彼女は、夫が関白に従って下(1587年・天正15、九州平定・薩摩討伐)の戦争に旅立った時、またとない好機と思われたので、自分に仕えており、最も信頼している幾人かの貴婦人たちにその希望を打ち明け、夫の命令で昼夜を問わず邸を監視していた番人たちに気づかれることなく、自分が我らの教会に説教を聞きに行くことができる方法はないものかと相談した。
たまたま日本では彼岸と称される時期にあたり、異教徒の間では霊場巡りをする時で、人々は寺院へ説教を聞きに行ったり貧者に施しを行ったりして、ちょうど我らの聖週間(復活祭)のようであった。そこで奥方の親しい者、また内輪の者のうち六、七名が、奥方を見つからないように自分たちの間で取り囲んで連れ出すことを申し出た。ただし番人がいる開かれた門から敢然と出ていくのではなく、奥方が鍵を持っている人通りの少ない小さな傍門から出るようにした。またこうした行動の間に生じ得るあらゆる突発事故の備え、彼女たちの間に包まれるように身を寄せて歩いて出て行くことにし、邸に残った者には、番人たちに対して、また外から使いの者が来たような場合にいかに処すべきかについて注意が与えられた。
教会に着くと、幸運にもその日はちょうど復活祭にあたり、折から正午過ぎであった。奥方は教会を眺め、とりわけ彼女の眼に美しく映じた救世主の新しい肖像を喜んだ。室内の装飾,祭壇の造作と清潔さ、教会の地所なども彼女を非常に満足させた。彼女はしばらくそれらのものを眺めた後、内部に取次ぎを請うた。教会の内部からは、説教係の修道士が外出していて不在であるが、もしお急ぎでなければ別室で待たれるがよい、との返事がもたらされた。その部屋は非常に清々しく清潔で、他日関白が思い立って我らの修道院にくつろぎに来るようなことがある場合に備えて、わざわざ設置されたところであった。それらの部屋は極めて清潔で立派な構造である上に、大坂における最も優美な眺望のひとつを備えていたので、彼女はその部屋を見たことをこよなく喜んだ。大坂の上長の司祭(セスペデス・Gregorio de Céspedes神父)が、部下を通して彼女の侍女の幾人かに、かの婦人はいかなるお方かと尋ねてみた。しかし彼女らは、奥方から十分言い含められていたので、誰ひとりとして奥方の名を打明けたり、どなたの奥方であると口外する者はいなかった。
コスメ髙井の説教と教義に関する質疑応答
日本人のコスメ(髙井)修道士は帰るのが非常に遅れたが、帰って来るやいなやただちに説教をし始めた。ところで(最初の述べたように)越中殿の奥方は実に鋭敏で繊細な頭脳の持ち主であったから、彼女は次のような二つの大いなる悩みの真只中に置かれた。その一つは、自分が聴聞した話に関して生じてくる疑問を数々の質問によって解決したいという願望が果たされぬことであり、もう一つの悩みは、時間がないことであった。
すなわち、すでに陽はほとんど沈みかけていて、説教に続きを聞き逃さぬようにしようとすれば、質問に費やされる時間を短縮せざるを得ないからであった。とはいえ、博識な彼女は、そうした質問をする以外の学び方に甘んじるはずはなかった。かくて彼女は多くの質問を修道士に持ち出し、さらに霊魂の不滅性、その他の問題について禅宗の幾多の権威を振りかざして反論を試みたので、修道士は彼女の頭脳の敏克さに驚いて,後ほど、自分は過去十八年の間、あらゆる宗派についてこれほど明晰かつ果敢な判断ができる日本の女性と話したことはなかった、と漏らした位であった。
彼女は(キリストの)福音の教えと、自らがその時まで奉じてきた禅宗との間にある相違を見届けると、再びそこ(教会)に来ることができぬ身であることを承知していたから、聖なる洗礼を授けて欲しいと大いに願い、幾たびか、両手を合わせてその願いを繰り返した。
そしてまだ理解し聞かねばならない説教の残りの部分は、その時にすでに開始されていた。説教の台本である教理本を、できれば拝借し、それによって学ぶことにしたいと申し出た。
(だが)その時、彼女の願いを受け入れることは見合された。というのは、司祭たちは彼女が何者であるかを知らず、関白は大候たちの娘を多く囲っていたから、あるいは関白の重立った側室の一人かも知れないと疑ったからである。そこで、もはやほとんど夜に入ってしまったので、また今後、別の機会に教会に来て、もっとゆっくり説教を聞かれ、ゆとりをもって受洗される方がよろしかろう、と希望をもたせ,鄭重に彼女を送り返した。
彼女の邸の番人たちは、外出したことを知っていた婦人たちの帰りが遅いことから、彼女たちと一緒に、奥方も外出されたことを悟るに至った。そこで彼らは駕籠で迎えに来て教会から奥方を連れ去った。だが司祭たちは、この件を確認し、彼女がいかなる身分の人であるかを知ろうとして、一人の若者をして彼女たちに尾行させ、どこの邸に入って行くかを見届けさせた。そしてその若者は帰ってきて、一行は丹後の国主(細川)越中殿の邸に入ったと告げたので、教会ではかの貴婦人がその奥方であることを知った。
清原いととガラシャ
翌日、彼女はその邸の重立った夫人の一人を通じて教会に伝えるところがあった。その婦人は(細川)家の家事いっさいを司っており、奥方の親戚にあたり、かつて大和の国において、もう一人の貴人・結城山城殿とともにキリシタンになった(清原)外記殿という内裏の師傳を務めた一公家の娘(清原いと)であった。奥方の師であり(細川)家の侍女頭でもあるこの婦人は、知識においても奥方にほとんど劣りはしなかった。奥方はこの婦人を通じて教会で受けた持て成しに対して礼を述べ、前日の説教に関して生じた幾つかの疑問を書きしたためてこの婦人に携えさせ、彼女にそれらについての返答を持ち帰るように命じた。
さらにこの同じ婦人(清原いと)に、彼女が教会で特別にカトリックの教理の説教を聞き、帰宅後に、自分にそれらを伝える役目を続けるようにと命じた。こうすることによって、奥方の胸中には、デウスの教えに対する嗜好と、己が救霊への異常なばかりの情熱や熱意が高まっていき、自分に仕える貴婦人たちと一緒にいる時には、昼夜を問わず、デウスの教えとか、教会や伴天連たちのこと、それにキリシタンになりたいとの燃えるような希望以外のことは決して話さなくなった。
ついにこの侍女頭(清原いと)は、すべての説教を聞き終えると、聖なる洗礼を受けた。そして洗礼と共に多くの(主なるデウスの)恩寵を受け、その結果、この奥方の洗礼への望みもますます強められた。
善事は元来、人々に伝わっていく性質のものであって、彼女はこれほどまでに望んでも洗礼を受けるために教会に行くことができないことが判ると、自分に奉仕しているかの貴婦人たちを教会に遣わしてキリシタンにさせようと、あらゆる方法を求め工夫をこらした。
そのために、ある者は親族の病人を訪ねるのだと言って外出の許可を求め、別の者は約束した願い事を果たすためだと言って許しを求めた。奥方もまた彼女らに伝言を託して送り出すように装った。このようにしてある時は数名が、また別の折には幾人かがというように説教を聞き、十分理解した上で少しずつ洗礼を受けていき、そしてその数は十六名に達した。
それは奥方の夫(細川忠興)が大坂にいたならば到底あり得ぬことであった。侍女の貴婦人たちは、邸に帰って来るたびに、説教の内容や、教会での動作、ミサ聖祭、キリシタンの出入り、煩繁に告白に来る人たち、説教を聴聞に来る人たちなどについて奥方に報告した。
ことに、彼女たちはすでに聖なる洗礼によって(信仰の徳に)飾られていたから、奥方が彼女たちに対して抱いている聖なる羨望の念は異常なほどで、奥方は、彼女らは仕合せものだが、それに引き換え自分は不仕合せだと言い、その思いを胸中に留めておくことができなくてしばしば大いに涙した。
細川邸でのキリシタン婦人たち
奥方(細川玉)は、これらの婦人の一人一人にキリストのコンタツ(ロザリオ)を作らせ、それで祈らせた。そして彼女も、彼女たちの誰にも劣らぬほどの信心と熱意をもって、毎日、聖母のロザリオを全部と、その他の祈りを唱えた。また奥方は、日曜日や祭日に、キリシタンたちは労働を休み、それらの日には、特にデウスを讃美し、己の救霊のことに携わることがカトリック教会の命ずるところだと聞かされたので、日曜日や祭日には、その家では誰も働かないようにと命令し、婦人たちには縫い仕事を禁じた。奥方は、それら特定の日には、すでにキリシタンになっていた婦人たちをすべて招かせ、前から抱いていたのとは異なったいっそうの愛情をもって彼女らを愛した。

小笠原少斎とガラシャ
この奥方は、これらの重立った番人たち、かつ邸の監視人のうちの一人(小笠原少斎)をキリシタンにできうる方法はなかろうかと切に望んでいた。そのうち狙いを付けた人物(小笠原少斎)の妻は、浄土宗という一宗派の熱烈な信徒で、丹後の国にいる仲間と一緒に教えを受け、救いの道に与ろうとして、一人の仏僧をその僧院においていっさいの面倒を見ていた。ところで奥方(玉)は、その番人がキリシタンになれば、彼はほかの事情をすべてわきまえて、自らは心安んじ、もっと自由に教会へ伝言を持たせて人を遣わすことができると考えた。
そこでこの奥方は父(明智光秀)の命日が近づくと、家臣であるその男(小笠原少斎)を呼んで来させ「父の法事を営みたいので、必要な準備をさせてください」と言った。そしてその家臣が平伏して用件を承り、次いで外に出ようとすると、彼女はわざともう一度彼を呼び止めて言った。「そなたに申しましたように私は父のためにこの法事を営むことに決めています。ですが私に仕えています侍女たちが言いますには、キリシタンたちは,私どもが営むこうした(仏式の)法事は無益で笑うべき行事だと考えているとのことです。そこでそなたにお願いがあるのですが、そなたは伴天連の教会に行って、本心からのように見せかけて説教を聞きたいのだがと願ってはくださらぬか。そしてその後、よい機会を見計らって、伴天連にキリシタンの法事と私たちのそれとはどのように違うのかと訊ねてみていただきたい。と申しますのは、私はあの侍女たちの言うことを軽々しく信じたくはないからなのです。ところでもしも私たちの法事がことによって役立たぬようなものでしたら、それを行うには及びますまいし,無駄にお金を費やすこともないでしょう。」とその善良な人物(小笠原少斎)は、奥方がどのように立派な考えを持っているのか、またどのような意向で自分を教会に遣わそうとするのかを知らずにいた。
奥方(細川玉)は、この男(小笠原少斎)が邸を出るに先立って,密かに司祭たちに通告し、これこれの男がそちらに赴くが、この人(小笠原少斎)は他の多くに人々を改宗させるために私に手先となる必要が大いにある大切な方で、彼にデウスのこと,並びに仏教とキリシタン宗門の法事の違いについて特に話して聞かせていただきたい、と願っておいた。
大坂には、我らのうちで最も優れた説教家であり今日までイエズス会に入った日本人のうち、最も稀な才能の持ち主であるヴィセンテ修道士がいた。彼はあらかじめこのことについて知らされていたので,件の男(小笠原少斎)が到着するとただちに説教を行ったが、修道士は、異教徒が陥っている誤り、とりわけ彼らの法事の愚かさと虚偽、またそれらが人々に何ら役立ちはしないことを明示したので、その男は心を奪われてしまったかのようであった。
彼は感心し、キリシタンになりたい気持ちになって帰ってきて奥方に言った。『私は今だかつてあれほどの人の話を聞いたことがございませぬ。今ひどく悔やまれますのは、数年前に、いとも馬鹿馬鹿しい法事に、この上もなく無駄な費用をかけたことです。』と。
そして彼は神仏(浄土宗)の非常に熱心な信奉者であったのもかかわらず、それからというものは、何もかもなげうち、直ちに数珠とか、仏僧たちから与えられていた位牌を焼いてしまった。それのもみか、既述のように、彼にも増して阿弥陀の信心に厚かったその妻までが説教を聞きに行くようになり「アガタ」という教名の非常に立派なキリシタンになるに至った。
奥方はそのことについてさりげなく彼に言った。「そのような次第なら、このたびの法事は取り止めなさい。そなたの言う通りだとすれば、私の父(明智光秀)にとって何の益にもなりませぬから」と。

ガラシャが熱心に読んだ「キリストに倣いて」
奥方は司祭たちに、デウスの教えについての関心をいっそう深めていきたいので、御身らのお手元にある日本語に訳され日本の言葉で書かれている霊的な書物を是非とも送っていただきたいと願った。司祭たちは当初『コンテムス・ムンジ』(キリストに倣いて)を送ったところ、彼女はそれがいたく気に入り、片時もその書を身から放そうとせず、我らヨーロッパの言語に出てくる言葉とか未知の格言について生じる疑問をすべて明瞭に書き留め、侍女の(清原)マリアにそれを持たせて教会に遣わし、それらの回答を自分のところに持って帰らせた。奥方の文字は日本では極めて稀なほど達筆であり、彼女はそのことで極めて名高かったから彼女は後に自筆でもって他の多くの霊的な書物を日本語に書き写した。(中略)
奥方は、祝祭日には、既述のキリシタンの婦人たちを自分のところに集め、彼女自らジェルソン(キリストに倣いて)のいずれかの章を読むか、または自らが書き写した教理書に記されていることを話した。
奥方は、デウスのことを聞いてからは、大いに貧者に施すことを好むようになり、ある日には教会に百本の太い蝋燭を届け、それを祭壇で使用してもらいたいと願った。
彼女はただ一度、復活祭の日に我らの修道院に出かけただけであったにもかかわらず、それ以後、彼女は家庭的に極めて打ち解けた女性となり、まるですでに多年キリシタンであるかのようであった。
ガラシャの洗礼
当時奥方が外出するには大いなる危険が伴ったので、司祭たちは奥方の側近者で親族でもあるマリア(清原)に、聖なる洗礼の授け方と言葉、ならびに授洗者としての役目に必要な条件や心構えを教えた上で、彼女の手によって自邸で奥方に洗礼を施すことにした。かくて奥方はよく準備を整え、平素彼女が身を隠している部屋の中の不断に祈りを捧げている(聖なる)肖像の前で、跪き、両手を挙げ、侍女の(清原)マリアから聖なる洗礼を受けた。そして彼女にはガラシャ(伽羅奢)の教名が授けられた。
聖なる洗礼によって彼女は至高の満足と喜悦を覚え、熱心さに溢れ、信仰の証のために生命を捧げたいとの大いなる決心に燃え、直ちに司祭に対して、この度の授洗についての工夫や配慮について謝意を述べさせるとともに、たとえ司祭たちが立ち去ることになっても、自分に関してはなんら疑念を持つことなきようにと伝えさせた。そして司祭たちが出発する少し前に、旅費の一助にと、若干の金子を彼らに送った。
鬱病だったガラシャの心と態度の変化
ガラシャは彼女の領国(丹後)にひとつの立派な教会を建て、そこで住民の大改宗を企てる決心でいた。キリシタンになることを決めて後の彼女の変わり方は極めて顕著で、当初はたびたび鬱病に悩まされ、時には一日中室内に閉じ籠って外出せず、自分の子供の顔さえ見ようとしないことがあったが、今では顔に喜びを湛え、家人に対しても快活さを示した。怒り易かったのが忍耐強く、かつ人格者となり、気位が高かったのが謙虚で温順となって、彼女の側近者たちも、そのような異常な変貌に接して驚くほどであった。
夫忠興との不和の問題
大坂の上長の司祭(オルガンティーノ Soldo Organtino・イタリア人、56歳)は彼女と夫の間にいくらか不和が存することを承知していたので、彼女が現在奉じているデウスの教えによれば、正しいことにおいては夫に従い、救霊について知識が得られるよう夫君を導く努力をすべきである、と彼女に注意するところがあった。
それに対して彼女は答えて言った。「尊師におかれては、私の過去のことについてどうか驚き遊ばされますな。と申しますのは、私にはデウス様の光や真実の救いとか来世についての知識とてありませんでしたからそのことから夫に従うについて難しいことが生じていたのでございます。つまり私は、たとえ父(明智光秀)を失った身であるとは申しながら、そのために私を落胆させたり辱めたりすべきではないことを夫の悟らせようとしてあのように振舞ったのでございます。でも今は伴天連様がお命じになることが良く判りましたし、主なるデウス様の御恵みによって、御命令を、身をもって実行するよう努力いたすつもりでございます」と。
清原マリアの決心
ガラシャを助け、その身辺のことを見ることに非常に尽くしている侍女頭で、親戚でもあたるマリア(清原)は、奥方に洗礼を授けた後、教会に行き、大坂の上長(オルガンティーノSoldo Organtino神父)と話しながら次のように述べた。「私にあのような髙く尊い役目をお与えくださいましたデウス様の御恵みはいとも大いなるものでございました。それは伴天連様方独自の御役目でありますのに、この賎しい私を道具に用いられ、奥方様が私に手から受洗されることを嘉し給うたのでした。今では奥様方は、まるで霊魂の母であるかのように私に対して特別な尊敬を抱いておいで遊ばしますからには、私はこの上は今後、世俗のことに心を囚われたくはありません。(彼女はまだ若く、立派な天稟の資質を備えていた)。それ故今後は死に至るまで貞潔に生きることをデウス様にお約束いたします。そのために剃髪(それは日本では世を捨てた印しである)することをお許しくださいますよう、尊師にお願い申します」と。
こうして彼女は告白を終えた後、頭髪を剃り、信仰への強い関心と、この度の迫害において仲間たちが強固であるよう手伝いたいとの強い願望を示した。
ガラシャが初めて教会を訪れた際に、修道士コスメ髙井との教義のやり取りで、キリスト教の教義について注意深く説教を聞き、彼女たちが質問したこと、および教理に属することを説明させた。この説明を非常に注意深く長い時間聴いた。その後ガラシャは彼に対して激しく論争をしかけ、日本の宗派の説く道理で彼に答え、彼に様々な質問をし、我らの教えについて論議したので、コスメ髙井修道士は大いに驚き、日本でこれほど理解力を持ち、また日本の宗派について良く知っている婦人を見たことがない、と言った。ついに夜が近づいてきて、細川藩邸から迎えが来たので、奥方一行は別れを告げて邸に帰った。彼女は我らの教えに極めて満足したので、好奇心は讃嘆と信心に変わり、我らの教えが真実で(修道士が説明した通り)確かで、内容があり、日本の宗派は誤りで欺瞞であると固く考えるようになった。ここから、すべての説教を聴きたいという生き生きとした願いが生じ、キリシタンになりたいと思い始めた。
*16、17世紀イエズス会日本報告集 第Ⅲ期第7巻 227~231頁
1588年2月20付、有馬発信、ルイス・フロイス(Luís Fróis)の書簡
1587年度日本年報
五畿内より別の司祭がキリシタンの準備と熱気を知らせた後の一節は次の通り
尊師に知っていただきたいのは、ついに今回の艱難が五畿内において教会の新しく、また美しい顔を明らかにしたことである。というのは、我らは今まで我らがここに待っていた宝を知らなかったからである。我らの主に称えあれ。当地のキリシタンたちにかくも恵み豊かに伝えられしことを。
「この迫害に嵐に中で生じた幾つかの目覚ましい出来事は、幾人かの異教徒がキリシタンになることを望んだことであるが、当然第一に挙げるべきは、丹後の国のガラシャ夫人である。この夫人が、先年書き送ったように信長を殺した明智(光秀)の娘で、その国の領主の(細川)越中(忠興)殿という異教徒に嫁いでいた。この人物は生来非常に乱暴で、特に嫉妬深く、邸の中で厳格であった。今回関白殿に従って西国の戦(九州平定)に行くことになったので、彼はその奥方に、彼が帰るまで決して外出しないように厳重に命令していき、自分の信頼している二人の老家臣に奥方を託した。彼らは異教徒であり、大坂に有している豪壮な邸に妻と住んでいたが、この人たちに奥方を厳重に監視するよう、また邸の外に絶対出さぬよう頼んでいた。というのは右近(髙山右近)殿の親友であり、右近殿は彼に常に説教し,他のすべての友人の殿たちとの時と同様に、我らの教えのことを話していたからである。
そして彼を動かしてほとんど説教を聴きに来るところまで来ていた。奥方はこの人物の妻で、日本の教えについて非常に知りたがり、特に禅宗(日本の宗派の中でも主なもので、貴族が多く信じている)については非常によく知っていたが、生来好奇心が強く、生き生きした才知の持ち主なので、キリシタンの掟には何があるか知りたいという願いを持つようになった。しかし夫は関白殿と戦に行き、彼女は彼の命令でとじこめられていたので、望んでいたように司祭たちと話す合便宜がなかった。しかし我らの教えを知ろうという願望が刺激を受けて高まっていたので、何らかの方法で司祭たちと話すことを探す決心をした。
日本では、異教徒たちがその偶像のある神社や仏閣を何度も巡歴する一定の季節(彼岸)が到来したので、この機会をとらえて、次女の間に隠れ、寺院に行くふりをして我らの修道院に来る決心をした。六、七人の貴族の侍女たちに混じって、その中に一人になりすまし、そのような方法で彼女の目的を達した。我らの修道院に着き、教会が清潔できれいに飾ってあるのを見(当日は、たまたま我らの復活祭に当たったため)、祭壇の装飾が立派で、また、そこにあった我らの救世主の美しい画像を見て、我らの教会に大いに満足し、幾人かの身分の高い夫人が説教を聴き、我らの掟の教えの内容を知りたいと言っているので、だれかよい説教師を派遣してほしいと、司祭たちに伝言をつたえさせた。
どのような婦人たちか問い合わせたが、どうしても言いたがらなかったので、司祭たちはどこかの有力な奥方が、そのように隠れて来たのであろうと想像し、すぐコスメ(髙井)修道士を派遣して説教させ、彼女たちが質問したこと、および教理に属することを説明させた。この説明を非常に注意深く長い時間聴いた。この夫人は、彼に対して激しく論争をしかけ、日本の宗派の説く道理で彼に答え、彼に様々な質問をし、我らの教えについて論議したので、修道士は大いに驚き、日本でこれほど理解力を持ち、また日本の宗派について良く知っている夫人を見たことがない、と言った。
ついに夜が近づいていたので、別れを告げて邸に帰った。彼女は我らの教えに極めて満足したので、好奇心は讃嘆と信心に変わり、我らの教えが真実で(修道士が説明した通り)確かで、内容があり、日本の宗派は誤りで欺瞞であると固く考えるようになった。ここから、すべての説教を聴きたいという生き生きとした願いが生じ、キリシタンになりたいと思い始めた。」
豊後の国主・大友宗麟と禅宗

大友宗麟(Frenisco)略歴
1530年(享禄3) 1月 豊後国主第20代大友義鑑の嫡子として誕生
1539年(天分8) 11月 塩法師丸元服 義鎮(よししげ)と称する
1549年(天分18) キリスト教伝来、ザビエル(Francisco de Javier)
1550年(天文19)2月 「二階崩れの変」義鑑死去、義鎮が21代国主になる
1551年 (天文20) 8月 ザビエル、府内の大友義鎮と面会する
1556年(弘治2) 山口の教会、戦火により消滅、豊後府内に本部を移転する
1557年(弘治3) アルメイダ、府内に育児院、病院を建築する
1559年(永禄2) 6月 義鎮、豊前、筑前国守護職に補任される
1562年(永禄5) 5月 義鎮、臼杵丹生島城に入り、府内の行政機構を移転させる。 大友義鎮入道して『瑞峯院三非斎宗麟』と号する
1573年(天正元) 宗麟、家督を嫡子義統(よしむね)に譲り後見役になる1577年(天正5) 12月 日向伊東氏、薩摩軍に侵略され宗麟を頼って豊後へ逃避する
1578年(天正6) 春頃 正室奈多夫人と離婚、臼杵城から新妻と共に城外に移り住む
4月 第1次日向侵攻 縣(延岡)土持氏、滅亡する
7月 宗麟、洗礼を受けキリシタンになる、ドン・フランシスコ
11月 第2次日向侵攻 髙城・小丸川の戦いで大敗する
1580年(天正8) 秋頃 ヴァリニャーノ、臼杵に修練院、府内にコレジオを設立する
1582年(天正11) 2月 伊東マンショ・天正遣欧少年使節、長崎を出発する
6月 「本能寺の変」勃発
1583年(天正11) 宗麟、津久見に移り天徳寺(キリシタン教会)を建立
1585年(天正13) 豊臣秀吉・関白になる
1586年(天正14) 3月 宗麟上洛し秀吉に島津征伐のための援軍を要請する
10月 島津軍、豊後に侵入、豊後軍、宇佐まで撤退する1587年(天正15) 秀吉の援軍到着、島津軍、豊後より撤退する
5月 宗麟 津久見の屋形で死去、享年58歳 7月 秀吉の九州平定が完了、
博多箱崎宮で「伴天連追放令」発布

大友義鎮入道して『瑞峯院三非斎宗麟』と号する
一五六二年(永禄五)五月三〇日
京都大徳寺(臨済宗大徳寺派)に塔頭(子院)瑞峯院を建立。
京都の大徳寺から怡雲宗悦(いうんそうえつ)という高僧を招き、怡雲宗悦のために『臼杵の御殿と城に向かい合った地、臼杵城(丹生島・にうじま)の北側、臼杵川と熊崎川・末広川が合流して流れ込む臼杵湾を隔てた対岸の北側の臼杵の諏訪山に大きな禅宗寺院を建立した。この寺が『紫野壽林寺』であり、この寺で大友義鎮(三三歳)は入道して『瑞峯院三非斎宗麟』と号した。*フロイス・Luís Fróis・日本史
『壽林寺』は現在の臼杵市諏訪地区にあったことが江戸時代中期に著かれた『臼陽寺社考』等などから推定されている。壽林寺は一五八六年(天正一四)島津軍臼杵侵攻直後、あるキリシタン女性の放火によって全焼したことがフロイスの記録にある。壽林寺跡地には江戸時代臼杵藩別邸が建てられていた。大友宗麟は臼杵を城下町として整備して、臼杵の丹生島に城を築き、臼杵が大友氏の政庁所在地となった。
*『壽林寺』推定地
旧市街地より県道二〇五号線で臼杵川を渡り次の交差点を右折、臼杵大橋を渡った右側袂周辺付近が『壽林寺』跡地
*完訳フロイス(Luís Fróis)日本史7 大友宗麟編Ⅱ
第33章(第1部106章)78~79頁
禅宗に深く帰依していた大友宗麟
「この国主(大友宗麟)は徹底的に日本の宗派の本質を見極めることに常に非常に心を傾け、それに絶えず大いに熱中していた。そして禅宗がもっとも諸侯や大身の間で重んぜられていたので、国主は都において紫という禅宗の本山(大徳寺)に、一人の息子を入れるために小堂と住院(瑞峯院)を建設せしめ、また同所にいた最も名望ある僧侶(怡雲宗悦)の一人を豊後に来させ、彼から同宗派の観想の諸点について教えを乞うことにした。この僧侶が豊後に来た時に、国主は、自分とその政庁の最も身分の高い殿たちがいつも仕事をしている臼杵の御殿と城に向かい合った側(臼杵の諏訪地区)に特別な配慮をもって、その僧侶のために一寺院(寿林寺)を建立させ、同寺院に十二、三歳になる次男の息子を入れるために、その寺院に相当な扶持をあてがった。
和尚と呼ばれ、都から来た国主の師匠である仏僧(怡雲宗悦)は、大いに賢明に、自らの権威と名誉を保持することを心得ていた。しかし彼は一同からきわめて敬われたので、ひどく傲慢となり、ついにはまったく発狂するに至ったので、国主は彼を監禁し、狂人として都に送り返してしまった。」
*完訳フロイス(Luís Fróis)日本史7 大友宗麟編Ⅱ
第36章(第Ⅱ部1章)114~118頁
「豊後国主(大友宗麟)は(禅宗に帰依しており)同宗に対する好意,並びにその宗派の知識によって自らの名声を高めようと考えていた。そのためからは都のある紫と称される同派最高の僧院(大徳寺)にひとつの高貴な建物(瑞峯院)を作り、その維持費を豊後から送るとともに、息子の一人をそこに居らしめることにした。
また臼杵の自分御城と向かい合ったところに多額に費用をかけて非常に荘厳な僧院(寿林寺)を建て、都の著名な学僧(怡雲宗悦)をそこに住まわせるべく招聘し、領内最高の封禄を給した。彼(宗麟)はその事業に大いなる関心を示し、そのほとんどすべてを自らの手でなすことを欲したほどであった。また彼は次男(親家)をその僧院(寿林寺)に居らしめて、将来はその息子を、封禄を受けるその僧院の上長に仕立てるつもりであった。
ところでその若者は,同所に幽閉された状態であったことはともかく、さらに僧侶になることに内心深く怒りを感じていたので、国主は彼をなだめ、反逆的で恐るべき性質の持ち主であるこの息子を、万事につけ、父である自分に従わせるためにはキリシタンにするのが良いと考え、彼を僧院から出し、洗礼を受けさせた。
領内の貴人や有力者たちは、国主をいっそう喜ばせようとして禅宗の信徒になったが、国主は他の人たちにもそうすることを勧告した。だがそうした全期間を通じて、フランシスコ・カブラル(Francisco Cabral)師は、国主のためミサを捧げることをやめなかったし、日本在住の他の司祭たちにもそのためミサを捧げるように命じた。彼はこのように役立つ国主、しかもイエズス会に実に多くの恩恵を手ずから授かってきた人物を失うことを深く憂慮し悲しんでいたからである。とはいえ、国主がその禅宗に対して示してきた関心と恩恵は(人間的な言い方をすれば)その改宗への希望をはるかに上廻るものがあった。
かの寺院の上長として都から来た国主の師匠(怡雲宗悦)は、国主をはじめ、すべての重立った人々から神託者のように崇められ、その面前で人々は低頭し平伏した。毎日彼の許には莫大な贈物や黄金がもたらされたので、彼は尊大不遜となり、もはや貴人たちに対しても軽蔑した態度で話し、国主すらも、自分の目下であるかのように遇した。だが我らの主なるデウスは、人々が悪魔的な傲慢に陥ることをこよなく嫌悪し給うので、その僧侶(怡雲宗悦)がこの途方もない増長に長く留まることを許されなかった。すなわち彼はついには理性を失ってしまい、まったき狂人となり、監視を付けられたまま都に送り返されるに至った。(それは禅宗に対する小さからぬ悪しき不吉な前兆であった)。(中略)
嫡子(大友義統)はまた、仏僧たちとその寺院から扶持を没収して、それらをそこで奉仕する人々に与えた。最も多くの特権を掌握し、その時まで最高の尊敬を受けていた人たちが扶持を没収され、三千ないし四千クルサードの財産を接収された者も少なくなかった。
異教徒たちにとってこのように振舞うことは不敬罪に等しく、豊後において、寺院を汚し、その扶持を没収し、仏僧たちの権威を衆人の前で失墜せしめるがごときは、前代未聞もことであったから、この出来事に人々は目を見張った。またこのことは、身分ある若侍たちに取り締まる役目を思いつかせ、彼らは仏僧たちの職権と財産を没収しようとして、その際、些細な悪事でも見つけ次第その摘発にあたった。そしてそのようにして摘発された者は少なくなかった。
豊後の有力者の一部は、嫡子のこのまったく新しく、誰もそれまで試みたことのない行動が、いかなる理由によるものか知りたく思った。それにつき嫡子は、仏僧たちは民衆を骨の髄まで食い尽くし、贅沢三昧な生活をし、貧者や、戦場で戦って生命を失う兵士たちを嘲るからである。と答え、さらな次のように言った。「彼らが宗派の掟に従って生活し、人々が、神や仏は来世では賞罰を、現世では繁栄と財宝を与え得ると信じるように振舞うならともかく、仏僧たちの無軌道ぶりは周知の事実で、彼らの生活は悪癖と偽善と欺瞞に満ちており、その犠牲と祈祷は何の役にも立たず、何らの実も結びはしない。それらを見て見ぬふりをすることは、とてつもない無知というものである。(織田)信長も都の地で,与と同様のことをなしたが、そのため彼は神や仏から罰せられなかったばかりか、彼の事業はいよいよ繁栄したのである。そのような理由から,予は仏僧たちに、世帯を持つか、それとも兵士となって出陣するかを勧めたのであり、仏僧たちが親族の有力者とか友人の嘆願によって、嫡子である予の諒承を得た場合でも、彼らは自費でもって身代わりとなって戦場に赴く者を差し出さねばならぬ」と。
城中では往昔から、年に何回か偶像に奉献される盛大な儀式が催され、その際、仏僧たちは種々の経典を読誦し、部屋の内外や場内の広場には、御守袋とか教条がしたためられた紙が貼りつけられることになっていたが、嫡子はそれらいっさいの行事を禁じ、それらを除去するように命じた。
かつては学問、権威、身分によって非常に尊敬されていた仏僧たちは、今やまったく零落し、場内の馬小屋に群れをなして現われたり、有力者の邸へ、扶持や職務を哀願して参上している有様には目を見張らざるを得ない。
当年、二ヵ月にわたって、驚くべき光を放った一彗星が天空に現れた。後に仏僧たちは、この星の運勢は自分たち自身の上に落ちたのだと語っていたが、事実それは、彼ら、並びにその宗教や扶養財や寺院の破滅以外の何物も暗示するものではなかった。」
*1578年10月16日付、豊後臼杵発信、ルイス・フロイス(Luís Fróis)
16,17世紀イエズス会日本報告集 第Ⅲ期第5巻 92~93頁
大友宗麟の信仰告白
また日曜日の一般の説教の後、国主は通常誰も入らない部屋に修道士と共に入り、かつてないほど胸中を明かし、司祭に伝えさせるために長々と語った。
『予は生来、一度決めたことは変えぬ気質の人間であり、デウスの教えが司祭らによって日本に広まる当初から,予はその教えを好み,心中では善きものとして認めていたが、二つの理由のために予は幾年もの間、キリシタンとなることを見合わせた。
その第一は、適当な機会が訪れるのを望んでも、これは容易ならず、長い時間をかけて準備せねばならぬが、嫡子がすでに年齢に達し、諸国の政治を彼に譲り、より良く自省するための暇を得たことでようやくその機会が到来した。
第二は、日本の諸宗派の完全さ,奥義、学理がどの程度のものか見極めたく、諸派の方法は禅宗のそれ(と同じ)であり、これを悟れば、他の宗派についてもたちまち知り得ることが明白なので,予は多大な経費をかけてかの僧院(寿林寺)を建て、教えを請うべき学者らを都から招き多年にわたって瞑想を続けたが、禅宗の奥義を知れば知るほどますます底の浅いことを感じ,予の心は穏やかならず考えもいっそう混乱した。
そして予はデウスの根本の教えを相当に聴き、司祭(カブラル・Francisco Cabral)には予が日向に到着した後に洗礼を受けると伝えさせたが、今思うに、三、四ヵ月これを延期するのは好ましいことではなく、司祭は下(の地方)への道中にあるが、いくつかの特別な理由から、司祭の手により洗礼を受けたいので、一ヵ月後に(豊後へ)帰れるように用務を早めることを懇願する旨、」司祭に伝えられよ。それまで予は残りの祈祷を暗記するであろう。汝は予のため、日本語で発音しやすく、かつ、他の人たちがあまり用いない名前(洗礼名)を考えてもらいたい,というものであった。
*1578年10月16日付、豊後臼杵発信、ルイス・フロイス(Luís Fróis)
16,17世紀イエズス会日本報告集 第Ⅲ期第5巻 97~98頁
大友宗麟の洗礼
フランシスコ・カブラル(Francisco Cabral)師が下(近畿地方)への往復に一ヵ月以上要することなく当地に帰還すると、それから二日後、国主は彼に伝言を送り、帰還したことを非常に喜んでいること、および、(洗礼の)希望をもって待ち望んでいた故、さっそく翌日にも洗礼を授けるよう願う旨を伝えた。また、司祭が洗礼をいっそう盛大にするため府内から司祭と修道士を呼び寄せる考えであることを知ったので、彼は、かくも遠方より来るのは難儀であるから彼らを招かず、一般の人に対すると同じ方法で行ってもらいたいと伝えさせた。
彼(宗麟)の請願は申し分のないものであったので、時期を見てここ臼杵の小さな教会の聖堂のみ整えた。栄光の博士聖アウグスチヌスの(祝)日、彼は六、七名の青年武士の身を伴い,駕籠に乗って当修道院に来た。青年武士らは彼に奉仕する者たちで、すでにカテキズモ(教理)の説教をすべて聴いており国主と共に洗礼を受けるため随行してきた。(司祭が)長い説教をして、彼がこれまでの説教で聴いたことの要約を述べた後、彼は深い喜悦と謙虚をもって聖なる洗礼を受けた。司祭は従前の願いに従って彼にフランシスコの(教)名を授けた。
彼は己のいる場所に深甚の敬意を抱いていたので,聖堂の中に留まることを望まず、その外で紙と墨をもって受洗すべき者たちの名を自らの手で記し、ミサに列席した。これは彼にとって最初のミサであったが、この後、頻りに求められてふたたびミサを聴くため聖堂の一隅に身を置いた。当日、我らは彼を当所に招いたが、彼は賜った洗礼と歓待に深い満足を表し、後にはわざわざ人を遣わして謝意を伝えた。後に或るキリシタンが語ったところによると、国主は教会から私邸に戻ると、心は刷新され(以前と)異なる眼で物を見ているかのような思いに捕らわれ、また、駕籠の中から路上の多数の人を見た時、彼らは皆異教徒であり、キリシタンにならねば、やがて死して永久の罰に処せられることを思い、我らの主なるデウスより授かった多大の恩恵の中でわが身を省みるとき、涙を禁じ得なかった。と述べたそうである。
キリシタンになった大友宗麟の影響
大友宗麟の影響も、豊後における初期のキリシタン史においては非常に大きい。
1577年(天正5)12月、薩摩軍に追われた日向の国の伊東氏は宗麟の影響で庇護された豊後野津に於いて保護されて領地を賜り、宗麟の勧めでキリスト教を受け入れ、その中から天正遣欧少年使節の正使として伊東マンショが遣わされた。伊東家からもマンショの実弟勝左衛門、母、姉、従兄弟の義賢、祐勝、叔父伊東祐右がキリシタンとなった。
1587年(天正15)宗麟の嫡子・義統は黒田官兵衛如水孝髙の勧めで中津教会に於いて、ゴメス(Pedro Gómez)神父より洗礼を受けたが、秀吉の「伴天連追放令」に恐れて信仰につまずき、迫害者になり信者の尊い血を流した。朝鮮の役での敵前逃亡の罪で領土豊後を失い毛利輝元に預けられていた。
1600年(慶長5)関ヶ原の戦いの時、豊後を取り戻す戦いを起こし豊後石垣原(別府)の戦いで敗れて、黒田官兵衛如水孝髙の執り成しで命を助けられ、再度孝髙の勧めで信仰を取り戻し、キリシタンとしての模範的生活を送り、罪の償いのための祈りと苦行の生活を続け、コンスタンティーノ義統として信仰を全うして息を引き取った。
*結城了悟著『宣教師は異国で、なぜ大名やその子女を入信させることができたか』『細川ガラシャの総て』上総英郎編 新人物往来社
宗麟の影響で娘たちは他家に嫁いでも信仰を繋いでいった。久留米城主・毛利秀包(ひでかね)に嫁いだマセンシア孝子(宗麟の七女)は特に毛利家のキリシタンの中心となりその子孫にキリシタンが多くいる。
