
「くまのプーさん」(Winnie the Pooh)その2 第6話~10話
このノートは、Winnie the Poohの第6~10話を翻訳したものです。第1~第5話は以下のリンクにあります。Project Guntenberg eBookのルールに従い英文テキストと挿絵を使用しています。このノートの複写、転載はご遠慮ください。商業的な目的ではない朗読のほか引用等はできますがnote筆者に連絡をお願いします。
Winnie the Poohの解説を行ったノートは以下のリンクです
原作及び挿絵他は、以下のGutenberg eBookを使っています。
第6話
イーヨーが誕生日にプレゼントを2つもらう話
はじめに
陰気で面倒くさい性格のイーヨーがよく描写されており、その名言が光るお話となっています。"Good morning. If it is a good morning. Which I doubt" (おはよう、本当に早いのならね、それは疑わしいが。)はその中でも有名な台詞であり、今でも比喩的に使われます。以下のWashington Postの記事では、英国銀行総裁が記者に対して暗い経済情勢を説明する際に、この台詞を使う機会を逃したと論評しています。
本当は誕生日を祝ってほしいが、それを素直に言えないイーヨー。イーヨーを喜ばせようと、それぞれプレゼントを運ぼうとするピグレットとプー。しかし、思ったものとはならなかった(みじめな)プレゼントを喜ぶ姿には、人格者としてのイーヨーの魅力が秘められています。途中に登場するプーが作った詩は、韻をふんだリズミカルなものとなっているため、七五調で訳してみました。
本編
灰色の年老いたロバ、イーヨーは、小川のそばに佇(たたず)み、水面(みなも)に映る自分を見ていました。
「悲しいかな」と彼は言いました。「こういうものなのだ。悲しいかな」
彼は振り返り、小川を下流に向かってゆっくりと20ヤード(18メートル)ほど歩き、しぶきをあげて川を横切り、反対側をゆっくりと戻ってきました。そして、再び、水面に映る自分を眺めました。
「思ったとおりだ」と彼は言いました。「向こう側から見てもさして変わらない。だけど、誰も気にしない。どうでもいいんだ。悲しいかな。そういうものなのだ。」
彼の後ろのシダの茂みでパチパチいう音がして、プーがでてきました。
「おはよう、いい朝だね、イーヨー」と、プーが言いました。
「いい朝だね、くまのプー」と、イーヨーが陰気に言いました。「もしも、良い天気の朝ならばね」と言ってから「それは疑わしいが」と言いました。
「いったい、どうしたの?」(**)
「なんでもない、くまのプーよ、なんでもないんだ。何でもできるわけじゃないし、やらないやつもおる。それだけのことだ」
「いったい、なんのことかなぁ?」と、鼻をかきながらプーは言いました。
「陽気になれ。歌って踊れ。桑の実のなる茂みを回って。」
「あぁ」とプーが言いました。彼は、長いこと考えて、それから聞きました「ところで、桑の実のなる茂みでなーに?」
「良いダチってとこかな」イーヨーは陰鬱に続けました「フランス語のよいダチって意味さ」と彼は説明しました。「文句を言っているんじゃないさ、だけど、そういうことなのさ。」

(*) 「おはよう」は「Good Morning」で文字通りでは「よい朝=天気の良い朝」の意味となります。しかし、「おはよう」は天気にかかわらず使う挨拶であると同様に「Good Morning」も天気にかかわらず使います。なので、「おはよう。天気の良い朝かは疑わしいが」というひねくれた会話となっています。

プーは大きな石の上に座って、なんのことか考えようとしました。彼にとってとても謎めいて聞こえたのです。とっても小さな脳みそのクマにとって謎解きは苦手でした。なので、かわりに、カトルストン・パイ(*)の歌を歌いました。
カトルストン、カトルストンパイ、カトルストン、
ハエは鳥には なれないさ。でもね鳥なら 飛べるんだ。
答えるからさ 謎かけて:
「カトルストン、カトルストンパイ、カトルストン」
これが一番目の歌詞でした。ここまで終えたところで、イーヨーはこれが嫌いだとは言いませんでした。なので、プーはご親切なことに第二番の歌詞を歌いました。
カトルストン、カトルストンパイ、カトルストン、
口笛できない、お魚は。そうさ自分も できないさ。
答えるからさ 謎かけて:
「カトルストン、カトルストンパイ、カトルストン」

イーヨーは、相変わらず何も言いませんでした。なので、プーは静かに三番目の歌詞を口ずさみました。
カトルストン、カトルストンパイ、カトルストン
なぜ鶏(にわとり)か? 知らないさ。
答えるからさ 謎かけて
「カトルストン、カトルストンパイ、カトルストン」
「そのとおり」とイーヨーが言いました。「歌え。アンティーティディ―、アンティーツーってね。ナッツとコーンを集めに行こうや(*)。皆んな、楽しくなと」
「楽しんでますよ」とプーは言いました。
「楽しめるものもいるさ」とイーヨーが言いました。
「なぜ?なにか問題があるの?」
「なにか問題かい?」
「イーヨー、あなたはとても悲しそうに見えるけど」
「悲しい?どうして悲しくなきゃいけないんだい?今日は自分の誕生日なんだ。一年で一番楽しい日さ」
「誕生日なんですって?」プーはびっくり仰天して言いました。
「もちろん、そうだよ。見えないかい?これまでにもらったこれだけのプレゼントを見てごらん」と足を片側から反対側へと振りました。「誕生日ケーキを見てごらん。ろうそくとピンク色の砂糖飾りを。」
プーは、最初に右側をみて次に左側を見ました。
「プレゼント?」とプーは言いました。「誕生日ケーキ?」とプーは言いました。「どこにですか?」
「見えないのかい?」
「見えませんけど」とプーは言いました。
「自分もさ」とイーヨーが言いました。「冗談さ」と彼は言いました「ハ、ハ!」
プーは、ちょっと謎をかけられて、頭をかきました。
「だけど、本当に誕生日なんですか?」と尋ねました。
「そうだよ」
「あぁ、そうなんだ。じゃあ、良いことが沢山ありますように、イーヨー」
「くまのプー、君にも良いことがたくさんあるようにな」
「だけど、今日は、僕の誕生日ではないけれど」
「今日は、私の誕生日だよ」
「だけど、僕に、「良いことがたくさんあるように」って言ったでしょう」
「あぁ、もちろんさ。自分の誕生日のときに惨めな気持ちにはなりたくないだろう?」
「あぁ、そういうことか」とプーは言いました。
「もう十分に悪い」と、ほとんど泣き崩れんばかりにイーヨーは言いました。「惨めだ。プレゼントもケーキもろうそくもなくって、誰も気が付いてくれないし。そして、もし、他のだれもが同じように惨めになるというなら・・」
プーにとってこれは余りに余ることでした。
「そこにいてください!」とイーヨーに言って、彼は向きを変えできるだけ限り急いで家に帰りました。なぜなら、気の毒なイーヨーのために何かとりあえずのプレゼントをすぐに探さなければと思ったからです。そして、そのあとで、適当なものを考えればよいからです。

家の外で、ドアの前で呼び鈴(*)に触ろうと飛び跳ねていたピグレットを見つけました。
「ピグレット、こんにちは」と彼は言いました。
「こんにちは、プー」とピグレットが言いました。
「いったいなにしてるの」
「呼び鈴に触ろうとしていたんだよ」とピグレットが言いました。「ちょうどこの辺りに来たんだよ・・・」
「じゃあ、手伝ってあげるよ」とプーは親切に言いました。そして、彼は近づいてドアを呼び鈴を鳴らしました。「ちょうどイーヨーを見たところだったんだ」とプーは話し始めました。「かわいそうなイーヨーはとても悲しんでたんだ。だって、今日は、彼の誕生日なのに、だれも気がづかないし、彼はとっても陰気だしーーよく知ってるよねぇ、イーヨーのことはーーそれで、彼はそんな感じで居てーーいったい誰が住んでいるのか知らないけどなかなか出てこないねぇ」と彼は、もう一度、呼び鈴を鳴らしました。
「だって、プー」とピグレットは言いました。「これは君の家じゃないか!」
「あぁ」とプーが言いました。「そうだった」、「じゃあ中に入ろう。」と言いました。
そして、彼らは家に入りました。プーは、最初に食器棚へ行ってハチミツの入ったとてもちいさな壺があるかを見て、あることが分かったので、それを持って下ろしました。

「これをイーヨーにあげようと思うんだ」と彼は言って、「プレゼントとしてね。君は何をあげるかい?」と聞きました。
「同じものじゃだめかな?」「つまりぼくたち二人からってことで?」とピグレットは言いました。
「だめだよ」とプーが言いました。「それは良いとは思わないな」
「わかった。それなら、僕は風船をあげるよ。パーティーでもらったのがっ一つ残っているんだ。それを取りにいこうと思うけどどうかな?」
「それだよ、ピグレット、とてもよいアイデアだ。それこそ、イーヨーが元気になるために欲しがるものだよ。風船で元気にならない者なんていないさ」
それで、ピグレットは小走りして去りました。プーはハチミツの壺をもって反対方向に行きました。

その日は暖かく、彼は、長い道のりを歩かねばなりませんでした。半分もいかないうちに、なにか不思議な感覚が彼の体中から気味悪く湧いてきたのです。それは、彼の鼻先に始まって体中に流れわたり足の裏から出てきました。それは、あたかも、体の中にいるだれかが「さぁ、プー、おやつの時間だよ」と言うようでした。
「おや、なんてことだ」とプーが言いました。「こんなに時間がたっていたなんて」そして、彼は座ってハチミツの壺の蓋を開けました。「運よくこれを持ってきてたじゃないか」と彼は思いました。「このような暖かい日に外出するクマはたくさんいるだろうけれども、このようなちょっとした食べものを持ってくることなんか 思いもつかないものさ」そうして、彼は食べ始めました。
「さてと」と彼は、壺の中を最後にひと舐めして思いました。
「どこへ行くんだったっけ?あぁ、そうだ、イーヨーのところだ」彼はゆっくりと起き上がりました。
そして、突然、思い出しました。かれはイーヨーにあげる誕生日のプレゼントを食べてしまったのです!
「あれま!」とプーは言いました。「どうしよう。彼に何かをあげなくちゃ」

少しの間、彼は、何も考えることができませんでした。それから、彼は考えました。「そうだ、これはとてもよい壺だから、ハチミツが入ってなくっても、きれいに洗っておきさえすれば、そして、「誕生日おめでとう」と誰かに書いてもらえば、イーヨーはこの壺にものを入れることができて、それは便利かもしれない。」それで、彼は、ちょうど百エーカーの森を通り過ぎようとしたとき、そこに住んでいるフクロウを訪ねようと森に入りました。
「おはよう、フクロウさん」と彼は言いました。
「おはよう、プー」とフクロウはいいました。
「イーヨーの誕生日のお祝いになんだけど」とプーが言いました。
「ほお、それがそうなのかい?」
「あなたなら何をあげますか?フクロウさん」
「君なら何をあげるかね?プー」
「ぼくは、ものをいれるのに便利な壺をあげるつもりで、それであなたにお願いしたくて来ましたーー」
「それかい?」と、プーの手から壺を取ってフクロウが言いました。
「そうです。それでお願いしたかったのはーー」
「だれかがここにハチミツをいれておいたのだな」とフクロウが言いました。
「なんでも入れることができます」とプーが真顔でいいました。「それはとても便利な壺なんです。それで、お願したいのですがーーー」
「おもてに「お誕生日おめでとう」と書かねばならないね」
「それだからお願いに来たんです」とプーが言いました。「なぜなら、自分が書くとグラグラになっちゃうからなんです。つづりは良いんだけどグラグラなんで、文字が間違ったところに入っちゃうんです。すみませんが、「お誕生日おめでとう」と書いてもらえませんか?」
「いい壺だね」とフクロウがそれを見まわしながら言いました。「これを私からもあげることができないかな。つまり、二人からと言うことでは?」
「だめです」とプーが言いました。「それは良くはありません。まず、きれいに洗いますから、それから、書いていただけますか?」
彼は、壺をきれいに洗って乾かしました。そして、フクロウは、鉛筆の先をなめながら、「誕生日」をどう書けばよいのかと思案していました。
「プー、読めるかい?」彼は、少し不安げに聞きました。「ドアの外にノックと呼び鈴についての張り紙があるだろう、クリストファー・ロビンが書いてくれた。それを読めるかい?」
「クリストファー・ロビンは何が書いてあるか言ってくれたから、できると思います。」
「では、私がなんと書いてあるかを言うからね。そうすればきみもできるだろう」
そして、フクロウは書きーーそしてそれはこんな感じでした。

HIPY PAPY BTHUTHDTH THUTHDA BTHUTHDY.
ハッ、ハッピィ、バッバースス、ススディ、バスディ
プーは感心して見つめました。
「「誕生日おめでとう」と言てるのだよ」とフクロウはなにげなく言いました。
「素敵な長めの言い方ですね」とプーは、とても感激して言いました。
「実は、もちろん、「プーから愛をこめてとってもよいお誕生日を」と言ってるのだ。とうぜん、このように長いことを書こうとすれば鉛筆もたくさん使うのだ」
「あぁ、そうですね」とプーが言いました。
こんな出来事があったころ、ピグレットはイーヨーにあげる風船を取りに家に戻りました。彼は、それが飛んでいかないようにきつく抱きしめました。そして、プーが到着する前にイーヨーのところに行こうとできるだけ早く走っていきました。それは、誰かに言われたからではなくって、まるで、自分が思いついたかのように、イーヨーに最初にプレゼントをあげる人となりたかったからです。そして走りながら、イーヨーがどれほど喜ぶだろうと考えていたので、どこに向かっているかに気が付かず・・そして、突然、彼はウサギの穴に足を突っ込み、そこに前のめりに倒れてしまったのです。
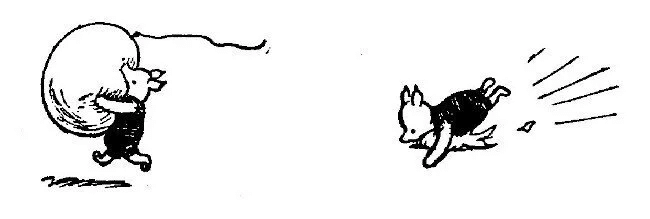
バーン!!!???***!!!
ピグレットは、何が起こったのだろうと不思議に思いながらそこに横たわりました。最初、彼は、世界全体が吹き飛んだんじゃないかと思いました。それから、多分、森の一部だけが吹き飛んだんだと思いました。それから、多分、彼だけがと思いました。そして、彼は、月かどっかに一人残されて、クリストファー・ロビンや、プーやイーヨーには二度と会えないのだろうと思いました。そして、「うん、もしも月に居たとしたら、自分はずっと顔を下に向けている必要はないや」と思いました。そして注意深く起き上がってあたりを見回しました。
でも、彼は、ずっと森に居たのです!
「ウーン、これはおかしいな」と彼は思いました。「いったい何が破裂したんだろう。自分が倒れるくらいじゃあんなに大きな音にはならないし。そして、風船はどこに言ったんだろう?そして、この小さな湿ったぼろきれはいったいなんだろう?」
それは、風船だったのです!
「あれまあ」とピグレットは言いました。「あれまあ。あれあれ。あれまあ。もうしょうがない。もう帰ることはできないし、別の風船は持っていない。そして、イーヨーは風船はあんまり好きじゃないかもしれないし」
それで、彼は、悲しげに小走りを続けて、イーヨーがいる側の小川まできて、彼に大声で声を掛けました。
「おはよう、いい朝だね、イーヨー。」とピグレットが大声で言いました。
「おはよう、ピグレットちゃん」とイーヨーは言いました。「もしもよい朝ならね」と言いました。「それは疑わしいけども」と言って「どうでもよいことだが」と続けました。
「今日はよいことがたくさんありますように」とピグレットは言って近寄りました。
イーヨーは小川の中に映る彼を見るのをやめて、ピグレットの方に向いて見つめました。
「もう一度言ってごらん」彼は言いました。
「たくさんのよいーー」
「ちょとまて」
三本の足でバランスを取りながら、かれは、もう一本の足を注意深く耳に寄せようとしました。「きのうこうしたんだ」と、三度ほど転んだ時に彼は言いました。「簡単なことなんだ。聞くことができる限り・・ほら、できた。君はなんと言ったんだい?」彼は、蹄で耳を前の方に押しました。

「今日は良いことがたくさんありますように。」と、ピグレットがもう一度言いました。
「私へかい?」
「もちろんですよ、イーヨー。」
「私の誕生日?」
「もちろん」
「本当の誕生日を迎えるってことかい。」
「そうですよ。イーヨー、そしてプレゼントを持ってきましたよ。」
イーヨーは右耳から右側の蹄を下ろして、反対側を向いて、とても苦労しながら左の蹄を耳に置きました。
「これをもう一方の耳に置かなきゃならんのだが」と彼は言って、「ところで」
「プレゼントです」とピグレットが大声で言いました。
「私へだっていうのかい。」
「そうです」
「まだ、私の誕生日のことかい。」
「もちろんですよ。イーヨー。」
「私が本当の誕生日を迎えるって?」
「そうですよ、イーヨー。だから、風船を持ってきました。」

「風船?」とイーヨーは言いました。「風船と言ったね?あの膨らませる大きくて色の付いたものかい?楽しく、歌って踊れや、さあここだ、さああそこだ?」
「はいそうです、だけど、大変申し訳ないんだけども、持ってこようと走っていた時に転んでしまっんです。」
「おやおや、それは不運だったねぇ!君は速く走りすぎたんだろう、多分。怪我はしなかったかね、ピグレットちゃん?」
「大丈夫、だっ、だけど、イーヨー、僕は風船を割っちゃったんです!」
そして長い沈黙が続きました。
「私の風船を?」とイーヨーがようやく言いました。
ピグレットがうなづきました。
「私の誕生日祝いの風船を?」
「そうです、イーヨー」とちょっと鼻をすすりながらピグレットが言いました。「これなんです。お誕生日に、よっ、良いことがたくさんありますように。」そして、彼はイーヨーに小さな湿ったぼろきれのような風船をあげたのでした。
「これがそうなのかい?」とイーヨーがちょっと驚いて言いました。
ピグレットがうなづきました。
「私へのプレゼント?」
ピグレットが再びうなづきました。
「風船?」
「ええ。」
「ピグレット、ありがとう、」とイーヨーは言いました。「聞いてもよいかな?」と言って彼は続けて「ところで、この風船はーーその風船だったとき、何色だったのかい?」
「赤です。」
「多分・・・赤じゃないかと思ったんだ」、とイーヨーはもごもごと言いました。「自分の好きな色だ・・・どのくらい大きかったのかな?」
「ぼくと同じくらい。」
「そうじゃないかなと思ってた。君と同じくらいのと、」彼は悲しそうに独り言を言って「自分の好きな大きさだ、ふむ、ふむ。」
ピグレットは惨めな気持ちになり、なんと言ってよいのかわかりませんでした。彼は何か言おうと口を開けたままでしたが、川の反対側から叫び声がしてプーが来たと分かったとき、何かを言っても良いことにはならないだろうと判断しました。
「今日は良いことがたくさんありますように、」とそのことはもう言っていたことを忘れてプーは言いました。
「プーよ、ありがとう。いいものを持ってるところだよ。」とイーヨーが陰気にに言いました。
「あなたにプレゼントを持ってきました」、とプーは興奮していいました。
「プレゼントはもうあるよ」、とイーヨーが言いました。
プーは、イーヨーに向かって小川の中をしぶきを上げながら渡ってくるところでした。そして、ピグレットは少し離れて座っていて、手で頭を抱え、鼻をすすっていました。
「便利な壺なんですよ」、とプーは言いました。「はい、これです。そして、「プーから愛をこめてとってもよい誕生日プレゼントを」と書いてあります。それが全部書いてあるんです。壺にはものを入れることができますよ。ほら!」
イーヨーは壺を見ると、とても興奮しました。
「なぜなら!」と彼は言いました。「この中にちょうど風船が入るだろうと思うのだ!」
「おや、それはちょっと、イーヨー」、とプーは言いました。「風船は壺の中に入れるには大きすぎるんじゃないかな。風船は、抱えてもってーー」
「自分のはちがうのさ」、とイーヨーは自慢げに言いました。「ピグレットを見てごらん!」そして、ピグレットが申し訳なさそうにあたりを見回したとき、イーヨーは、風船を歯でくわえて壺の中に注意深く入れたのでした。そして、取り出して地面において、それから、もう一度拾い上げて、注意深くもとに戻したのでした。
「そうですね!」とプーは言いました。「うまく入りますね。」
「そうですね!」とピグレットは言いました。「うまく取り出せますね。」
「そうだろう?」とイーヨーは言いました。「中に入れるのも出すのもうまくいく」
「とても嬉しいです」、とプーは幸せそうに言いました。「あなたに、何かを入れることのできる役に立つ壺をあげようと考えつくことができて。」
「とても嬉しいです」、とピグレットは幸せそうに言いました。「あなたが役に立つ壺にいれる何かをあげることを考え付くことができて。」
しかし、イーヨーは聞いていませんでした。彼は、風船を取り出し、また、戻し、それで最大限幸福だったのです・・

「そして、ぼくはなにもあげなかったかな?」とクリストファー・ロビンが悲しそうに言いました。
「もちろんあげたさ」と、私は言いました。「きみは、ほら、覚えていないかい--かわいらしい、かわいらしいーー」
「僕は彼に絵を描くための絵の具が入った箱をあげたよ」
「そうだよ。」
「どうして、僕は朝のうちにあげなかったんだろう?」
「君は、パーティがうまくいくように準備に忙しかったからね。彼には、てっぺんがアイシングされていて、ろうそく3本と、ピンク色の砂糖で彼の名前が書かれたケーキがあったから。そしてーー」
「そうだ思い出したよ」とクリスオファー・ロビンが言いました。
(おしまい)
第七話
カンガと子供のルーが森にやってきて、ピグレットが風呂に入る話
だれもがどこから彼らが来たのかは知らないようでしたが、彼らは、森の中にいたのです。それは、カンガとその子供のルーでした。プーがクリストファー・ロビンに「あの二匹はどうやってここに来たの」と聞くと、クリストファー・ロビンは「いつものようにさ、何をいってるかわかるならね、プー」と言いました。それで、プーは、実はわかりませんでしたが「あぁ!」と言いした。そして、頭を二度ほど下げてうなずき「あぁ、いつものようにか」と言いました。そして、そのことをピグレットがどう思ってるのかと思い会いに行きました。そして、ピグレットの家で彼はウサギを見つけました。なので、皆でその話をしました。

「この話でいいと思わないのはね」とウサギが言いました。「ほれ、ここに、君、プー、君、ピグレットと僕がいてーーそして突然ーー」
「イーヨーも居るよ」とプーが言いました。
「そう、イーヨーもーーそして突然ーー」
「フクロウも居るよ」とプーが言いました。
「そう、フクロウもーーそして突然ーー」
「あぁ、そしてイーヨーも」とプーが言いました「彼のこと忘れてた。」
「ここにはね、我々がーー」とウサギがゆっくりと注意深く言いました。「我々ーーみんながーー、そして、朝起きてみると、突然、何をみつけたと思う?なんか不思議な動物を見つけたわけだ。いままで聞いたことがないような!家族をお腹のポケットにいれて運ぶ動物を!もしも、自分が家族を自分のポケットに入れて連れて行くとしたらい、いったいいくつのポケットが必要となることやら?」
「16個じゃない」とピグレットが言いました。
「17個じゃないかな?」とウサギが言いました。「そして、ハンカチを入れるためにもう一つーーなので18個。上着に18個ものポケット!そんなことやってられないよ」
皆、黙って長い間考えて・・そして、何分間かの間ずっと顔をしかめていたプーが「自分なら15個だな」と言いました。
「えっ?」とウサギが言いました。
「15」
「15のなんだって?」
「君の家族さ」
「彼らはどうなんだろうね?」
プーは鼻をこすり、ウサギが彼の家族の話をしているのだと思ったと言いました。
「そうだっけ?」とウサギがそっけなく言いました。
「そうだよ、その話をしてたーー」
「きにするなよ、プー」とピグレットが我慢できずに言いました。
「問題はだね、カンガについて皆でどうしようかだ?」
「あぁ、そうだった」とプーが言いました。
「一番いいのは」とウサギが言いました。「一番いいのは、赤ん坊のルーを盗んで隠してしまうことではないかな。そして、カンガが「私のあかちゃんのルーはどこに行ったの」と言ったら、我々は「ほぉ」って言うんだ」
「ほぉ!」とプーが試して言いました。「ほぉ!ほぉ!・・もちろん」、そして、続けて、「赤ん坊のルーを盗まなくっても「ほぉ!」と言えるね」と言いました。
「プー」とラビットは親切に言いました「君は脳みそがないんだねぇ」
「そうだけど」とプーはペコペコして言いました。
「みんなで「ほぉ!」っていうのは、カンガが我々が赤ん坊のルーの居場所を知っていることがわかっているからだよ。「ほぉ!」は、もしも、カンガが森を去って2度と帰ってこないと約束するならば赤ん坊のルーの居場所を教えてあげるよ、って意味なんだ。考えてるときに話しかけないでくれるかな」
プーは角のほうに行って「ほぉ!」と言うのを小さな声で練習しました。
あるときは、ウサギの言う通りかもしれないし、ある時はそうではないと思えました。「ちょっと練習だね」そして、「カンガはこのことを理解しようとして練習するんじゃないかな」と思いました。
「一つ言えることは」とピグレットがちょっとそわそわしながら言いました。「クリストファー・ロビンと話をしていたんだけど、カンガは一般にどう猛なたぐいの動物とみなされてるんだって。僕はいつもの感じならどう猛な動物には驚かないけども、もしもどう猛な動物がその子供を奪われるとどう猛な動物2匹分になるってことはよく知られてるよね。だとすると、「ほぉ!」って言うのは多分ばかげたやり方かもね」
「ピグレット」とウサギは鉛筆を取り出してその先をなめながら言いました。「君は勇気ってものがないんだね」
「勇ましくなるのって難しいさ」とピグレットは少し鼻をすすりながら言いました。「とってもちいさな動物にとってはね」

ウサギは忙しく書き物を始め、見上げて言いました。
「君はとても小さな動物だから、我々がこれから冒険する際にとても役にたてるだろう」
ピグレットは、役に立つと言われてとても嬉しかったので、怖がったことをすっかり忘れてしまいました。そして、ウサギがカンガは冬の間で唯一のどう猛な動物で、他の季節は優しいたちであると言うと、もうじっとしていられずもう一度役に立ちたいと思ったのでした。
「自分はどうなの」とプーは悲しげに言いました。「たぶん、自分は役に立てないということだね?」
「気にしなくていいさ、プー」とピグレットがなだめるように言いました。「また、別の機会があるさ」
「プーがいなくては」と、鉛筆を削りながらウサギが厳かに言いました。「冒険はできないさ」
「そうか!」とピグレットは、がっかりしたそぶりを見せないように言いました。しかし、プーは部屋の角に行って誇らしげに独り言を言いました。「自分がいないとできないんだ!自分はそういうクマなんだ。」
「みな、聞いてくれないか」とウサギが書くのを終えて言いました。そして、プーとピグレットは座り、口を開けて一生懸命聞き入りました。これが、ウサギが読み上げたことです。
赤ん坊のルーを捕まえる計画
一般的な所見:カンガは、ここにいる誰よりも、なんと、自分よりも速く走る。
より一般的な所見:カンガは、自分の赤ん坊のルーから目を離すことはない。ただし、ルーが彼女のお腹のポケットの中の安全ボタンをかけているときを除く。
なので、もしも赤ん坊のルーを捕まえようとするなら、我々はカンガよりもずっと前に居なければならない。なぜなら、カンガは、ここにいる誰よりも、なんと自分よりも速く走るから(1.を参照)
考えるに、もしもルーがカンガのポケットから飛び出してピグレットが代わりに飛び込めば、カンガはその違いが判らないだろう。なぜなら、ピグレットはとても小さな動物だから。
ルーと同じくらい。
しかし、カンガは、ピグレットが入ってくるのを見ないように、先に反対側を見ていなければならない。
2.を参照
もう一つ考えるに、もしもプーが彼女に面白い話をしていれば、彼女は反対側を見ているかもしれない。
そして、自分はルーを連れて走って逃げるとができる。
急いで。
そして、カンガは後になって違うことに気づくこととなる。

ふむ、とウサギがこれを誇らしげに読み終えました。しばらくの間誰も何もい言いませんでした。それから、音もたてずに口を開け閉めしていたピグレットが、とてもハスキーな声でなんとか言いました:
「で、ーーそれで?」
「カンガがついに違うことに気がついたときは?」
「そのときは、皆で「ほぉ!」っていうんだ」
「それは、ぼくたち3人で?」
「そうさ」
「えっ」
「なにが問題なんだい、ピグレット」
「なにも」とピグレットが言いました。「ぼくたち3人が一緒に言う限りは。ぼくたち三人がそう言う限りは気にはしないさ。」とピグレットが言いました。「じぶんは構わないけど」と彼は言い、「だけど、自分は「ほぉ」とは言わないな。あまりよくは聞こえないと思うんだけど、どうかな。」と彼は言い、「冬の期間についてのこと本当に確かなのかい?」
「冬の期間?」
「そう、冬の期間だけどう猛だったよね」
「あぁ、そうだ、そうだ。その通り。だよね、プー?何をしたらよいかわかるかい?」
「いいや」とくまのプーが言いました。「いや、まだわからない」と彼は言いました。「何をしたらよいのかな?」
「きみは、カンガが他のものに気付かないように一生懸命話せばよいんだ」
「なにについて話せばいいの?」
「なんでも好きなこと」
「カンガになにかちょっとした詩のようなものを話せと言うこと?」
「そのとおり」とウサギが言いました。「素晴らしい。さあ、やろうじゃないか」
それで、彼らはカンガを探しに出かけました。
カンガとルーは森の中の砂地となっているところで静かな午後を過ごしていました。赤ん坊のルーは、砂のなかでちょっと飛び跳ねる練習をしていました。そして、ネズミの穴に落ちてそこから這い上がっていました。そして、カンガはそわそわしながら言いました。「ジャンプはあと一回だけにしようね。そして家に帰りましょう」そして、そのとき、ほかならぬプーが丘をのしのしと登ってきました。

「こんにちは、カンガ」
「こんにちは、プー」
「ぼくの跳ねているとこ見て」とルーはキイキイ声で行って、べつのネズミの穴に落ちました。
「ハロー、ルー、かわいいおともだち!」
「ちょうど家に帰ろうとしていたの」とカンガは言いました。「こんにちは、ウサギさん、こんにちは、ピグレット」
ウサギとピグレットは、丘の別の方からのぼぼって来ていたのでした。そして、「こんにちは」「ハロー、ルー」と言い、ルーは自分がジャンプするのを見てほしいとお願いしたので、彼らはそれを見ていました。
そして、カンガも一緒に見ていました。
「ねぇ、カンガ」と、ウサギが2回ウィンクした後にプーは言いました。「あなたは詩に関心あるかなぁ?」
「まったくないわ」
「あぁ!」とプーは言いました。
「ルーちゃん、ジャンプはあと一回にしておうちに帰りましょう」
ルーがもう一つのネズミの穴に落ちてる間、ちょっとだけ静けさがありました。
「続けて」と、前足で顔を隠してウサギが大きな声で呟きました。
「詩について言うと」とプーが言いました。「ここに来るときに、ちょっと作ったんです。こんな感じで。あー、えっとぉーー」
「素敵ね!」とカンガは言って、「さあ、ルーーー」
「きっとこの詩を気にいると思いますよ」とウサギが言いました。
「気に入りますよ」とピグレットが言いました。
「とても注意深く聞かなきゃいけませんね」とウサギが言いました。
「一つも漏らさないように」とピグレットが言いました。
「えぇ、そうね」とカンガが言いましたが、相変わらず赤ん坊のルーを見ていました。
「どう言う感じなんだい、プー?」とウサギが言いました。
プーはちょっと咳払いをして始めました。
とても脳みそが小さいくまがつくった詩
月曜日、暑くお日様 照らすなか
考えるもの 多いかな
真実なのか 否なのか
なにがどれだか どれがなにだか?
火曜日は、雹(ひょう)と雪とが 降る中で
深く深ぁく 思い深める 我が身かな
どこのだあれも 知り得ない
それがこれらか これがそれらか
水曜日、空は青く 晴れ渡り
なにもすること なかりけり
ときおり思うは これ真実(まこと)?
だれがなにやら なにがだれやら
木曜日、凍てつく寒さ 始まって
木々には白い 霜が付き
いかほどにまで 備えられん
それは誰かの 誰のだそれは
金曜日、ーーー
「そう、そうよね」と金曜日に何が起きたか最後まで聞かずにカンガが言いました。
「ジャンプはあと一回だけよ。ルーちゃん、そして、本当に帰りますよ!」

ウサギはプーに急げと肘(ひじ)をつきました。
「詩の話ですけど」とプーは静かに言いました「向こうの木に気がつきました?」
「どこ?」とカンガ―が言いました。「ほら、ルーーー」
「ちょうどあそこです」とプーが、カンガの後ろを指して言いました。
「だめ」とカンガがいいました。「さあ、ジャンプしてお腹に戻ってルー。そして家に帰るから」
「あそこにある木をみなければなりませんよ」とウサギが言いました。「ルー、抱っこしてあげようか?」そして、ルーを前足で拾い上げました。
「ここから鳥が見えますね」とプーが言いました。「それとも魚かな?」
「ここから鳥を見なければ」とウサギがいいました。「でないと、あれは魚に」
「あれは魚じゃない。あれは鳥だよ」とピグレットは言いました。
「ならば」とウサギが言いました。
「あれは、ムクドリかクロウタドリだね」とプーが言いました。
「それがすべての問題ですね」とウサギが言いました。「それが、クロウタドリかムクドリか?」
そして、ついにカンガが頭の向きを変えました。そして、彼女の頭が回ったその瞬間、ラビットは大きな声で「中に入りなさい、ルー」と言い、ピグレットがカンガのピケットの中に跳びこみ、ウサギがルーを前足に抱えてできる限りの速さで逃げるようにそこを離れました。
「なぜ、どこにウサギが行ったの?」とカンガが振り返って言いました。「ルーちゃん、大丈夫?」
ピグレットは、カンガのポケットの底からルーをまねてキーキー声を出しました。
「ウサギは行かなければならないことがあったんです」とプーは言いました。「たぶん、急に、見に行かなきゃならないことを思いだしたんだと思います」
「で、ピグレットは?」
「ピグレットも、同じとき、そんなこと考えたんだと思います。急に」

「そう、私たち家に帰らなくっちゃ」とカンガは言いました。「さようなら、プー」そして、大きなジャンプを3つほどして去っていきました。
プーは彼女の行くあとを見ていました。
「ぼくも、あんなふうにジャンプできるといいな」と彼は思いました。「できるのもいれば、できないものもいる。そんなもんだね」
しかし、ピグレットはカンガができないでいてほしいと思うときがありました。しばしば、ピグレットは、森を通って長い道のりを家に向かうとき、鳥だったらよかったなと思うのでした。でも、今は、カンガのお腹のポケットの底で、がくがくしながら思うのでした。
「こ こんなこと なら とぶ
かんがえ ないよ」
そして、空に舞ったとき、彼は、「おぉぉぉぉー」と言い、落ちるときには「いたぃっ!」と言い、彼はカンガが家に着くまで「おぉぉぉぉーいたぃっ、おぉぉぉぉーいたぃっ、おぉぉぉぉーいたぃっ”と言い続けてたのでした。
もちろんん、カンガがお腹のポケットのボタンをはずすや否や彼女は何がおこったか知りました。初めはちょっとびっくりしたように思いまいたが、それからそうではないことを知りました。なぜなら、クリストファー・ロビンはルーに危害を加えることは絶対にないと確信してたからです。それで、彼女は、「もしもあいつらが私をからかおうとしたのなら、私もからかってやる」と独り言をいいました。

「さぁ、ルーちゃん」と彼女は、お腹のポケットからピグレットを取り出しました言いました。「お休みする時間よ」
「ほーお!」とピグレットは、恐ろしい道中のあとでできるかぎり言いました。でも、それは、あまりうまい「ほーお!」ではなく、カンガはそれがどういう意味かを理解する様子はありませんでした。
「まず、お風呂ね」とカンガは陽気に言いました。
「ほーお!」とピグレットは、他の二人がいないかあたりを心配そうに見まわしながらもう一度言いました。しかし、ほかの二人はそこには居ませんでした。ウサギは彼の家で赤ん坊のルーと遊んでいて、どんどんとルーのことがかわいくなっていました。そして、カンガのようになろうと考えていたプーは、ジャンプの練習をしながら、森の丘の砂地にとどまっていました。

「どうしたらよいかしら」とカンガは思慮深く言いました。「今晩は、冷たい風呂に入るのはどうかしらね。そうれでどう?ルーちゃん」
ピグレットは、そもそもお風呂が好きではなかったので、長いことわなわなと震えて、それから、勇気を出して言いました。
「カンガ、はっきりといわないといけないようだね」
「どうしたの、ルーちゃん」と、水風呂の支度をしたカンガが言いました。
「ぼくは、ルーじゃない」と大声でピグレットが言いました。「ぼくはピグレットだ」
「そうよ、そのとおり」とカンガはなだめるように言いました。「そして、ピグレットの聲をまねしているわ。おりこうさんね」と、戸棚から大きめの黄色い石鹸を取り出して、彼女は続けました。「さて、次になにをするのかしら」
「みえないのかい」とピグレットが大声を出しました。「目の玉があるんでしょう。僕のことをみて!」
「あなたのことを見てるわよ、ルーちゃん」とカンガは厳しめに言いました。「そして、きのう私が言ったことを覚えてるわよね。お顔を作ること。もしも、ピグレットのようなお顔でい続けるなら、ピグレットのようになるわよーーそして、それはいやだなと思うことでしょう。さあ、お風呂の中で、もう一度この話をさせないようにね」
彼がどこにいるかを知る前に、ピグレットは湯船に入っていて、カンガは彼を大きな泡だらけのタオルでごしごしとこすっていました。

「いたぃ!」とピグレットは叫びました。「だしてよ!ぼくはピグレットだよ!」
「口を開けるんじゃないわ。石鹸が入るわよ」とカンガが言いました。「ほら、言ったでしょう?」
「だ、だって、ーーわざとやっているじゃないか」と早口で、言葉を言える範囲でピグレットが言いました。・・そして、石鹸だらけのタオルが口に入りました。
「ほら、おしゃべりしないで」とカンガが言いました。そして、ピグレットは風呂から取り出され、乾いたタオルでごしごしされていました。
「さぁ」とカンガが言いました。「お薬があるわ。そして寝なさい」
「おっお薬?」とピグレットが言いました。
「あなたが大きく強く育つためのものよ。いつまでもピグレットのように小さいままでは居たくないでしょう?」
そのとき、扉をノックする音がしました。
「いらっしゃい」とカンガが言うと、入ってきたのはクリストファー・ロビンでした。

「クリストファー・ロビン、クリストファー・ロビン!」とピグレットが叫びました。「カンガに僕だって言ってよ。カンガはぼくのことをルーだっていうんだ。ぼくはルーじゃないよね?」
「ルーにはなれないさ」と彼は言いました。「だって、ついさっき、ウサギの家でルーが遊んでいるのを見たから」
「ほう」とカンガは言いました。「驚いたわ!こんな間違いをするなんて」
「ほらね!」とピグレットが言いました。「いったじゃないですか、僕はピグレットだって」
クリストファー・ロビンは彼の頭をもう一度言いました。
「いや、君はピグレットじゃないよ」と彼は言いました。「僕はピグレットのことをよく知ってるよ。ピグレットはこんな色じゃない」
ピグレットは、これは、風呂に入れられたからでと言おうとして、で、言うのはやっぱりやめておこうと思い、そして何か言おうとしたとき、カンガは薬をスプーンで口の中に滑り込ませ、ピグレットの背中を叩いて、慣れれば本当はとても良い味だわと言いました。
「ピグレットじゃないって知ってたわ」とカンガが言いました。「そうであるはずないわよね」
「多分、プーの親戚じゃないかな」とクリストファー・ロビンが言いました。「姪かおじさんかなんかじゃないかな?」
カンガは多分そうだと同意して、なんか名前をつけて呼ばなくちゃと言いました。
「ぼくならプーテルと呼ぶけど」とクリストファー・ロビンが言いました。「ヘンリー・プーテルを略して」
そして、そう決めたとき、ヘンリー・プーテルは身をくねらせてカンガの腕からすり抜け地面に飛び降りました。とても嬉しかったのは、クリストファー・ロビンが戸を開けっぱなしにしていたことでした。ヘンリー・プーテル・ピグレットは、彼の家にたどり着く本当の直前まで、休むことなしにこれまでこんなに速く走ったことがないというほど速く走っていったのでした。しかし、100ヤード(90メートル)ほど離れたところで走るのをやめて、のこりは転がって帰りました。そうすれば、今までのようなお馴染みの彼の色に戻れるからでした。

そう言うわけで、カンガとルーは森に留まることとなりました。そして、ルーは、毎週火曜日は、とっておきの友達のウサギと過ごし、カンガは、毎週火曜日は、とっておきの友達のプーと過ごしてジャンプの仕方を教え、ピグレットは、毎週火曜日は、とっておきの友達のクリストファー・ロビンと過ごすのでした。そうすることで、みんなが幸せになったのです。
第8話
クリストファー・ロビンが隊長となって北極ティェケン(探検)をする
ある晴れた日、プーは、友達のクリストファー・ロビンがくまについて興味があるかどうかを知るために、森のてっぺんの方までとぼとぼ歩いていきました。その朝の朝食(ミツバチの巣の一つか二つにママレードを薄く塗った簡単なものでしたけど)をとっていたときに、急に歌を思いついたのです。こんな感じでした。
「歌おうよ、ホー!、くまの人生 楽しくね」
ここまで考えたところで、かれは頭をかいて、思ったのでした。
「これはとてもよい出だしだな。だけど、つぎはどうしようかな?」かれは「ホー」と歌うのを二・三回試しましたが、役には立ちませんでした。多分、「こうした方がよいかな、くまの人生のためにハーイと歌う方が」と思ったので、そのように歌いましたけど、・・・そうではなかったのです。「そうか、それなら、最初の行を二回歌えば、それも少し速く歌えば、三行目と四行目を考えることなく歌ってって、それでいい歌になるかもしれない。やってみよう。」
歌おうよ ホー、クマの人生 楽しくね!
歌おうよ ホー、クマの人生 楽しくね!
雨が降ろうが 雪だろが 気にはしないさ
なぜならね 蜂蜜たっぷり あるんだよ ぼくのきれいな 鼻先に
雨が降ろうが 雪だろが 気にはしないさ
なぜならね 蜂蜜たっぷり あるんだよ ぼくのきれいな 手のひらに!
歌おうよ ホー、クマさんに!
歌おうよ ホー、プーさんに!
おやつ食べるぞ いっときご(一時後)!
彼は、森のてっぺんに向かうまでに自分が歌った歌に喜んでました。「ずっとうたってればもっと長くなるな」と彼は思いました。「もうおやつの時間だよ。だから最後の一行は間違ってるよ。」それで彼は鼻歌に変えました。
クリストファーロビンは彼の家の玄関の外に居て、大きなブーツをはこうとしていました。大きなブーツを見つけるや否や、プーはなにか冒険が始まろうとしていることを知ったのでした。そして、手の甲で蜂蜜のついた鼻を拭ってできる限り身なりを整え、何が始まろうと準備ができてるように見せました。
「おやよう、クリストファー・ロビン」と彼は呼びかけました。
「くまのプーさん、こんにちは。ブーツを履けないんだよ」
「それはたいへん」とプーは言いました。
「自分の背中によっかかってくだされないかな。靴ひもを強く引っ張ろうとすると後ろに倒れちゃうんだ。」

プーは座って、地面を掘るように足を突っ張ってクリストファー・ロビンの背中を押しました。そして、クリストファー・ロビンはプーの背を強く押すようにしてブーツのひもを引っ張り、また、引っ張り、ようやく靴を履きました。
「そう、そうだね」とプーが言いました。「で次は何をするの?」
「みんなで探検にでかけるんだ」とクリストファー・ロビンは立ち上がって体をブラシではらいながら言いました。
「ティェケンに行くんだって?」とプーが熱を込めて聞きました。「たぶん、ぼくは言ったことがないと思うんだ。ティエケンでどこに行くの?」
「探検だよ、おばかさん。言葉の中にx(ん)が入ってるのさ」
「ほぉ」とプーは言いました。「そうだよね」と。でも、彼は本当は知らなかったのです。
「みんなで北極を発見しに行くんだよ」
「ほぉ」とプーがもう一度言いました。「北極ってなに?」と尋ねました。
「それを発見しに行くんだよ」と、あまり確かではなかったもののクリストファー・ロビンは無造作に言いました。
「あぁ、そうなんだ」とプーは言いました。「くまも発見する役にたつかなぁ?」
「もちろんさ。そして、ウサギとカンガとみんなだよ。探検なんだ。探検の意味が分かるかい?みんながつくる長い列なんだ。きみは、僕が銃が大丈夫か点検している間に、他の仲間に、準備してって言ってくれないかな。そしてみんなで糧秣(りょうまつ)を持って行くんだ」
「持って行くって何を?」
「食べ物さ」
「あぁ」と嬉しそうにプーは言いました。「きみは、糧秣といったと思ったんだ。みんなのところに行ってそう言うから」
そして、とぼとぼと歩いていきました。
最初に会ったのはウサギでした。

「ウサギさん、こんちは」、「君だよね?」とプーが言いました。
「そうじゃないことにしてみようか?」とウサギは言いました。「どうなるか見てみようじゃないか」
「伝えることがあるんだよ」
「そうじゃない人にあげたら」
「みんなで、クリストファー・ロビンと一緒にティェケンに出かけるんだ」
「そりゃなんだい?いつなんだい?」
「舟のようなものじゃないかな」とプーは言いました。
「あぁ、そういうやつか」
「うん。それで、皆でポールとかなんかを発見しに行くんだ。いや、モール(もぐら)だったかな?ともかく、それを見つけに行くんだよ」
「みんなって、俺たち?」とウサギは言いました。
「そうさ、そしてみんなで糧(りょう)ーーあの、食べるやつさ。食べたくなった時用の。ぼくは、これから丘を下りてピグレットのところに行くから、君はカンガに言ってくれないかな」
プーはウサギのところを離れてピグレットの家に急いでいきました。ピグレットは家の玄関の前の地面に座って、楽しそうにタンポポの綿毛を吹きながら、「それ」があるのは今年かな、来年かな、いつかな、それとも来ないのかなと占い遊びをしていました。かれは、「それ」がきっと来ないことを悟って、「それ」がなんだっかた覚えていようと思いました。そして、来ることがないなら「それ」は良いものじゃなきゃいいさと思っていたときに、プーがあらわれたのです。

「ピグレット!」とプーは興奮して言いました。「これからみんなでティェケンに行くんだよ。食べ物を持ってね。何かを発見するんだ」
「なにを発見するんだって?」と心配そうにピグレットが言いました。
「だからなんかだよ!」
「どう猛じゃないよね?」
「クリストファー・ロビンはどう猛かどうかについてはなんにも言ってなかったよ。かれはただ、なかに「ん」(エックス)が入っていると言っただけさ」
「もしも野獣の首(ネックス)のことなら気にならないさ」とピグレットが真剣に言いました。「それは歯のことじゃないかな。だけど、クリストファー・ロビンが一緒に行くのならなにも気にならないさ」
すこしして、二人は準備をして森のてっぺんに居ました。そして、ティェケンが始まりました。最初に、クリストファー・ロビンとウサギが来て、それからピグレットとプーがきました。それから、カンガ―がプーをお腹の袋にいれてきました。それからフクロウ。そしてイーヨー。そして、最後に、長い列を作ってウサギの友達や親せきたちが来ました。

「彼らには頼まなかったんだけどね」とウサギは無造作に説明しました。「ただ来ただけなんだよ。いつもそうなんだ。かれらは最後についてくればいい。イーヨーのあとに。」
イーヨーは言いました。「自分が言いたいのは」、「それはまだ決まってないってことなんだ。自分はこの「ティェ」ーーその、プーが言ったやつ、に参加したいとは思わなかった。でも、そうしなくちゃならないから来ただけさ。でも、ここに居るんだ:そして自分が「ティェ」の最後に居るならーーその、みんなで話をしていたやつだけどーーであるなら、自分は最後にしておいてくれるかな。でも、もしも、ちょっと休みたくて座ろうとするときは、まず、ウサギの仲間の小さいのを半ダースほど払いのけねばならない。そして、もしもこれが「ティェ」じゃないならーーいやなんでもいいけどもーーそれはただ、訳のわかんない音だということだ。それを言いたかったんだ。」

「わしはイーヨーの言うことがわかる」とフクロウが言いました。「もしも、私に聞いてくれるならね」
「私は誰にも頼まないさ」とイーヨーが言いました。「自分は、みんなに言っているだけだ。われわれは北極を探せるかもしれないし、それとも、みんなで「5月にナッツを集めよう」ゲームのアリの巣の最後のところを遊ぶかだ。自分にとってはおんなじことだ。」
そのとき、列の先頭の方で大きな声がしました。
「いくぞ!」とクリストファー・ロビンが叫びました。
「いくぞ!」とプーとピグレットが叫びました。
「いくぞ!」とフクロウが叫びました。
「みな、始めるぞ!」とウサギが言いました。「行かなくっちゃ」そして、クリストファー・ロビンとティェケンする先頭へと急ぎました。
「わかった」とイーヨーが言いました。「みなで行こう。あとで私のせいにはしないでくれよ」
そうして、みんなで北極を発見しに出発しました。歩きながら、あれやこれやとお話をしていましたが、プーだけは自分の歌を作ろうとしていました。
「これが最初の歌詞さ」と、出来上がったときプーはピグレットに言いました。
「なんの最初の歌詞だって?」
「僕の歌の」
「なんの歌?」
「これだよ」
「どれ?」
「まず、聴いてみてくれないかな。ピグレット、聴けばわかる」
「どうして僕が聴いていないって分かるの?」
プーはその問いには答えられなかったので、歌い始めました。
ぼくらはみなで ポール探しに でかけたさ
フクロウ、ピグレット、ウサギとみんなで
それは皆で見つけるんだ、そういわれたのさ
フクロウ、ピグレット、ウサギとみんなに
イーヨー、クリストファー・ロビンとプー
そしてウサギの親せきみんなで行った
ポールはどこかは 誰も知らずに
歌おう!ヘイ!フクロウ、ウサギ、そしてみな
「しっ!」とクリストファー・ロビンはプーの方を向いて言いました。「ちょうど危ないところに入ってきたんだよ」

「しっ!」とプーは急いでピグレットの方に向きを変えて言いました。
「しっ!」とピグレットはカンガに言いました。
「しっ!」と、ルーがとても静かに何度も自分に言っている間に、カンガはフクロウに言いました。
「しっ!」とフクロウはイーヨーに言いました。
「しっ!」とイーヨーは恐ろしい声でウサギの友達と親類仲間全員に言いました。そして、かれらは列の最後にいる仲間にまで伝わる様に、互いに急いで「しっ!」っと言い合いました。そして、最後尾にいたもっとも小さな友達と親類は、ティエケン隊の全員が自分に「しっ!」と言っているのに慌てふためき、地面の割れ目に頭をうずめてしまい、そこで、危険がなくなるまで二日ほどじっとしてました。それから、とても急いで家に帰り、かれの叔母とずっと静かに暮らしました。かれの名前は、アレクサンダー・ビートルでした。

みんなは、川の流れが高い岩に囲まれてねじ曲がり渦を巻いているところに来ました。そして、クリストファー・ロビンはそれがとても危険であることがすぐにわかりました。
「ここだよ」と彼は説明しました。「危険が潜んでいる(Ambush)」
「どんな茂み(bush)なの」とプーはピグレットにささやきました。「ハリエニシダの茂みかな?」
「プーよ」とフクロウが優越に浸って言いました。「きみは、アンブッシュ(Ambush)の意味を知らないのかね?」
「フクロウさん」とピグレットは、彼の方を振り返り厳しく言いました。「プーがささやいたのはプライベートな話なのだから、口を突っ込む必要はーーー」
「アンブッシュさ」とフクロウは言いました。「言うならばびっくりするようなことだ」
「ときにはハリエニシダの茂みでもある」とプーが言いました。
「アンブッシュのことは、これからプーに説明しようとしていたんだ」とピグレットが言いました。「言うならばびっくりするようなことなのさ」
「だれかが急にとびでて君を襲えば、それがアンブッシュだよ」とフクロウがいいました。
「それがアンブッシュさ、プー。だれかが急に君にとびついたらね」とピグレットが説明しました。
注:フクロウは、jump out atと表現し、誰かが急に飛び出てきて襲うということを言っている。それに対して、ピグレットは、間違って、好機に飛びつくというjump atを使っている。
プーは、ようやくアンブッシュの意味が分かったので、ある日、彼が木から落ちたときにハリエニシダの茂みが突然彼に跳ねて、その後、棘を抜くのに六日間もかかったと言いました。
「私たちはハリエニシダのことをいってるんじゃない」とフクロウは少し怒って言いました。
「僕がいってるんだよ」とプーが言いました。
みんなは、小川を注意深く、岩から岩へと上っていきました。しばらくすると、両側の川岸が広がって両側に細い幅で草が生えていて休めるようなところがありました。それを見た途端、クリストファー・ロビンは「とまれ!」と言いました。そして、みんなは座り休憩しました。
「僕が思うに」と、クリストファー・ロビンが言いました。「ここで持ってきた糧秣(りょうまつ)を全部たべて、持って行くものを少なくしよう」
「なにを全部食べるんだって?」とプーは言いました。
「持ってきたもの全部だよ」とピグレットが、食べ始めながら言いました。
「そりゃいいね」とプーが言い、かれも食べ始めました。
「みんな、何か持ってきたかい」とクリストファー・ロビンは口いっぱいにして言いました。
「僕以外はね」、「いつものことだけど」とイーヨーが言いました。彼は物悲しくあたりを見回しました。「だれもアザミの上に座っていないとよいけども」
「僕は座っちゃったと思う」とプーは言いました。「痛いぃ!」と彼は起き上がって後ろを見ました「確かにそうだ。そう思ったんだ。」
「ありがとう、プー。もしも、もう使い終わっていたらね。」彼はプーがいたところに行って、アザミを食べ始めました。

「それに座っていてもよいことはないよね。よくわかるだろう」と、彼はむしゃむしゃと食べながら見上げました。「すべての生命を取り上げるんだ。次のときに覚えておくとよい。他人へのちょっとした配慮と考慮をすることで、全然話が変わってくるんだ。」
昼食を食べ終えようとしていたとき、クリストファー・ロビンはウサギにささやき、ウサギは「うんうん、もちろんさ」と言い、二人は小川を少しだけ上って行きました。
「ほかのものたちに聞こえないようにしたかったんだ」とクリストファー・ロビンが言いました。
「そのとおり」とウサギが大事そうな面持ちで言いました。
「あのーーどうかなーーきっと君だけ、多分、君はしらないだろうけど、北極ってどんな感じのものかな?」
「あぁ」とウサギはひげをさすりながら言いました。「ぼくに聞いているんだね?」
「知ってはいたんだ。ちょっと忘れちゃったんだよ」とクリストファー・ロビンは無造作に言いました。
「おかしいなぁ」とウサギが言いました。「知っていたことをなんか忘れていたような気がするんだ」
「それって地面に刺さっているポールじゃないかな?」
「そうにちがいないさ」とウサギが言いました。「ポールと言うんだから、そしてポールなんだったら、地面に突き刺さっているはずだよね?だって、他に刺さるところなんかないんだから」
「そうさ、そう思ったんだけど」
「問題は」とウサギは言いました。「それがどこに刺さっているかだ」
「だからそれを探しに行くんだよ」とクリストファー・ロビンが言いました。
二人は仲間のところに戻りました。ピグレットは背中を地面につけて静かに寝ていました。ルーは小川で顔と手を洗っていましたが、カンガはそれをみんなに、ルーが初めて顔を洗ったのだと自慢げに言いました。そして、フクロウはカンガにエンサイプロペディアとかシャクナゲというような長い言葉ばっかりをつかったエピソードを語っていましたが、カンガはぜんぜん聞いていませんでした。
「こういう洗い方には賛成できないけども」とイーヨーがぶつぶつと言いました。「青二才のすることとかいうナンセンスだね。プーはどう思うかい?」
「えっと」とプーが言いました。「たぶん・・」
しかし、プーが何を考えていたなんか知る由もありません。なぜなら、ルーがとつぜんキーキーと言い、水しぶきが立ち、カンガが危ないと大きな叫び声をあげたからです。
「もう洗うのは十分だろう」とイーヨーが言いました。
「ルーが水に落ちた!」とウサギが叫びました。そして、クリストファー・ロビンは急いで助けに向かいました。

「泳いでるのを見て!」とルーは水たまりの中からキーキー言いました。そして、一つの水たまりから次の水たまりへと滝を急に落ちていきました。
「ルーちゃん、大丈夫なの?」とカンガが心配そうに聞きました。
「大丈夫だよ!」とルーは言いました。「見て、泳いで・・・」そして、彼は、次の滝を超えて次の水たまりに落ちていきました。
ルーを助けようと皆が何かをしていました。ピグレットは、突然、目を覚まし、飛び跳ねながら、「おぉ、だから」と雑音を上げるように騒いでいました。フクロウは、突然の一時的な浸水の事態において重要なのは、頭を水面の上に出しておくことだと説明しました。カンガは、「本当に大丈夫、ルー?」と言いながら川岸を飛び跳ねました。ルーは、そのとき、どの水たまりにいても、「泳いでいるのを見て!」と答えたのでした。イーヨーは振り返ってルーが最初に落ちた水たまりにしっぽをたらし、この事件から背をそらすようにぶつぶつと独り言を言っていました。「すべては顔を洗おうとしたことから始まったんだ。だけど、私の尻尾につかまりなさい、ルー。そうすれば解決できる。」そして、クリストファー・ロビンとウサギはイーヨーを急いで通り越して前にいる者たちに声をかけて行きました。
「大丈夫だよ、ルー、助けに来たよ」とクリストファー・ロビンは言いました。
「だれか、下流の方で流れを跨ぐようななんか渡そう」とウサギが言いました。
しかし、プーは何かを持っていました。ルーが居た水たまりの二つほど下に彼は居て、長いポールを手に持っていました。カンガがやってきてポールの一方の端をつかみ、川下の方で川を跨るように二人でポールを持ちました。そして、ルーは、依然として誇らしげに「見てみて、泳いでる」とぶくぶく言っていたのがポールのところまで流れてきて、それによじ登ったのでした。

カンガがルーを叱りこする様に下ろしていたとき「ぼくが泳いでいるところを見た?」とルーは興奮して叫びました。「プー、僕が泳いでいるのを見た?あれが泳ぐってことだよね。ウサギさん、僕がやってたの見た?泳いでたよ。ねぇ、ピグレット。ピグレットったら。僕がやってたのどうだった?泳いでたんだよ!クリストファー・ロビン。僕のこと見てた?--」
しかし、クリストファー・ロビンは聞いていませんでした。彼はプーのことを見ていました。
「プー、どこでそのポールを見つけたの?」と彼は言いました。
プーは両手に持っていたポールを見ました。
「ただ、みつけたんだ」と彼は言いました。「それが役に立つと思ったんだ。だから拾ったんだ」
「プー」とクリストファー・ロビンが厳かな趣で言いました。「探検はおしまいだ。君が北極(ノース・ポール)を見つけたんだよ」
「あぁ、そうなんだ!」とプーは言いました。
イーヨーは、皆が彼のもとに戻ったとき、尻尾を水につけて座っていました。

「誰か、ルーに急げっていってくれないか」と彼は言いました。「しっぽが冷たくなってきたんだ。言いたくはないけども言ってしまったね。文句を言うつもりではないんだがそうなんだ。しっぽが冷たいんだ」
「来たよ」とルーがキイキイ声で言いました・
「なんだ、いたのかい」
「僕が泳いでいるの見た?」
いーよーは水の中から尻尾を引き上げ、左右に振りました。
「予想していたとおり」と彼は言いました。「なにも感じない。しびれてる。そういうことなんだ。しびれてる。いや、だれも気にしなければそれでいいんだ」
「かわいそうなイーヨー。僕が乾かしてあげるよ」とクリストファー・ロビンが言って、ハンカチを取り出し尻尾をもむように拭きました。
「ありがとう、クリストファー・ロビン。君だけが尻尾のことをわかってくれたようだ。だれも、それが誰かの問題だとはしらないんだ。想像力がないのだよ。尻尾はかれらにとって尻尾じゃなくって、お尻にあるちょっと余分なものでしかないんだ」
「気にしないでよ、イーヨー」とクリストファー・ロビンは一生懸命さすりながら言いました。「これでよくなったかな?」
「たぶん、尻尾らしく感じてきた。ようやく自分のものになったようだ、分かるよね、何を言っているのか」
「やぁ、イーヨー」とプーは、ポールを持ってきて言いました。
「やぁ、プー。気にかけてくれてありがとう。だけど、今日か明日にはそれを使うことになるだろうさ」
「使うって何?」とプーは言いました。
「話していたことだよ」
「何のことも話していなかったけど」と、プーは当惑して言いました。
「自分がまた間違ったんだな。私は、君が、私の尻尾がしびれているのを気の毒がって、何かできるのかいと聞くのだろうとおもったんだ」
「そうじゃないよ」とポーは言いました。「それは、自分じゃないんだ」と彼は言いました。彼は、少しだけ考えて、助けになろうと言いました。「多分、誰か別のひとだね」
「そうか、では、その人を見つけたらお礼を言ってくれないか」
プーは心配そうにクリストファー・ロビンを見ました。
「プーが北極をみつけたんだ」とクリストファー・ロビンが言いました。「よかったじゃないか」
プーは控えめに下を見ていました。
「そうなのかい?」とイーヨーが言いました。
「そうなのですよ」とクリストファー・ロビンが言いました。
「みなで探そうとしていたのはそれだったのかい?」
「そうなんです」とプーが言いました。
「ほぉ」とイーヨーは言いました。「それじゃ、ともあれーー雨はふらなかったんだから」と彼は言いました。
彼らは地面にポールを指して、クリストファー・ロビンはそれにメッセージを付けました。
北極(ノース・ポール)
プーにより発見される。
プーが見つけた。

それからみんなは家に帰りました。そして、多分、あまり自信はないのだけど、ルーはお風呂に入ってすぐに寝たんだろうと思う。だけどプーは自分の家に戻って、やったことをとても誇らしげに思って、元気づけのためにおやつをちょっと食べたんだ。
第9章
ピグレットが洪水で完全に囲まれてしまう話
雨が降って雨が降って雨が降りました。ピグレットは、これまでの生涯でなかったな、何年くらいかわからないけどーー3年、それとも4年かな?ーーこんなに雨が降ったことを見たことはないな、と独り言を言いました。何日も、何日も、そして何日も。
「ただ」彼は窓の外を見ながら考えました。「雨が降り始めたときに、プーの家に、あるいは、クリストファー・ロビンの家に、あるいは、ウサギの家に居たらばなぁ。ずっとお仲間がいたんだよなぁ。一人でなすことなくいつ止むかななどと思うこともなかったのに」そして、彼はプーと居ることを想像して、「プー、こんな雨みたことある?」するとプーは、「ひどいよねぇ。ピグレット」と言って、ピグレットが「クリストファー・ロビンのところにいく道はどうなっているかなぁ。」というとプーが「かわいそうに、年寄りのウサギさんはいまごろ水没してるかもしれないね」。こんな風に話していると楽しいだろうし、こんなすごい洪水に会って、そのことををだれかと話すことができないなんて良いことはないのでした。
それは多少わくわくすることでした。ピグレットがよくにおいを嗅ぎまわっていた小さな乾いた溝は小川のようになり、しぶきを散らして水遊びしていた近くにあった小川は川のようになり、その川は両側の土手で楽しく滑って遊んでいた急な斜面の間に大きく広がってあちこちを水浸しにしてしまっていたので、ピグレットは自分のベッドも水につかるのではないかと心配し始めていました。
「ちょっと心配になってきた」と彼は独り言を言いました。「水にすっかり囲まれたちっぽけな動物になってしまうんじゃないかな。クリストファー・ロビンとプーは木を登って、カンガは飛び跳ねて、ウサギは穴を掘って、フクロウは飛んで行って、イーヨーはーー助けが来るまで大きな声を出して逃げることができるだろうけど、自分は、水に囲まれたらなんにもできないや」
雨が降り続き、日一日と水かさが高くなり、もうピグレットの家の窓の高さ近くまで来ていましたーーそしてピグレットはまだ何もしていませんでした。

「プーはね」と彼は思いました。「プーは脳みそがあまりないけど、害になることは絶対にない。かれはバカなことばかりしているけどそれがみなオーライになる。フクロウはね。実は頭がいいわけじゃないけど物知りだよね。彼なら水に囲まれたときに何をすればよいかわかるだろうな。ウサギはね。本からは学んではいないけども、いつも賢いんだよね。カンガはね。賢くはないけども、ルーのことをとても心配して何も考えずにすごいことをするんだよね。そしてイーヨーはね。惨めなんだけどそのことを気にはしていない。だけど、クリストファー・ロビンだったらどうしてるだろう?」
すると、突然、彼は、クリストファー・ロビンが離れ島に居た男が瓶に書き物を入れて海に流した話をしてくれたことを思い出しました。そして、ピグレットは、もしも彼がボトルに何か書いたものを入れて水に投げれば、誰かが助けてくれるんじゃないかと思いました。
彼は窓から離れて、水につかっていないものすべてを家の中で探し始め、ついに、鉛筆と乾いた紙のかけらとコルクで栓がしてある瓶を見つけました。そして、彼は、その片側にこう書きました。
助けて!
ピグレット(ぼくだよ)
そして反対側にはこう書きました。
ぼくだよ。ピグレットだよ。助けて、助けて。
それから、彼はその紙を瓶につめて、コルクできつく蓋をしました。そして、落ちない程度に窓の外の方へとよっかかりできるだけ遠くに瓶を投げたのでした。ーー水しぶきがしてーー少しすると瓶は水の中で揺れながら、少しずと遠くへと漂っていくのでした。彼は、見ていて目が痛くなるくらいまでそれを見で追いながら、ときに彼はそれが瓶だと思い、時に彼は水面のさざ波のように思い、そして、突然、彼は、それが再びは見えなくなって彼としてはやれることはすべてやったと思ったのでした。

「さぁ、これで」、と彼は思いました。「誰かが何かしてくれなくちゃ。早くして欲しいな。だって、そうしてくれないと自分が泳がなくっちゃならないし、でも泳げないから。だから、すぐに助けてほしいな。」そして、とても長くため息をついて言いました。「プーがここに居てくれたらなぁ。二人ならもっとずっとホッとしていられるんだけども。」
雨が降り始めたとき、プーは眠っていました。雨が降って、雨が降って、雨が降り続けました。そして、プーは寝ていて、寝ていて、ずっと寝ていました。プーはそのひとても疲れたのです。覚えているでしょう、プーがどうやって北極(ノース・ポール)を探したか。プーはとても誇らしく思ったので、クリストファー・ロビンに、他にも脳みそが足りないクマが探せるようなポールがあるか聞いたのでした。
「南極(サウス・ポール)があるよ」とクリストファー・ロビンが言いました。「そして、東極(イースト・ポール)も西極(ウエスト・ポール)もあるんじゃないかと思うんだ。みんなそのことは言わないけども。」プーはこれを聴いてとても興奮し、それなら東極(イースト・ポール)を探しに探検に出ようよと言ったのですが、クリストファー・ロビンはカンガをどうしようと考えていたのでした。それで、プーは一人で東極(イースト・ポール)を探しに出ました。発見でたかできなかったのかは忘れちゃいましたが、家に戻ったときはとても疲れていたので、夕食のさなか、30分ちょい食べていたところで、椅子に座ったまま寝てしまい、寝て、寝て、寝続けたのでした。
それから、突然、夢を見ました。彼は、東極(イースト・ポール)に居て、それはとても冷たいポールで、もっとも冷たい雪や氷が覆っているところでした。彼は、寝場所となる蜂の巣を見つけたのですが、彼の足を入れるスペースがなかったので、足は外に出していました。そして、東極(イースト・ポール)に居るような野生のウーズルたちがやってきて、かれらの子供の巣をつくるためにプーの足の毛皮の部分をぜんぶかじってしまい、痛い!と言って突然目が醒めたのでした。そこで、プーは足を水につけて椅子に座っていて、かれの周りは一面が水となっていたのでした!
「これは大変だ」とプーは言いました。「脱出しなければ」
それで、彼は、一番大きなハチミツ壺をもって、水面よりはずっと高いところにある太い幹のところに逃げたのでした。それから、もういちど下りて行ってもう一つハチミツ壺をもって逃げました。ーーという風にやってすべての壺をもって木の枝にあがり、足をぶらぶらさせ、そのわきにはハチミツ壺が十個ならんでいました。

二日経ったとき、プーは、枝に座って足をぶらぶらさせ、そのわきにはハチミツ壺が4つありました。。。
三日経ったとき、プーは、枝に座って足をぶらぶらさせ、そのわきにはハチミツ壺が1つだけありました。。
四日立ったと、プーは、、

そして、四日目の朝に、ピグレットが流した瓶が彼のところに流れ着いてきました。プーは、「ハチミツだ!」と大きな声を上げて水の中に跳びこみ、瓶を捕まえて、木のところに何とか戻ってきました。
「やれやれ」とプーは言って瓶を開けました。「すっかり濡れちゃったのにこれかい。この紙切れが何の役に立つんだ?」
彼は紙を取り出してそれを見つめました。
「”ミ”ッセージが書いてある」と彼は独り言を言いました。「そうだ。そしてこの字は大文字の「P」だよ。そうだそうだ。「P」は「Poo」だから自分のことだ。だとすると、これは自分にとってとても重要なミッセージだね。だけど僕は読むことができない。クリストファー・ロビンかフクロウ科ピグレットを見つけなくちゃ。彼らのような賢い読み手なら読むことができて、このミッセージが何のことを言っているのか教えてくれるんだけど。ああ、僕は泳げないんだよな!」
それから、彼は良いことを考えました。脳みそがとても小さなクマにとってはとてもよいことだったはずです。彼は独り言を言いました。
「もしも瓶が浮かぶことができるならば、壺も浮かぶことができるはずだし、壺が浮かぶことができるならその上にのっかることができるよね。もしも大きな壺なら。」

そして、彼は一番大きな壺をもって上に蓋をしました。「舟にはみんな名前がついているよね」と彼は言って、「それなら、自分のは「漂うクマ」と名付けよう。」そして、こう言ってから、かれは自分の舟を水に落としてからそれを追って飛び込みました。

少しの間、プーと漂流するくまは、どっちが上を向くのかがわからなかったのですが、一つ二つポジションを変えて、ようやく、漂流するくまがプーの下におさまりプーは勝ち誇ったようにそれに跨り、一生懸命、足で漕いでいきました。

クリストファー・ロビンは森の一番高いところに住んでいました。雨が降って、雨が降って、また雨が降りました。でも、彼の家まで水が来ることはできませんでした。谷を見下て、そこがあたり一面水びたしとなっている様子を見るのは愉快にさえ思えましたが、雨があまりに強く降るために彼はほとんど家の中に居て考えごとをしていました。毎朝、彼は、傘をもって外に出て、水が来たところに木の枝を刺しましたが、毎朝、刺した枝が見えなくなったので、また、水がきたところに新たに枝を刺して家へ戻ったのでした。そして、毎朝、家へ戻る道は短くなっていったのでした。五日目には、彼の周り一帯に水が来ていて、彼は本当の島にいることがわかりました。それは、とてもわくわくするものでした。

まさにその朝に、フクロウが水面を超えて飛んできて、友達のクリストファー・ロビンに「元気かい?」言いに来たのでした。
「フクロウさん」とクリストファー・ロビンが言いました。「これちょっと面白くないかな。自分は島に居るんだよね!」
「このところ大気の状況がとても芳(かんば)しくないのだ」とフクロウがいいました。
「なんのこと?」
「ずっと雨が降り続いておる」とフクロウが説明しました。
「そう」とクリストファー・ロビンが言いました。「ずっと降ってる。」
「水かさが今までになかった高さになっているのだよ」
「誰が?」
「一面が水になってるということじゃ」とフクロウが説明しました。
「そう」とクリストファー・ロビンが言いました。「そのとおり」
「しかしながら、この先は急速に好転すると見通されている。いつにでもーー」
(*)Flood-level (水かさ)がWhoに聞こえて、誰かがとても背が高くなったと聞き間違えている。
「プーを見なかったかな?」
「見なかった。ずっとねーー」
「プーが問題なければいいんだけど」とクリストファー・ロビンが言いました。「ずっとプーがどうしているかと思ってたんだけど。ピグレットと一所に居るんじゃないかと思うんだけど。行って二人とも大丈夫かみてきてくれないかなぁ、フクロウさん?」
「そのように考えるね。うん、いつでもねーー」
「行ってみてきて、フクロウさん。だって、プーはあまり大きな脳みそはないからバカなことをしているかもしれない。だからプーが好きなんだけど。フクロウさん、分かるよね。フクロウさん?」
「そのとおりじゃ」とフクロウは言いました。「行ってすぐに戻ってくるから。」そして、飛び去って行きました。

少しして、彼は戻ってきました。
「プーはそこには居ない」と彼は言いました。
「そこにいなかったって?」
「そこには居たのだ。彼は、彼の家の外で、9つのハチミツ壺と共に木の幹に座っていたんだ。でも今はそこにいない。」
「おぉ、プー!」とクリストファー・ロビンが言いました。「どこにいるんだ、君は?」
「ここにいるよ」と唸るような声が後ろから聞こえました。
「プー!」
二人はいそいで近寄り互いの腕で抱き合いました。
「ここにどうやってきたの、プー?」と、話すことができるようになってクリストファー・ロビンが聞きました。
「舟に乗ってね」とプーは自慢げに言いました。「僕宛のとても重要なミッセージがあるんだけど、目に水が入って読むことができなかったんで、君に見てもらおうと持って来たんだ。ボートにある。」

こうして自慢をしてからプーはクリストファー・ロビンにミッセージがかかれたものを渡しました。
「だけど、これはピグレットからだよ!」とそれを読んだクリストファー・ロビンは叫びました。
「プーのことはなにも書いていないの?」とクマはクリストファー・ロビンの肩越しに聞きました。クリストファー・ロビンは大声でミッセージを読みました。
「あぁ、その「P」はピグレットのことなの?僕は自分のことだと思った。」
「みなで助けに行かなきゃ!プー、君と一緒だとおもっていたんだ。フクロウさん、ピグレットを救って背中に乗せてくることはできるかな?」
「それはできないと思う」とフクロウは深く考えてから言いました。「十分なだけの背筋があるかどうかが疑わしいのじゃーー」
「ならば、すぐに飛んで行ってこれから助けが来るよと言ってもらえないかな?そして、プーと自分がどう助けるか考えてできるだけ早く向かうから。おぉ、もうしゃべらないでいいから早く行ってください。フクロウさん。」
そして、何を言おうかと考えていたのですけれども、フクロウは飛び立っていきました。
「それで、プー」とクリストファー・ロビンが言いました。「君の舟はどこにあるの?」
「言わなきゃと思ってたんだけど」と島の岸に向かって下の方へと歩きながらプーが説明し始めました。「それが普通の舟じゃないんだ。あるときは船だけど、あるときはほとんど偶然なんだ。状況によるんだ。」
「状況によるってなに?」
「それは、自分が上に乗ってるか下にいるかってことなんだ。」
「ほう、それでどこにあるの」
「あそこだよ!」とプーは「漂うクマ」を自慢げに差しながら言いました。
それは、クリストファー・ロビンが思っていたものとは違いましたが、よく見つめれば見つめるほどプーは勇敢で賢くいクマだと思えてくるのでした。そして、クリストファー・ロビンがそう思うと、プーは謙遜して鼻を見下ろしそうじゃないよというふりをするのでした。
「だけど、僕と君とでは小さすぎないかな」とプーは悲し気にいいました。
「ピグレットを加えて3人だよ」
「じゃあ、もっと小さすぎるよね。あぁ、プー。どうしようか?」
そして、このクマさん、くまのプー、ウィニー・ザ・プー、F.O.P、つまり、ピグレットの友達のプーで、R.C、つまりウサギのおともだちで、P.D.(極地の発見者)で、E.CとT.F、つまり、イーヨーの慰め役であり尻尾を見つける者であるーーつまりプー自信がーークリストファー・ロビンがあんぐりと口を開けて目を見開いたままとなるようなすごく賢いことをいったのでした。これは本当に、彼がずっと大好でいた、とっても脳みその小さなクマなのだろうかと思ったのでした。
「ぼくたち、君の傘にのればいいんじゃないかな」とプーが言いました。
「?」
「ぼくたち、君の傘にのればいいんじゃないかな」とプーが言いました。
「??」
「ぼくたち、君の傘にのればいいんじゃないかな」とプーが言いました。
「!!!!!」
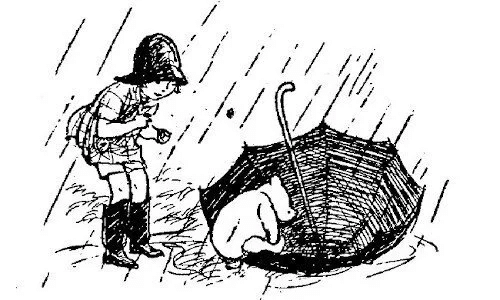
突然、クリストファー・ロビンは、そうしたらいいんじゃないかと思いました。かれは、水に向けて下向きに傘を開きました。傘は浮きましたがグラグラしました。プーが乗り込みました。かれは、ちょうど大丈夫だと言おうとしたとき、そうならなくって、意図せずに水を飲むこととなって水の中をなんとか歩きながらクリストファー・ロビンのもとに戻りました。「これを「プーの脳みそ」と名付けよう」とクリストファー・ロビンが言いました。そして、「プーの脳みそ」は南西の方向に向かって、優雅に回転しながら進んでいったのでした。

舟が見えたときに、ピグレットがどれほど喜んだか想像できますよね。その後何年も、彼は、彼が大洪水のときにとっても大変な危険にさらされだけれども、本当に危険だったのは、彼が閉じ込められていた時の最後の半時間のことで、それはフクロウがちょうど飛んできて、木の幹に止まって彼を慰めにきたときに、彼が、誤ってカモメの卵を抱いてしまったアリについてのとても長いお話をしたときであって、それはさながらこの文章みたいに延々と続いたので、ピグレットは希望を失って窓からずっと聞いていたのが、静かに自然に寝てしまい、水に向かって窓からゆっくりと滑り落ちてしまい、足のつま先だけが引っかかっている状態になって、それでも幸運だったのは、フクロウが突然大きな叫び声をあげて、それは、お話の一部でアリが話したことではあったのだけど、ピグレットの目を覚まさせたため、ピグレットはすんでのところで安全に戻ることが間にあって、「面白いお話だね、そして彼女はどうしたの?」と言うことができて、そして、ねぇ、想像がつくと思うけども、彼のことを助けに海を越えてやってきた「プーの脳みそ」号(船長は、クマのPの最初の友達であるC.ロビン)の姿をピグレットが見つけたとき彼がどれほど喜んだか。

クリストファー・ロビンとプーが再び・・
そして、これが物語の本当のおしまいで、パパは最後の文章のところでとても疲れちゃったので、ここでやめることにするね。
第10章
クリストファーロビンがプーのためにパーティをして皆でさよならと言う話
ある日のこと、森の向こうからサンザシの香りとともにお日様が戻ってきて、森を流れる小川がもときれいな姿にもどり、自分が目にしてきた生命とかれらがとてもことを成し遂げてきたことを夢見るように小さな水たまりが散在し、森の暖かさと静けさの中でカッコーが自身の鳴き声を気に入るかどうか注意深く試し鳴きをするようにさえずり、モリバトは怠惰で居心地よく過ごしているのは彼らの仲間のせいだとぶつくさ言っていて、でもそんなに気にしている様子もありませんでした。そんな日に、クリストファー・ロビンは、特別なやり方で口笛を吹くとフクロウが百エーカーの森から出てきて彼が何をしたいのか見にきたのでした。

「ふくろうさん」と、クリストファー・ロビンが言いました。「パーティを開こうとしているんです」
「ほう、そうなのかい?」とフクロウが言いました。
「そしれ、それは、とても特別なパーティなのです。なぜなら、プーが洪水からピグレットを救ったときにプーがしたことについてだからなのです。」
「ほう、それがその理由だというのだね?」と、フクロウが言いました。
「そうなんです、できるだけ早くプーのところに行って話してもらえますか?プー以外の皆にもですけど。だって、パーティは明日なんです。」
「ほう、そうなのかい?」と、できるだけ助けになろうとフクロウが言いました。
「なので、フクロウさん、皆のところに行って伝えてもらえますか?」
フクロウはなにかとても賢いことを思いつこうとしたのですが、できなかったので、彼は、皆に伝えるために飛んでいきました。最初に伝えた相手はプーでした。
「プー」と彼は言いました。「クリストファー・ロビンがパーティをやるんだって。」
「そう!」とプーは言いました。そして、フクロウが他に何かを言うのじゃないかと見てから、「ピンク色の砂糖がアイシングされたケーキとかでてくるのかな?」
フクロウはピンク色の砂糖がアイシングされた小さなケーキのことを話のは自分の品位にかかわると思い、クリストファー・ロビンが言ったことを忠実に伝えて、イーヨーのところへ飛んでいきました。

「ぼくのためのパーティ?」プーは考えました。「なんて贅沢な話だろう!」そして、かれは、他の動物たちがそれが特別のプーのためのパーティだとしるのだろうかと思い、クリストファー・ロビンが皆に、かれがこしらえて航海したすべての素晴らしい舟と「漂流するクマとプーの脳みそ」について語るのだろうかと思い、もしもだれもがそのことを忘れてしまうならとてもいやだなと思い始め、そしてだれもがパーティがなんのためかよくは知らず、このように考えるにつれ、あたかもすべてがうまくいかない夢のように彼の心の中でパーティが混乱してきたのでした。そして、彼の頭の中で夢が歌いだしたのでした。それはこんな歌でした。
心配な プーが歌う
プーに万歳 三唱しよう!
(だれのため?)
プーのためーー
(なにをしたんだ?何のため?)
知っていると 思ったよ;
水につかる 友達を 助けたんだよ!
万歳三唱 クマさんに!
(えっ、どこに?)
クマのためーー
かれは泳げは しないんだ、
だけども彼は 助けたよ!
(助けた人は 誰のこと?)
ほらほら聞いて よく聞いて!
誰って言うのは プーのこと!
(えつ、だれを?)
プーのこと!
(忘れてばかりで すみません)
そうなんだよね くまのプー すごい頭脳の 持ち主さ
(なんって言ったの もう一度?)
すごい頭脳の 持ち主さー
(すごいなんたら なんだって?)
彼はたくさん 食べるけど
泳ぐかどうかは しらないが
彼は何とか 漂った
乗って行ったは 舟みたい
(乗って行ったは なんだって)
そうそうそれは 壺みたい
さあさあ彼に こころから 万歳三唱 あげようよ
(さあさあ彼に 三人の 優しい魔女を あげましょう)
ずっとずうっと 何年も 一所にいようと 期待して
願おぅじゃないか 育つのを 知恵も富をも 健やかに
万歳三唱 プーさんに!
(誰にだって?)
プーさんに!
万歳三唱 クマさんに!
(どこにだって?)
クマさんにー
万歳三唱 プーさんに とてもすてきな クマのプー!
(ちょっと教えて くれないかーーいったいなにを 彼がした?)
これが彼のなかで続いているときに、フクロウはイーヨーと話していました。
「イーヨー」とフクロウは言いました。「クリストファー・ロビンがパーティを開くんだ」
「それは面白い」とイーヨーが言いました。「踏みつけらたいらないものをわしに送ってくれるというのだな。ご親切で思慮深いことだ。どういたしまして。お礼を言うにはおよばないだろうが。」

「あなたを招待するのだよ」
「いったいなんだって?」
「招待だよ」

「あぁ、聞こえたさ。だれが落としたんだと?」
「これは食べ物ではないのだよ。パーティにきてくだされと言ってるんだ。明日の。」
イーヨーはゆっくりと頭を振りました。
「ピグレットのことを言っているのかい?あの興奮気味の耳をしたちっちゃなやつ。そう、ピグレット。自分から伝えとくよ。」

「いや、ちがうのじゃ」とフクロウは少しイライラして言いました。「あんたのことじゃよ」
「マジかい?」
「もちろんマジだ。クリストファー・ロビンは「みんなだ、みんなに伝えてくれ」と言ったのじゃ」
「イーヨー以外のみんなかい?」
「みんなじゃ」とフクロウはむっとしていいました。
「おぉ」とイーヨーは言いました。「間違いだろう。そうに違いない。だけど、わしは行くよ。雨が降ったとしてもワシを責めんでおくれ」
しかし、雨は降りませんでした。クリストファー・ロビンは長い木の板で長いテーブルを用意して、皆がその周りに座りました。クリストファー・ロビンは机の一つの端に着き、プーはその反対に着きました。そして、その間の片側にはフクロウとイーヨーとピグレットが、その反対側にはウサギとルーとカンガが着きました。ウサギの友達と親類は草の上に広がり、誰かが話しかけれくれないか、何か落としてくれないか、或いは時間を聞いてくれないかと期待して待っていました。
生まれて初めてのパーティーだったので、ルーはとても興奮していました。席につくや否や、彼は話し始めました。
「こんにちは、プー」ときいきい声で言いました。
「こんにちは、ルー」とプーが言いました。
ルーは椅子の上でしばらくの間飛び跳ねていましたが、また、話し始めました。
「こんにちは、ピクレット」ときいきい声で言いました。
ピグレットは、何か言おうと忙しかったので、前足を振りました。
「こんにちは、イーヨー」とルーが言いました。
イーヨーはルーに向かって陰気に頷きました。「まもなく雨が降るさ、そうじゃないか見て居てごらん。」と彼は言いました。
ルーはそうなるかと見ていましたが、雨は降らなかったのでフクロウに「こんにちは、フクロウさん」と言いました。ーーそしてフクロウは、「こんにちは、小さなおともだち」と、優しそうに言って、クリストファー・ロビンに彼が知らないフクロウの友だちが遭遇しそうになったなった事件について話をつづけました。そして、カンガはルーに、「さいしょにミルクを飲みましょね。お話はそれからよ」と言いました。すると、ミルクを飲んでいたルーは、両方とも一緒にできるさと言おうとして・・・そのあとしばらくの間、背中をたたいてもらったり、濡らしたところを乾かしてもらわなければなりませんでした。

十分にお腹いっぱいになったとき、クリストファー・ロビンはテーブルをスプーンでたたき、みんなはおしゃべりを止めてとても静かになりました。ルーは、おっきなしゃっくりをして音をたてたところましたが、自分ではなくてウサギの親類がやったんだというふりをしました。

「このパーティは」とクリストファー・ロビンが言いました「だれかがやったことのためのパーティであって、そして、みんなが誰のことか知っていてるから、彼のためのパーティで、彼がなしたことで、僕は彼にプレゼントを用意したん。ほれ、この通り」そして、彼は、ちょっとの間そこらを触り、ささやきました。
「どこにいっちゃったんだろう?」
彼が探していたとき、イーヨーは厳粛そうに咳払いをして話し始めました。
「友よ」と彼は言いました「そして、他の方々も含めてだが、このパーティで皆さんにお目にかかれるのは、というか、これまでご一緒できていることは、私にとってとても幸せなことと言うべきだろう。私がしたことはたいした話じゃない。そして、あなた方もーーウサギとフクロウとカンガは除外してだがーーそうだろう。あぁ、プーもだ。もちろん、私が言おうとしていることは、もちろん、ピグレットとルーにはあてはまることじゃない。なぜなら、二人とも小さすぎる。皆が、同じことをしてただろう。しかし、たまたま私にがすることとなったまでのことだ。言うまでもないが、それはクリストファー・ロビンがいま探していることを見つけようとしてわけでもない。」そして、彼は、前足を口につけて大声でささやきました。「テーブルの下を試してごらん」ーー「それを私がやったんだーーなぜなら、私らみんなが役に立つためにすべきことだからだ。私は、そう思うんだーー」
「しゃっくり!」と、ルーは突然声を出しました。
「ルー、あなたは」と、カンガはルーを叱るように言いました。
「ぼくが?」と、少し驚いた様子でルーが聞きました。
「イーヨーはいったい何を言ったのかな?」と、ピグレットはプーにささやきました。
「ぼくもわかんない」とプーは悲しそうに言いました。
「これは君のためのパーティだと思ったけど」
「ぼくもそう考えていたんだけど。だけど、違うようだね」
「イーヨーのためのより君のためのものの方がいいんだけど」と、ピグレットが言いました。
「ぼくも、そう思う」と、プーが言いました。
「し、しゃっくり」とルーが再びいいました。
「私が、言ってきた通り」と、イーヨーは大声で厳しい感じで言いました。「たくさんのものが大声を出して私の話をさえぎっているが、私が思うにはーー」
「ほら、これだ!」と、クリストファー・ロビンが興奮して言いました。「これを、おばかさんのプーに渡してくれる。これは、プーへなんだ」
「プーのための?」と、イーヨーが言いました。
「もちろんそうさ。世界で一番のクマだから」
「知ってればよかった」とイーヨーが言いました。「つまるところ、文句など言っておられん。私には自分の友がいる。誰かは昨日私に話しかけたよ。そして、それは先週だったか、先々週だったか、ウサギが自分のところに跳びはねてぶつかって「やれやれ」と言ったさ。それがお付き合いってもんだ。いつも誰かがやっとることだ。」
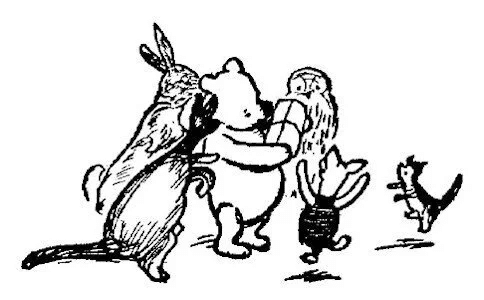
だれもイーヨーのことは聞いていました。それは、みんなが「開けてみて、プー」、「なにかな?プー」、「ぼく、知ってるよ」、「知ってるわけないじゃない」とか、こんな感じの役に立ちそうな見解を言い合っていたからです。もちろん、プーは、大急ぎでそれを開けましたが、ヒモは切らないようにしました。なぜなら、ちょっとしたヒモの切れ端がいつ役に立つかわからないですからね。そして、ついに、それが開きました。
プーがそれを見たとき、彼は嬉しさのあまり、倒れそうになりました。それは、特別の鉛筆入れだったのです。クマ(ベア)を意味する「B」の文字が書かれた鉛筆と、役に立つクマ(ヘルピング・ベア)を意味する「HB」と書かれた鉛筆と、勇敢なクマ(ブレーブ・ベア)を意味する「BB」と書かれた鉛筆が入っていました(注)。鉛筆を削るためのナイフと、スペル間違いをして書いたものはなんでも消すことのできる消しゴム、それから、単語に添える線を書くための定規が入っていて、定規には何かが何インチかを知ることができるようにインチ目盛が付けられていました。それから、なにか特別なことを青、赤、緑で書くために使う青鉛筆、赤鉛筆、緑鉛筆が入っていました。これらすべてが特別なケースの小さな溝に収められていて、プツンと閉めることができるようになっていました。そして、それらはみんなプーのためのものだったのです。
(注)HB、B、BBは鉛筆の芯の硬さを意味するもので、HBは普通の硬さで筆記用に使われ、B、BB(2B)となるに従い柔らかくなって描画に使われることが多い。
「わぁ!」とプーは言いました。
「わぁ、プー!」とイーヨー以外のみんなが言いました。
「ありがとう」とプーは唸り声をあげました。
しかし、イーヨーは「この筆記用具。鉛筆とそれ以外のもの。過大だな。自分の意見を言わせてもらうなら。つまらんものだ。中身がない」と、独り言を言いました。
そのあと、みんなが「さようなら」と「ありがとう」をクリストファー・ロビンに言ってから、プーとピグレットは、金色の夕暮れの中を深く思いに浸って歩いて家に帰りました。そして、長い間二人とも黙っていました。

「明日の朝、目を醒ましたときにさ、プー」と、ついにピグレットが沈黙を割りました。「最初に、自分になんて言うのかな?」
「朝ごはんはなにかな?」と、プーが言いました。「君はなんて言うかな、ピグレット?」
「自分なら、今日はどんなエキサイティングな日になるかなって」と、ピグレットが言いました。
プーは感慨深げにうなづきました。
「おんなじだなぁ」と、彼は言いました。
「そして、どうなったの?」と、クリストファー・ロビンが聞きました。
「いつのこと?」
「次の日の朝」
「しらないなぁ」
「考えてみて、ぼくとプーに教えてくれる?いつか」
「もしもどうしてもっていうなら」
「プーがそうして欲しいんだ」とクリストファー・ロビンが言いました。
彼は深いため息をついて、くまのプーを彼の後ろに引っ張りながらクマを足でつかんでドアのところまで歩いていきました。ドアのところで振り返って言いました。
「ぼくがお風呂に入るの見に来る?」
「たぶん」と私が言いました。
「プーの鉛筆箱は僕のよりも良いものかなぁ?」
「ちょうどおんなじものだよ」と私は言いました。
かれは頷いて、それから出ていきました。・・それから、少しして、彼が階段を上がるときに彼の後ろで、くまのプーが階段にドン、ドンとぶつかる音を聞きました。

(おしまい)
