
三浦綾子 「奈落の声」(「病めるときも」収録短編)読んでみた
「氷点」や「塩狩峠」で知られる作家、三浦綾子。60年以上経たデビュー作から晩年の代表作まで、没後25年を迎えた現在も多くの読者に愛される、昭和平成の日本文壇を代表する言わずと知れた大大大作家。ファンの推し活も極めて盛んで最近は #綾活 という公認ファン活動が始まっています。

遅ればせながらX(Twitter)のスペースを用いて2024年11月11日に行われた #綾活 「しゃべり場」第一回を拝聴しました。テーマは「病めるときも」収録の【奈落の声】という、マニアックな短編一本! のはずなのに表示される時間は1時間30分超。バグかと思いました。世話人である三浦綾子記念文学館の難波さんも、お集まりの皆さんも本当にどうかしています。
【スペースのアーカイブはこちら】
https://x.com/i/spaces/1OyKAZBZmRLGb
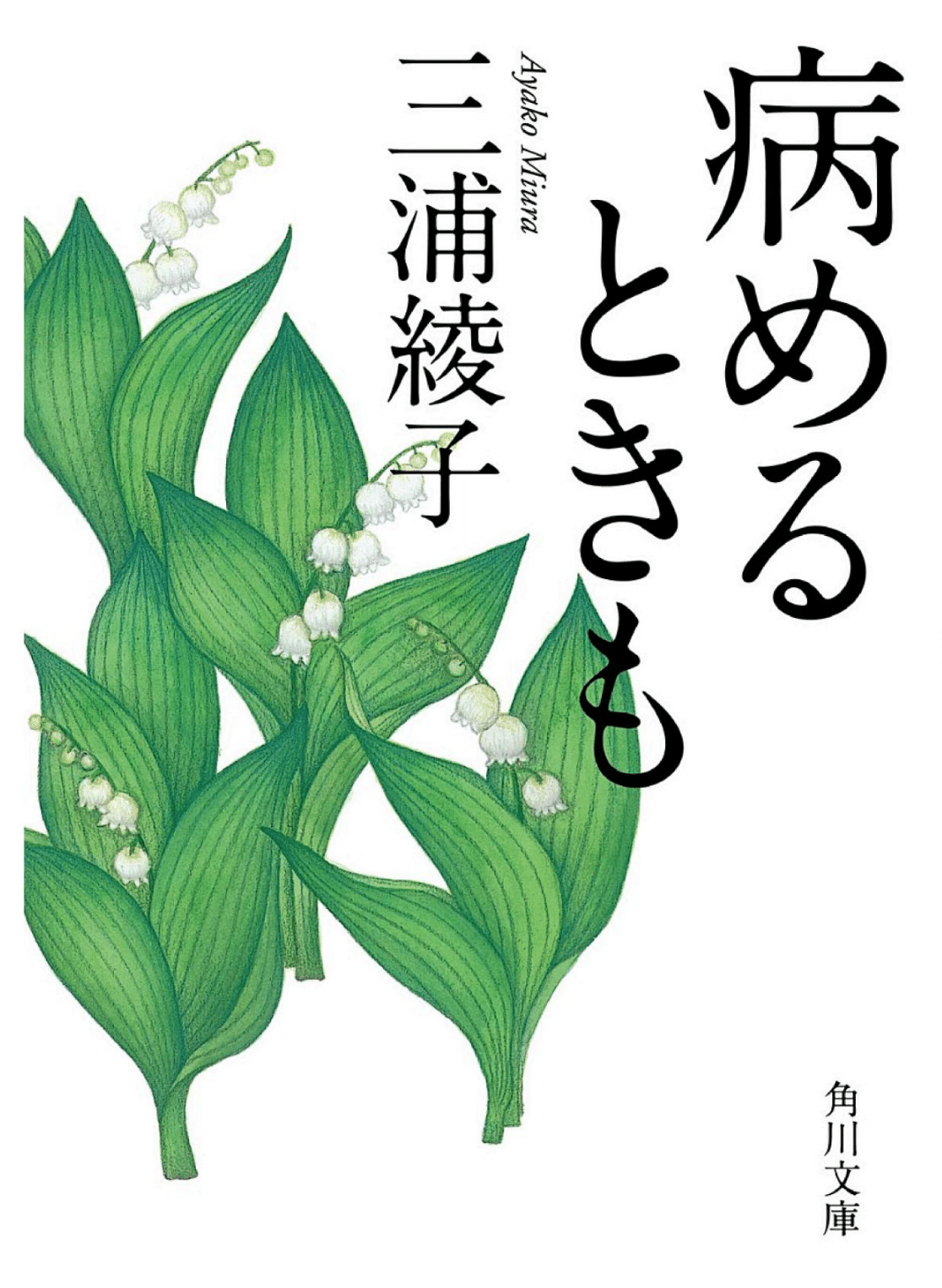
第1回ということでもあり皆さん探り探り語り始める空気感がとても良く、なにやら素敵な推し活イベントの誕生に立ち会えたようなワクワクと陶酔感に浸っちゃいます。というのも束の間、一発目から「なんちゅータイトルつけるんだ」というご感想、頷きすぎて首がもげそうになりました。本当にそうですよね。なんちゅータイトル。『奈落の声』。奈落につき落とされた誰かの声なのか、奈落の底でうごめく何者かの声なのか。
ラストシーン、清志少年の絶叫「かあさーん!」も、橋のたもとで引きずられながら虚空に向けて発せられるわけですが、これはまぎれもなく奈落に落ちていく者の声なんでしょうし、清志の父が発する言葉のひとつひとうも、奈落の底の先住人の、度し難いそれであるとも受け取れます。
なんてしっくり来るタイトルなんでしょう。などと思いながら皆さんのお話を聞いて、まるでリアルタイムに参加しているような気持ちで頷きながら、笑いながら、驚きながらの90分、私なりにも感じることを書き留めながら聞いていたので、ちょっとまとめてみました。
(追記:書き終えてみると5,000字を超えてしまい、減らそうと推敲したら6,800字に増えてしまいました。活字中毒でもない限りここから先読まない方がいいですマジで)
個人的な感想を書き散らかしただけです。「です!」と断言するような書き方してますが、本当に個人の感想ですからね!感じ方は十人百色!
◼️登場人物たち
スペースでも深掘りされていましたが、まずは登場人物ですよね。この短い物語の中に登場するキャラクターたち。
普段の三浦作品ではとても丁寧に、じっくり文字数が使われる人物描写ですが、『奈落の声』は短編の割には登場人物が案外多く、さらに限られた文量であるにも関わらず見事に人物像が描き分けられ、さらに良い塩梅に読者の想像力にも委ねられており、やっぱり綾子さんすんげぇな、と改めて感じさせられます。

◼️沢野清志
なんと言っても主人公の清志少年です。旅一座という特殊な生育環境にあって、母に捨てられ、父の不貞を毎日目の当たりにし、あまつさえ母との別れの場面を来る日も来る日も演じさせられ、しかもそれを褒めちぎられる地獄。物語冒頭から既にぶっ壊されていたといっても過言ではない清志少年。
とはいえこの時点では既に、幼いながらも諦観の境地にもあって、言葉は悪いけど時代的によくあったであろう地の底すれすれ、奈落の底の超低空飛行のような暮らしを続けていく「はず」だったんですよね。気の毒ですが、何せ昭和15年ぐらいのお話ですから。
ところがマキコの登場によって清志が失っていた、諦めていたはずの灯りが目の前に差し込んでしまう。
そんな小さな光を求めてしまった、細〜い糸を掴んでしまった、そして砂上の楼閣(それどころか砂の楼閣)に登ってしまった清志少年が最後の最後、些細なことで再び奈落の底に叩き落とされてしまうという綾子ワールド。
これは清志が単に奈落の底に戻ったわけではなく、おそらくこの先の人生でまみえると思っていなかった「希望」を見せられてからの再転落であることが、清志少年をして「駄目だ、駄目だ!=もう駄目だ」と思わせる「もう一段階上の絶望」が与えられてしまったんだと思うんです。
これはスペースにご参加されていたマイさんがおっしゃるとおり「バッドエンド綾子」の中でも異質のバッドエンド。
他の作品は比較的平穏な、幸せな(幸せを取り繕った)状態が、小さな綻びから少しずつ壊れていき、最後に完全な瓦解を迎えるパターンが多いのでしょうが、「奈落の声」は冒頭最下層からはじまって、ちょっと上らせて再び落とされるという、窒息でもがき苦しむ深海で灯りを見つけ近づいたら深海魚にパクッといかれた感じ。最悪じゃないっすか。
これは三浦ホラーのトップクラスのブラックエンドだと思うんですよ。特に救いになるようなことも描かれていないので「この後清志にはいいことあるかもね」とはちょっと思えません。たぶんその後の清志くん、数日泣き暮れたあとにまた元の奈落の底に戻っていると思うんです。またいつか砂の楼閣に(落ちるために)登らされてしまうのは数年後か十数年後か。もしくは傷を負ったまま旅役者として生き、いつしか忌み嫌った父のような人生を歩んでしまうのではないでしょうか。悲観的すぎるかな。
◼️高津真樹子
一方マキコは意外と評価が分かれるような気がするのですが、マキコの登場(大通りでのアイスキャンディーのくだり)の仕方って、三浦文学では最後まで「正しめの好人物」であることが多いような気がするんですよね。ちゃきちゃきして物おじせず、深い思いやりのある心根、みたいな。何より三浦作品では“えくぼ”がある時点で良い人確定です。
そのマキちゃんに最後の最後であの台詞を吐かせたこと(あの役割を与えたこと)ってのはとても意味が大きいと思うんです。
それは信頼してた教師が裏切った、実は大した人間ではなかった、悪い大人だった、ということでもなく、こういう人のこういう言動であっても「結果的にこうなることもあるよ」ということなんだと思います。
ブラウスが汚れたことで清志の気を病ませたことも、最後のセリフであっても、マキちゃん自身は当然なんの悪意もないし過失と言える過失でもない、もし私が同様の場面にでくわしたとき理想の言動ができるかというと、絶対にそうはならないです。
同じ三浦綾子作品の「泥流地帯」でも描かれた、武井シンの「うちらは心掛けが良かったから泥流に遭わなかった」的なセリフと共通するものがあると思うのですが、泥流地帯でもシンが単なる嫌な奴、悪い奴として描かれていたというよりは、綾子さんも含め読者、それどころか総ての人間が避けることのできない本質として描かれていたような気がするのです。
もし「泥棒でも〜」のセリフを、清志が「まあうちの父さんに育てられりゃ普通はグレるわな」と、一般論として受け流せば(そんな4年生イヤですが)、マキちゃんの「罪」は顕在化することはなかったはずです。私もそうですが、読者の中でマキちゃんのあのセリフが出た瞬間に、清志の深い絶望とラストシーンを想像できた人は少ないと思うのです。続く清志のセリフが「まあ、そうだわな」的なものでも案外違和感なく進んでしまったのではないでしょうか。
それはつまりマキコ(のセリフ)が絶対悪なのではなく、結果からみた悪(罪)でしかないと。泥流地帯のシンのセリフも、人(状況)によっては大したことではないし、または深い傷を負わされてしまう。ただ、それは避けられるようなもんではないよ、その悪(罪)とともに我々は生きていかなければならないんだよ、という示唆があるのだと私は感じています。
◼️沢野清十郎
清志の父親も(ところで父の名前「清十郎」なんですね。無駄にかっこいいです)、後の三浦作品の小者や悪役たちの原点のような、いや〜な人物なのですが、これはこれでなんとも言えない小者なりの悲哀も描かれているんですよね。
生業である旅一座としての生き様を行く先々の学校で蔑まれ(もちろん小者が故の卑屈な受け止めによる自爆なのですが)徐々に歪んでいく様子なんかは、なんだかあまり手放しに批判するのもなんだな、という気もしてきます。
一方では同じダメ親父だとしても現代のダメ親父とはちょっと風合いが違うというか、これはいつも思うことなんですが、この作品に限らず、当時の小説など創作物の「悪い父親」って、現代のそれと比べて「言うほど悪い奴かね」と思わされることが少なくないんですよね。
きっと現代(ここ20〜30年?)の「悪い父親」の必須条件て「家族に対する無関心」だと思うんです。そうすると清十郎パパは清志とも結構コミュニケーションとろうとしていますし、数日に一度の編入もいちいち学校に連れて行ったり(成りすましで一座の者に行かせそうなものですが)、清志が居なくなったとなれば町中を走り回って探したりするんですよね。見つけてぶん殴りますけど。まあ清志は看板役者なので「金の成る子」として大事にしていたと見ることもできますが、楽屋や駐在所の場面など良し悪しはさておき清志に対しては父として向き合っているような気がします。
今どきのガチな毒オヤジ像を描くとしたら、絶対こうはならない。もちろん綾子さんの意図としては最悪の父親として描かれているのでしょうから、そう読ませてはいただくのですが、範馬勇次郎がなんだかんだ言っても結局子煩悩なのと同じように(伝わらなくてもいいです)ブレちゃうというか、いつも引っかかっちゃうんですよね。これは三浦作品に限った話ではなく、国内外問わず近現代文学を読む上での深刻な悩みでもあります。
◼️銀子
あと皆さん銀子ってどう解釈されてるんでしょう?何者なんですかねあの人(笑)
背が高く普段はむっつりしているのに舞台上では誰よりも艶やかな笑顔を見せ、清志を気味悪がらせ(ひどい)る銀子さん。「旅一座で踊り子をしながら夜は講義録で勉強する若くてスタイルが良くて陰のある女子」なんて設定、普通モブには使わないですよね。
といいつつ17歳の春美の「清志ちゃん、抱いて寝てあげようか」という直球のセクハラに「何いってんの、子供と寝たって、しようがないじゃないの」と突っ込み、さらに春美の「そうでもないわ。しようがあるわよ」という目も当てられない返しに(踊り子三人で)ゲラゲラ笑う描写がありますから、訳ありクールビューティーに見せかけて下ネタの感性はおっさんです。
さて真面目に考えると、そもそも旅一座のメンバーはどういう境遇なんでしょうか。座長である清十郎でさえ前述の扱いであったのなら、一座の役者、ましてや若い踊り子などのヒエラルキーどうであったか、想像に難くありません。割と能天気に踊り子生活をしていそうな春美に対し、銀子は勉強を続け、いつかこの境遇から抜け出そうとしている様子が伺えます。
やがて一座の中で夫婦にでもなり家族を築くパターンもあるのでしょうが、若い踊り子三人衆は少なくとも親が健在であって帰る実家もあるとは考えにくいですよね。東京に戻っているときも清志家族は祖父の家へ、他のメンバーはいつもの安宿に、とありますし。
さて、この物語自体、清志少年の深い絶望がテーマになっていることは間違い無いのでしょうが、一方の銀子さんはどうなのでしょう。親兄弟を既に失っているのか、口減らしに出されたか(貧乏旅一座に金で売られた、ということは無さそうですが)。
「母に」捨てられた清志少年ですが、銀子さんは子供時代に「両親に」捨てられた可能性も高いわけです。
加えて座長の息子で看板役者でもある清志に対し、銀子はなんの後ろ盾もなく、若くてスタイルの良い旅一座の踊り子という、正直(考えたくもありませんが)性的な防衛力さえ皆無の状態で旅をしています(料理屋と弊業の劇場、なんて描写も不穏な気持ちにさせられます)。
これも春美のように明るく暮らしているならまだ救いはありますが、「抜け出したい」と思っている(講義録で勉強してますから)人間にとってはまさに地獄でしょう。
この、よくよく見ると主人公より条件の悪いキャラクターがいて、それ自体はまあよくあることなんでしょうけど、それがモブのはずなのにプラスアルファの描写をされているということは、どうしても私の綾子菌に冒された脳が「これ何かあるよ!」と警鐘を鳴らすんですよね。
結局人間の幸せも不幸も、その人の立ち位置、見方、見え方でどうとでも変化するもんなのだ、絶対的な悪も絶対的な善もないように、幸も不幸もあなたの生き方にかかっているのよ…みたいなペラいことではないにせよ、綾子さんが物語に何か含めているような気がします。
銀子が清志に対して手放しに同情したり可愛がったりしないのも、そういうことなんじゃないかなと。この辺はいつかもっと読み込んでみようと思います。
◼️衝撃のラストシーン
そして、そしてですが、なんと言ってもあのラストシーンです。
他の三浦作品(のブラック群)ではだいたい主要キャストの何人か、または全員が絶望し、転落し、破滅し、もしくはそれらの未来が示唆され、仲良くバッドエンドに向かっていくのですが(最近「積木の箱」読みましたがあれも大概でしたよ)、この作品では清志だけなんですよね。
親父は家に帰ったら清志をぶん殴って酒をかっくらって愛人の膝で寝るんでしょう。昨日、一昨日と同じ生活です。
もちろんマキちゃんは(たった1日だけ受け持った)生徒をイメージどおりに慰められなかったことをある程度悔やむのでしょう。しかし彼女はラストシーンの清志の慟哭に込められている深い絶望も知り得ませんし、ある程度事情を知っていたとはいえ教師をしていれば星の数ほど向き合うであろう「よくあるしんどい家庭」の一つとして遠からず心も整理され(そうしないと教師なんてやってられないでしょうし)、その他大勢の受け持ち生徒の笑顔のため、今日も明日も元気に教育に勤しむでしょう。
一座のメンバーも「清坊、最近調子あがんねぇな」ぐらいのものでしょうし、洋服屋の店番娘や警察官など言わずもがな。清志以外の登場人物は冒頭とラスト、さらにそれ以降では(この物語に起因する)さしたる変化はないはずです。
たった1日、2日の出来事で、ただ一人清志少年だけが、地の底からつまみ上げられ、そして叩き落とされる。
父が女をつくらなければ
母がアイスキャンディーを頼まなければ
近藤のオヤジがアイスキャンディーを押しつけなければ
同級生が連れションに誘われなければ
首におしろいが残っていなければ
中年の教師に立ちションが見つからなければ
マキちゃんがその現場を通りかからなければ
ブラウスに鼻水をつけなければ
一円で買えるブラウスが見つからなければ
店番が居眠りをしていなければ
父が店の前を通らなければ
清志が逃げ出さなければ
警官が清志を信用してくれれば
父とマキちゃんが喧嘩しなければ
どれか一つの「れば」があればラストシーンは成立しないのに、たった一人、清志を叩き落とすためだけに、複雑で膨大な手順を踏み、ほぼ全ての登場人物に何かしら関与させるという念の入れように、ちょっと怖さも感じるほどであります。
◼️救いはなくても
で、このラストシーン(というかこの物語)に救いはあるのかどうかっていうと、私個人的には「ない」と思っておりますし、それが悪いことではないとも思っています。何か学びを得る必要もありませんし、読後感としては「ぅわお!!!」でいいんだと思います(もっと言えば「ぅわおwwwちょwww綾子さんwww」でいい)。
これは物語の舞台が「K町」となっていることも無関係ではないというか、綾子さんいつもはあまり架空の地名出さないですよね。石狩平野から東に40分の炭鉱街だとか、「美唄、上砂川ときて今ココ」だとか、長ヒョロいだとか、東西結ぶ幹線道路を縫うように川があるとか、まあどう考えても歌志内で、綾子さんの教員時代の原風景なんだろうなと思わせつつも、昭和15年という場面設定で(「皇紀2600年を祝う〜」とあるので)人口2万人に満たないなどとぼかしたり(実際は当時3万人を軽く超えます)、「K町」表記としたり(昭和15年ならちょうど綾子さんが勤務していた歌市内の「神威小学校」のKだったりして)、いろいろモザイクをかけています。
こういう時って実在の地域に負のイメージを与えないための配慮がある場合だと思うんですよね多分(三浦マニアたちは易々と「ああ、歌志内ね」とモザイク突破してしまうわけですが)。つまり綾子さん自身、物語自体が「負(陰)」という認識なんだと思うんです。
だからこの作品についても、読者は特に秘められた教示も救いも見出す必要がなく、普通にネガディブで、でも何故かわからんけどめちゃ記憶に残るわ〜、という作品として読んでもいいような(と綾子さんも言っているような)気がします。
◼️三浦文学の奥深さ
そんな感じで「で、結局どういう話なの?」と聞かれるとちょっと返答に困ってしまう名著で難著の『奈落の声』ですが、全国屈指の三浦ファンが90分語っても足りないほど、「ちょっとこれどういうこと⁉︎」という読者の戸惑いなど綺麗に吹き飛ばすほど練り上げられたストーリーですから、これを機会に「あら私も読んでみようかしら」と文庫や電子書籍を手に取ってくれる人が増えるのは本当に素晴らしいことですし、そうなることを祈るばかりです。もちろん「三浦綾子はじめて読むんです〜」だとしたら「や、君ちょっと最初は別の読まないか」と言いますけどね普通に。
何せこの作品を第一回のテーマにチョイスした三浦綾子記念文学館難波さんのご慧眼、すごいを通り越して「凄くすごい!」ですがとにかく、今回再読する機会を得たことと、皆さんのお話をじっくり聞けたことで、より深く深く読み込むことができ、楽しむことができ、三浦文学の厚みをあらためて感じさせていただくことができました!ありがとうございました!!!
