
本土決戦に備えて実際に軍が発注した「槍」と、その槍が戦後に引き起こした「槍裁判」ー長野県出身者絡みであり、さらに情報求めます!
かなり昔に古本屋で格安で購入した「大東亜戦史」(全10巻、富士書苑。1979年発行)、棚に突っ込んだまま読んでないなと思って、何の気なしに「国内編」を開いたところ「槍裁判」という項目が。そそられて読んでみますと、岩手県盛岡市の話題でしたが、当事者が長野県人! ということで概要を紹介させていただきます。
なお、この項の記述に当たり、盛岡市先人記念館やご親族の御協力で「大東亜戦史」の記述の誤り(特に名前)を正し、補足を入れて、当事者となった平出新蔵の奮闘を記録させていただきます。関係者の皆様に感謝申し上げます。(この項、敬称略)

「大東亜戦史」は、「従軍記者が伝える報道文学の決定版」と添え書きがあり、国内編は従軍記者ではありませんが、いずれも当時取材活動をしていた人たちによる記録集となっています。「槍裁判」は鈴木正七が担当、執筆当時の肩書は元日本新聞協会編集部、となっていました。

さて、この「槍裁判」、実は戦後の話ですが、まずはその発端となる敗戦までのあらましを紹介させていただきます。
主役の平出新蔵(大東亜戦史の「平田伝蔵」は誤り)は、「盛岡の歴史を語る会」刊行の「続もりおか物語・河南編」とご親族によりますと、1894(明治27)年、長野県諏訪郡境村(現・諏訪郡富士見町)に生まれ、17歳の時に信州鋸の行商で全国各地を回る中、大正時代に「盛岡の人情風俗が一番気に入り」(続もりおか物語)、南部鉄瓶などで知られる同地に落ちつきました。
1923(大正12)年「平出金物店」を創業。家庭金物、建築金物、大工道具等を販売しており、1930(昭和5)年に「平出合資会社」を設立し、亜鉛板、銅板、釘、針金などの扱いも始めます。この間、忙しいからと故郷から弟の貢も呼び寄せ、1935(昭和10)年には支店も設け(このころ貢が「平出貢金物店」として独立)るなど、着実に業務を拡張していました。
◇
このようにそこそこの成功を収めていた1944(昭和19)年の夏の終わりごろ、平出新蔵に陸軍の弘前師団から「本土決戦用突き棒」と称する槍3,000本の製作発注がありました。既に兵を召集しても渡す小銃はおろか銃剣まで不足していたという事情があったのです。が、中の人としては、具体的に軍が槍を発注した事例は初見で、驚きでした。
一方、平出新蔵は既に物資不足で鉄瓶など作っていられる状態ではなかったため、この注文に力を籠めることとしましたが、人を突く武器なので「鋼」の支給を要求しました。「これは当然の話である。鋼の入らない刃物では、いわゆるなまくら以外のなにものでもない」(大東亜戦史9)からでしたが、「鋼の支給は現状においては全く不可能なるにつき、手持の鋳物にて製造されたし」(同)との回答。そこで平出は「俺も金物で30年を立て通してきた。軍がそれだけ困っているなら、鋳物だけでも突棒を作りあげてお役にたてよう」(同)と作業に着手。穂先も20㌢から40㌢とばらばらでしたが、2カ月で1230本を作り上げます。
1944年11月、弘前師団に平出が持ち込んだ「槍」は鋳物の穂先が30㌢ほど、柄の長さ150㌢余り。弘前師団兵器部長・白井大佐は兵器部員・新藤大尉を呼んで3人でしばらく話し合い、ともかく使えるか試そうと司令部裏庭の標的のところへ。標的は2本の丸太の間に60㌢四方、厚さ30㌢ほどの藁束へズックを被せた銃剣術用。新藤大尉は型どおりの正確さで1歩進めて標的の真ん中に突き棒を突き出し、同じ力で元の姿勢へたぐりよせました。
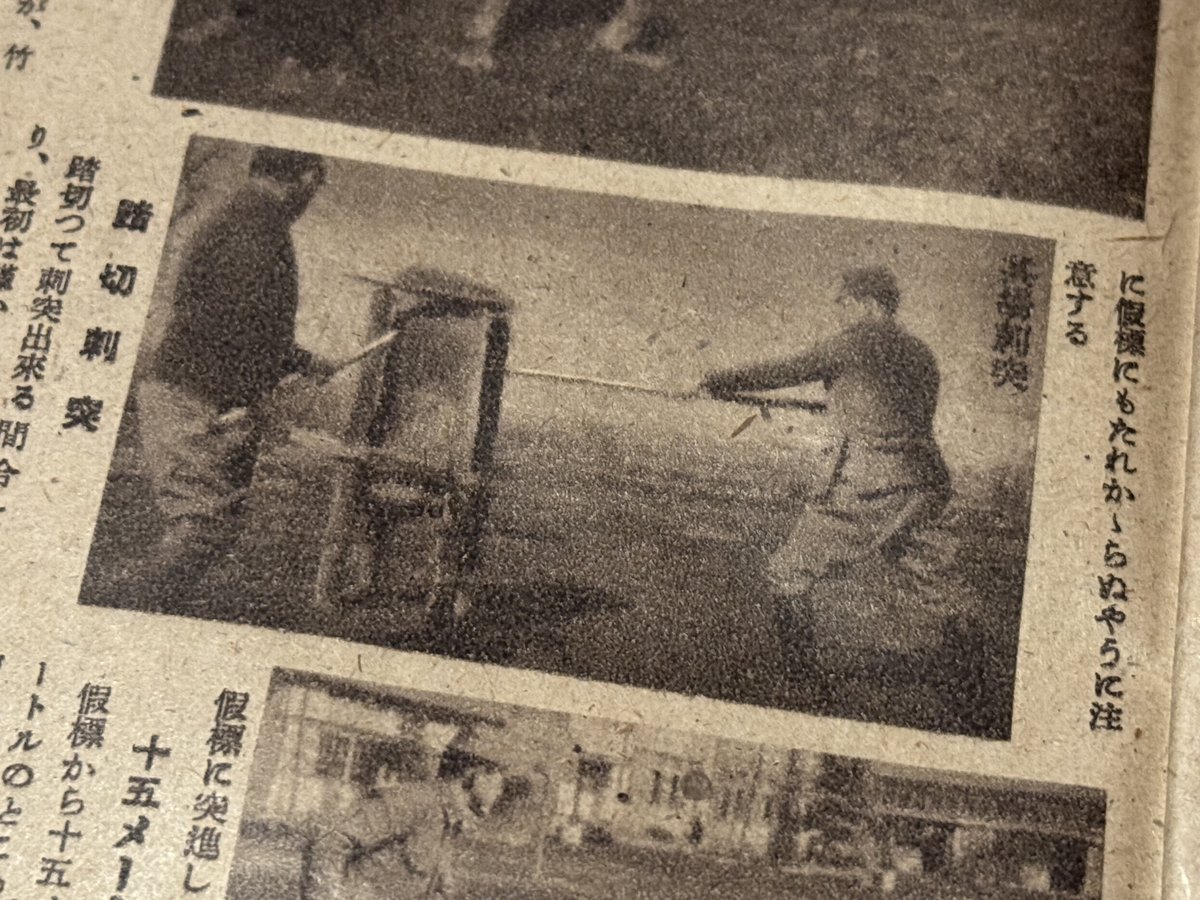
しかし、この一撃で「槍」の穂先は1-2ミリほどまくれあがってしまい「わらの標的にさえまくれるようなチャチなものでいったい人間が突けると思うか。竹槍なら豚を突けるが、こんななまくらでは、豚も突けはせんぞ。こんなものは兵器として役にはたたん。だめだ。即刻持って帰りたまえ」と白井兵器部長は率直にいい切りました(大東亜戦史9)。鋳物だけでこれ以上鋭利にするのは不可能として「槍」1230本は平出が倉庫にしまいました。
盛岡市の南部鉄器協同組合によりますと、南部鉄器で鋳物のペーパーナイフは作られていますが、紙を切ることしかできない、それ以上鋭利なものはないとのことで、鋳物だけでは無理だったことを裏付けてくれます。
◇
さて、行き場がなくなっていた「槍」も、1951(昭和26)年2月、新潟県三条市との刃物屋との間で処分が決まって運送屋に出します。ところが荷馬車が駅前に付いたところで警官に見とがめられ、見た目は槍だと差し押さえられて、荷主の平出新蔵が盛岡警察署に呼び出されます。盛岡署では銃砲等所持禁止令にあたるとし、平出は目の前で穂先を曲げてみせ戦時下のいきさつも説明し槍ではないとします。しかし、盛岡署は禁止令違反として書類を検事局に送ります。検事局では予審の末、担当した小山検事が全国的にも類例がないので、略式裁判による罰金納付で済ませないかと持ち掛けます。
しかし、平出は「納得できないまま罪の汚名を着たくはない」とまたも一徹なところを見せ、検事も槍とみとめられるかどうか迷って居るとしつつ、法廷でということになります。これが「槍裁判」です。
盛岡地裁での裁判では、くだんの白井元大佐が証人に立ってくれるほか、警視庁で禁止令の制定にかかわった島岡警視も刀剣ではないとの証言をしてくれるはずでした。ところが、島岡警視は「明らかに刀剣類」と逆の証言をします。島岡警視の翻意は、警察のつながりゆえだったのでしょうか。裁判長は、サーベルについて尋ねると島岡警視は兵器と答え、白井元大佐は指揮刀は兵器ではなく被服と証言します。求刑は懲役3年罰金5万円というこちらも過酷なものになりましたが、同年秋、無罪判決が下ります。サーベルが兵器でなければ、突き棒はただの金物との判断でした。
しかし、検事は仙台高裁に控訴します。それでも平出新蔵は意気盛んだったということです。(同)
◇
「槍裁判」の結末はどうなったか。「大東亜戦史」は初版が1953(昭和28)年のため、書かれた1952(昭和27)年の時点では2審の結果が出ていなかったせいで記述がありません。平出新蔵のその後も不明。そこで、中の人は南部鉄器協同組合、盛岡市教育委員会、それに盛岡市先人記念館に問い合わせてみました。いずれも「槍裁判」のことはご存じありませんでした。
その後の平出新蔵は「もりおか物語・河南編」によりますと、1954(昭和29)年に「新和建材(株)」を設立し、土木建築資材、セメント、鋼材などの販路を拡大、1964(昭和39)年ごろに亡くなります。平出金物店は同社の金物部となりますが、昭和50年代には閉店。現在、弟が開いた平出貢金物店を、2代目の平出喜加夫が経営しています。
◇
戦時下の「槍の発注」があったという事実と、兵器失格とされた「槍」が今度は刀剣として敗戦後に裁判になったという、ねじ曲がった解釈に翻弄されながらも、そのたびに一徹な姿勢を示して意思を貫いた信州人がいたことは、記録しておきたいと思いました。もしこのnoteを読まれ、何か分かる方がおられましたら、メールなどいただくとありがたいです。
いいなと思ったら応援しよう!

