
【ニッポンの世界史】#20 戦後の「世界史全集」ブームのゆくえ
出版ジャーナリズムが世界史をダメにした?
これまでたびたび紹介してきた歴史学者上原専禄は、1950年〜60年代までの世界史に関連する出版物の変遷について、次のように評しています。
このように、戦後二十余年にわたる変遷を展望すると、世界史ジャーナリズムというものが、当初、企業の私的利益と国民の公的な文化要求とを少くとも調和させようとする積極的姿勢のもとに始まり、次に、1960年を間にはさんで、一方では読書と思索における市民的自由を尊重し、他方では執筆における学問の自由を保障するたてまえのもとに出版が行なわれ、最近——殊に1967年以後——は、私的な企業利益の露骨な一方的追求をジャーナリズムの特徴とするにいたったことが、はっきりわかる。
この1969年に書かれた論考で上原がここで批評の対象としているのは、古代から現代までをカバーする「世界史全集」のことです。
全集といえば、「世界文学全集」や「百科事典」が刊行されるようになるのは、戦前の大正時代からのこと。新潮社の『世界文学全集』(全57巻、1927〜32年)は1冊1円の「円本」と呼ばれ、百科事典では平凡社の『大百科事典』(全28巻、1931〜34)が、戦後の『世界大百科事典』(1955年)の前身として好評を博しました。
その後、戦中にいったん排除された西洋の著作は、戦後の「教養主義」のなかで敗戦後続々刊行され、さらに高度経済成長に入った1960年代になると「百科事典ブーム」が巻き起こります。各家庭の書斎や居間に百科事典が鎮座する光景は、ある種の大衆的ステイタスとなりました。
・1961年 『国民百科事典』(全7巻、平凡社)
・1962年 『日本百科大事典』(13巻+別冊、小学館)
・1965年 『現代新百科事典』(全6巻、学習研究社)
・1965年 『世界原色百科事典』(全8巻、小学館)
・1967年 『大日本百科事典ジャポニカ』(18巻+別巻4、小学館)
世界文学全集を定期購読していたことが、実家の酒屋の文化資本から越え出る機会となったと回想する文芸評論家の鹿島茂や(鹿島茂『歴史の風 書物の帆』小学館、2009)、実家にあった百科事典を片っ端から読み込んだという実業家の堀江貴文(堀江貴文『ゼロ』ダイヤモンド社、2013)のように、そのすべてを読むことなどたいていはできなかったでしょうし、たんなる置き物と化す場合も多かったでしょう。
しかし、こうした「教養」のシンボルが一般家庭にも入り込み、実際にある時期までのあいだ、子どもが世界の情報にアクセスする入口として機能しえたという点はやはり重要です。
こうした中、出版社は歴史学者や作家を監修者・執筆者にたてて、さまざまな世界史全集を企画します。
上原はこれらを「資本主義的生産の仕方にしたがって一つの商品として生産されるジャーナリズムのかたちにおいて、大衆の前に提供され」る商品、すなわち「世界史ジャーナリズム」と呼んでいます。マルクス主義と距離をとっていた上原の思考に沿えば、要するに「世界史をテーマとした、一般向けの「売れる本」」くらいの意味でしょう。
彼の列挙する世界史全集を、「世界史ジャーナリズム」の度合いに従って分けられた彼の整理にしたがい、挙げてみましょう。
1. 「戦後の日本という自覚に立って、世界史の全体像を新しく創り出してゆこうとする熱情にもえるもの」
これらは「売れる本」としての要求を満たそうとするものでありながら、戦後の日本という自覚に立って、「読者大衆の国民としての歴史認識の文化要求に、想像的にこたえようとする姿勢があった」と評価されます。
・1949〜54年 毎日新聞社版『世界の歴史』(全6巻+別)
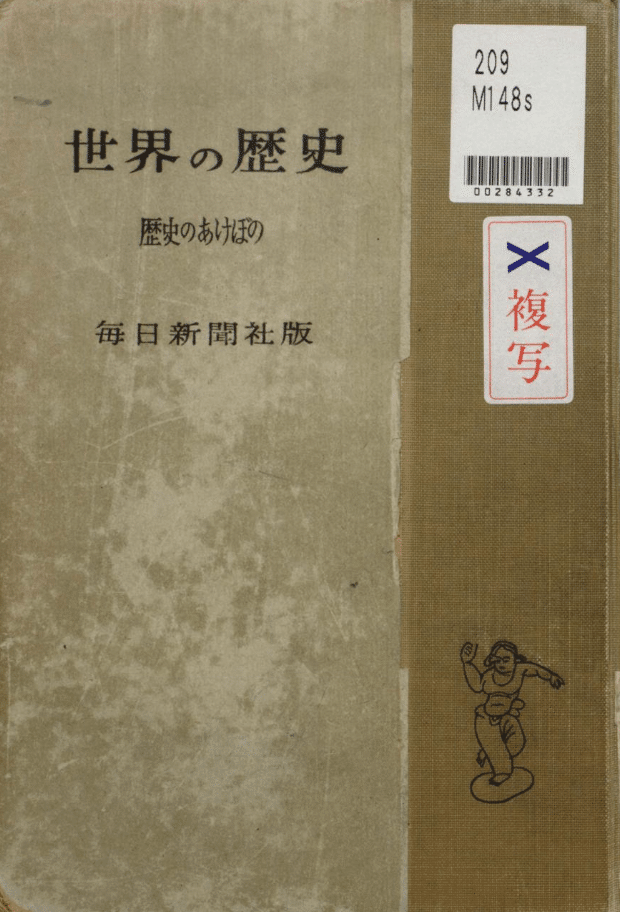
刊行の言葉には「日本人のための最初の世界史」とあり、世界史が、敗戦直後のいまの日本になぜ必要なのかを情熱的に伝えています。
これまでのわが国のあゆんできた道が、ひどく歪んでいたことは、敗戦によって、いま身をもって知らされているところである。新しい世界への出発において、われわれがこれからの道を踏み誤らぬためには、その原因がどこにあり、またいかに間違っていたかを正しく知ることが第一歩でなければならない。歴史のきびしい学問的反省こそ、再建日本の礎石である。
歴史再検討の必要は、今日すでに世人のひろく認めるところであり、その交流は終戦後における著しい現象の一つでもあるが、久しきにわたって植え付けられた誤った見方の根は断ち切られてはいない。学校における歴史教育は混迷の中にあり、戦後書かれた歴史書は少くないが、新しいものはまだ国民大衆となっていないのである。
本社はここに現代史学界の第一線に立つ諸氏の協力を得て、「世界の歴史」(全6巻)を世におくる。その顔ぶれを一見すれば明らかなように、これこそ真実に書きかえられた歴史であり、日本人のための最初の世界史である。全巻に盛り上る学者的良心と平易な表現は生きた国民的文化財であることを実証するものと確信する。
1巻は「歴史のあけぼの」、つまり先史時代に関するもので、江上波夫・杉浦健一・板倉勝正が参加し、人類の出現からオリエント文明の展開までをカバーしています。
2巻は「西洋」の歴史を、古典古代、中世—封建社会、近代—絶対主義の時代・自由主義の時代(〜19世紀)のように、ヨーロッパ的な三区分法にのっとって叙述され、遅れた東洋=敗戦国・日本が、いかに西洋とちがうのかが、底流にあるテーマとなっています。執筆者は
オリエントの国々では人間でありながら神としてあがめられた専制君主が支配して、人民は少しも自由というものをもっていなかった。その社会は、よく考えてみると、昔の中国だとか日本にたいへん似ているところがあって、これから話すギリシアやローマのそれとは非常にちがうのである。
3巻は「東洋」の歴史を、中国・インド・イスラムにわけて古代から近代までの長いスパンがおのおの叙述されます。執筆者は、仁井田陞、松本善海、増井経夫、野原四郎で、注目すべきは最終章の「東洋とは何か」です。ここでは、アジアを単にヨーロッパのネガととらえたり、国策に利用された「アジアは一つ」という単純化が批判され、「むしろ東洋と西洋とは重なりあっていた」(353頁)と、アジアをみる視点の刷新を説いています。なお、日本中世は専制的支配がうすれ「東洋的な性格が弱まっていた」という視点がみられるのは、のちの日本特殊論につながる論点でもあり、おもしろいところです。
4巻が「日本」の歴史を扱っている点は、このシリーズの特徴でしょう。あとがきには「歴史を人民大衆のものとする」と、勇ましく述べられています。執筆は遠山茂樹、石母田正、高橋磌一です。この4巻は第二次世界大戦までの日本を扱っているのですが、最終巻の5巻は、途中で止まっていた2巻の東洋・3巻の西洋の続きを「現代」という区分を設定し、「帝国主義の形成」から扱っています。執筆は、江口朴郎と村瀬興雄です。
このように、現代より前の時代については、西洋・東洋・日本をわけて論じていることから、げんみつには「世界史」とはいえませんが、戦後の不安定な出版状況のなかで、日本国民の置かれた状況を歴史的に考える手はずを用意しようとこれだけの成果をのこした、その情熱を買っているわけですね。
・1955〜56年 東洋経済新報社版『世界史講座』(全8巻)

こちらには『日本国民の世界史』の上原専禄、『世界史の可能性』の尾鍋輝彦、江口朴郎、三上次男、山本達郎と、ここまで読まれた方なら馴染みのある面々が監修者に名を連ねます。
第1巻が「東アジア世界」からはじまる点は、『日本国民の世界史』と共通しています。
2.「モノグラフィーの集録」
新しい目の付け所や研究成果を示したものもあるが、「世界史というものの全体としての動態と構造をどう見るか、という問題」が取り組まれておらず、全体の構成は「19世紀以来のヨーロッパの学界の古びた体型」のままと、厳しい評価。世界史全体に対する視点が足りないという意味で「モノグラフィー」=あるひとつのテーマに関する論考の寄せ集めになっていると指摘されつつも、よく言えば「全体像の押し付け」を避ける「自由主義」的な態度があるともフォローしています。
・1957〜『世界史体系』(全17+別、誠文堂新光社)
・『図説世界文化史体系』(角川書店)
3.「最大限の利潤をあげることが書物生産の目標とされる」もの
ようするに「売れればなんでもあり」の本。「提供される世界史像は、調理の労をはぶくインスタント食品のように、手軽で完成されたもの」になってしまっているとバッサリ。上原が世界史を学ぶ出発点としていた、戦後の日本国民としての生活意識のようなものとは無縁の代物です。
「与えられるもの」としての世界史批判
こうしてみてみると、上原の世界史一般書にとっての目にはきわめて厳しいものがあります。
特に、そういった本を買っているほうではなく、そんな本に加担している学者あるいは研究者は、いわば「資本と出版業者の奴隷」であるとまで言っています。そんな企画がもちあがっても、誘惑されずに断り、ヨーロッパ学界のレディメイドの世界史像をありがたく受け取るのではなく、もっと主体的に「世界史研究の名に値する実証的研究をおこなうべきだ」と。
そのうえで上原は、世界史像が「与えられる」のをただ待っている読者ではなく、世界史像を自分ごととして「つくりだす」ことのできる読者を育てる必要性を主張します。
彼がいちばんの理想とするのは、自分自身の置かれた生活現実を出発点にして、自主的に形成していこうとする読者像です(=読者像(1) 主体主義・実践主義的な読者)。
主体主義的な読者とは「世界史像は…他者から与えられるものではないこと、他者の描いた世界史像はあくまで参考品に過ぎないものなのであって、権威でもなければ典拠でもない」ことを知っている読者のことです(「えらい学者が言っているからといって鵜呑みにしてはいけない」、そう、えらい学者が言っています)。
しかし現在の日本では、そんな読者は「世界史ジャーナリズム」に毒気をかけられ窒息寸前であり、自分で世界像をつくりあげようとするのではなく、受動的で消極的な読者が増えてしまっていると憂慮します。
なにが受け身であるかというと、アジアやアフリカの独立運動を報じる国際ニュースを見て、「かわいそうだ」「がんばってほしい」などと共感し、世界がおおきく変わっているのだから、ちゃんと勉強して時代にキャッチアップしておかないとなあと「取りあえず世界史的現実についての知識を求める」姿勢です(=読者像(2) 客観主義的な読者)。
この姿勢は、ようするにただ単に、「世界情勢の変化への対応」という要請に迫られて受け身的に知識をもとめる知識主義であって、学者の側の「大衆に知識を与えよう」という啓蒙主義と背中合わせとなり、人々の主体性を失わせることになってしまうのだ、と上原は否定的です。
こうして上原が1960年代後半にかけて大勢を占めるにいたったとみる、3つ目の読者(=読者像(3)享楽主義・恣意主義的な読者)があらわれます。
これは単に「面白ければなんでもよい」とばかりに文化財を興味本位を享受しようとする態度で、「小説よりも面白い」変わった事件を、まるで世界旅行に行くような感覚で消費するような姿勢の読者です。
1960年代には歴史小説がブームとなり、エジプト・ブームもありました。人々の関心が困窮した問題情況から完全に離れていったわけではないものの、消費生活の向上に注目の対象がうつっていった時期にあたります。
これについて論じた論考「世界史の起点」は著作集に載るまでは未発表でしたが、安保闘争の幕引きと「所得倍増計画」とともに経済の「季節」に入った日本人の多くが大衆消費社会を謳歌しつつある時代情況を、上原は苦々しく思い、以上のように厳しい批判の眼差しをむけていたわけです。
戦後まもなくから「世界史像」の自主形成にとりくんできた上原の主張には聞くべきところも多くありますし、当時の出版物をみていると、煽情的なエピソードを雑多にあつめた世界史の書籍も目立ちます。
しかし他方で、ここでの上原がいらだつように、知識を「えらい人」から求めようとしたり、歴史に関するコンテンツに接したりすること自体を、レベルの低いモノと位置付けることにも、正直違和感があります。
上原の議論がどの程度あたっているのか。これを知るには、そろそろ1960年代から抜け出し、さらに歩みをすすめ、1970年代の「ニッポンの世界史」の展開を見ていく必要がありそうです。
(続く)
このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊
