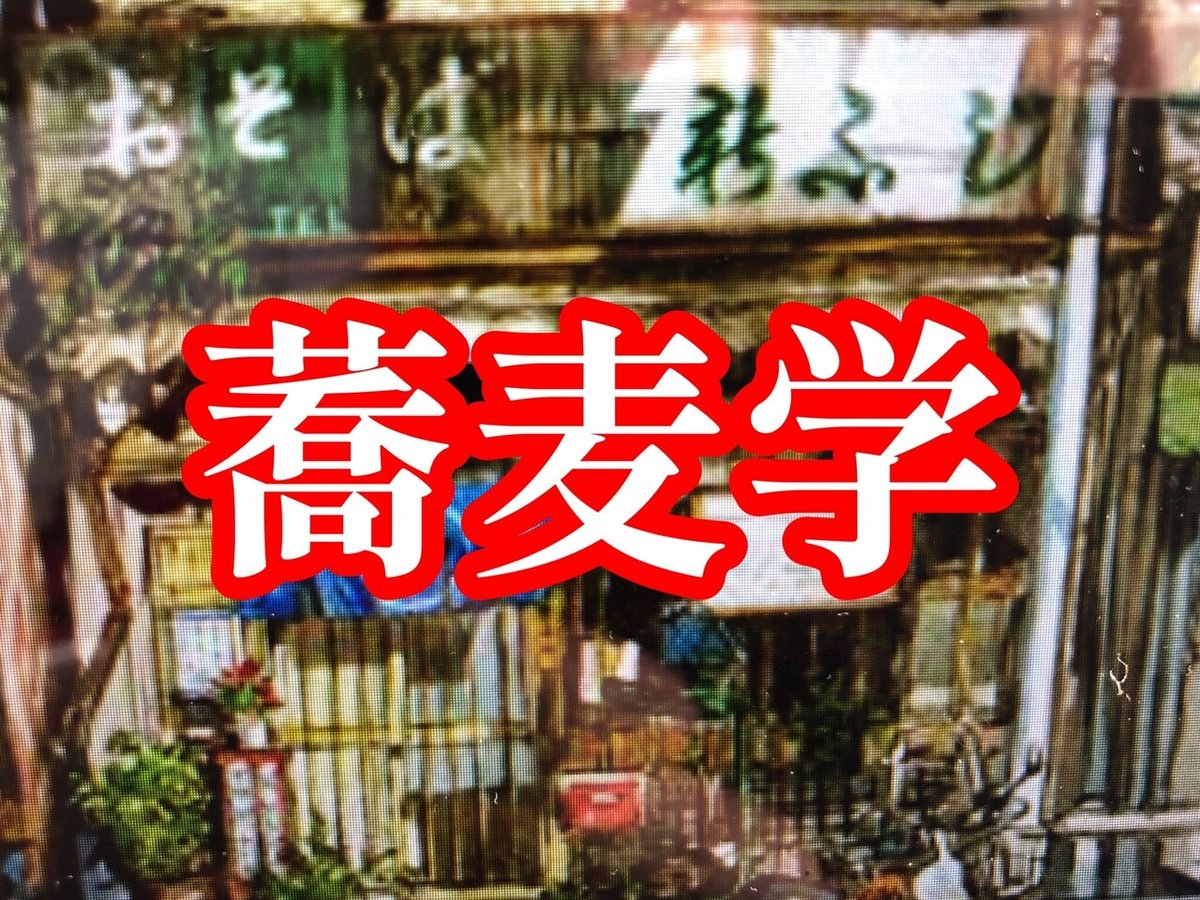江戸時代『節分そば』とは『年越しそば』。2月3日には蕎麦を食べませんか。

節分』と言えば『豆まき』、そして関西一部地域の風習が今や全国に広がった『恵方巻き』などがありますが、江戸時代の『節分』には蕎麦を手繰(たぐ)る習わしがありました。またこの節分に食べる蕎麦を『年越しそば』と呼んでいました。何故でしょうか?

それは、旧暦では二十四節気というものがあります。この二十四節気でいうところの新年とは『立春』の前日である『節分』にあたります。ゆえに江戸時代の人にとっては『節分』が年越しとなりますので『節分』に食べる蕎麦を『年越しそば』と呼んでいました。
またなぜ江戸時代、新年を迎えるにあたって蕎麦を食べたのでしょう?

蕎麦の事典(新島繁著)を調べてみました。
『節分そば』とは
節分は季節の移り変わりの境目で立春、立夏、立秋、立冬の前日がすべて『節分』だが一般的には立春の前日を指している。この日、清めのそばを食べて晴々しく立春を迎える、本来はこの節分そばを『年越しそば』といい『大晦日そば』と区別される。
因みに『大晦日』に手繰(たぐ)る蕎麦を『年越しそば』と呼ぶようになったのは明治時代中期頃からと言われています。江戸時代、月の終わりには蕎麦を手繰(たぐ)る習慣がありました。
商家では月末は集金や棚卸しで忙しかった為、使用人を労(ねぎら)う為に蕎麦を出前し振舞いました。これを『晦日(みそか)そば』と呼んでいたのです。
明治以降、月末を『晦日(みそか)』という呼び方がされなくなり 12月31日だけが『大晦日(おおみそか)』として残りました。

年越しに蕎麦を食べる言われには諸説ありますが、定説は『人生を蕎麦になぞられて細くても長く生きるという願いをこめる』ことです。
蕎麦の食べ方については特に決まった食べ方があるわけではなく、内容等も決まりはありません。

2月3日(立春の前日)の節分には蕎麦を手繰(たぐ)りましょう。
因みに「毎年2月3日が節分の日」と思っている人が多いかと思いますが、それは間違いです。確かにここ30年程はずっと2月3日ですが、実は2月2日になったり2月4日になったりします。(2021年から4年に1度、節分の日が2月2日になります。)