
可愛がっていたイモリが、とつぜん消えた日。生き物を飼う意味について考えた
その日、可愛がっていたアカハライモリの赤ちゃんが突然消えた。
心の準備など、まったくできてはいなかった。ずっと大きくなるまで見届けられると思っていた。
いつもの日課で、洗面台に置いてある水槽を掃除していたときのこと。
赤ちゃんとはいえ、小さな可愛いウンチを沢山するので、すぐ水がよごれてしまう。
それをスポイトで取り除いて水を入れ替えるのが私の役目だ。
しかし、その日はなんだか様子が違った。
水槽で、気配が全くしないのである。赤ちゃんイモリは、体長は2cmをやっと超えていたと思う。
まだ小さいながら、水草にも石の影にも、いつもならチョコンと見えるイモリちゃんのしっぽがどこにもない。
これは、おかしいな…と思って石を持ち上げても、水草を持ち上げても、どこにもいない!
私はショックを受けた。昨日は、まだ、この水槽にいて、ほんの少し頭をもちあげることができるようになったイモリを可愛いなと思ってみていた。
そして、その姿を写真にとったばかりだった。
ずっと、いてくれると思ったのに、急にいなくなってしまった。
もしかしたら朝、息子が何かしたのだろうか……。
突然いなくなってしまったことの理由が分からずに、ショックを受けて、ただただ悲しかった。涙も出てきた。
息子達が学校から帰り、さっそくイモリについて問い詰めると、2人とも何も知らないという。
そこで、ようやく頭をぐるぐるさせた結果、脱走したのかもしれない…という可能性に思い至った。その可能性を思いつくまでもうずいぶん時間が経ってしまっていた。
まだ赤ちゃんだし、エラもあるから、まだまだ水から出て上陸する事はないだろうと思っていた。
まさか6cmほどある水槽の壁を、まだ数cmの赤ちゃんが登れるはずはないと、良く調べずにたかをくくっていた。
イモリは、上陸すればあっという間に脱走するということを、後から調べて知った。
イモリの水槽があった周辺をくまなく探して、お風呂場も探して、隣のリビングの窓際にもいないか探してみたが、どこにもいなかった。
おそらくイモリは脱走して、すぐそばにある洗面台の排水溝に向かってしまったのだと思った。
涙が出てきて、ただただ悲しかった。
自分の知識不足で、イモリちゃんが排水溝に流れてしまったのかもしれないと思うと、悲しくてしかたがなかった。大きく落ち込んだ。
生き物を飼うのは難しい。喜びもあるけど、悲しい事も、それ以上にずうっーーと多いのだ。
それでも息子は、そんなことおかまいなしに、どんどん新しい生き物を飼おうとする。そんなことに意味があるのだろうか。
実の所、私の中では、そんな思いが、息子が生き物に夢中になって以来、ずっとモヤモヤと渦巻いていたのだ。
でも、ようやく、その答えが見つかった気がするので、それについて書いてみたいと思う。

アカハライモリが、うちにやってきた日。
アカハライモリは、長野県の稲倉棚田からやってきた。
イモリをとりたいと息子が言い出して、棚田サポーターとなり5月に田植えに参加した。そこで息子がつかまえた可愛いイモリのオスとメスのペアを、うちにもって帰ることになった。
気がついたら卵が4個ほど生まれていて、そのうち1つだけが奇跡的に孵った。
無事孵ったときは、それはそれはびっくりして嬉しかった。それ以外の卵は、どれもうまくいかなかった。
卵から孵ったばかりの赤ちゃんは、1cmもないくらいの小ささで、うっすら透き通っていて、いかにも頼りなげだった。
それから、毎日のように水槽をながめて、成長を見るのが楽しみになった。
息子から、ママはイモリの世話係ね!と命じられて、エサやりも担当していた。エサは、ブラインシュリンプというもので、塩水につけ孵化させて、磁石で殻を取り除き、塩水から真水に移して…という、おそろしく手間がかかるものだった。
ブラインシュリンプを一生懸命食べる姿や、ひとしきり食べ終えて、お腹がパンパンになり赤くなったイモリちゃんを見ると、私も満たされた気持ちになった。
目立たなかった足と手がしっかりと出てきて、その足で歩くような姿を見せた時。
からだをグッと曲げられるようになった時。
脱走する前日には、しっかりと頭を上げられるようになって、もしかしたら上陸する日も近いかもと思っていた。
でも……
お別れの日は突然やってきた。
自分のせいで、イモリちゃんの命が……と思うといたたまれなかった。
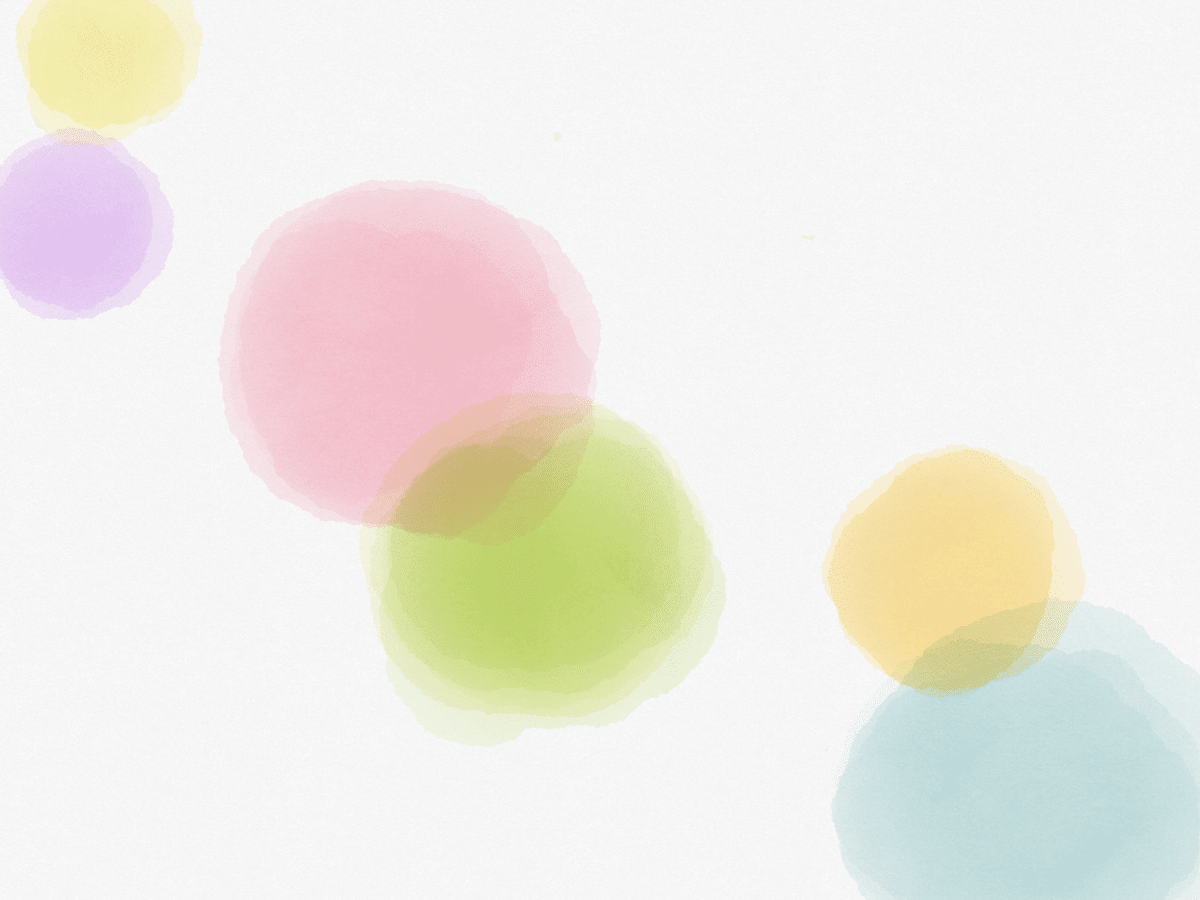
生き物を飼うことは、生と死と向き合う事
でも、こんな悲しい事は、今に始まった事ではない。
うちに大量にいるクワガタやカブトムシ達は、夏が終われば当たり前のように命を終える。
もう多分、なん十匹と……。
家に亡骸が転がっていても、もうなんとも思わないぐらいに私は鈍感になった。
先日は、息子が近所の用水でとってきた、ドジョウや魚が入った水槽で、何かの病気が発生したのか、4匹中、3匹がバタバタと召されていった。
先日卵から孵ったカナヘビの赤ちゃんも、2ヶ月ほど元気にしていたけど、急に餌を食べなくなり、眠りについてしまった。
とっても可愛かったから、このときもツラかった。
早く放してあげていれば……と、後悔はつきない。
やっぱり、そういうときはいたたまれなくて、どうしてこの子達をうちにつれてきてしまったのだろうか……と息子を責めるような気持ちになってしまう。
うちにこなければ、あの用水で元気にやっていたんじゃなかろうかと思うとつらい。
だから、できるだけ持って来ないようにしようね、という気持ちなのだけど、息子にはやっぱり飼いたいという気持ちがあるので、その気持ちも大切にしたい。
でも、なぜ飼いたいのだろう??
一体、その生き物を家で飼いたい気持ちというのは、何なんだろう??
と、ずっと不思議でもあった。
可愛いのは分かるのだけど、やっぱり悲しいことは嫌なわけで。
私自身の中にモヤモヤとした思いがうずまいていて、その問いに対して、はっきりとした答えを持っておきたい気持ちがあった。
キャッチ&リリースのが、お互い幸せなんじゃなかろうかという気持ちがぬぐえなかった。
一方で、ヤゴから育てたコオニトンボがうちで羽化する様子を見たのは本当に素晴らしい体験で、人生史上最高レベルに感動した出来事だった。
カブトムシが羽化して、土からひょっこり顔を出したときの感動も忘れられない。
もし、キャッチ&リリースに徹していて、あの体験を味わえなかったと考えると、それは私にとって、少し寂しいことだったと思う。
生き物を飼うということは、うごめく生と死の輪廻を目の当たりにすることで、当然、私の感情はその度に、のたうち回る。
けれど息子はそれを割と平然とみているというか、意に介さないというか。
それで、いいのか?いいんだろうか?とずっと思っていた。
自然をそばに置いておきたいという気持ち
ずっと釈然としない気持ちをかかえていたときに、1つ答えらしいものが見つかった。
それは、原由希奈さんが書かれたインタビュー記事。子どもの頃から、様々な生き物を家で育て、その後動物園の飼育員となり、現在は「ハビタットデザイナー」として活躍されている本田直也さんの記事を読ませていただいた時だった。
本田さんの生き物を飼う理由は、
「自然の一部を持ってくる、というか、動物の生態や繁殖のさまを再現することが興味深いから」だと、記事に書かれていた。
なるほどなぁ、と思った。
養老孟司さんはある動画で、自然とは「人間が人工的に作ったもの以外」と定義することができると言っていた。
その定義からすると、生き物とは、まさに自然そのものだ。
人は、全くのゼロから生き物を生み出すことはできない。生きものの生と死は、人間が人為的に制御しきれない最たるものなのかもしれない。(例外はあるものの…)
ふと自分の机の周りを見渡すと、たしかに人工的に作られたものばかりで、自分自身の身体以外に、自然は見あたらなかった。
もしかしたら、そういう自分自身のような自然と、人は無意識につながっていたいと思うものなのかもしれない。

生と死の体験が飼育の最高の価値
また現在は猟師でもあり、数々の生き物番組や本などの監修をされている新宅広二さんに、今回のイモリの脱走のことをご相談した所、色々と親切に教えていただいた。
そして、生き物を飼うのは難しいです……という気持ちを、つぶやいたところ、以下のようなコメントを頂いて、大変助けになった。
私は生き物の飼育は大事なことだと思っています。
猫も杓子も壮大な地球環境や絶滅危惧種の話しばかりですが、アリんこ1匹でも人間の力でちゃんと飼うのが難しいことを、オトナもコドモも多くの人に経験してほしいですね。
昆虫採集ですら〝キャッチ&リリースが善〟という子供向けの環境教育が大流行ですが、飼育をせずに、そこから得られるものはほとんど無いと私は思うくらいです...。
人間の子どもが獲って飼うくらいで、絶滅するような身近な生き物はいませんからね...。
生と死の体験が飼育の最高の価値であり、それが自然を知ることだと思っています。
「生と死の体験が飼育の最高の価値であり、それが自然を知ること」
なるほどなぁ。
そういうふうに考えたことは、今までなかったので、とても救われたような気持ちになった。
そして、私がずっと抱え続けていた疑問に対して、はっきりとした答えを見いだせた気がした。
新宅さん、ありがとうございました!
突然すぎる別れはツラい。それは、人であっても動物であっても生あるものであれば、とても驚くし、ツラいものだ。
でも、それは同時に、自分が抱えている実は意外と儚い「生」についてもありありと思い出させてくれる瞬間であったりもする。
イモリちゃんのおかげでそんなことを考えたりした。

私を励ますつもりだったらしい。
翌日には「あれ、ママ案外大丈夫じゃん!」と言われるほど、元気になりました。
いいなと思ったら応援しよう!

