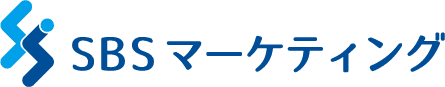マーケティングとセールス間の軋轢を回避する方法とは!?~『良いリード』と『悪いリード』~

◆リードとは?
※現場でよく使う表現として『良いリード』と『悪いリード』を用いています。ご容赦ください。
リード=見込み客とは、企業の商品やサービスに興味を持ち、購入してくれる可能性がある方の個人情報のことです。主に、氏名、所属する会社名、部署名、役職名、電話番号、メールアドレス、住所を指します。
ビジネスを継続する、売上を上げていくためには、自社の商品・サービスに興味があるリードを増やしていくことは欠かせません。
※『リード』の詳細については下記の記事をご覧ください。
■BtoBで使われる「リード」の意味とは?

◆営業が欲しいのは『良いリード』
BtoBの事業会社では一般的に、マーケターが戦術施策を通じてリードを獲得し、リードナーチャリング(※)を実施、検討確度が上がってきたら、組織体制によりますがインサイドセールスが架電などでアポイントを取得したり、フィールドセールスがフォローし商談・案件化、受注に向けて活動を行います。
※『リードナーチャリング』の詳細については下記の記事をご覧ください。
■BtoB領域におけるリードナーチャリングとは?
理由としては、BtoBの場合はBtoCとは異なり、Web上で購入まで完結するケースは稀だからです。
このBtoBビジネスの商文化・特性については、下記の記事をご覧ください。
■BtoBマーケティングの成果を見極める&受注確度を上げるためには!?
そんな受注に向けて活動するフィールドセールスから、「マーケティングが獲得するリードの『質』が良くない。もっと質が高い『良いリード』を渡してくれ」とオーダーを受けることが多々あります。事業会社に所属するマーケターのほとんどがそんな経験をしたことがあるのではないでしょうか。
確かに、リードを商談・案件化、受注に向けてフォローするフィールドセールス(外勤営業)からすれば、マーケティングから渡されたリードの多くが、興味が少しあるだけ、まだ情報収集の段階であれば、空振り感が強くフォローのし甲斐が無いというのもわかります。
つまり、フィールドセールスが欲しい質が高い『良いリード』とは、フォローすると商談・案件化、受注につながる可能性の高いリードを指します。

◆マーケが獲得できるのは『今すぐ客』になりにくいリードの比率の方が大きい・・・
という営業の要望はマーケティング側もよくわかるはずです。
質が高い『良いリード』=商談・案件化、受注につながる可能性の高いリード=今すぐ客、という認識はマーケティングも一緒だと思います。
マーケティングの立場としても、『良いリード』を獲得したいという気持ちで活動しているはずです。とはいえ、マーケティング施策で獲得できる多くのリードは『良いリード』と反対の表現に当たる『悪いリード』の比率が多くなってしまいます。
マーケターとしては、これは決して言い訳でもなく、そもそもリードを獲得すること自体、個人情報を第三者に提供するということなので難しいことであると思っていますが。。
『良いリード』に対する表現としての質の悪い=『悪い』リードとは、購入・導入するための予算も確保しておらず、ニーズも明確ではなく、導入時期も考えていないまだ情報収集の段階のリードを指します。
これらBANT情報(※)を得る段階でないリードだと、商談化・案件化にはなりませんので、「まだまだ客」であるということになります。
※『BANT情報』の詳細については下記の記事をご覧ください。
■案件確度が高まり売上の見通しが立つ!?マーケターも把握しておきたい『BANT情報』

◆『良いリード』を狙って獲得できるか?
まず、リードの獲得方法についてですが、マーケティング用語では「リードジェネレーション」と呼びます。
Webサイトに設置したホワイトペーパーなどコンテンツをダウンロードする、展示会で名刺交換する、広告を出稿しその広告をきっかけに問い合わせてもらうなど、オンライン(デジタル)、オフラインさまざまな流入経路でリード情報を取得します。
『リードジェネレーション』の詳細については下記の記事をご覧ください。
■BtoB領域におけるリードジェネレーションとは?
次に、『良いリード』を狙って獲得できるか、という点ですが、(いろいろ制約が発生するという前提のもとで)可能と言えば可能です。

リードジェネレーション施策によって特性があります。
確度の高いリードを獲得できるが少数のリードに留まってしまう、反対に確度の低いリードになってしまうが多く獲得できる、また、確度の高いリードを獲得できるが時間がかかってしまう、確度の低いリードになってしまうが短期間で獲得できるなどが挙げられます。
つまり、リードの獲得施策には「向き不向き」があるので、自社の状況に応じて選定する必要があります。なので、『良いリード』を獲得したい場合には、傾向として獲得件数が少なく、時間がかかってしまうので、そういった制約があることをマーケティングもセールスも事前に把握・理解しておく必要があります。
◆営業とマーケ間で発生しがちな『リード』についての軋轢を回避するためには?
≪リードを定義し、フォローの役割分担をルール化する≫

こういった営業とマーケティングの間で起こりがちな、『リード』に関する軋轢を回避するためには、まず、「どの段階のリードをどの部署がフォローするか役割分担を決める・ルール化する」ことが必要です。
「この段階のリードはセールスがフォローする」、「この段階のリードはマーケティングがナーチャリング(フォロー)する」といった形で、役割分担を明確にすれば、営業側の「フォローしたけど空振りだった」というケースは減らすことができます。
具体的には、トライアル希望や価格や詳細説明を希望し問い合わせてきてくれたリードはセールスがフォローする、商品やサービスのホワイトペーパーなどの資料をダウンロードしたリードであれば、マーケティングがナーチャリング(醸成)するといった分担です。
その後、ナーチャリングによってWebページへの流入頻度が増えたリードは、確度が高まったと判断し、インサイドセールスが架電したりフィールドセールスがアタックするのが望ましい形と言えます。
さらに、ルール化するためには、「今すぐ客」か「まだまだ客・これから客」かのどちらのリードなのかを判別する必要もあります。
検討確度に応じたクオリフィケーション(選別)を行わなければ、リード側の状況に応じたフォローができなくなってしまいます。
その場合、「資料をダウンロードして営業から電話がかかってくるならもう情報収集するのはやめよう」といったケースも発生してしまい、リード側の検討確度が上がらなくなり、さらに電話アプローチや配信メールを拒否されてしまうリスクがあるので注意が必要です。
≪新規リードを獲得する、既存リードを掘り起こす≫

リードごとの定義と役割分担を決めた後は、リードの獲得件数・案件数を増やすアクションが必要です。
そのための考え方として、「新規リードを獲得する」「既存リードの掘り起こし」の2パターンが挙げられます。
忘れてはならないのが「既存リードの掘り起こし」です。
マーケティングとしても新規リードを獲得することに注力しがちですが、これまでの事業運営で獲得したリードがあるのであれば、それらのリードにアプローチするのも有効です。
営業としても、新しいリードをフォローしたい気持ちに駆られるかもしれませんが、保有している既存リードは『資産』にもなり得るので、可能性を見出すのも営業の腕の見せ所と言えます。
つまり、下記の3点が軋轢を回避するポイントとなります。

●「今すぐ客」か「まだまだ客・これから客」かのどちらのリードなのかを判別する
●どの段階のリードをどの部署がフォローするか役割分担を決める・ルール化する
●その後、新規リードを獲得する、既存の保有しているハウスリストを掘り起こす
保有している既存リードへのアプローチについては、マーケティングだけでなく営業も戦略プランを立案して実施することが望ましい形と言えます。

◆最後に
そもそもですが、『質の高い良いリード』が欲しいというのは、とても失礼な話です。
興味を持ってもらえる、買いたいと思ってもらえるように、自社が販売したい商品やサービスを価値のあるモノにして、価値があると認識してもらえるよう、対外的なメッセージを改める、そして、買わない・買う気がない人にアプローチしないよう社内体制を構築するなど、売りたい側は買う側の目線で考え努力すべきです。
そして、マーケティングもセールスも『売上を上げる』という目標は同じはずです。
それなのに、社内の交通整理やルールが定まっていないと、部門間で軋轢を生み、受注の機会損失も生んでしまいます。
それぞれの部署ごとに行うべき役割を決めて、一緒に同じゴールである売上を上げていく活動をしていきたいところです。
リードジェネレーション施策に関しましては、当社のコンサルティングサービスにて、会社様に応じて詳しくご提案させていただいております。

●中規模・小規模企業様はこちら→リードジェネレーションサポートサービス
●個人事業主・フリーランス様はこちら→見込み客獲得サポートサービス
ご興味ありましたら、お問い合わせください。
BtoBマーケターより。