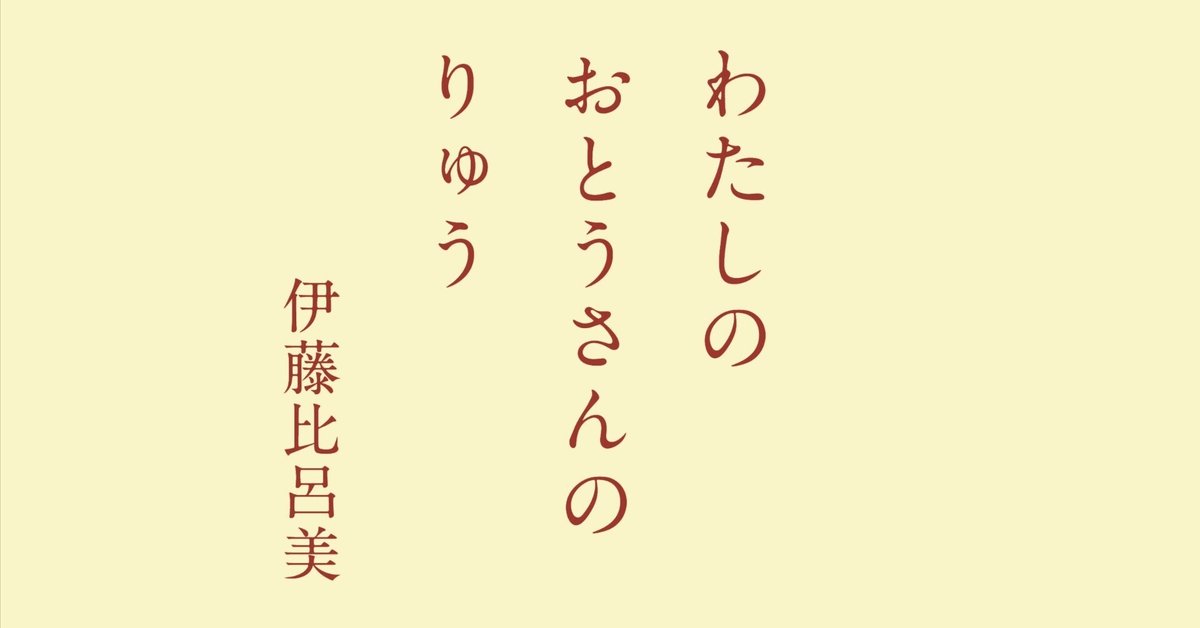
わたしのおとうさんのりゅう 〔第5回〕
詩人の伊藤比呂美さんの連載。『ドリトル先生物語』(ヒュー・ロフティング作、岩波書店)の中で好きだったのは「ネコ肉屋」のマシュー・マグ。父と重なるその姿から思い出されるのは、「私」が生まれ育ち遊んだ裏町の路地裏にいた人々、父を囲んでいた若い工員たち。
記憶をたぐるうちに、「私」は一葉の写真を思い出す。それはもっと若く、そして、高校生、中学生といっていいような若い男たちに囲まれて笑う、軍隊にいたころの若い父の姿だった。かつて読んだ作品たちは、若いころの父の過去へとつながっていく。お楽しみください。
ドリトル先生アフリカゆき2 ひみつ、そしてネコ肉屋
ひみつを解く鍵は、ダブダブ、そしてオシツオサレツの声にありました。
ダブダブが、先生に向かってこういいました。横に英語の原文を並べてみますね。
「そんなことはございません」Yes, you do.
「先生、おぼえていらっしゃらないんですか」Don't you remember....?「まあ、すこしはっきりなさってください」Oh, do be sensible!
英語の原文はどれも、普通に、だれもがだれもに、話しかけるさいの言い回しです。そこになんらの階級差も性差も年齢差も感じられないものです。しかし日本語のダブダブの声は、若くない女の分別と経験と、分別と経験を持っていることに対する自恃と、それから話しかけている相手に対する尊敬と愛情をまんべんなくあらわしておりました。
そして、オシツオサレツの言葉はこうでした。そしてこちらの英語原文もまた、ダブダブと同様に、丁寧ではありますが、尊敬も謙譲もない表現でした。ちなみにこの生き物はheで呼ばれています。先の二例は交渉に来たさるたちに対する言葉で、次の二例は先生に対する言葉です。
「いやでございます」No.
「人に見られるのが、だいきらいでございます」I hate being stared at.
「はい、お供いたします」Yes, I'll go.
「さようでございます」Yes.
井伏鱒二の文章のすごさとは、動物たちと先生との間の、平易で平等な英語の会話文を日本語に移し替えたときに、いきなり階級差を、そして親しみを、さらに敬慕を、子どもの世界ではとうていありえない、おとなの世界でもすでに死語となっていた敬語システムを駆使して、表現しつくしたことだったのでありました。
ドリトル先生シリーズはファンタジーと分類されているわけではありません。でも井伏鱒二はまったくのところ、その洗練された敬語システムによって、パドルビー(英語を読んで初めて解りましたが、「水たまり村」とでも訳したい場所の名前です)のドリトル先生(これも英語を読んで解りましたが、「なんにもできない人、やぶ医者」とでも訳したい名前です)の世界を、まるで中つ国みたいに作りあげたわけです。
ちなみに英語版で、「これはしたり」はMy! で、「いやはや」はWell, well! でした。これもまた、英語版の気づき、おどろき、感じ入りという常套句を、井伏版では、若くない男たち、教養も経験もある男たちを、ちょっとしたひょうきんさも交えて、あますところなく表現しているのでした。
ここから先は
¥ 200
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
