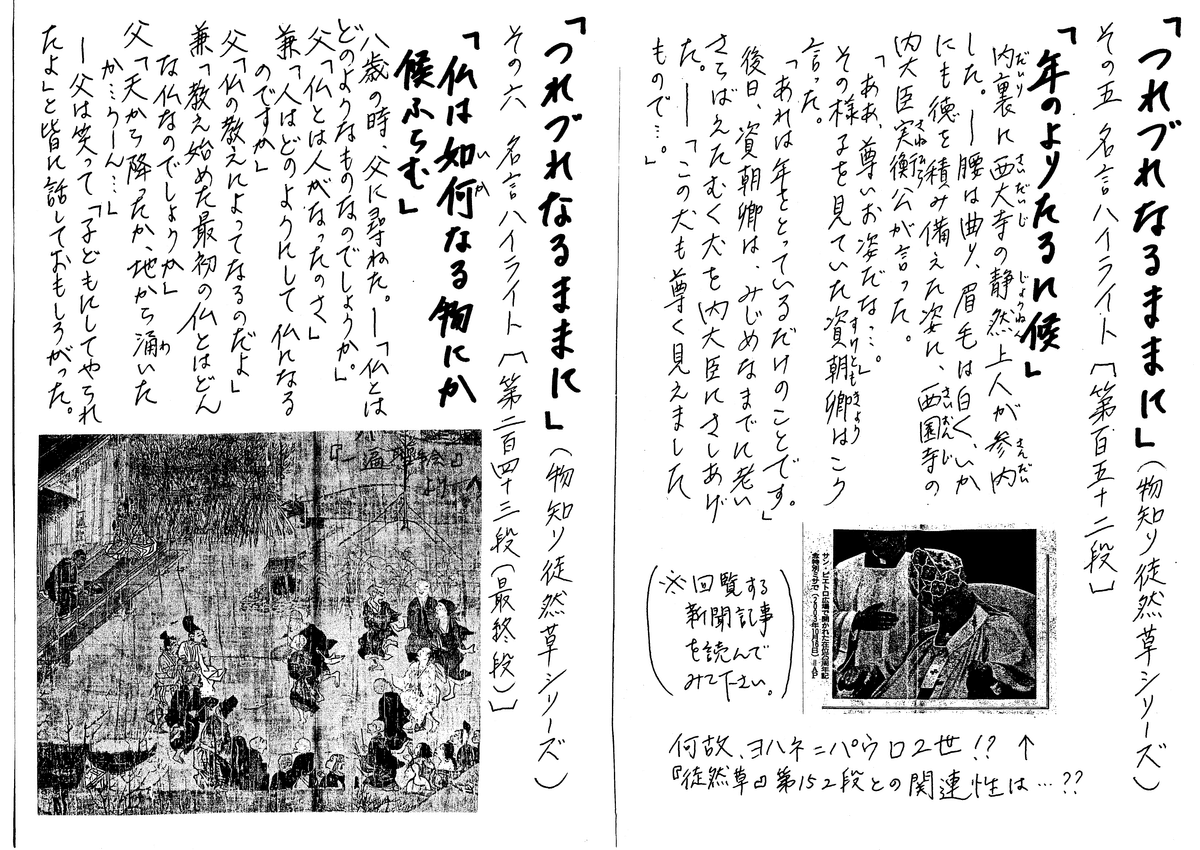『徒然草』―名言ハイライト6 第二百四十三段―(2013年9月29日)
第二百四十三段は、『徒然草』の最終段です。八歳の兼好は父に「仏とは如何なる物にか候ふらむ」と問いかけ、兼好に問い詰められて答えに窮した兼好の父は、この話を面白がっていろいろな人に話したということで、八歳の兼好の聡明さが際立つ逸話となっています。
逸話自体の考察はメルマガで行っているので、それはまた別の機会に紹介するとして、本ブログではメルマガの方でも焦点を当てた「智」について、もう少し考えてみたいと思います。
鎌倉時代末期は、兼好のような「智者」がたくさんいたと私は想像しています。
『徒然草』第百三十一段では、「おのが分を知りて、及ばざる時は、速にやむを智というべし」とあります。「ゆるさざらむは人のあやまりなり。分を知らずして、しひてはげむはおのれが誤りなり。貧しくて分を知らざれば盗み、力衰へて分を知らざれば病をうく。」
「分を知る」ことで、自らの不足に対して過剰になることを回避することができるという、「智」の効用がテンポの良い筆致で示されています。まさに「智者」兼好が凝縮されたような段落です。
第百三十段には、「人に勝らんことを思はば、ただ学問して、その智を人にまさらむと思ふべし。」ともあります。「ただ学問の力」のみが、「大きなる職をも辞し、利をもすつる」ことを「道」のためにすることが可能だいうのです。逆説的ですが、「智」を極めることで、世俗的な勝負などを超越し、結果的に「人に勝」るということなのでしょう。
「智」のこの合理性・有用性を多くの人々が享受し始めたのが、実はこの鎌倉時代末期であったに違いありません。
一方で、第百六段では「智」の愚かさと、行き過ぎた「智」に対抗しうるものが何かということを考えさせられます。
「高野の証空上人」なる人が、すれ違った馬の口を引いていた男のまずい綱さばきで馬ごと堀に落とされ、「かくのごとく優婆夷(うばい)などの身にて、比丘を堀へ蹴入れさする、未曾有(みぞうう)の悪行なり」と叫びます。〝仏の弟子の中で一番高位にある自分を、一番劣る身分のお前が堀に蹴り入れさせるとは前代未聞の悪行だ!〟と言うのです。
しかし男にはそんな理屈は通じません。「いかに仰せらるるやらむ、えこそ聞きしらね」、〝なにをおっしゃっているのか、さっぱりですわ〟とすっとぼけた様子で答えるのです。
「何といふぞ。非修非学(ひしゆひがく)の男」と声を荒らげたところに、はっと我に返ったのでしょう、上人は「きはまりなき放言(はうごん)しつと思ひける気色にて、馬引き返して逃げられにけり。」とあります。
兼好はこれに「尊かりけるいさかひなるべし。」とコメントしています。
頭にきたのだったら、素直に〝何だ、この野郎!〟とでも言えばいいのに、仏の教えを使ってその怒りをぶつけようなどというのは、不自然なことなのです。
「非修非学」、つまり、「智」が一切通用しないゆえに男は、「えこそ聞きしらね」と言うわけです。上人は自分でも、自分の発言が怒りでしかなかった、それなのに「智」で取り繕うとした、その愚かさに気づかされたのです。
「智」の合理性・有用性が、それを適用すべきでない場面にまで適用されながら、それでもまだ「智」の毒に完全には犯されていない、あるいは、馬を引いていた男のような「非学非修」のあり様が、「智」の毒気を抜くことも十分に可能であった時代――とても興味深い時代であり、『徒然草』を何度読んでも次から次に興味が尽きない理由も、そこにあるととらえています。