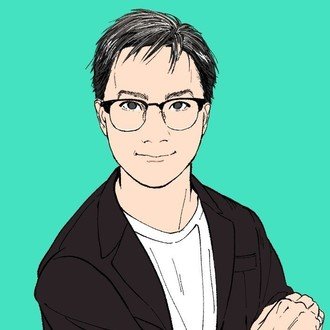【Vol.328】セロトニンを誘導する!
【本のタイトル】
BRAIN DRIVEN パフォーマンスが高まる脳の状態とは
【著者】
青砥瑞人
【引用文章】
βエンドルフィン以外に、ホメオスタシス的に脳の状態を整えてくれる脳内化学物質にセロトニンがある。セロトニンは脳や身体の反応として自動的にも作られるが、意識的にも誘導できる。
一つ目は、単調リズム性運動に反応して合成される。イライラすると貧乏ゆすりをしたり、指をカタカタしたりする人が多い。それらの行動には、セロトニンを合成してストレス反応を抑える意味がある。
そう捉えると、貧乏ゆすりをしている自分や他人が「ストレスに対して適応反応しているな」と客観視できる。また、意図的に単調リズムを刻むことも考えられる。
好きな音楽を聴きながらリズムに乗るのも、単調リズム性運動になる。あらゆる文明、文化に音楽やダンスがあるのは、人類がDNAレベルの欲求としてストレスに適応してきたからだろう。
ガムを噛むなど咀嚼による単調リズム性運動も効果がある。種類は違っても、昔から人類には多大なストレスがあったと思う。それに適応していく上で、リズムを伴う運動は我々をストレスから解放し、ストレスに対して冷静に向き合わせることで学びに昇華させてきたのではないだろうか。
有名な経営者に、皿洗いをすると落ち着く人がいる。皿洗いという単純作業もリズム性運動として考えられる。無心で集中することで、セロトニンが誘導される可能性は高まる。もちろん「なんでこんなことしなきゃいけないの?」と不満を溜めながらやると、不満の思考に神経回路が使われ、セロトニンを合成する脳部位の活動は弱まる。結果として、不満によるストレスばかりが溜まる。
単調で、それだけで集中でき、自分が心地よく感じるリズム性の動作を見つけると、セロトニンによって生活にゆとりの時間が広がるかもしれない。世の中の宗教的な儀式には、単調な動作の繰り返しやそれに伴って言葉を唱えるものがある。それらが長く続いているのには意味があり、その安らぎにはセロトニンの効果もあるかもしれない。
ただし、その効果の前提として自分の行為を信じ、集中することが必要だ。「信じるものは救われる」とは心理を言い当てているかもしれない。
【具体的アクションプラン】
セロトニンを誘導する!
→気分が落ち着く単調作業を行い、セロトニンを誘導する!
いいなと思ったら応援しよう!