
遊びをせんとや生まれけむ
平安時代末に後白河院(1127~92)が編纂、京都の人々を魅了したその時代の流行歌謡を集めた「梁塵秘抄」(りょうじんひしょう)。
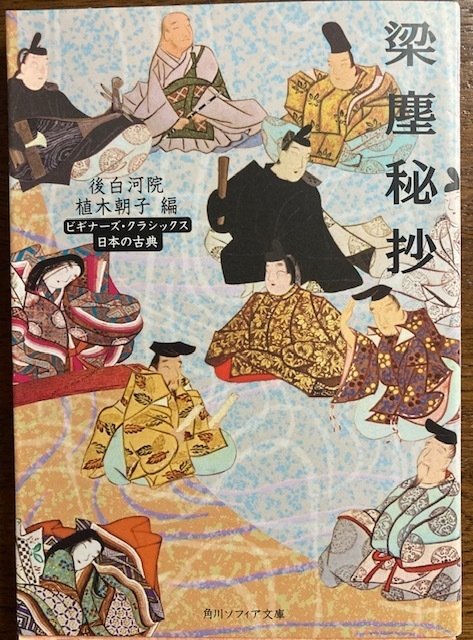
その中に、こんな歌があります。
遊びをせんとや生まれけむ
戯れせんとや生まれけん
遊ぶ子どもの声聞けば
わが身さへこそ揺るがるれ
【訳】
遊びをしようとしてこの世に生まれてきたのだろうか、
戯れをしようとして生まれてきたのだろうか、
一心に遊んでいる子どもの声を聞くと、
私の体まで自然に動き出してくることだよ
先日、新幹線でたまたま隣り合わせた人が読んでいた本。
その本が気になって、自分も読んでみました。
その本を読んでいた時に、ふと、「遊びをせんとや生まれけむ」の歌を思い出しました。
とある日。
所用を済ませて新幹線で家に帰る道すがらの出来事。
2人シートの窓側に座り、缶ビールを飲みながら車窓からの流れる風景をぼーっと眺めていました。
途中から、自分と同じくらいの年齢の男性が隣の席に。
上の荷物棚にバックを置く際に軽くお互い軽く会釈。
その男性は一冊の書物と缶のハイボールを座席テーブルにおいて一息。
どこかでゴルフをした帰り道のような雰囲気。
日に焼けている。
そして、日頃鍛えているような精悍な感じ。
自分も本を手にしていましたが、なんだか読む気になれず。
一方、隣の男性は、ハイボール片手に結構熱心にその本を読んでいる。
何の本を読んでいるんだろうか。
熱心に読む姿を見て、なんだか気になってしまいました。
とは言え、自分はずっと窓に向かってぼーっと風景を見ているのに、振り返って露骨に見るのもなんだなあ、、と思っていまい確認出来ずじまい。
そうこうしているうちに、その男性ふと立ち上がり、席の前の網ポケットに本をいれて席を外し、何処かへ。
その本はちょうどカバーがされておらず(もしかしたら駅のキオスクで買ったのかな)、網ポケットに入れて行ったその本を見てみました。
本のタイトルは、
「林住期」(五木寛之)。
「林住期」?
著者が五木寛之ということもあり、とっても気になり、早速、書店で買い求め読んでみました。

本はシニア世代の「生き方」にまつわるエッセイでした。
古代インドでは人生を四つの時期に分けて考えていたとのこと。
①学生期(がくしょうき):青年
②家住期(かじゅうき):壮年
③林住期(りんじゅうき):初老
④遊行期(ゆぎょうき):老年
以前の人生50年という時代から、今や人生100年時代と言われている中、四つの期はそれぞれ25年づつの過ごし方になるのではと著者は語っています。
そして、
人生のクライマックスは、じつはこの後半、ことに50歳から75歳までの「林住期」にあるのではないか、最近つくづく思うようになってきた。
「林住期」は「必要」からではなく、「興味」によって何事かをする動くということにある。
とも語っています。
学生期は心身を鍛え学び学ぶ時期。家住期は職を得、家庭を作る時期。林住期は仕事や家庭の細かなことからも解放されて思索の時を持つ時期。
これだけ生き方の多様性の中で、そう綺麗に「学」→「家」→「林」のステップを踏むことは難しくなっているのかもしれません。
とは言え、林住期を人生の黄金期と捉えた時、その時期をどのように過ごすか見直してみようと思いました。
その時期の充実が、第4コーナーをスムーズに曲がり切り、次のステージにステップアップすることができる。
そして、最終コーナーを曲がった先には人生の締めくくりとでも言うような時期を「遊」行期としている。
はて、有終の美を飾る時期は、なぜ「遊」なんだろうかとふと思いました。
そもそも、この四住期の考えは、バラモン教法典が規定する四つの段階で、「遊行期」は一定の住所をもたず乞食遊行時期とのことのようです。
なかなか乞食遊行するのは難しいものの、人生の最後の場所を求め、遊ぶように何事にも囚われない人生の最終盤とも捉えられます。
サンスクリット語を漢字に変換したときに、「遊」の字を当てはめたのは大変意義深いのではないかと思いました。
「遊」とは何か?
①あそぶ。楽しむ。 ②勉学などのために他国へ行く。旅をする。 ③自由に動きまわる。 ④使われずにいる。 ⑤つきあう。 ⑥あそび。ゆとり。よゆう。(漢字ペディア)
「遊」の漢字の成り立ちで見た場合、「神様が自由に行動する」という意味合いのようで、後に「人間が心のおもむくままに行動して楽しむ」という意味に転じたそうです。
神が「ゆく」こと、気ままに行動することを遊・游(ぶらぶら歩くこと)という漢字で表現されている。
最終段階の第四期にも「遊」の漢字が使われているのは印象的です。
改めて、人生の最終段階は、なぜ「あそぶ」、「楽しむ」なのだろうか?
そして、それだけなのだろうか?
そんなことを考えていた時に、これもまたご縁で、為末大氏の講演を聴く機会があり、著書「熟達論」を手にしていました。
「人はいつでも学び、成長できる」という、この本の中にも「遊」が出てきます。

為末大氏は陸上競技の選手として三度のオリンピックに出場。世界陸上選手権では2大会で銅メダルを獲得。
陸上競技を通じて成長や学び、学習の在り方の思索を深め、言語化し、世に発信している「走る哲学者」。
為末氏は人間の成長のプロセスを「熟達」という言葉で表しています。
「熟達」とは人間総体としての探求であり、技術と自分が影響しあい相互に高まること」これが本書での熟達の定義である。
成長成長の段階を以下の五段階のステップ踏んで行く。
①「遊」(ゆう):不規則さを身につける
遊びは感覚的なもので、不規則さと面白がる姿勢を身につけられ、その感覚があることで探求が続くようになる。
②「型」(かた):無意識にできるようになる
技能の土台をつくるもの。型を持つ事で無意識に本格的な動きができる。
③「観」(かん):部分、関係、構造がわかる
視覚のみではなく、全身で行う観察行為により何が重要か、その本質がつかめる。
④「心」(しん):中心をつかみ自在になる
中心をとらえる事で、手に入れた型の輪郭が崩れ、中心部分だけが身体に残っていく。
⑤「空」(くう):我を忘れる
熟達の最終段階は、自我が無くなり、制約から解放され、技能が自然な形で表現される。いわゆる「ゾーン(zone)」に入った世界。夢中で我を忘れる
著者自身の陸上競技での試行錯誤の実体験に基づく、丹念で納得感ある議論を展開しています。
ここまで読み進めてみて、
あれ、第五段階の「夢中の瞬間に我を忘れる状態」って、、
「遊び」の状態そのものではないか。
何かの「遊び」でホントに楽しい時は、夢中で、あっという間に時間が早く過ぎている。
これは、著者の言うところの「熟達論」第五段階の「空」の領域の「時間感覚の変容」にもあたるのではないか。
ということは、「遊」→「型」→「観」→「心」→「空」ときて、また「遊」に戻り、螺旋階段を上って行くように、成長のスパイラルアップの循環を生み出していくことに繋がるのではないか。。
そんなことを感じながらページをめくって行ったら、本書の最後の章のタイトルが、
「遊」に始まり、「遊」に戻る
熟達の道は終わらないだろう。もう意味というものに頓着することはない。ただ面白い、ただやってみたい、という理由なき衝動がある。すべては遊びから始まった。熟達への道のりを経て、私たちはまた遊び戻っていく。
為末大氏の「熟達論」での「遊」は、「始め」でもあり「到達点」もある。
あくまで「到達点」であり「終わり」ではない。
したがって、為末氏は「遊に始まり、遊に戻る」であって、「遊に始まり、遊に終わる」とは表現していない。
バラモン教の四住期は終わりある人間の期間(段階)を示しており、その最終段階を同じ漢字の「遊」としているのは大変興味深いです。
もしかしたら、四住期の遊行期の「遊」であっても、最終コーナーを回った領域であっても「遊ぶ」ことで新しい、豊かな「熟成」をさらに循環させていくことで「遊行期」をさら楽しい時期にしていくことができる。
そんなことに繋がるのではないかと思いました。
であるならば、人生の黄金期は林住期だけはなく、遊行期でもあり、そして学生期でも家住期でも訪れるものなのかもしれません。
為末氏の「熟達論」は、人生のライフサイクル論としても読み解かれるものではないかと思ました。
さて、今年はどんな「遊び」をしようかな。
